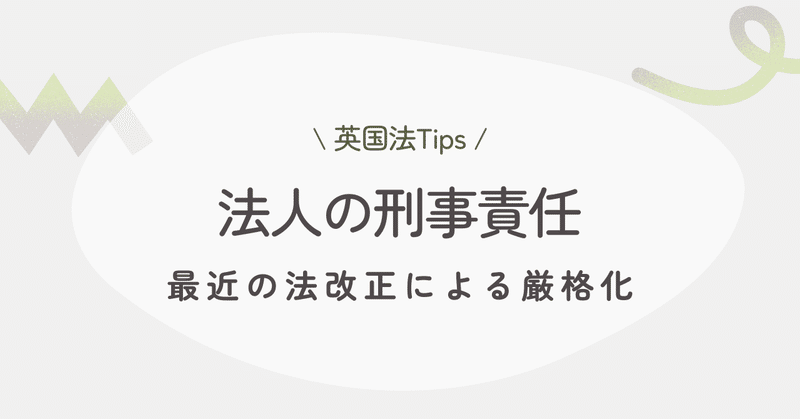
【英国法】法人の刑事責任 ー最近の法改正による厳格化ー
こんにちは。
お読みいただきありがとうございます。
本日は、英国における法人の刑事責任と、これにまつわる最近の法改正について書きたいと思います。
刑事弁護というと、日本では人権擁護に熱心な弁護士が採算度外視でやっているイメージがまだまだ根強いように思います(もちろん、実際はそうでもない局面も多いです)。他方で、イギリスでは、いわゆるホワイトカラー犯罪の弁護は、確立された企業法務の業務分野の一つであり、どの大手事務所もプラクティスチームを抱えています。
その背景には、犯罪を犯した個人のみならず所属先の法人も刑事責任を問われることが、日本に比して比較的多いことも挙げられるのではないかと、個人的には思っています。
そして、日本と英国では、法人の刑事責任に関する基本的な出発点が違っており、日本の常識で見ていくとちょっと議論を追いづらいこともあります。
そこで、今回は、英国における法人の刑事責任に関する議論の概要を抑えるともに、最近の法改正によって法人の刑事責任が厳格化されつつある現状をご紹介したいと思います。
なお、法律事務所のニューズレターとは異なり、分かりやすさを重視して、正確性を犠牲にしているところがありますので、ご了承ください。
英国における法人の刑事責任
英国法の下では、法令に別段の定めがない限り、法人は、ほとんどの刑事犯罪について責任を負う可能性があるとされています。つまり、原則として企業は、刑事罰を受ける客体となります。
日本の刑法が、基本的に、刑を科す対象を自然人に限定しており、いわゆる両罰規定が定められていない限りは、法人は刑事責任を負わないとされているのとは対照的です。
法人に刑事責任を負わせる理論
「なぜ、法人は自然人と同様に刑事罰の客体とされる(べき)のか」という根本的な問いは、日本の刑法を勉強してきた者としては、それはそれで興味深いのですが、ここでは、英国法が、どのようなロジックで法人に刑事責任を負わせているのかという点に迫りたいと思います。
法人は身体もなければ意思もない
英国の刑法も、日本と同様に、犯罪に係る行為と意思が重要です。例えば、殺人罪(murder)であれば、罪の成立のためには、不法な行為(unlawful act)、及び、死又は深刻な傷害に至らしめる意図(intention to kill or to cause grievous bodily harm)の存在が不可欠です。
しかしながら、法人は、概念的な存在であり、自らがピストルを撃ちませんし、「こいつを殺してやろう」という意思を持つこともありません。
したがって、英国法の下でも、実際に犯罪を犯すのは、必ず自然人になるはずです。企業犯罪の文脈でいえば、それは、取締役であったり、従業員であろうかと思います。
では、英国法は、どのようなロジックで、取締役等の犯罪行為と法人の刑事責任を結び付けているのでしょうか。
代理責任(vicarious liability)
英国法の下でも、従業員の不法行為について使用者に責任を負わせる場合があり、代理責任の法理(*1)(doctrine of vicarious liability)などと呼ばれます。日本の使用者責任を思い出すかもしれませんが、実は、英国では、民事上の責任に止まらず、従業員の犯罪行為についても、企業が刑事責任を負うことがあります。
もっとも、犯罪行為に係る企業の代理責任については、一般的に、厳格責任の犯罪に関して適用されると言われています。つまり、過失の要素がない犯罪(例えば環境や食品衛生に関する犯罪など、業法の違反に係る刑事犯罪が多いです。)について代理責任が問われることになります。
裁判所は、代理責任の法理に基づく刑事責任を問うか否かは、法解釈の問題であり、当該行為を犯罪と定めた法の趣旨を考慮するとしています。そのため、ある犯罪について、代理責任の法理による刑事責任が問われないと判断された例もあります(*2)。
同一視原則(identification principle)
上記のとおり、代理責任の法理は、基本的に厳格責任の犯罪について適用されるものです。そうでない犯罪であるときは、同一視原則(identification principle)と呼ばれる理屈によって、企業に刑事責任を負わせています。
これは、犯罪を犯した自然人が、会社の「directing mind and will」であるか、又は、「embodyiment of the company」であった場合に、会社と行為者を同一視して、刑事責任を負わせるというものです。
会社と同一視されうる人物は、代理責任の法理における従業員の範囲よりも狭いと考えられています。具体的には、上級役員、取締役レベルの者に限られます。
ここから、同一視原則に基づいて企業が責任を負いうる場面が限定されることに多くの人が気づくと思います。一般的に、ほとんどの犯罪は厳格責任ではなく、その中にはホワイトカラー犯罪も含まれることを考えると、企業にも責任を求める立場からすれば、同一視原則は適用範囲が狭すぎるという批判もあり得るところだと思います。
また、近年の重要判例であるSFO v Barclays事件において、同一視原則を適用するためには、非常に高いハードルが設定されていることが改めて浮き彫りになりました。同事件では次のように述べられています。
(対象となる上級役員は)完全な裁量権や完全な自律性を有しておらず、職務遂行の方法について別の人物に責任を負っていたため、当該行為を遂行するための意思決定者であるとはみなされなかった。刑事責任を(被告に)帰することが出来るのであれば、(当該上級役員が)完全な自律性を持っていたことを示さなければならなかった。
一定以上の規模の会社で、このような「完全な裁量権・自律性」を有する役員は、ほぼいないように思われます。
そうなると、大企業の上級役員は、一般的に、中小企業のオーナーよりも大規模な経済犯罪を犯し得る立場にあるにもかかわらず、後者にのみ同一視原則が適用されるという結果となりかねません。
Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023
法人の刑事責任の厳格化
このような歯がゆい状況にあるにもかかわらず、近年、マネーロンダリングを始めとする経済犯罪の大規模化がさらに進んでいる状況です。
そのような背景を受けて制定されたのが、Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023(以下「ECCTA」)です。ECCTAの目的は、商業登記に関する比較的大規模な改正がメインではありますが、同一視原則を再定義することも行われました。
なお、商業登記に関する改正については、こちらで紹介していますので、良ければどうぞ!
特定の組織への経済犯罪の刑事責任の帰属
ECCTAのs. 196(1)は、次のように定めています。
企業体又は組合(以下「組織」)の上級管理者が、実際の又は外形上の権限の範囲内で行動して関連犯罪を犯したときは、本条の施行後、組織もその犯罪の責任を負う。(後略)
ポイントは、上級管理者(senior management)が実際の又は外形上の権限の範囲内で行動して関連犯罪を犯したと言えれば、企業に刑事責任を問えることです。つまり、行為者が「完全な裁量権・自律性」を有していなくとも、与えられた権限の範囲内で行動していればOKということで、検察にとっては、かなりハードルが下がることになりました。
上級管理者とは?
ECCTAは、上級管理者について、次のように定義します(*4)。
「上級管理職」とは、組織に関して、以下のいずれかのような重要な役割を果たす個人をいう。
・ 組織の活動の全体又は相当部分をどのように管理または組織化するかについての決定を行うこと。
・ それらの活動の全部又は相当部分を実際に管理または組織すること。
分かったような、分からないような規定ですね。上記のとおり、ECCTAに基づいて企業が刑事責任を負うのは上級管理者による犯罪のみですので、今後、裁判所が上級管理者の範囲をどのように解釈するかで、検察にとってのECCTAの使い勝手が変わってきそうです。
ただ、この定義は、Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007(以下「CMCHA」)の「上級管理者」と同じですので、基本的には、ECCTAにいう上級管理者の解釈も、CMCHAのそれと同様になされるようにも思えます。とはいえ、これまでCMCHAが適用されたケースは、ぼくが知る限り比較的小規模な企業が対象でしたので、大企業の役員のホワイトカラー犯罪の裁判において、どこまでストレートに適用されるのかは未知数です。
関連犯罪とは?
もう一つ注目すべきは、関連犯罪の定義です。この「関連犯罪」は基本的に、ECCTAのSchedule 12に列挙された犯罪です。パッと見ですが、主要なホワイトカラー犯罪は含まれています。
なお、政府は、二次法によってある犯罪を「関連犯罪」に含めることが可能であると定めており、政府は将来的に全ての犯罪を「関連犯罪」とすることを約束しています。
いつ施行されたのか?
特定の組織への経済犯罪の刑事責任の帰属を定めたECCTA S. 196は、2023年12月26日に施行されています。
おわりに
いかがだったでしょうか。
本日は、英国における法人の刑事責任とECCTAによるその厳格化について、紹介しました。
以下のとおり、まとめます。
・ 英国では、法令に別段の定めがない限り、法人は、ほとんどの刑事犯罪について責任を負う可能性がある
・ 法人に刑事責任を負わせる理論:
・・ 代理責任(厳格責任の犯罪の場合に適用)
・・ 同一視原則:適用範囲が限定的
・ ECCTAによる法人の刑事責任の厳格化
・・ 上級管理者が、実際の又は外形上の権限の範囲内で行動して関連犯罪を犯したときは、本条の施行後、組織もその犯罪の責任を負う。
・・ 2023年12月26日に施行済
ここまで読んで頂きありがとうございました。
この記事がどなたかのお役に立てば、嬉しいです。
【注釈】
*1 この和訳が一般的かどうかは、分かりません。日本の不法行為でいう使用者責任に近いのですが、全くイコールというわけではなく、混同を避ける意味で、上記の訳を当てています。
*2 Seaboard Offshore Ltd v. Secretary of State for Transport [1994] 1 WLR 541
*3 SFO v Barclays PLC and another [2018] EWHC 3055 (QB)
*4 S. 196(4), ECCTA
免責事項:
このnoteは、ぼくの個人的な意見を述べるものであり、ぼくの所属先の意見を代表するものではありません。また、法律上その他のアドバイスを目的としたものでもありません。noteの作成・管理には配慮をしていますが、その内容に関する正確性および完全性については、保証いたしかねます。あらかじめご了承ください。
X(Twitter)もやっています。
こちらから、フォローお願いします!
こちらのマガジンで、英国法の豆知識をまとめています。
よければ、ご覧ください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
