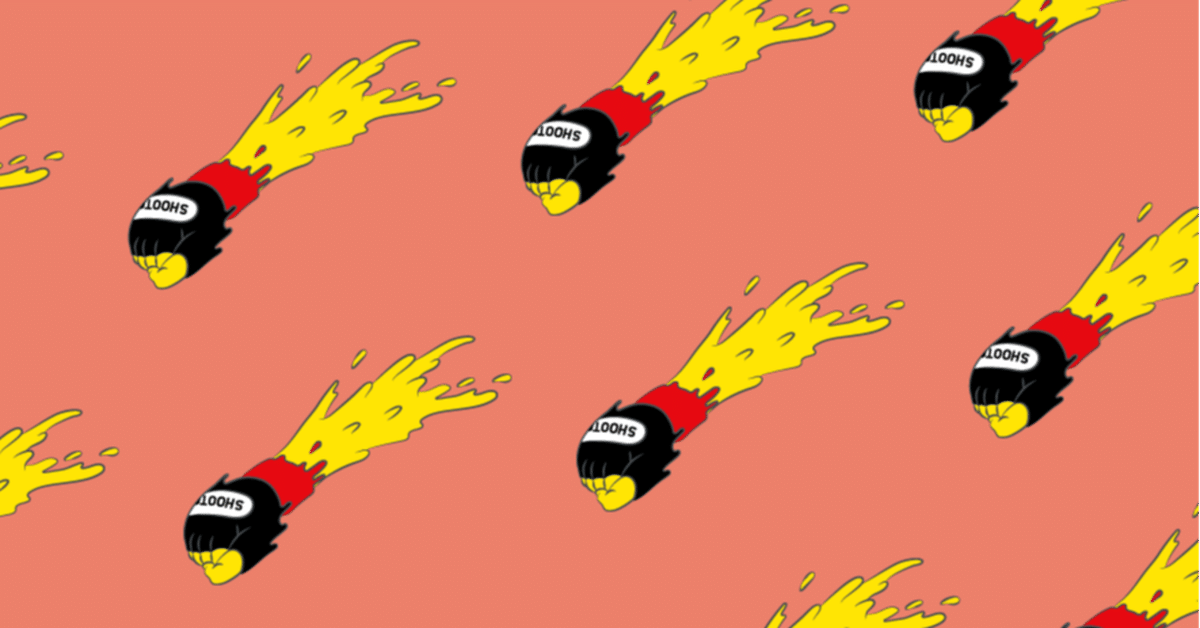
猫曾木団地と狐憑きのナミダ
第5回阿波しらさぎ文学賞の落選作です。それにしては長いと思われる方もいるかもしれませんが、規定枚数のところで切って応募しました(長編では聞くけど短編では聞きませんね……)。じゃあこれが完成形なのかと言ったらそうでもなくて、長編の冒頭にしかなってません。しかもこの先の展開は何も考えてないという。そんなわけでタイトルも(仮)もいいところ。同賞にいつか長編部門ができたら完成させて応募したいです。続きが読みたいという方がいたら励ましのコメントでもください。書くというお約束はできませんが。
猫曾木団地は灼熱の公衆便所のように蒸し暑かった。
まだ五月だというのに気温は三十度を越え、黙っていても汗が垂れてくる。年に一度剪定業者が入るまで放置される植栽は通行の妨げになるほど好き放題に枝葉を伸ばし、その重苦しい見てくれはケツを思いきり蹴りあげられた古いギャグ漫画のキャラクターみたいに団地の不快指数を跳ね上げさせていた。
住民たちの大半は築五十年以上経つおんぼろ団地のそれぞれの薄汚れた部屋に引っ込み、外をうろついてるのは用もないのにホームレスみたいに敷地内をうろつかずにはいられないいつもの連中だけだ。こいつらはこのご時世に夜も玄関ドアを開け放したまま寝るのだ。
誰一人変化を望んでいない、いつもの猫曾木団地の風景だった。そんな中を、おれはまるで人食いヒグマに追われる山岳遭難者みたいに生きた心地がしない気分で脂汗をにじませながら走っていた。感じていたのはむしろ寒気だった。冷蔵庫の奥で何日も忘れられていたエクレアのせいで腹を下し、今にもケツのダムが決壊しそうだったのだ。
お袋とどちらのエクレアがより大きいか、あるいはより重いかで言い争ったのはまったくの無駄だった。おれは発見者の権利を主張し、お袋は金を払った者の権利を主張したが、議論はどこまでいっても平行線だった。最終的におれはじゃんけんで負けた。お袋は「お前はいつも最初にパーを出す。子どものときから同じ。まったく成長しない」といって大きく見え、かつ重く感じられる方を取った。だが、どんな神の思し召しか、どちらのエクレアも中のクリームが傷んでいたのだ。
先に腹が痛いと言い出したお袋をせせら笑ったのは、おれの完全な勇み足だった。少し遅れて自分にも同じ症状が出はじめたときには、部屋に一つしかないトイレはお袋のアドバルーンみたいに膨らんだ、ありとあらゆる障害物をその弾力で跳ね返すどでかいケツで塞がっていた。
いくら出てくれとドア越しに頼んでも、お袋は「こっちは取り込み中なんだよ」と言ってまともに取り合おうとしなかった。もしかして、でかすぎるケツが便器にはまって身動き取れなくなったんじゃないかとも疑ったが、おれが「実の子が頭を下げて頼んでるんだぞ」と言いながらドアを蹴飛ばすと、お袋は「親不孝もの。とっとと自立してればこんな目に遭わなかったんだよ」とケツのところで内線が勃発してるみたいな爆発音を炸裂させながらおれを責め立てた。うぅだの、あぁだの、聞きたくもないお袋のあえぎ声まで漏れてきた。
こっちも限界だった。顔色が死んだイカみたいに青ざめているのが自分でも手に取るようにわかった。おれの追い詰められた脳みそはもうトイレのことしか考えられなくなり、おれは部屋着のまま飛び出して団地の階段を駆けおりた。三十代半ばにもなってくそを漏らすなんてわけには絶対にいかなかった。
目指すのはこの団地で唯一の公衆トイレだった。猫曾木団地は同じ作りをした五階建てのぼろい建物が80棟以上も集まった巨大団地で、そこに300世帯以上の入居者が暮らしていた。
棟ごとの作りが同じせいで部外者には団地の風景はどこも同じように見えるらしいが、ここで生まれ育ったおれには違いがはっきりとわかる。外壁のひび割れ具合、表に放置されたゴミや植木鉢、駐輪場の自転車の並び、さまざまな落書き、窓に貼られた新興宗教のポスター、ガムテープで補強されたガラスのひび割れ。あるいは、いつもベランダに佇んでいる痴呆老人、屋内から漏れ聞こえてくる罵り合い、子どもたちの叫び声。そういったすべてが棟を見分ける目印になるのだ。
公衆トイレは団地の南側にある中央公園に面したところ、管理事務所や集会所の並んだ一帯の裏手にあった。おれの部屋からはちんたら歩くと五分もかかる場所だ。今のおれには気の遠くなるような距離に感じられたが、一瞬でも括約筋を弛めたらおしまいだった。おれはケツの穴をきゅっと引き締め、できる限り振動が少ないやり方で、まるで競歩の強化選手みたいに団地を駆け抜けた。
22号棟を回り込んで、27号棟と32号棟の間の細道を通りすぎる。敷地内にある保育園の裏を抜けてバス通りに出ると、団地の南北を分断するように流れる猫曾木川に沿って200メートルほど進む。橋を渡り、48号棟の裏庭を斜めにつっきって左を見ると、ようやく中央公園が目に入った。ほとんど日陰のできない公園だか、よく見ると遊具の物陰でおっさんが涼んでいた。寝ているように見えるが、死んでいる可能性もあった。前にもそういうやつがいたのだ。
いずれにしろ、今はかまっている暇はなかった。フェンスで囲われた球技用広場の脇を通って、管理事務所の裏に回るとトイレはすぐそこだった。ぎりぎりだった。ケツの穴のすぐそこのところで、排泄物が鬱憤の溜まった囚人たちみたいに暴動を起こしてやろうと待ち構えていた。
一つしかない個室のドアを体当たりするように押し開けると、鍵を閉める余裕もなかった。体を半回転させしゃがみ込みながらズボンを下ろすと同時に、火災現場に駆けつけた消防車の放水みたいにケツからそれが吹き出した。勢いのあまり、つんのめって前の壁に顔をぶつけそうになるほどだった。
いったん放出がはじまるともう留まるところを知らなかった。おれはさながら正面ゲートを破壊された収容所だった。解き放たれた囚人たちが我先にと出口に殺到し、次から次へと外に飛び出していった。そのたびにゲートは無理やり押し広げられて傷ついた。おれはなす術なく、ただ便器の上で汗だくになり、エスプレッソマシンみたいにかたかた震えながら収容所の崩壊を見守るしかなかった。
最初の波が過ぎたあとも囚人たちの小グループが何度かに分けて出口に押しかけ、そのたびにおれのケツは汚水の間欠泉みたいに濁ったシャワーを噴き出した。やがてピークを越えた頃には、おれは体中の水分という水分が抜け出てしまったのではないかと思うほどぐったりしていた。道端でもらすという最悪の事態は回避できたが、ただ座っているだけで息切れがした。しばらく身動きがとれそうになかったが、まだ残党どもが奥の方に留まって出るか出まいか相談している気配が感じられた。もう少しここで座っていた方がよさそうだった。汗で肌にべったり張りついたシャツが不快極まりなかった。
そのとき、おれはとんでもない事実に気がついてしまった。紙がない。紙がなかった。この個室には、トイレットペーパーがただの1平方センチメートルもなかったのだ。ホルダーは芯ごと空になっており、すぐ上についてる予備ホルダーもすっからかんだった。嘘だろと思って無駄にカバーをかぱかぱやってみたが、マジックみたいにどこからともなく紙が転がり出てきたりはしなかった。急に目の前が暗くなったが、それは怒りのせいか、絶望のせいか、あるいは脱水症状のせいか、自分でもわからなかった。
おれはすぐに誰かが盗ったのだと結論づけた。根拠がないわけではない。ここの住人は手癖の悪いやつばかりで、それがこの貧乏団地が近隣住民から疎まれる理由になっているくらいなのだ。慌てて部屋を出たせいで、おれはハンカチの一つも持ってなかった。大声を出して助けを呼ぶという考えが頭をよぎったが、管理事務所にいる重松のおっさんにわざわざおれの窮地を知らせたくなかった。重松のおっさんは長年この団地で管理の仕事をやっているハゲ親父で、人の不幸が三度の飯より好きという人間だ。ちょっとドアを開ければ中から不幸が雪崩のように転がり出てくるような家だらけのこの団地で働いてるのも、それが高じてのことではないかと思えるほどだった。おれは今おれの身に起きている悲劇に尾ひれをつけて言い触らされ、笑いのネタになどされたくなかった。
清掃用具入れもないトイレだったが、よく探せば紙の代わりになるものが何かあるかもしれない。そう思ってこっそり個室を出てみようとしたところで、窓の外から男女の笑い声が聞こえてきた。おれはびびってわずかに浮かせたケツを再び便座に下ろした。今のおれにはそれだけの動きすら重労働で、もう一度立ち上がる気力はすぐには出なかった。
最後の手段でハクのやつに頼ることにした。唐谷伯嗣は言ってみればおれの幼なじみみたいなものだ。この団地の住人ではないが、すぐ近くにあるおれの師匠の家に住んでいる。師匠というのはハクの祖父でもある今は亡き唐谷泰山剣道範士八段のことで、その唐谷泰山はハクにとっても師匠だった。おれとハクは、小学生のときに師匠が開いていた剣道道場で出会ったのだ。道場といっても、このすぐ裏にある団地の集会所が道場代わりで、師匠はそこで子ども相手に剣道を教えていた。まだこのトイレが和式だった頃の話だ。
師匠は尊敬に値する武道家だったが、孫なみに若い女の尻を追いかけていたときに車に跳ねられた。それで死んだわけではないが、武道家としての寿命が少なからず縮んだことには間違いなかった。師匠はその数年後にぽっくり逝き、孫であるハクに小さな一軒家を残したのだ。師匠は、親と折り合いが悪く、おまけに社会性まで欠如したハクのことを昔から心配していたのだ。
携帯のメッセージアプリで緊急事態を知らせると、現在無職のハクからすぐに反応が返ってきた。誰かがトイレに入ってきたときのことを考えてそのままアプリで簡単に事情を説明する。トイレットペーパーを持ってきてほしいことを伝えると、少し間を置いて爆笑を表すスタンプが送られてきた。おれからすればまったく笑いごとではなかったが、どうしようもなかった。お袋も揃って下痢というところがハクにとってはツボだったらしい。
おれはハクの家のトイレットペーパーの在処まで丁寧に説明してやった。もちろんあいつの家のことなのだが、あいつは整理整頓ができないタイプで、おれの方がどこに何があるか詳しいくらいなのだ。すぐにうるせえよと今度はそっけない返事がくる。あいつが家で一人で呆れてるのが目に見えるようだったが、念のためだ。マジで持ってきてくれよと頼み込んだが、もう返信はなかった。
助けが来るまで便座の上でじっとしているしかなかった。泥だらけのケツが周りからだんだん乾いてくるのが感じられた。人の用足し後のケツを舐める妖怪がいるなら出てきてほしいくらいだった。おれはハクのやつが面白がってトイレットペーパーを持ってくるのをやめたり、途中で他のことに気をとられて忘れたりしなければいいがと案じた。いかにもあいつがしでかしそうなことだからだ。
そのとき、トイレの入口ドアが開くと同時に、期待していたのとは違う、野太くてどこかひけらかすところがあるような声が狭い空間に響いた。
「やりとりは全部スクショしとけよ。何が脅しに使えるかわからないからな」
「あいっす。今日の女はどうするんすか?」
「ウリだな」
「風俗?」
「当たり前だろ」
どちらかが小便器の前に立つより早くチャックを下げる音が聞こえ、男たちは下品に笑いながら連れションをはじめた。二人組のようだった。何やら物騒な話題に感じられて、おれは余計なことに関わるまいと息を殺してやりすごすことにした。男たちは個室におれがいることには気づいてないようだった。
「シバさん、そいつとやったんすか?」
下っ端らしい方が言うと、シバと呼ばれた男はそれには答えずに鼻で笑った。
「そらそろ目が覚めるだろうからお前が相手してやれよ」
「いいんすか?」
下っ端の男は本気で喜んだようだった。その間も小便は水道の水を無駄遣いする男のように音を立てて出続けていた。
「すげーたまってるわ」
シバという男は、どこかの女の意識を奪い、さらうか何かしたように思われた。おれはこのまま聞かなかったふりをするべきか気持ちが揺れたが、下痢が完全に収まっていない今の自分にできることは極めて少ないことはわかっていた。
「メンヘラだぞ」シバという男がこき下ろすように言った。「なんかやばいんだわ。自分は狐憑きだとかなんとか言って」
「キツネ?」
「ビョーキだろ、ビョーキ。そういう女の方が扱いやすいっちゃそうなんだが」
「はぁ」
そのわかったようなわからなかったような相槌から、下っ端の男はいくらか頭の鈍いやつらしいと察せられた。推察される所業にもかかわらず、どこかやりとりがちぐはぐで滑稽なところがある二人組だった。小便の音がようやくやむと、シバという男が一仕事終えたかのように深く息を吐いた。
「六時間ぶっ通しで運転だったからな」
「ヤバイすね。どこの女なんすか」
「徳島」
「あぁ。聞いたことある」
徳島も知らないのかと思い、おれは目の前の板壁を見つめた。徳島。四国の右上。いや、右下か。正確な位置はおれも怪しかったが、いくら何でも県名くらい知ってるだろう。それを、聞いたことある。次第におかしくなってきて、おれは折り曲げた肘の内側に鼻と口を埋めた。
「四国な」
「あぁ」
シバが突っ込むわけでもなく単純に教えてやってるのが余計に笑いを誘った。おれは何とか堪えた。だが、緩み切ってしまったケツの穴の方は、おれの意思の及ぶところではなくなっていた。
ぶじゅびーっ!
おれのケツの穴から、笑いの代わりに長たらしくも場違いな屁がもれた。収容所の残党をまとめて放出する下痢便混じりのやつだ。
その途端、ドアの向こうの空気が一変し、会話がぴたりと止んだ。
「おい、誰だ」
シバの声は調子に乗って喋ったのが裏目に出たことを他人のせいにするみたいにムカついていた。
「出てこいやこら!」
下っ端の男がさっきまでとはうってかわって、やたら攻撃的になって個室のドアを蹴ってきた。予想外の強烈な一撃に、おれは便座から尻を5ミリほど浮かせた。二発目がくると、蝶番のビスがわずかに浮き上がるのが見えた。
まずい状況だった。事情を説明したところで、連中はトイレットペーパーを取ってきてくれるような親切心など持ち合わせていないだろう。ケツを拭かないことには出ようにも出られなかったが、おれが聞いてしまったことは明らかに犯罪に類していた。やつら自身が冗談に決まってるだろうとごまかしてくれればひとまず合わせてやれないこともなかったが、そういう駆け引きを好む連中でもなさそうだった。あるいは、単に人をいたぶるのが好きで、そういう機会を見つけたら逃さない習性なのかもしれない。
「いつまでもくそしてんじゃねぇぞ!」
ドアが激しく揺らされる。おれのくそは要求に反していつまでも出そうだったが、このままでは何分ともたないだろう。ドアを破られたら受けて立つしかないが、相手は二人で、なおかつこちらは狭い密室に閉じ込められている。下痢のせいですでに体力を使い果たしていることもあるし、控え目に言っても不利だった。
おれは、個室内についているおれが子どもの頃からいつもわずかに開いていて虫が入り放題の窓から脱出を試みることにした。壁に手をついてなんとか立ち上がり、ズボンをそろそろ引き上げる。普段はきれい好きなおれがそんなことをするなんて自分でも信じられなかったが、拭かないまま履こうというのだ。ケツについたくそを避けるように慎重にズボンをあげていく。だが、それも限界があった。どうしてこうもはっきりくそがズボンについたことがわかってしまうのかは信じがたいほどだった。一度生地についてしまうとあとはどうにでもなれという気になり、残りを一気に引き上げた。
便座の上に乗りあがり、窓をそっと開け広げる。外を覗くと眼下の壁沿いにはつつじが植えられていて、飛び越すのは難しそうだった。いったん顔を中に戻す。視界の隅にくそで溢れかえった便器がちらりと見えたが、直視はできなかった。ドアが激しく揺らされ続けているせいで流している余裕もなかった。二人組はおれのくそたちに出迎えてもらうしかなさそうだった。
おれはなるべく音が立たないようにタンクに足をかけて窓枠を掴み、いつもより何倍も重く感じる体を持ち上げた。できるなら足から地面に下りたかったが、向きを調整する時間的、体力的かつ空間的な余裕がなかった。おれはそのまま腹を窓枠につけると、あとは頭を下にして重力に任せる形で表に転がり出た。受け身は形ばかりのものだったが、枝がクッションになってくれてたいしたダメージは受けなかった。
やつらが回り込んで来る前に何とか姿をくらませたかった。起き上がって路上に目をやると、少し離れたところに悪ぶった男が好みそうな角ばったボディの白いSUVが停められていた。窓にはスモークが貼られ、車体の後部には鮫をデザインしたステッカーがついている。ふいに、車の内側から車体を蹴りつけるようなこもった音が耳に届いた。中に誰か閉じ込められているのだ。
連中がトイレでしていた話は本当だったというわけだ。おれは考えるよりも前に車に近づいていた。ハクだったらやめておけと言うだろうし、自分でも少し考えたらわかるはずなのだが、トラブルに首を突っ込まないでいられない性分なのだ。特に一方が不当に不利な立場に立たされているようなトラブルに。
取っ手に手をかけると、トランクには当然のように鍵がかかっていた。外の動きに気づいて内側からの音が激しくなる。同時に、んーんーともがくような声もかすかに聞こえた。テープか何かで口を塞がれているのだろう。手をかざして中を覗き込もうとしたがスモークのせいでかなわなかった。おれは「待ってろ」と声をかけたが、素手で窓を割れるとも思えず、キーがないことにはどうしようもなかった。
「待てこら!」
男たちがトイレを回り込んで走ってきた。トランクの中の誰かを残してその場を離れるのをためらっているうちに、あっという間に追いつかれた。
「このくそ下痢野郎。めちゃくちゃ臭かっただろうが」
下っ端の男は顔に見覚えがあった。団地で不良として知られている若いやつで、教師をぼこぼこにして高校を退学になったとか、団地のジジババどもから金をゆすり取ったとか、昔からろくな噂がないやつだ。名前は確かテツオ。
「殺してやる」
テツオは、まだ顔の回りにおれのくその臭気が漂っていて、それを振り払おうとするみたいに首を左右に振りながら言った。いざトイレに踏み込んだら便器の中が地獄絵図だったことがお気に召さなかったらしい。もっとも、あの便器は自分で見たってショックを受けるものだった。だが、流す余裕を与えなかったのはこいつらなのだ。
「おれの車に触るんじゃねえ」
シバは無断で自分の車に触れられたのがよほど面白くなかったらしく、全身に怒りを漲らせてこちらを睨みつけた。おれが手を洗ってないことも影響していたのかもしれなかった。拭いてないのだから手は汚れようもなかったが、それはこいつらには知る由のないことだった。
この二人に武術や格闘技の心得がないことは立ち方からわかったが、加減を知らないやつら特有の危なっかしい雰囲気が漂っていた。特にシバの方は人を威嚇することに慣れており、それなりに場数を踏んでいるようだった。
テツオは痩せ型でおれとどっこいどっこいの体格だったが、シバの方は首が短くずんぐりしていて、体はおれよりでかく頑丈そうで、どこか立ち上がったもぐらを思わせるところがあった。ウルトラ怪獣にいそうな感じに見えなくもない。木刀の一本でもあれば話は別だが、近くには武器になりそうなものもなかった。普段ならともかく、エクレアに当たって体力ゲージが残り1くらいの今の状況で、しかも二対一とあってはさすがに厳しかった。
シバとテツオは呼吸を合わせるでもなく襲いかかってきた。おれはいったん車から離れて背後のスペースを確保した。一人をダウンさせて一対一に持ち込めば何とかなるかもしれなかったが、策らしい策は思いつかなかった。
テツオが拳を振りあげて殴りかかってきた。おれは半身になって攻撃の軌道をかわし、相手の肘と肩を押しやるようにしてパンチを流す。バランスを崩したテツオに後ろから仕掛けようとすると、シバが飛び蹴りで割って入ってきた。おれは後ろに跳ねてかわすが、シバは右、左と蹴りを連発しながら追ってくる。足や肘を使ってカットするが、体格差と下痢のせいで一つひとつの攻撃がやたら重い。押されているうちにテツオも加わってきた。距離を詰められないように後ろに引きながら攻撃をさばくが、反撃の余裕はなかった。ガードをすり抜けてきたテツオの拳が耳に当たり、勢いに負けて片膝をつかされたところへ、シバが腹に前蹴りをぶちこんできた。下っ腹にもろに食らった衝撃で奥の方にまだ残っていたものがケツの穴から飛び出した。ぶびびーっ!
「おわっ! しやがった!」
テツオが驚いて飛びのく。
「下痢なんだよ」
おれは腹を押さえながら、倒れないように踏ん張った。二人相手に地面に抑え込まれたらおしまいだ。ズボンにくその染みがじんわり広がる何とも不快な感覚があったが、屈辱を感じる余裕はなかった。テツオはともかく、シバの方は手を緩める気配がなかったからだ。そのシバを見て、テツオも気を引き締め直した。
二人が再び攻め込んでこようとしたそのときだった。脇からトイレットペーパーが二つ飛んできて、シバとテツオの横っ面にヒットした。こぼれ落ちたトイレットペーパーが路上に白線を引きながら数メートル転がる。シバとテツオは一瞬面食らったが、何が当たったのか見て取ると屈辱に顔を歪めた。
ハクだった。
「どうなってんだ。お前のくそが敵に変身して襲ってきたのかと思ったぜ」
「来ないかと思ったぞ」
「それも面白そうだと思ったけどな。おれが同じ状況になったときに助けてもらえないと困るから恩を売るつもりで来てやった」
「よく言うよ」
「ホントのこと言うと、トイレットペーパーの場所を教えてくれなかったらやばかった」
「やっぱりな」
「大丈夫か? あの女にふられたときみたいにげっそりした顔してるぜ。なんだっけ、あのメイドカフェの」
「ナメてんのかこら!」
シバが苛立ちもあらわに遮ってきた。自分がおれのくそに喩えられて怒り心頭のようだった。おれはそうじゃなくてもこいつらはくそ野郎だとわかりはじめていた。女をさらって風俗に売り飛ばすようなことを生業にしているやつらなのだ。
「その寝癖野郎もまとめてボコってやる」
「寝癖だぁ?」
今度はハクが苛立つ番だった。ハクは確かにイギリスの前首相ボリス・ジョンソンみたいな、一見ぼさぼさに見える髪型をしていたが、自分ではそれをチャームポイントだと考えていたし、髪型を貶されることを何よりも嫌った。おれみたいにわざわざ他人のトラブルに首を突っ込む癖はないハクだったが、売られたケンカは必ず買うやつだった。物言いが率直すぎるハクの方が先に自覚なく相手を侮辱していたというケースも多々あるのだが。数から言えば、おれよりもハクの方が人とトラブルになることがずっと多い。
「壮也。偏見は持ちたくないが、こいつらはどこからどう見ても悪者に見えるぜ」
「ワルなのは保証する。車に人が閉じ込められてる」
おれは路肩のSUVを顎で指して小声で付け足した。ハクはちらりとそちらに目をやって確認する。
「なるほどな。お前はまたトラブルを呼び込んだわけだ。手こずるような相手なのか?」
「下痢のせいでな」
「その言い訳には正当性があると認めてやるぜ。紙ももってきてやったし、助太刀もしてやるんだから二回分の貸しだぞ」
「悪いな」
おれは体勢を立て直して連中と向き合った。こいつらが悪者に見えるとすれば、おれとハクはどこからどう見ても中高年ワーキングプアに見えるだろうが、そのことはわざわざ言わないでおいた。
「そういや、お前──」
ハクは自分が放り投げたトイレットペーパーにちらりと視線をやると、何か恐ろしい事実に気がついたというようにおれの顔を見た。
「拭かないで出てきたのか? いや、言わなくていい」
「あとで説明させてくれるんだろ」
「多分な」
「いい加減にしろ、じじいどもが。殺してやる」
シバが青筋を立てながら指の関節をぽきぽき鳴らし、いきり立ってハクに突進した。ハクは勢い任せのパンチを冷静にかわし、あとの攻撃も右に左になぎ払っていく。軽快なフットワークは祖父譲りのものだ。
一歩遅れてテツオががなりながらおれに突っ込んできた。おれは膝を狙った蹴りで相手の勢いを殺したが、テツオはそれでも前に出てきて顔面めがけて拳をめちゃくちゃに振り回してくる。おれは両手のガードを上げつつ上体をしならせるようにしてそれをかわし、攻撃後の隙を狙って細かくジャブを当てる。苛ついたテツオが蹴りを大振りしてくるとバックステップでかわした。相手の爪先が横っ腹にかすっただけと思ったが、自分でも思った以上に機敏さが失われていて、かわしきれていなかった。
「ぐあっ」
内臓にくるダメージを感じて動きが止まったところへ、テツオが大学のアメフト部みたいになりふりかまわずタックルしてきた。腰に腕を回されてバランスを崩されたが、なんとか倒れざまに相手の後頭部に肘を打ちおろした。地面に倒れると同時にやつの手が離れ、おれは組み敷かれる前に横に転がって何とか抜け出す。
「大丈夫か?」ハクから声がかかる。
「あぁ」
おれは答えながら相手の死角に回り込み、四つん這いで頭を軽く振っているテツオの側頭部を狙って全体重を乗せた膝蹴りをかました。手応えがあり、テツオは気を失って地面に突っ伏したが、おれもそのままアスファルトに倒れ込んだ。
少し動いただけで息が切れてしまい、すぐには加勢できそうになかった。おれは地面にうつ伏せになったまま顔だけ横を向いてハクの方を見た。
シバが執拗に攻撃を繰り出していた。ハクは防戦一方のように見えるが、すべての攻撃をきっちりガードし、うまく相手と距離を取って詰めさせなかった。相手の苛立ちを誘っているのだ。シバは自分の体力が削られていることに気づいてない様子でひたすら攻め込んでいく。相手の攻撃は重いが、ハクは衝撃をうまく逃がしていた。
「ちょろちょろするな、寝癖野郎!」
「また言ったな」
ハクは簡単に挑発に引っかかり、策を台無しにするかのように前に出た。そこへシバの強烈な右フックがガードを突き崩してハクの顔面に当たり、ハクはわずかによろけた。落ち着けと言いたかったが、腹に力が入らず、でかい声が出せなかった。シバは好機を逃すまいと続けざまに攻撃を浴びせ、ハクは何発かもらった。おれは加勢しようと気力を振りしぼって起き上がった。
シバが一気に決めようと顎を狙った回し蹴りを放ったとき、ハクは冷静さを取り戻した。いや、最初からそれを狙っていたのかもしれないが、ハクに挑発に乗る振りなんてできるかどうか怪しいからたまたまかもしれない。
ハクは身を低くして蹴りをかわすと、低姿勢のまま流れるように相手の懐に潜り込んだ。そのまま半回転するようにして相手の背中に回り込むと、腕を腹の前に回してがっちり組む。踏ん張りをきかせてシバのずんぐりした体を抱えあげ、そのまま虹を描くように後ろにそり返った。ジャーマン・スープレックスだ。一連の動きはまるで解説動画の模範演技のように淀みがなく、シバは受け身も取れなかった。
アスファルトに後頭部を強打する鈍い音が響くと、二人ともそのままたっぷり十秒も動かなかったみたいに感じた。意識を失ったシバの体から力が抜け、下の角をすくいとられた杏仁豆腐みたいにくにゃりと崩れ落ちた。ハクはそれを横に押しやるようにして抜け出すと、よっと立ち上がり景気よく手をはたいておれににやりと笑いかけた。
「ドニー・イェンだな」おれは技の出典を確かめた。
「『フラッシュ・ポイント』。中盤に出てくる大技だ。一度試してみたかったんだ」
「あの映画は傑作だよな」
「当たり前だぜ」
その映画の中でドニー・イェン演じる刑事が悪党の背後にとんでもないスピードで回り込み、強烈なジャーマン・スープレックスを決めるシーンがあるのだ。ハクはそれを試す機会を伺いながらやり合うだけの余裕はあったらしい。
おれとハクは小学生のときから格闘技映画のファンだった。古今東西のその手の映画を片っ端から見ては、コマ送りにするなどして技を研究し合ったものだ。派手な技を現実の試合や喧嘩で決めるのは無理だとか何とか言いながらも、そうやってお互いのスキルを磨き上げていった。
ハクは頭もよかったから偏差値の高い有名大学に行ったが、おれにはそんな可能性は金のエンゼルが三回続けて当たるほどにもなかった。かといって師匠みたいに武道家としてやっていけるわけもなく、映画ファンが高じてスタントマンを目指したというわけだ。それで今のおれが何をしているかといったら、ヒーローショーなんかで着ぐるみをかぶるしがないスーツアクターだ。それも悪役専門の。年がいってることと、きちんと受け身が取れるという、真っ当な理由によってだ。ヒーロー役をやるには顔がまずいというのもあるかもしれなかった。着ぐるみで見えないとはいえ、見た目は何にでも影響するのだ。ともかく、ヒーローショーの仕事は不定期で稼ぎも少なく、おれはいまだに自立できずにこの猫曾木団地に縛りつけられているというわけだ。
「こいつらはどこからわいて出たんだ」
「あっちは見覚えがある。この団地のやつだ」おれはテツオを指しながら言った。「もう一人は知らんが、まだ他にも仲間がいるかもしれない」
「関わりたくない連中だな」ハクは顔をしかめながらシバとテツオを見て言うと、おれに向き直った。「それでお前は下痢ピーのくせにお姫様を助け出す勇敢な騎士になりたいと思ったわけか」
「そういうわけじゃない」
「そういうわけなんだよ。まったく相変わらずお前は自分を買いかぶってるぜ」
反論できなかった。映画の見すぎでおれに夢見がちなところがあるのは事実だった。映画の主人公だったらどうするとか、映画だったら次はどうなるとか、何でも映画を基準に考えてしまうのはおれの悪い癖だった。ハクも同じだけ映画に夢中だったはずだが、やつはおれよりずっと現実的で、なぜそういう違いが生まれたのかおれにはわからない。
「そんなことより、お前──」
ケツの辺りに視線を感じておれはいやなことを思い出した。ハクが目を細めてこちらを見ていた。
「わかってるから言うな」
「泥水に座り込んだみたいになってるぜ」
「腹を蹴られた拍子に残りが出ちまった」
さっきより余裕ができたおれは、恥じ入りながらケツに貼りついたズボンの生地を引っ張った。そのねとついた感覚がまた不快極まりなかった。
「くそっ」
「まさにな。お前が自分を買いかぶってると言ったのは取り消すよ。先に着替えてくるか?」
ハクなりに気を使っての発言だったがおれは黙って首を振った。閉じ込められている女はおれなんかよりよっぽど酷い目に遭っていて、一刻も早く解放されたいはずだった。
おれはくそを漏らしたという事実に打ちのめされながらシバのズボンのポケットを探り、車のキーを取り出した。キーにはドクロのキーホルダーがついていて、頭頂部の突起を押すと目のところが紫色に光った。うんざりする趣味だった。一緒に出てきた財布に入っている免許証を確かめると石橋佑士とあった。どうやらイシバシの真ん中の二文字を取ってシバと言っているらしい。おれはどこか歪んだ自己愛を感じながら財布を元に戻した。
ステッカーのサメやキーホルダーのドクロに憂鬱な気持ちになりながらトランクを開ける。乱れた長い髪が顔の半分を覆っている女が、髪の毛の間から恐れるような助けを求めるような目でこちらを見上げていた。口はテープでふさがれ、手もやはりテープで後ろに結ばれている。本当にどこかに売り飛ばされようとしていたのだ。腹の底が怒りで熱くなるのを感じたが、おれはそれを表に出さないように努めた。
「もう大丈夫だ」
そう言うと彼女はおれとハクを見比べ、おれたちは怖いやつじゃないと表情と仕草で示した。おれたちがただのイケてない貧乏中年にしか見えないことに気づいたのか、彼女は口を突き出すようにして息が苦しいことをアピールをした。おれはテープの端を掴んで引っ張ったが、粘着面に髪の毛が絡みつき、彼女は毛を引っ張られる痛みに顔を歪めた。テープが剥がれると彼女は思い切り息を吐き出し、胸を激しく上下させてあえいだ。
手の方も早くほどいてやりたかったが、おれは彼女の呼吸が少し落ち着くのを待った。彼女にとっては心外かもしれないが、酸素を求めてあえぐその様はどこか魅惑的で甘美ですらあり、おれは夢で繰り返し見たような救出劇から飛び出してきた美女が今まさに目の前にいるような感覚に陥った。
おれは、彼女がまさにおれの好みの女だと悟るのと同時に、隣にいたハクが彼女がいかにもおれの好きそうなタイプだと直感したのも感じた。嫌みを言うのは後にしろとハクに無言の圧をかけると、やつは面白くなさそうに片方の眉を吊り上げてみせた。
「あいつは?」
彼女が怯えたように聞いた。
おれは振り返ってシバが倒れてるところに彼女の視線を誘導する。シバは地面に倒れたままぴくりともしなかった。彼女の顔から恐怖が次第に消えていき、改めておれとハクの顔を見比べた。おれたちが金はないかもしれないが安心をもたらす男だとわかったのか、その顔にかすかに微笑みが浮かんだ。その途端、彼女は不快そうに眉根を寄せた。
「なんか、臭くない?」
おれは死神に背後から忍び寄られて首を絞められたみたいに喉が詰まるのを感じた。彼女の視線がにおいの元を探り当てたようにおれに向くと、おれの口の中はお袋がベランダで育てようとしたミニトマトの鉢植えみたいに完全に乾いてしまった。
「こっちもいろいろ訳ありでね」
ハクが笑いをこらえるようにしながら割って入った。おれは一歩下がってなんとか威厳を保とうとしたが、一気に彼女から5キロも遠のいたみたいな気分だった。においが届かないようにそれくらい離れたい気分でもあった。それもこれも腐ったエクレアを食わせたお袋のせいだ。
「とりあえずそこから出るか?」
彼女はうなずき、後ろ手に拘束された手を上向きにするように身体をひねった。ハクがトランクの縁に腰かけ、手首にぐるぐる巻きにされたテープをべりべり音を立てながらほどいてやった。
まもなく、彼女は長時間狭いところに閉じ込められていたなんて嘘としか思えないような軽やかさでトランクから飛び出ると、猫曾木団地の地面に着地した。白無地の半袖Tシャツに細い足にぴたりと張りついたジーンズというラフな格好だが、長い髪をシャンプーのコマーシャルのようになびかせ、肌の白い手足はすらりと長いその様は、まるで四国からやってきた妖精だった。彼女の着地点から、貧困と倦怠とシケた犯罪にまみれた猫曾木団地の土地に、浄化の環が拡がっていくみたいだった。
おれはこれから巻き込まれる事件のことなど、まだ何もわかってなかったのだ。
いただいたサポートは子供の療育費に充てさせていただきます。あとチェス盤も欲しいので、余裕ができたらそれも買いたいです。
