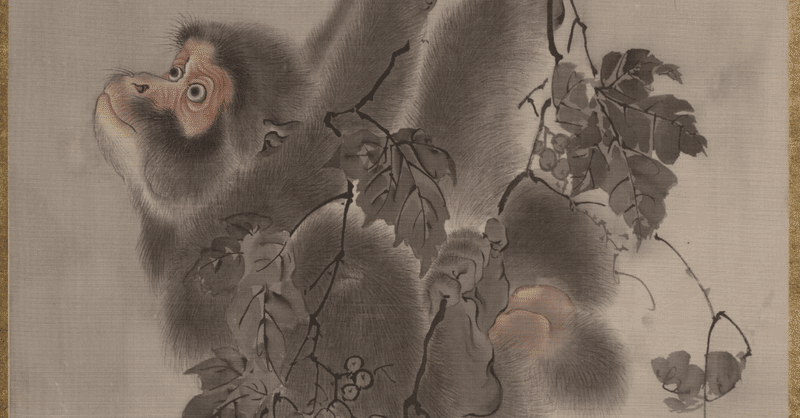
【短編小説】馬鹿も食わない!
犬も食わないものは馬鹿も食わない。
三人組シリーズの世界線の話ですが、独立した話です。
「あーやっと終わったー」
うんと伸びをしてシャーペンを机の上に放り投げる。そこには全ての欄が埋まった紙が一つ。
「ホント苦労したわー。まったく先生もさ、もうちょっと宿題減らしてくれればいいのになー」
俺バカだから余計に時間かかるんだよなーと間延びした独り言が部屋に落ちた。
何度も何度も書いては消し、唸りながら無い頭を振り絞って、やっとのことで全部埋められたのだ。
頭の中で、もうちょい早く終わらせろよと幼馴染の少年の呆れた声が聞こえた気がするがそれは右から左に流そう。終わればいいのだ、終われば。
長時間机にかじりついていたせいで肩が凝っている。首を回して光太は立ち上がった。
さて、これで今日やるべきことは片づけた。あとは全部自由時間だ。
「よっしゃ、これでゲームできる」
はやる気持ちを抑えつつ引き出しからゲーム機を起動させ、傍らの布団に飛び乗ったその時だった。
「なあ聞いてくれよー」
突然ドアが開かれる。そこに立っていたのは黒髪黒目に人付き合いのよさそうな爽やかな青年だった。しかし今はその形の良い眉はすっかり下がり、なんとも情けない弱りきった表情を晒している。
ノックもせずに部屋に入ってきたのは年上の従兄火上響だ。とはいっても彼が突然部屋に来ること自体は何の不思議もない。
実は光太の家と響の家は向かい合って建っており、二人はまるで自分の家のように互いの家を行き来するからだ。だからこのように何の連絡もなくこちらの家にいるのはよくある。
しかし、しかし、だ。
「だけどノックくらいしてもいいんじゃないですかねぇ。ほら親しき中にもレーギありっていうじゃん」
「えー俺とお前の仲じゃーん。それよりさー聞いてよ」
くねくねと体をくねらせながらこちらににじり寄ってくる。
うわメンドクサ。光太は冷ややかな目で従兄弟から距離をとり、ゲームを安全なところに避難させた。
「俺、今からゲームやる予定なんだけど。お前の話きくヒマないから帰ってくれない? もう聞き飽きたし」
「ええーそんなこと言うなよ。まだ一言も喋ってないのにさ」
「言わなくてもわかるから言ってんだよ」
この後続く言葉は分かっている。一週間前くらいからずっと同じことを言い続けているからだ。
あからさまに顔をしかめた光太を無視して響は続ける。
「どうしたらいいと思う? もう一週間前から連絡きてないんだよー。どうしよう、このままだと自然消滅するじゃん」
手足をバタバタさせて床に転がる彼は悪い意味で歳不相応だ。
幼稚園児みたいな情けない姿を晒しているのが自分の従兄弟かと思うと、頭が痛くなる。
光太は苛立ちも隠さずに声を荒げた。
「だーかーら、お前から連絡すればいいって何度も言っているだろ! 別れるのがイヤなら早くやれよ!」
そうこの従兄弟は彼女がいるのだ。セミロングの毛先がくるんと丸まった清楚系の彼女が。学校でも人気の美少女である。
二人は一年前から付き合っていて相思相愛のカップルだった。
幼馴染たち曰く、いわゆるシオドリだかオシドリ夫婦みたいなものらしい。いつも学校でいちゃついている彼らを見るたびに、砂糖吐きそうと同じタイミングで顔をしかめる幼馴染たちの顔が浮かぶ。
お前らはまだいいほうだろ。光太は心の中で愚痴った。
こちとら付き合った当初から部屋まであがりこまれて、ずうっとずうっと惚気を聞かされてうんざりしているのだから。
プライベートは侵されず、学校で、しかも学年が違うため会う機会の少ない二人はまだ運がいいほうだろう。
と、そんなラブラブな二人にも最近暗雲が立ちこめている。
聞くところによると、互いに部活やらテストやらで会う機会が減っているらしい。とはいってもそれ自体は珍しいことではない。去年も互いに忙しい時期は存在した。
ただ去年はクラスが一緒だったのですれ違うこともなかったのだが、今年はクラスが端と端。つまり一番遠い場所になってしまった。そのためすれ違いも多くなり、諍いも増えた。
それでもいつもはすぐに仲直りするし、何より会えない夜は彼女の方からラインを入れてくれたりするのだが、ここ一週間それが途絶えているのだ。本当に何の音沙汰もないらしい。
いつもくるはずの連絡が来なくなり、コイツは彼女と自然消滅してしまうのではないかと毎晩毎晩光太の部屋でギャーギャー騒いでいる。
「いや、今まで俺からしてこなかったからそういうのって恥ずかしいじゃん!」
顔を赤らめてキャーと叫ぶ従兄を光太は冷ややかに眺めた。同性の従兄弟の恥じらう姿なんてどこに需要があるのだろうか。少なくとも自分にはない。
「じゃあ別れることになるけどいいんだ?」
「それはイヤ!」
光太は深くため息をついた。
実はなぜ彼女から連絡がこないか知っている。なぜなら幼馴染の少女、さくらの姉が彼女と友達だからだ。
さくら経由で聞いた話によると、どうやらいつも彼女からしか連絡してこなかったので本当に好きなのか不安になってしまったらしい。だからコイツの愛情を試すために連絡を絶っているのだ。
本当にくだらない。コイツがただ変な意地をはらずに連絡すればすむ話なのに、なにをこんなにグズグズしているんだろう。
テストは自分よりもずっとできるのに、なぜ自分でもわかる簡単なことができないのか理解に苦しむ。
「いいからさっさと連絡をいれろ!」
「痛った! お前いきなり蹴とばすなよ」
うじうじ面倒くさい背中を思い切り蹴とばした。従兄はよろめき、非難の声を上げたが、その目には未だに迷いが見える。
「え、えー、でもなんて打てばいいか……」
所在なげに視線をさまよわせる従兄に舌打ちをしなかった自分をほめてやりたい。
「なんでもいいだろ! 最近会えてないけど元気? とかテスト近いから勉強一緒にしない? とかさ」
「えっ、そんなんでいいの? でもさぁ、こう、やっぱり心の準備というか……」
いい加減堪忍袋の緒が切れそうだ。周囲の人々からは気が長いほうと言われるが、流石にもう耐えられそうにない。
光太は珍しく外まで響き渡るような大声を出した。
「いいから、さっさとやれ!」
「ハ、ハイ」
こちらの剣幕に押されて従兄弟は慌ててポチポチとスマホを打ち出す。
「打ったけど、これで何も来なかったらどうしよう」
「いや多分くるだろ」
この期に及んで何を言い出すんだコイツ。自分の彼女くらい信じてやれ。
呆れ返ったその瞬間だった。
ピロン
「あ」
「ほらきた。確認すれば?」
ちょうどいいタイミングで軽快な通知音が鳴り響いた。もたつきながら響はスマホを確認する。画面を追っていくうちにみるみる顔が明るくなっていくのを見て、光太は密かに安堵の息を吐いた。
「あっ本当に返事きた! ありがとな。じゃ、帰るわ」
「はいはい。とっとと帰れ」
シッシと手を振って従兄弟を追い出す。とはいっても彼はこちらをろくに見もせずに、騒がしい足音を立てて風のように去っていった。
再び一人に戻った部屋の中に疲労と安心の混ざったため息が響き渡る。
まったく人騒がせな従兄弟だ。ああ、これでゲームに集中できる。
「あーやっとうるさいのが帰った」
光太は大きく伸びをした。滞在時間は僅かだが、どっと疲れが押し寄せてきた気がする。
「まあ明日にはまた惚気話に付き合わされるのだろうけど」
だが別れてうじうじされるよりも、惚気で幸せそうにしてくれたほうがいいか。
光太は口元を緩めて、床に転がっているゲーム機に手を伸ばした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
