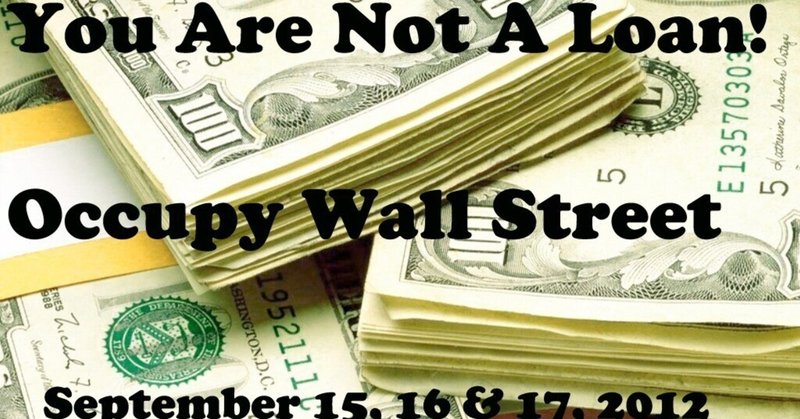
映画が描くバブルの実相とメンタリティ<3>『インサイド・ジョブ 世界不況の知られざる真実』~バビロン再訪#17
リーマンショックの内実を描いたアカデミー・ドキュメンタリー映画賞受賞作
2008年のリーマンショックの際、日本でもディベロッパーやゼネコンの倒産が相次いだ。80年代バブルの影響が少なく、急拡大、急成長を誇っていた新興ディベロッパーや中堅ゼネコンがバタバタと潰れていく様子は「突然死」と呼ばれた。
「突然死」の理由は、開発の失敗や保有資産の値下がりや営業赤字ではなく、世界的な信用収縮による資金ショートだった。
2000年にITバブルがはじけた後、アメリカの投資資金は有望な投資先として日本の不動産への投資を急拡大させており、ファンドを売却先とした物件やREITを受け皿とした開発(それらは不動産流動化事業と呼ばれていた)で急成長してきたディベロッパーがもろに影響を受けた。
アメリカでの出来事が、あれよあれよという間に、他国に拡大し、アメリカの住宅バブルやサブプライムローンとは全く無関係の企業に「突然死」をもたらし、世界を不況のどん底に突き落とした。
80年代バブルがドメスティックな不動産バブルだとするならば、リーマンショックはグローバルな金融バブルだ。
リーマンショックとはなんだったのか。
リーマンショックは人災。その「内部犯行」の手口とは
百年に一度といわれ、その後の世界を変えた、この大掛かりな崩壊劇の内実を知りたい人にとって、ドキュメンタリー映画『インサイド・ジョブ 世界不況の知られざる真実』(チャールズ・ファーガソン監督 2010年)は必見だ。その「内部犯行」の手口の一部始終をサスペンスフルな語り口で解き明かしてくれる。アカデミー長編ドキュメンタリー映画賞を受賞した。
アメリカは日本とは異なり人口増加社会だ。毎年約1%ずつ人口が増加している。1990年代の10年間でアメリカの人口は3,000万人増えている。その多くがヒスパニック系だ。旺盛な住宅需要に支えられ、アメリカの住宅価格は2001-2007年で約2倍になっている。
ここまではいい。健全な実需だ。あるいは単なる住宅バブルだ。
住宅バブルはいつかははじけ、住宅ローンは焦げ付く。ここまでもいい。価格下落で仕入れた土地が売れず不動産業者が返済不能に陥り、貸し手である金融機関が不良債権を抱える。よくある話だ。日本の80年代バブルはこの構図だった。
問題はその先だ。
住宅バブルの崩壊が住宅ローン会社と住宅購入者という債権・債務の当事者にとどまらなかったどころか、当事者があずかり知らないところで、あずかり知らない規模で、世界中に信用とリスクをばらまいていたというのがリーマンショックだった。
その理由は証券化とデリバティブだ。
ファニーメイやフレディマックなどの住宅債権保証会社やリーマン・ブラザースなどの投資銀行は、住宅ローンを担保にした債権(モーゲージ債)をほかのローン債権と一緒くたにし、証券化を繰り返す手法で、高リスク債権が優良債権へと化けるCDO(Collateralized Debt Obligation 債務担保証券)と呼ばれる商品に仕立て上げた。
証券化のミソは、銀行などのローンの貸し手にとって返済が滞るという直接的なリスクがなくなることだ。その結果、貸し手行は返済の能力のない顧客(サブプライム)にまで貸し付ける、あるいは同じ借り手に複数のローンを組ませるなど、とにかくローンをどんどん貸し込み、手数料確保に励むことになる。
住宅の価格が上昇し続けており、よしんば借り手が破綻しても担保の物件を売却すれば債券は回収できるとの思惑が拍車をかけた。クライアントである投資銀行の要求に応じ、ムーディーズなどの一流格付け会社が、リスクの実態を無視して平気でAAAの格付けをしていたという驚くべき事実もあった。
こうしてリスクの高い債権やクズ債権が大量に作られ、いつの間にか高い格付債権に仕立てられ、世界中の投資家にばらまかれた。
さらに信用規模を拡大し、事態を決定的に深刻にしたのが、CDS(Credit Default Swap)と呼ばれるデリバティブ商品だ。
CDSはCDOの債務先が破綻した場合に保証金を受け取れる仕組みのデリバティブだ。CDSはCDOの保有者かどうかによらず購入できるため、その信用額は実際の債権額とは無関係に膨張する。いわば破綻の可能性に賭ける掛け金の上限がないゲームのようなものだ。さらには複数のCDSを束ねた合成CDO(Synthetic CDO)と呼ばれる商品まで登場し、信用の規模は幾何級数的に膨らんだ。その結果、市場に出回るCDOの内容や規模を、もはや誰も把握していないという事態へと至った。
住宅の買い手とローンの貸し手という住宅購入現場のシンプルな関係が、金融技術を駆使する投資銀行が介在することで、いつの間にか、遠く離れた顔が見えない抽象的な関係、ヴァーチャルな電子空間のなかの数字だけの関係に変容し、その結果、誰も当事者としての意識とモラルを失っていく。
バブルは人災だ。人為的出来事だ。少なくとも本作が描くリーマンショックの実態と顛末はそう物語っている。

張本人である政・産・学が一体となった金融マフィア
大恐慌を経験した戦後のアメリカは、銀行/証券の垣根がはっきりした厳しい規制市場だった。事実、リーマンショックまでアメリカでは金融危機は起きていない。
1980年代以降、アメリカは金融規制緩和に舵を切る。学者、経営者、閣僚、コンサルタントなどを渡り歩きながら、規制緩和を推し進める、政・産・学が一体となった金融マフィアとでも呼ぶべき一大ロビー勢力の姿が描かれる。
なかでも、ジョージ・ソロスの「この幻想を生み出した張本人は経済学者だ」との言葉通り、金融緩和の強力な後ろ盾になったのが、ハーバード大学やコロンビア大学などの経済学者たちだ。
グレン・ハバードは、ブッシュ大統領の経済顧問として、個人所得税の引き下げ、遺産税の廃止、贈与税の引き下げ、配当・キャピタルゲイン税の減税など、富裕層に手厚い減税政策により、富裕層の資産形成を加速し、その後の経済格差の拡大の原因となったといわれるブッシュ減税を主導した人物だ。
コロンビア大学経済学部長となったグレン・ハバードは、ゴールドマン・サックスと共同論文で「CDSは市場を安定化させ、景気後退を緩やかにする」と主張した。
クリントン政権の財務長官を務めたローレンス・サマーズは、その後、ハーバード大学学長を務め、オバマ政権の国家経済会議委員長へと渡り歩いている。
リーマンショック直前までFRB議長を務めたアラン・グリーンスパンは 「バブルは事後になって始めてわかる」と開き直り、次代のFRB議長ベン・バーナンキは、「住宅価格の下落の可能性は極めて低い」と断言していた。
リーマンショック時の財務長官ヘンリー・ポールソンをはじめ、ロバート・ルービン(クリントン政権の財務長官)、ウイリアム・ダドリー(オバマ政権のNY連銀総裁)らは、全員ゴールドマン・サックスの出身者だ。
「われわれは音楽が止まるまで踊るしかない」
なかでも金融マフィアの犯罪的行為として描かれるのが、AIGとゴールドマン・サックス救済のケースだ。
ゴールドマン・サックスはクズのようなCDOを顧客に大量に販売すると同時に、CDOの債務先が破綻するリスクをヘッジするCDSをAIGから購入し、いわばクズCDOで二重の利益を目論んでいた。さらにCDSの売り手のAIGの倒産をも予測し、それに対するCDSも別会社から購入していた。
元ゴールドマン・サックスCEOで時の財務長官のヘンリー・ポールソンとその次代の財務長官のティモシー・ガイトナーは、市場沈静化のためにといってリーマン・ブラザースを破綻させる一方でAIGを国有化し救済する。救済には、投資銀行への訴訟権を放棄する前提が付されていた。その結果、ゴールドマン・サックスはCDSの保障金を国税によって満額支払いを受け、延命したAIGの役員はその後、多額のボーナスを手にした。
ゴールドマン・サックスの平均年収は60万ドル(2007年初の1ドル120円換算で約7,200万円)、ヘンリー・ポールソンのゴールドマン・サックスCEO時代の年収は3,100万ドル(同約37億2,000万円)だった。ちなみに在任期間中、数百億円の収入を得たといわれているリーマン・ブラザースCEOのリチャード・ファルドは、一回も取引業務のフロアに来たことはなかったそうだ。
本作の描く、想像を絶するような、呆れ果てる、傲岸な、厚顔な、強欲な、節操のないエピソードの数々に対する信憑性を高めているのが、すべてのキーマンが取材拒否をしているという事実だ。
ルービン、サマーズ、ポールソン、ガイトナー、ダドリー、グリーンスパン、バーナンキらのキーマン、あるいはその後ろ盾となったと指摘されているハーバード大学やコロンビア大学など、全員が取材を拒否している。
リーマンショックによる景気後退の影響で、アメリカでは600万件の住宅が差し押さえられ、GMやクライスラーなどの伝統産業が消え、欧米の失業率は10%を超えた。現在の分断社会はここから始まった。
一方でリーマンショックに関連して起訴・逮捕されたケースは一件もない。詐欺や粉飾決算で訴えられた企業や経営者もいない。逮捕者や自殺者が少なくなかった日本の80年代バブルとは大違いだ。むしろ金融企業はロビイストを3,000人規模に増やし、金融規制強化を阻止し、リーマン前より強大になっているそうだ。
「金儲けによって脳が刺激される箇所はコカインのそれと同じだ」、「金融緩和はタンカーの隔壁を取り除く行為だ」、「金融工学は夢を創る。悪夢になったらそのツケを払うのは別の人間だ」など本作ではさまざまな人がバブルへの警句を発する。
なかでもシティバンクCEOのチャールズ・プリンスの「われわれは音楽が止まるまで踊るしかない」との言葉は、まるで他人事のような、それでいてバブルの火中の当事者の立場を正直に吐露した言葉だといえる。
この言葉が一理あると思わせるところに、政・産・学が共犯して引き起こした人災としてのバブルというリーマンショックの本質が見え隠れしている。
(★)トップ画像 : photo by cloud 2013 - Occupy Wall Street - You Are Not A Loan! Adapted / CC BY 2.0
*初出:東京カンテイサイト(2019年)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
