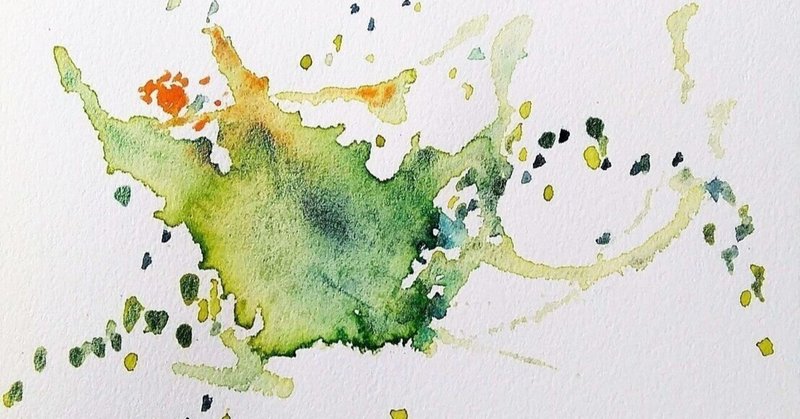
文章練習6[3分短編]
この出来損ないのプラ板のようにひび割れた凹凸の沿岸道路に、サニーロードなどと馬鹿げた名前を付けたのはいったい何処の誰だろうか。恐らく、年老いて痩せ細った保護犬に、桜だとか太陽だとか”そういう類い“の名前をつけるタイプの人間だろうと思う。おお、かわいそうに、人のエゴに触れてこんなにも痩せ細って、お前の名前は今から太陽だ、めいいっぱい可愛がってやる。という具合だ。しかしどうだ、年老いた犬に好き勝手名前をつけて愛玩しようというのだって人のエゴではないか。イカサマだ、と私は考えた。
妻は助手席で退屈そうに観光紙を眺めている。とうとう‘’ラーメン特集‘’に飽きたのか‘’あなたにささる秘境温泉‘’の頁を開き、そしてすぐにまた‘’ラーメン特集‘’の頁に戻り、今度は窮屈そうに膝を立てて両腕で抱いた。こういうのは、舞台の端から出てきた役者が、もう片方から捌けてゆくまでに一通りやってのける例の意味のない芝居だった。妻は「それでも」といった。
「それでも、もう少し友好的に接する事も出来たんじゃない?」
「もう少し」
「そう、もう少し。それに10分て事はないでしょう。向こうだって予定に合わせて時間を作って待ってるんだから。」
「時間を。」
「そう。おまけに、あまりいい態度じゃなかった。ああいう言葉遣いを聞くと私も気持ちが良くない」
「どこが?」私は苛立っていた。先ほどから外では雨が落ちていて、我々を乗せたステーションワゴンの車内は蒸し暑く、劣化して剥がれかけたワイパーゴムがフロントガラスを撫でる度に立てるきゅるきゅるという不快な音に支配されている。ストロークの調整だっておかしい。このワイパーは、死んだようにめっきり動かないか、もしくは貧乏ゆすりのように忙しく動くか、そのどちらかしかなかった。「僕だって自分の時間を使っている。それをいうなら、彼らの態度だって褒められたものじゃなかったよ」
「それはあなたが高圧的だから」きゅるきゅると音が鳴る「あなたが、あの子の事で兄さんを憎んで—」妻はそこまで口にしたところで、自分がまずいことを口走ったと気付いたのか、その言葉を取り下げる代わりに「許してあげて」とだけいった。妻はまるで地雷原の真ん中で途方に暮れているベトナム兵のようだった。キャッサバ畑で身動きの取れなくなったベトナム兵。
妻は娘の名前を呼ばなくなった。あの子と呼ぶ。あの子が好きだった絵本。あの子の服。あの子の写真。結局、それは私をひどく悲しい気持ちにさせる。由乃が居なくなった後の空虚を埋められずにいるのは私だけなのか。私の娘だ。そして妻の娘でもある。あの子だと?妻は、新しい赤ん坊を欲しがった。当然かもしれない。そうすることで必死に悲しみから逃れようとしたのかもしれない。義父は私の肩を抱いて、悲しいが、まだお前たちは若い。これからがある。といった。だが、砕けた時計から正常な部品を取り出して、新たな時計を作り出したとしても、もう私の時間が動き出す事はない。私は壊れているのだろう。きっと私は酷い顔をしているだろう、と思った。きゅるきゅると音が鳴る。サニーロードは雨に濡れそぼった老犬さながら右に左にふらふらと蛇行しながら続いている。
もう少し車を走らせる事もできただろうと思う。あと30kmも山道を行けば市街地に出ることができる。そこでガソリンを補給して、ファミリーレストランで昼食を取る。その頃には我々にまとわりついたぎくしゃくとした空気もすっかり溶けて、お互いに良い休日に戻ることが出来るだろうという予感があった。しかし、私は沿岸を抜けた先、国道を逸れた広場の入り口に建てられた小さなセルフガソリンスタンドへ入ることにした。妻は相変わらずキャッサバ畑で立ち往生している。長い沈黙の中、山越えの前に仕切り直しをしたかったのだ。
スタンド脇に立てられた看板に‘’スグソコ 300m サニーロード 海と太陽の町‘’と書かれている。海風に錆びたその看板は、塗料に吹いたあぶくが砕けて、路面に赤茶色いフケをばら撒いている。ピットへ車を乗り入れる時に、そのフケはタイヤに潰され大きくじゃりじゃりという音を立てた。
スタンドには古びたストアが併設されていた。どこにも店員が見当たらない。ストアの店先には裏返しのビールケースが3,4箱積まれており、スタンドとストアの間に建てられた塗炭作りのガレージから汚れた猫が我々を覗き込んでいる。あたりには撒き餌と油の入り混じったむんとする匂いが漂っている。ストアのガラス戸には黄色く変色したセロハンテープがこびり付いていて、かつてそこに貼り付けられていたであろうポスターやチラシの紙片が、テープとともにところどころ取り残されていた。遠くの方から波の音が聞こえる。
「やってるのかな」シートベルトを外しながら妻が言った。眠る猫の爪を切るように、恐る恐る、慎重に。「飲み物買ってくるから。何がいい?」
「お茶がいい。あと、ワイパーゴムが駄目になってるんだ。店員がいたら呼んできて欲しい」こくりと頷き、妻はストアへと歩いて行った。
妻を待つ間、私は給油を済ませ、スタンド脇の広場に駐車した。15分経っても妻は戻って来ない。ワイパーゴムのサイズでどめいているのだろう。だから店員を呼んでくれと言ったのに。私はステーションワゴンから劣化したワイパーゴムを引き抜き、丸めてジーンズの後ろポケットに詰め込み、ストアへ向かうことにした。
店先のビールケースは濡れた新聞紙が半分溶けてこびり付いている。四隅には猫の毛が絡み付いていてロゴは白く剥がれている。長い間のざらしなのだろう。ガラス戸越しに店内を覗いて見たが、妻の姿は見当たらない。それほど大きな店舗ではない。私は扉を半分すかして、店内に半身を突っ込む。うす暗い店内に商品が散乱している、妻の名前を呼ぼうと息を吸い込んだ瞬間、卵の腐ったような酷い悪臭が鼻をついた。思わず身を引くと、向かいの商品棚、暗がりの奥に飛び散った赤い染みのようなものが目に入り込んだ。私は急いで店内に駆け込む。途端、バックヤードから飛び出してきた影に私は押し倒され、背中からカウンターに叩きつけれる。馬乗りでもみくちゃにされ、辺りに散乱した酒瓶で顔面を何度も殴りつけられる。額をそれた酒瓶がリノリウムで砕ける。今度はその鋭く割れた断面が太ももを抉る。あまりの激痛に私は叫んだ。するとそれを合図に店内に大きな笑いが起こった。少年の笑い声。2人、3人。その内の一人が「漁れ。」と言った。馬乗りになった少年が、私の上着から、財布とステーションワゴンの鍵を抜き取った。
「妻は……」意識がもうろうとする。私の言葉は口から出た瞬間にはうめく様な音の塊となって床に転がった。少年たちはけたたましく笑い声を上げながら店の外に駆け出していった。そして砂利を踏みしめるタイヤの音が遠ざかっていく。抉れた太ももから赤黒い血液が溢れてくる。その傷口に割れた瓶の破片がいくつも突き刺さったまま肉の間から飛び出している。気を失いそうになりながら、ジーンズのポケットからよれよれになったワイパーゴムを取り出して、脚の付け根できつく縛り付けた。私は仰向けになり、天井を見つめる。右目はもう見えない。口もろくに動かすことができない。妻がどうなったか考えたくはない。
私の愚かな強情で、わがままで、偏狭さで、私は考える。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
