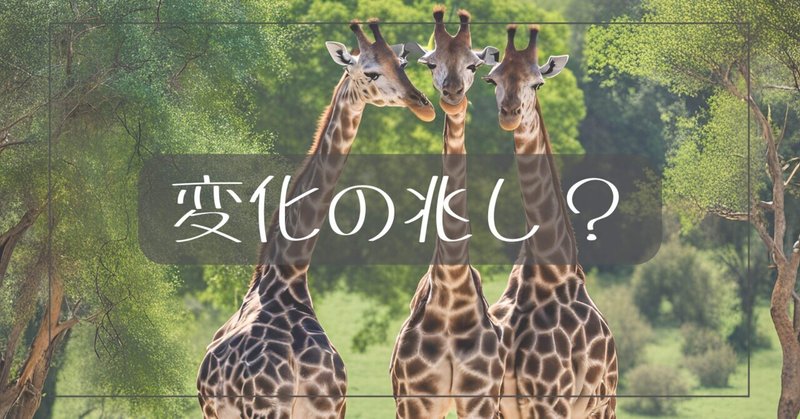
変化の兆し?
市教研の運営委員会に参加した。これは市の研究会の部長が集まり、本年度の研究会の進め方に関して検討し、方向性を決めていく場所だと僕は思っている。
しかし、現実はそうはなっていない。運営委員会で何をするかと言えば役員たちが伝える連絡事項を受け取るだけだ。また連絡してくることも、基本的には毎年何も変わらず改善されることはほぼ無い。
この状態に危機感を感じ、数年前に運営委員会でアプローチしてみたが、その時はうまくいかなかった。
改善していくことが起こらない原因は、物事の決定権が不明確なことだ。市教研の総会で議案の決議を取っている。ということは、決定権は総会にあるのかとも言える。しかし、実態としては総会は各校での書面総会で運営委員から出てきた議案書を読み上げられ、それに対しての承認か不承認が決を取る。はっきり言ってこの原案など誰も細かく読まないので。基本的には承認される。と言う事はこの総会にあげられた時点で、物事は実質的に決定しているとも言える。
では、この総会に対して提案を出すためにはどのようにすればいいのか。ここが不明確なのだ。数年前に出た運営委員会でも、今回の運営委員会でも、「物事の決定のプロセスを教えてください」と会長に聞いたのだが、会長ははっきりと答えてくれない。なぜなら市教研の会則にはっきりとした組織図がなく、どこの階層で提案を作れるのか、またどのようなプロセスをたどれば提案を作れるのかが明記されていない。
さらに難しいのは会長は1年ごとに輪番で回ってしまうと言うことにある。会長は市内の校長が勤めている。1年ぽっきりの会長職であれば、そこで大きな変更を自分はしたくないと考えるのは自然なことである。これは校長が悪いのではなく、システムそのものが不具合を起こしている。
この責任の所在がはっきりしないシステムを長年続けていることに誰も疑問を持たないのだろうか?
ただ今回の運営委員会は少し雰囲気が違うように感じた。周りを見れば半数以上の部長は知り合いだったし、前で司会と記録をやっていた役員の方も2人とも知り合いだった。
その方と運営委員会終了後に、少し会話をしたときに僕と同じような疑問を感じてくれていた。
また、副会長を務めている校長先生も現状の市教研の出席率の低さに課題を感じていると言う話をしてくれた。この市内の先生たちで行っている公的な学習会がどのようにしたらより良い場になるのか、本気で考えている様子だった。
現場の実態は何も変わっていない。しかし、参加しているメンバーの雰囲気が明らかに数年前とは変化が起きている。この変化の兆しをうまくキャッチし、どのように動いていけばし、市内の教育への向き合い方が1歩も良くなるのか考えたいと思える会となった。
ただ、会議はオンライン開催で良い。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
