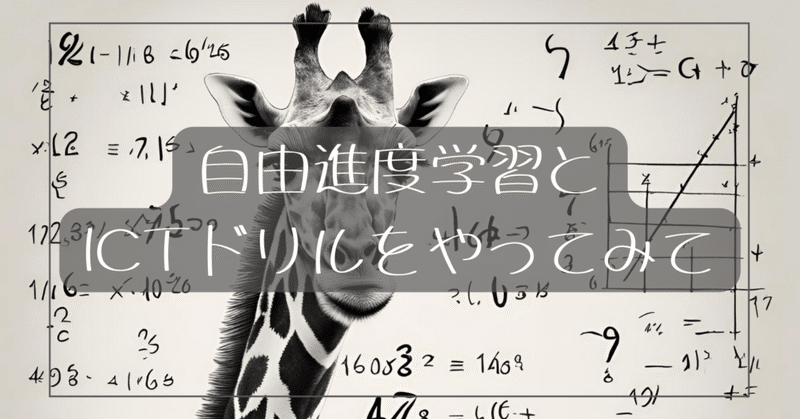
自由進度学習とICTドリルをやってみて
今年度の5年生で算数は、単元内自由進度学習に取り組んでいる。また、光文書院から出ているドリルプラネットと言うICTドリルもその中で活用している。3つの単元をこの2つで取り組んでみて気づいたことを記録してみる。
3単元を終えて、計画表で何をすればいいかわかっていない子が2名いる。1人は外国籍の方で日本語の問題で教科書が読めず進められない。もう1人の子はかなりの支援が必要で、教科書の読み方が理解できていない上に基礎的な計算の仕方もわかっていない。そのため1人で取り組むことがかなり難しい。この2人に対してどのような支援をしていけば良いのか。教科書を読むことが厳しいのでプリントを渡したり、ドリルをやるように言っているが難しそう…どうしたら学習に取り組めるのか色々と試してみるしかない。


次にわかった事は、ICT教材の良さと難しさ。良さは即時のフィードバックがあること。正解かどうかがすぐにわかる。またドリルプラネットは教科書と対応しているので、どこのページの問題をやりたいか自分で選択することができる。これは使いこなせればかなり有効だと思う。
難しさは、パソコンの画面に向かって学習をしているのでノートやプリントでやっている時より学びのプロセスが見えにくいことだ。それは教師にも見にくいし、友達にも見にくい。そうすると自然発生的な学び合いがとても起こりにくい。画面に向かって困っていると何に困っているのか全くわからない。
ICTドリル教材は理解している子の反復学習には有効なのかも。理解していない子が進めるのには難しいのではないだろうか。ポイントを稼ぐために1年生の問題をやっている子も数名…
1番感じる課題が学びが作業的になること。どうしても学習計画表のタスクをこなしていくような学びになっている。
進めるのが早いこととってはどんどん単純作業になるし、遅い子は内容が全て終わらせきれない場合もある。自分のペースで勉強は進められるものの、一斉指導と同じような課題も出てきている。
どの課題についても正直良い解決策は思いついてない。とりあえず僕が今感じている課題を子供たちに投げてみて、子供自身はどう感じているのかを聞いてみたい。その声をしっかりと受け止めより学びやすい授業にしていきたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
