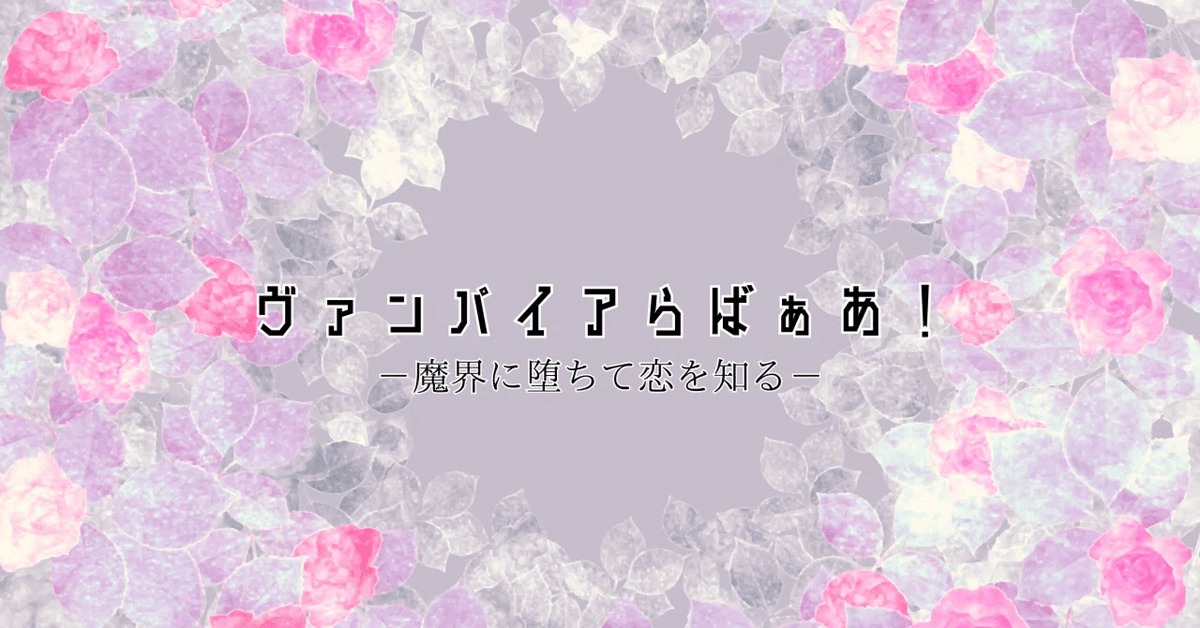
ヴァンパイアらばぁあ!―魔界に堕ちて恋を知る― 十一話
十一.第八章①:連続女性吸血殺人事件
「連続女性吸血殺人事件、か」
アデルバートは渡された資料に目を通しながら呟く。フェリクスに呼び出されたアデルは彼の執務室を訪ね、この事件の話を聞かされた。二人しかいない室内は静かでフェリクスは「現在も逃走し、犯行を繰り返している」と渋い表情を向ける。
連続女性吸血殺人事件とは、五年前から起こっている事件だ。種族は問わず一定の期間で女性が吸血されて殺害されている。犯人は痕跡を僅かにしか残さず、捜査は難航しており最後に現れたのは半年前だ。その時に殺害されたのはエルフの若い女性だった。
「犯人は吸血鬼とまでは絞れているがそれ以上の情報が少ない」
「これを俺に話した理由を聞いてもいいだろうか?」
この事件は魔族犯罪課が担当することになっているので、魔物対策課であるアデルバートには本来、来ることはない。連続吸血事件の時のように協力を要請されることはあるが、アデルバート一人というのは珍しいことだった。
フェリクスは「吸血鬼の中でも優秀で戦闘ができる者にのみ話している」と答える。殺人事件となっているので犯人と戦闘になる可能性と、吸血鬼は吸血鬼を見分けることができるため、それらを総合して任せられる捜査員にのみ話しているのだという。
アデルバートは吸血鬼の中でも優秀であり戦闘が得意だったので選ばれたということのようだ。なるほどと納得したアデルバートは捜査資料を捲る。捜査では変身能力や気配遮断などの魔法に長けた吸血鬼という犯人像が浮かんでいた。
「変身能力や気配遮断に長けた魔族なら街に紛れこんでも普通は気づかん。それらを見破れる可能性の高い優秀な吸血鬼を捜査に参加させることになったんだ」
「俺で問題ないと上は判断したと」
「そういうことだ」
この事件は任された魔族以外への他言が許されていない。特に吸血鬼にはとフェリクスに言われて、これは誰にも言うなということだろうと察する。ガルディア勤務であろうと信用してはいけないということのようだ。
「街での捜査も行われている。何か怪しい存在を見つけたら報告してくれ」
「了解した」
もう行っていいと言われてアデルバートは一礼すると執務室から出た。そのまま真っ直ぐ自分の部署まで戻って席に着くと捜査資料をデスクの引き出しに仕舞う。また厄介な事件の捜査を任されたなと小さく息を吐けば、隣の席のバッカスに「どうしたよ」と声を掛けられた。
「なんか、フェリクスに言われたかー?」
「仕事が増えただけだ」
「優秀な吸血鬼は大変だねぇ」
バッカスは仕事の内容を言わないことに察したようでつまんなそうに口を尖らせていた。自分も十分優秀だと自覚している彼からしたらお呼びがかからないというのは不満なようだ。今回は戦闘もできるという点でアデルバートが選ばれている。バッカスは戦闘はできるがサポート魔法が得意なので今回は外されただけだった。
なので、「今回は戦闘重視だった」とだけ伝えれば、「そりゃ、私には無理だわ」と納得したようだ。
「私はサポート特化だからなぁ」
「だから俺に回ってきた」
「それなら仕方ないや。頑張れー」
バッカスのなんとも心に籠ってない応援にアデルバートは眉を下げる。少し不満なのは変わらないようだが、それを指摘することなく片付け途中だった書類に手を付けた。
「あ、そういやどうなの。シオンちゃんと」
「……どうもない」
「あー、お前……そこはもっと頑張れよ」
何の進展もしていないことにバッカスは嘘だろといった顔をしていた。そんな顔をされても何もないし、行動できていないのだから仕方がないのだ。自覚しているならもっと行動をしろとバッカスに指摘されてアデルバートは言い返せない。
「お前、そんなんだとライバルに取られるぞ」
「……わかっている」
そう分かっている。ガロードというエルフは行動してシオンに近づいている。彼女も彼に対して悪い印象を持っていないので、いつそういった関係になるか分からないのだ。とはいえ、告白など相手が自分のことをどう思っているのか分からないので行動に移せない。
アデルバートは悩んでいた、どう行動すればよいのかと。今まで自分から誰かを好きになったということがないので、こういった時にどうすればいいのか分からない。そんな様子にバッカスは「もっとさ、誘うんだよ」と呆れたように言う。
「デートに誘ったりさ」
「そう言われてもだな……」
好意を持っていない相手から誘われるのは迷惑かもしれないだろうとアデルバートは渋面を作る。それにバッカスが「そんなの恐れてたら何も進まないぜ?」と返した。
行動に移さなければ何も始まらないのだ。断られることを嫌われることを恐れてはこの関係が変わることはない。それは理解できるけれどシオンの気持ちを考えてしまうと無理に誘うことはできなかった。
そんなアデルバートにバッカスは「お前なぁ」と溜息を吐かれた。吐きたいのはこちらなのだがと見遣れば、「そこまで面倒くさいとは思わなかったわ」と突っ込まれてしまう。
「なんでそうごちゃごちゃ考えるかね、お前。好きならもっとアピールしろよ。自分のこと好きになってもらわないと先に進めないだろ」
「それは分かっている」
「分かっててやれてないってどんだけ奥手なんだっつーの」
バッカスは「嫌われるのを恐れてたらいつまで経っても進展なんてしないぞ」と指をさした。その通りなのはアデルバートにも理解できたので言い返すことができない。
けれど、シオンの気持ちも尊重したいので無理強いはしなくなく、アデルバートはどうしたものかと彼女の事を想いながら眉を下げた。
***
教会の前を掃き掃除していたシオンはいつものようにやってきていたサンゴとカルビィンたちと話をしていた。今日は孤児院へ行くのは少し遅くていいので、のんびりと他愛ない話をしているとサンゴに「それ」と指をさされる。
「そのペンダントどうしたの?」
「あ、これ? アデルさんに貰ったんだよね」
首元を飾る蝶々のペンダントにシオンは貰った経緯を話した。それを聞いてサンゴは「防犯にもなるものね」と納得したように頷く。
「アデルさんも心配してるんだねぇ」
「あたしって危機感なさそうにみえるかなぁ」
「そうじゃないわよ、シオンちゃん」
サンゴに「シオンちゃんだから心配しているのよ」と言われてシオンは首を傾げた。それは危機感が無さそうに見えたからではないのだろうかと。それにサンゴは「そうじゃないのよ」とまた返した。
「シオンちゃんが危なっかしいのは認めるけど、そうじゃなくてね。シオンちゃんのことが大事だから心配しているんだと思うわ」
「大事?」
「そう、大事」
シオンが危なっかしいのは否定しないけれど、それとは違って大事に想っているから心配しているのだとサンゴは言い切る。何それとシオンは思ったけれど、「絶対にシオンちゃんが好きなんだわ」と言われて変な声を上げてしまった。
「ど、どうしてそうなるの!」
「勘ではあるけど、アデルさんってシオンちゃんの前だと雰囲気が優しくなるし。あと、ヒーローの話をしてからのその対応って、自分がシオンちゃんのヒーローになろうとしているっていう意味にも捉えられるじゃない」
何かあれば俺が助けようとそう言ったのならばとサンゴに指摘されてシオンは黙る。確かにヒーローの話をしてからアデルバートはこのペンダントを渡してそうやって言ったのだ。
(え、あたしのヒーロー?)
シオンの頭は混乱していた。アデルバートからもしかしたら好意を寄せられているかもしれないという事実に。そんな気は見せていなかったと思っていた、可愛らしいと言われることはあったけれど、そういった意味ではないと。
パニックになりつつあるシオンにサンゴは「落ち着きなさい」と冷静に言われてしまう。これをどう落ち着けというのだろうかとシオンは彼女を見た。
「私は絶対に好意があると思うわ。でも、シオンちゃんの気持ち次第よねって」
「あ、あたしの気持ち……」
「うーん、僕もそうかなぁ。なんとなく、そんな雰囲気あるし。シオンの気持ちだよね、問題は」
二人に言われてシオンは眉を寄せながらうーんと呻る。まだ好意を寄せられていると決まったわけではないけれど、そう受け取れてしまうことをアデルバートはしているのだ。それを気にしないというのはどうだとうかと考える。
自分の気持ちとは。誰かを好きだとか、愛しているだとか考えてたこともなかった。でも、好きか嫌いかならば、その二択ならば決まっている。
「好きか嫌いかなら、好きだけど……」
「それが恋かどうかってことよ」
「うーん……」
「まー、無理して考えなくてもいいんじゃないかなぁ。シオンは鈍感というか、そんな訳ないって思いこむ癖があるからさ。ゆっくり気持ちの整理をしていけばいいかなって僕は思うよ」
誰にだって最初は気持ちを信じられないことだってあるのだから、変に思い込んで考えずにゆっくり整理していけばいい。その中で自分の気持ちに答えがでることだってあるのだ。そうカルビィンに言われてシオンはなるほどと頷く、焦っても仕方ないのだなと。
(自分の気持ちか……)
自分は彼のことをどう想っているのだろうか。好きか嫌いかならば、好きだ。優しく、気遣ってくれて、相手の気持ちを汲み取ろうとしてくれるところが。人間であるからと決めつけで何かを言ってくることもなく、もちろん人間という種族に何か思うことはあるのだろうけれど悪く言うことはしなくて。そういった彼の温かさに惹かれる。
二人に何度も言われて同じような会話をしているけれど、こうやって断言されてしまうとシオンはそうなのかもしれないなと思ってしまった。
(この後、どうやってアデルさんに会えばいいのさー!)
絶対に意識してしまうじゃないか、変な反応をしてしまうかもしれない。おかしな子だと思われたらどうしようかとシオンは少しばかりサンゴを恨む。それを感じ取っているのか、サンゴはにこにこしていた。
「いいわ、いいわー。シオンちゃんが恋に悩んでるの! やっと春が来たのね!」
「それ、喜んでるの、揶揄ってるの、どっちなの、サンゴ!」
「喜んでるに決まってるじゃないの、シオンちゃん!」
鈍感なシオンちゃんに春が来たのだから喜ばないわけがないでしょとサンゴに言われて、シオンはじとりと彼女を見つめる。喜んでいるのは本当なのだろうけれど、楽しんでいるような気がしなくもないのだ。
うーっと見つめるシオンにカルビィンが「まぁまぁ」と宥めてくる。あれもサンゴなりの応援の仕方だからと教えてくれた。
「サンゴの応援の仕方ってちょっと斜め上なんだよねぇ」
「これでも真剣なのよ、カルビィン!」
「こんな感じなんだよ。だからシオンは気にしなくていいよ」
「うん、なんとなく理解したよ」
サンゴが応援しているという気持ちは伝わってきたので、彼女のやり方が少しばかり斜め上だっただけなのだとシオンは理解する。サンゴも自覚はあるらしく、「応援しているのは本当なのよ」と謝るように手を合わせた。
「まぁ、サンゴの気持ちは分らなくないからいいけど……。次にアデルさんに会う時、絶対に意識するからちょっと恨むよ」
「どんどん、意識するといいわよ~」
「こうでもしないとシオンは気づかなそうだからねぇ」
「うー、否定できない」
自分の鈍感さを痛感しているので否定することもできず、シオンは次にアデルと会う日を緊張しながら待つことしかできなかった。
***
モノクロテイストの見慣れたシンプルな室内は落ち着いている。座り心地の良いソファにいつものように腰を下ろしているシオンだが、内心は緊張していた。それもこれもサンゴとカルビィンのせいだった。
断言されてしまい、アデルバートのことを意識してしまったのだ。なんとか表情や態度に出さないように気を付けているけれど、不自然さが出ているかもしれない。
「シオン」
「な、なに!」
「いや、どうかしたのかと」
いつもと様子が違う気がしたんだと言われて、シオンは気づかれてしまっていると少しばかり焦る。意識してしまっていますとは言えないので、「そんなことないけど!」といつもの調子で答えてみる。
アデルバートは暫く見つめてきたけれど、「それならいいが」とそれ以上は突いてこなかった。納得したのか、引き下がったのかは分からないけれどシオンはその返答に小さく息をつく。
(落ち着くんだ、あたし)
そう、落ち着くんだ。まだ決まったわけではない、決まったわけでは。ここで慌てては相手を困らせるだけだとシオンは自分に言い聞かせる。なんでもないことを装うように渡された果実水の入ったグラスに口をつける。
(うん、いつもと同じで美味しい)
いつ飲んでもこの果実水は美味しいなとシオンは思いながら少しずつ落ち着きを取り戻していく。
「やっぱりこの果実水、美味しいよなぁ」
「一般的に売ってるものより良い果実を使っていると母上から聞いているから、それでだろう」
「このまま飲んでたら本当に他の果実水が飲めなくなりそう」
この果実水、高級品なだけあってかなり美味しいので最近、別のものを飲むと物足りないと感じるようになっていた。そんなことをシオンが話せば、アデルバートは「持って帰るか?」と提案してきた。
母親がたくさん送ってくるからと言われてシオンは迷う。林檎や葡萄などの他にも柑橘系の果実水もあると聞いて飲み比べてみたいと思ったのだ。けれど、そうすると普段、飲んでいる果実水が本当に飲めなくなりそうだったので、「此処に来るときだけ飲むことにする」と断る。
「他の果実水が飲めなくなるのちょっと嫌だし」
「そうか……。なぁ、シオン」
「何ー?」
「今度でいいんだが、食事に行かないか」
アデルバートの言葉にシオンは目を瞬かせる。突然の誘いに固まっていると、彼は「日頃のお礼にと思ったんだ」と訳を話した。契約とはいえ、定期的に血を分けてくれているので労いも込めてと。
「迷惑だったら断ってくれて構わない」
「迷惑ではないよ! 大丈夫、行くよ!」
なんとも申し訳なさげに眉を下げるアデルバートにシオンは慌てて返す。迷惑など思っていなかったのは事実で、一緒に食事に行くのは構わなかった。理由はともあれ、誘ってくれたことが嬉しかったので「ありがとう」とお礼を言えば、アデルバートが固まる。
目を少しばかり開いて固まる様子に首を傾げると、アデルバートは「なら、来週でどうだろうか」と何でもないように言う。今の間はなんだったのだろうかとシオンは疑問に思いつつも、言われた日時の予定を確認する。
その日は丁度、孤児院の子供たちと遠足で森林公園に行く日だった。お昼すぎには戻る予定なので大丈夫だろうとシオンは答える。
「孤児院の子供たちと遠足で森林公園に行くから、帰ってきてからなら大丈夫だよ」
「何時ぐらいに森林公園は出る予定なんだ?」
「えっと、お昼すぎかな?」
「なら、迎えに行こう」
「え、大丈夫なのに」
孤児院に戻ってからでも大丈夫なのにとシオンは言うのだが、「人手は多いほうがいいだろう」と返される。確かに孤児院のスタッフというのは少なく、帰りの準備などを手伝ってくれるというのは助かることだった。
けれど、アデルバートも忙しいのではとシオンが思っていると「その日は半日勤務だ」と口にする前に言われてしまう。それならいいのかなとシオンは納得して「じゃあ、お願いしようかな」と返す。
「手伝ってくれるのは助かるからありがたいよ」
「それなら、その時間に迎えに行こう」
「分かったー」
「何かあったら伝達魔法で知らせてくれ」
そう言われてシオンは首から下げていたペンダントに触れて頷く。アデルバートはペンダントを身につけてくれているのを見てゆっくりと目を細めた。
「ちゃんとつけてくれているんだな」
「え、つけてたほうがいいかなぁって」
「そうしてくれると嬉しい」
「嬉しい?」
「よく似合っている」
はいっとシオンは動揺する。アデルバートが嬉しそうに「似合っている」と言ってくるものだから。途端にまた思い出して、意識してしまう。せっかく落ち着いてきていたというのに最初に戻ってしまった。
それでもシオンは何でもないように「ありがとう」とお礼を言っておく。そうするとまたアデルバートが嬉しそうにするものだから、シオンはますます動揺してしまう。
(あー、ほんっと、サンゴとカルビィンを恨む!)
こんなふうに意識してしまうのは二人のせいなのだと、心の中で文句を吐いた。それが届くわけもなく、シオンは気持ちを落ち着けるのに必死だった。
***
「ここ近年で入ってきた魔族? ガルディアの人よ、そんなの沢山いるに決まってるだろ」
山羊の角を生やした白毛の年配の男性獣人が返す。中央街から少し離れた街を繋ぐ東外門の傍で商店を営んでいる年配の山羊獣人の男は「ここは王都だぞ」と荷物の入った箱を地面に置いた。
「王都なんだから田舎町よりも人の出入りが激しいのはあんたが一番、よく分かってるだろ」
「それは承知の上で聞いているんだ、すまない」
「アデルバートさんだっけ? あんたも大変だね、分かっていながら聞き込みしないといけないなんて」
山羊獣人の男はアデルバートに「お疲れ様だよ」と彼の気持ちを察したように声をかけた。アデルバートは今、連続女性吸血殺人事件の調査をしている。自身の魔物対策課の仕事の合間にやっているのだが、なかなか有力な情報というのは入らない。
この事件の調査をしている同僚たちも「手かがり無しだ」と頭を悩ませている。それほどまでに情報というのがないのだ。最後の事件が五年前ということもあってか、記憶力に長けていない魔族は忘れてしまっている。
この街を繋ぐ外門近くというのは人の出入りが多いので何かしら情報が手に入ると思ったのだが、どうやら当ては外れてしまったようだ。
「なら、五年前後で新しく雇った従業員などはいるだろうか?」
「うーん、うちの商店は身内しか雇わんからなぁ。新入りを雇うってことはないね」
「なら、知り合いはどうだろうか?」
「知り合い? あー、いくつかの店が雇ったって聞いてるよ」
「身元が分からない魔族を雇ったという話は?」
「それは聞かねぇなぁ。でも、親を亡くしてとか訳アリを雇ったっていうのは聞いたぞ」
変身魔術と気配遮断が得意とする犯人ならば、口上手く紛れ込んでいるかもしれない。アデルバートは「その店を教えてくれないだろうか」と問うと、「あぁいいよ」といくつかの店を教えてくれた。
何処に潜んでいるのか、それともこの街から出て行ったのか。この街にいないのならば探すことは難しくなるだろうなとアデルバートは考えながら、山羊獣人の男に礼を言ってその場を後にした。
メモしていた教えられた店の名前をアデルバートは眺める。飲食店やアクセサリーショップ、風俗店や民宿など統一性はない。身元が分からない魔族というのはあまり表にでないことが多いが確証はない。
(次の獲物を手に入れるならば、多くの魔族を人間を観察できる場所にいる)
まだ、犯人がこの街にいるのならばという前提ではあるが、連続で女性を吸血し、殺害しているのでまた犯行に手を染める可能性はあった。
(飲食店やアクセサリーショップなら女性を観察することはできるか……)
アクセサリーショップなど特に女性の客というのは多いだろう。女性を狙っている犯人からすれば、獲物を品定めするには丁度いい。あくまでも予想なので、別の職種に紛れているかもしれないのだが、一先ずはこの辺りから聞き込みをしようとアデルバートは決める。
連続女性吸血殺人事件の被害者の死因は様々だ。血を吸われた後に首を掻き切られて、首を絞められて、胸を刺されてと決まった殺され方をしていない。血を吸いつくすといった行為での殺害はなかった。
(共通点は血を吸われていることだけ。吸血鬼の反応が僅かにあった……やはり、変身魔術か……)
変身魔術は厄介なものだ。上手い者になれば誰が見てもその種族にしか見えない感じない疑わない。気配遮断だけでなく、その種族の気配すら纏うことができる。吸血鬼など一部の魔族というのは変身魔術に長けていた。
(変身魔術は得意ではない部類だ……)
アデルバートは変身魔術が得意ではない。基本的に戦闘特化である彼は補助技などが苦手なのだ。変身魔術に長けていれば見破るコツなども理解できるだろうが、そうではないので吸血鬼の元々の勘で探すしかない。
吸血鬼は吸血鬼を見分けることができる。それは同族故に魔力が惹かれ合うからだ。とはいえ、変身魔術や気配遮断などを組み合わせられてはそれも難しくなってしまう。
(これは同僚たちが頭を悩ませるわけだ)
彼らが手こずっているのも無理はないなとアデルバートは溜息を吐いた。考えているだけでは事件は解決しないので、アデルバートは教えられたいくつかの店の情報を捜査員と共有するべく一度、ガルディアへと戻ることにする。
メモ紙をなんとなしに眺めてふと一つの店に目が留まった。それは二つある民宿のうちの一つ、どこかで見たことがあったようなとアデルバートは記憶を辿る。けれど、ぱっと浮かぶことはなかった。
「どこかで……」
「あー、アデルー!」
呼ぶ声に顔を上げればバッカスが走ってきた。周囲を見渡せば、中央街の一番街まで戻ってきていたようで賑わう人々が目に入る。立ち止まっているアデルバートを魔族たちが気にする様子も見せずに通り過ぎていく。
賑やかな声を耳にアデルバートは随分と考え込んでいたのだなと気づいた。そんなことなど知らないバッカスは「どうしたよ」と首を傾げている。
「なんでもない。バッカスは巡回か?」
「そうそう、これから西外門の外で巡回。だから、お前を呼び戻そうと思ってたんだわ」
巡回の当番である時間になっていたのに気づいて、アデルバートは「わかった」と返事をしてからメモ紙をコートのポケットにしまう。その仕草にバッカスは気づいていたけれど察したようでそれについて何か問うようなことはしなかった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
