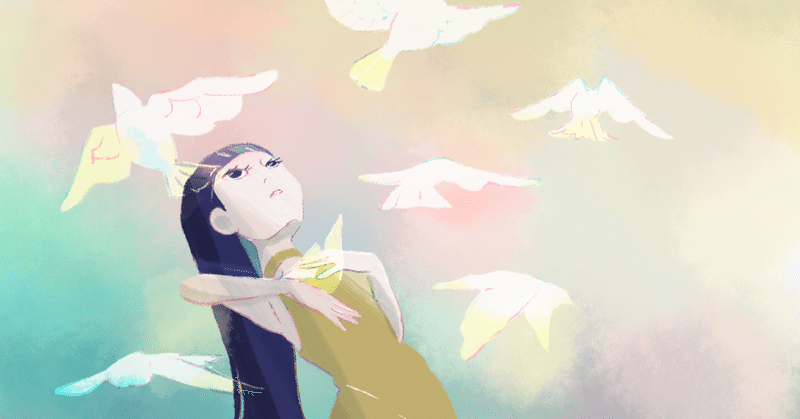
大声も小声も声だよ(差別用語の話)
こんなニュースを見た。
東急ハンズ公式Twitterが6月12日に「ゴリラゲイ雨が来たらちょっと困るけど、ゴリラゲイ雨を見てみたい気もする」などとツイート。数時間後、Twitter上で批判を多数集めたことから「不快に受け止められた方に謹んでお詫び申し上げます」と謝罪しました。
例によって「それは差別だと言って騒ぎすぎ」「揚げ足取りだ」というコメントがたくさんついていて、そっかー、と言う感じ。
こういう話について、私は大体「大袈裟」とか「言葉狩り」とか言う人の気持ちがわからないことが多くて、いつも疑問符が頭に浮かんでしまう。
反論意見を見ていると「差別認定される単語がむやみに増えることで、言いたいことが言えなくなるのは良くない」「言論統制が進む」というような事を書いている人が多いんだけど、個人的には、それもなんだか心配が過剰じゃないかな…と感じる。
「差別だ!」と誰かが言った段階では、その単語が、議論の土俵に乗った“だけ”だと思うのです。例えばそこで、発言主が批判を受けて謝罪したとしても「あのやりとりは正しかったのか?」という議論は人の中で続くわけで、完全に差別用語とされたり、放送禁止用語とかになったわけではない。
ただ、この「とりあえず土俵に乗る」というのがかなり大きいポイントで、その議論を受けて個人個人がその単語について考えて、OKとかアウトとか、どちらとも言えないとか考える…という流れそのものに意味があるんじゃないかな…。
声を上げる人に対して「ヒステリックに正義を振り回している」と感じる人の気持ちもすごいわかるし、私も完全にそう感じてたんだけど、大雑把に「正義で怒ってる奴ら」という感情のムーブメントとして一括りにすると、問題の真意が見えなくなるというのが、色々考えた結果、わかった。
自分が、間違いだと思っていないものに対していきなり「NO!」と叫ばれたらびっくりする。で、そのびっくりから、次のステップを考えたらいいと思う。
それでも尚、その単語や表現を守りたいならそうしたらいいし「やっぱり自分は違うのかも」と改めてもいいし、「どうなんだろう?」と誰かに話すのもとても良いと思う。ずっと考えて答えが出なくてもいいと思う。
あくまでその単語について考えること!「怒っているその人」ではなく。
何にせよ、面倒で煩く感じられたとしても、その声を、いちいち自分で考えることが大事なんじゃないかな…。
大きな声はどうしても目につくけど、意見を口には出さない人だって当然、社会の構成員。「個人的に考える」というのは小さな一歩だけど、それを100人の人がやったら100歩前進するんだよ。
あと…
例の「ゴリラゲイ雨」は私はアウトだと思ってます。不特定多数の人が見る公的なアカウントでやったらそりゃ炎上するよね…。仲間内でなら良いのかもしれないけど、私は自分の友達がゴリラゲイ雨とか言って笑ってたら引くなあ。そういう風に他者の属性を「ネタ」にする事が好きではないので…。
今日の絵。
感情が飛び立つ時間。

全力でフリーペーパー発行などの活動費にさせていただきます!よろしければ、ぜひサポートをお願いします。
