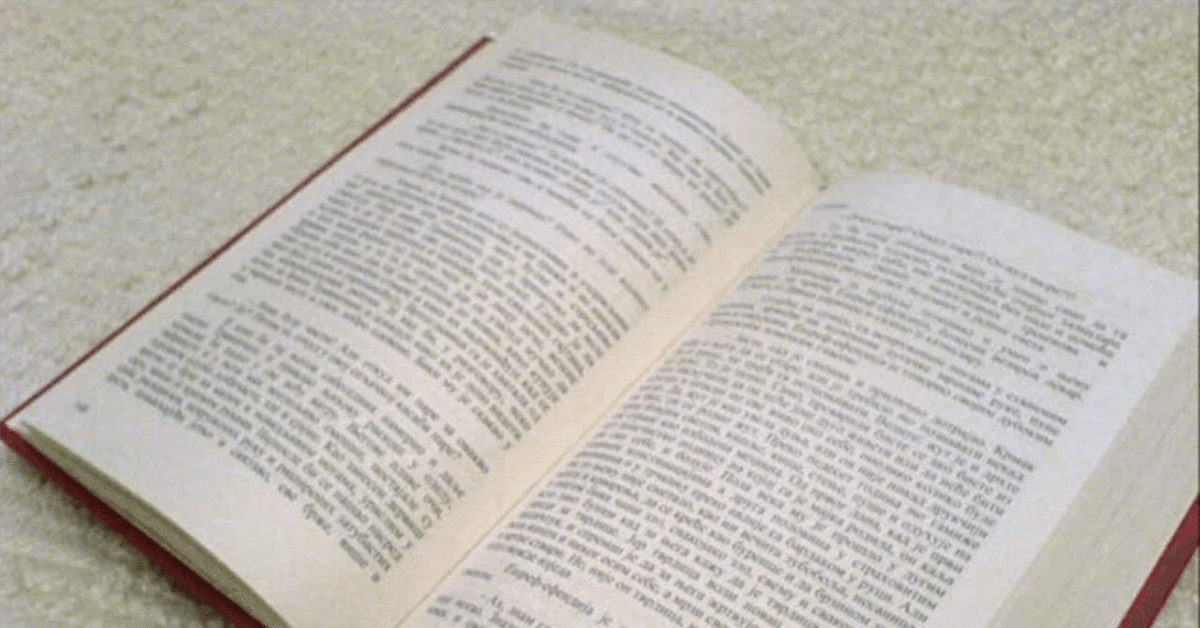
読書記録15:『文字禍』
中島敦『山月記』を読んで「俺も実は虎なのかもしれない」と考えることは、人生における必修科目の1つであり通過儀礼であると思っています。
ですが、どうやら現行の学習指導要領においてはそもそも「文学国語」が必修科目ではないため、「その声は、我が友、李徴子ではないか?」というあのセリフを目にせずに成人していく高校生が一定数現れるようなのです。
由々しき事態です。
あの漢文に由来する硬質で豊饒な語彙を思わず読みたくなりながら、そのわりに「虎になっちゃった」というファンタジーさと若気の至り丸出しの李徴の心境に寄り添っていく経験をしないなんて。
33歳で夭折した中島敦は、幼いころから漢文の素養を身に着けつつ、「字」というものへの存在論的疑いを持っていたそうな。
そんな彼が古代オリエントを舞台に文字そのものをとらえた『文字禍』を、世界史を学習している高校生に示そうとして、改めて読んでみたのでした。相変わらず、硬い文体でやわらかユーモアがほとばしっています。
獅子という字は、本物の獅子の影ではないのか。それで、獅子という字を覚えた猟師は、本物の獅子の代りに獅子の影を狙い、女という字を覚えた男は、本物の女の代りに女の影を抱くようになるのではないか。文字の無かった昔、ピル・ナピシュチムの洪水以前には、歓びも智慧もみんな直接に人間の中にはいって来た。今は、文字の薄被をかぶった歓びの影と智慧の影としか、我々は知らない。近頃人々は物憶が悪くなった。これも文字の精の悪戯である。人々は、もはや、書きとめておかなければ、何一つ憶えることが出来ない。着物を着るようになって、人間の皮膚が弱く醜くなった。乗物が発明されて、人間の脚が弱く醜くなった。文字が普及して、人々の頭は、もはや、働かなくなったのである。
アジア太平洋戦争中の1942年に発されたとは思えない、普遍的な一撃。スマートフォンをもって全くスマートになっていない我々にも突き刺さります。
最後の「文字が普及して」からの一節、読点ごとに「!」を入れたくなります。
文字で残ったものが歴史であるという老博士に「書き洩らしは?」という発言を平然と向けるシーンも現れます。それを書く胆力もさることながら、この一節はあらゆるものをデータ化し、言語化し、所有しようとすることの不可能性をも示します。
この時空のあらゆることが記録し所有されるビッグデータの時代、データ化されず検索にも表示されないものは存在しないかのように扱われます。『文字禍』の最後には、楔形文字を記した土板の塊によって老博士が文字通り押しつぶされるのですが、押しつぶすほどの重みも持たないデータたちは、我々に「データ禍」を及ぼすのだろうか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
