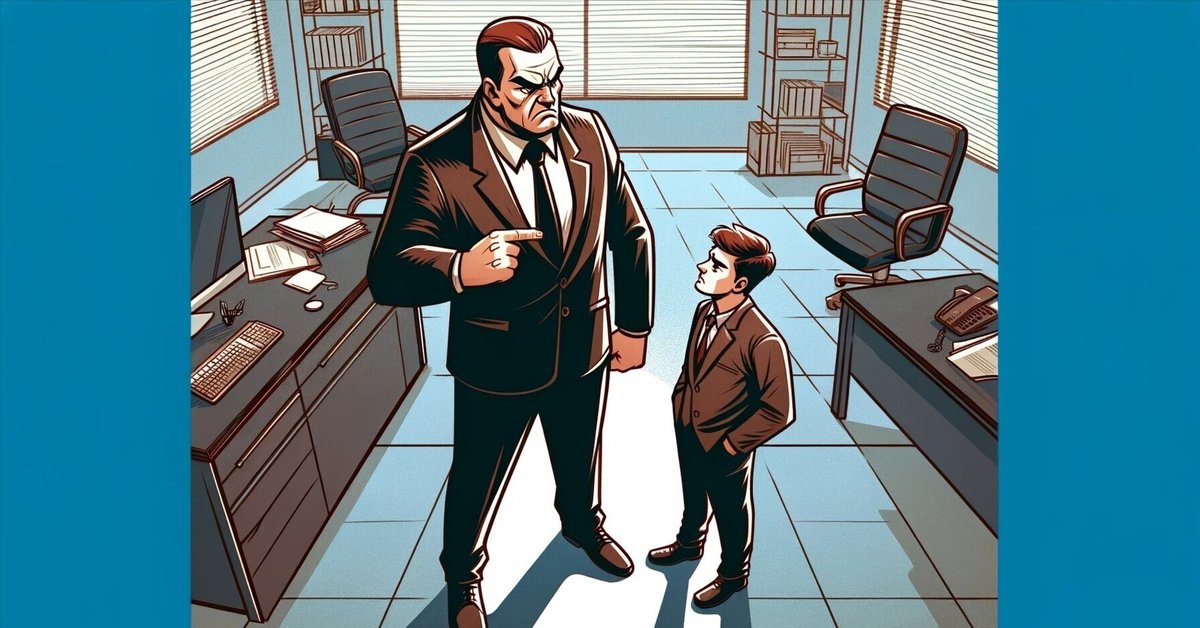
先輩後輩、上司部下という力学
先輩と後輩、上司と部下といった序列は、一部の日本人には極めて分かり易い論理とされている。しかしその使われ方をつぶさに見てみると、様々な文脈や論理が混在していることが分かる。
すなわち、年齢の上下、言葉遣い、態度、指示、空気、序列、仕事かプライベートか、といったようなことだ。
例えば、先輩のいる前で後輩がすべきことが暗黙に決められている。後輩は先輩の言うことを守らなければならない。先輩は後輩よりも偉い。
こうした文脈では先輩という単語を上司に、後輩を部下に入れ替えても成り立つと思われがちだ。しかし現実はそう簡単ではない。先輩が部下にいたり、後輩だけど上司がいたりする。さらにはそこに年齢が絡む。先輩だけど年下で上司だったり、後輩だけど年上で部下だったりする。
先輩、後輩、上司、部下、年上、年下、年配。様々な単語と文脈が入り乱れることで、日本人ですら判断に迷うことがある。
つまり先輩後輩といった関係性、すなわち上下関係の論理をベースにしたコミュニケーションはコストが高い。これが判断を遅らせたり誤らせたりする要因のひとつになる。その代わり、皆がその論理を受け入れている限りは上手くいくことが多いし、表立った問題は起きにくい。つまりそれなりのメリットがあったということだ。デメリットに目を瞑っている限りは。
本当は、ただ先輩だというだけで偉い訳では無いし、正しい判断が出来るという訳ではない。問題は上下関係の論理と文脈という特有の力学によってそこを錯覚してしまうことだ。仮に本心では先輩が言っていることは間違っていると思っても、先輩にはそれを言いにくい。上司に忖度するのは嫌だと思っても行く行くはその方が得だし、何なら早く自分も上の立場になればいいと思ってしまったりする。
こうした状況下では、先輩や上司におもねることで将来的に良いポジションを獲得しようという動機につながる。だから派閥のような集まりがそこかしこに自然発生する。いわゆる、つるむというやつだ。ちなみに、つるむの語源は交尾だ。
さて、ここに来て若い世代では上下関係の力学が昔ほどは通用しなくなってきた。もちろん全員ではなくてグラデーションはある。けれども脱ハラスメントに代表される倫理観念の広がりや多様性を認めようというムーブメントは、ようやく上下関係の力学を解きほぐすきっかけとして働き始めた。
こうした「新たな」観念は、いずれ消えゆく新しいブームなどではなく、社会の時流に基づいたものだ。小学校の時に同じクラスに肌の色が違う子供が普通にいたり、親の出身国が日本ではない子供が友達にいたという環境で育てば、それだけで上下関係の力学を支える土台は揺らがざるをえない。
上下関係の力学は、思想的に均質で永続するコミュニティを前提として育まれてきた。年功序列で繁栄した多くの日本企業とそれを支えた日本社会は、まさしくぴったり適合した環境だった。
しかし、様々な背景を持った多様な人々が混在する世界では、あるグループに入った時期の違いだけで力関係が決まったり、自分の裁量で出来る範囲が限定されたりする仕組みは機能しない。
このようなことを言うと、では上司の言うことを聞かなくても良いということか、それでは統制が取れない、先輩を敬う気持ちは大切じゃないか、と思う人がいるかも知れない。そうした疑念の対象は上下関係の力学と何ら関係のないところにあるのだが、力学があまりに深く浸透しているので私たちは全てを混同して考えてしまう。
企業において上司の指示に従うのは当然だ。それが具体的な仕事の指示であれば。
例えば、あなたの案件でクライアントにアポイントの連絡をするように上司から指示をされたら従わなければならない。しかし、コーヒー買ってきてという上司の頼みを聞くのは必ずしも妥当ではない。ここで完全に否定しないのは、ふたりの関係性によるからだ。役職の上では上司と部下であっても、人として対等な関係性が築かれていて、買ってきてあげようという好意が部下の側に自然に湧くのであれば問題ないからだ。問題なのは、上司のコーヒーを買ってくるのは部下の仕事だと上下関係の力学だけで決めつけるような場合で、その「仕事」が上司の個人的な欲求を満たすだけという場合だ。
仕事の場で正しく判断し、正しく行動するのに必要なのは、ポジションごとの役割と成すべき成果の把握であって上下関係ではない。しかし洋の東西を問わず上司に猫撫で声で近付かなければ爪弾きにされる。それが組織だ。だから長く続く組織は腐っていく。
先輩であろうが後輩であろうが他人を尊重するのは当たり前だ。尊重という言葉がしっくり来なかったらリスペクトと言い換えても良い。敬うと言葉は単なる尊重に加えて年長者を大切に扱うという想いが加わる。大切に扱うのは無条件に相手がコミュニティの先輩だからということではなく人類の先輩だからだ。だからと言って全て言いなりになる必要は無い。
服装や態度や言葉遣いに腹を立てる年長者は今でも多いが、その人達がそうした外面的な事でしか人を判断出来ない時代を生きて来たからだ。個性は悪という時代からすれば、個性的なファッションは異物にしか映らないし、タメ口で話しかけられることは辛うじて持っていた根拠のないプライドを傷付けられる。だから許せないのだ。
もちろん、それが日本の文化でもあるから、身なりや態度や言葉遣いがキチンとしているに越したことがないのは言うまでも無いが、殊更にその点ばかりを指摘して本質を見られないのは問題だ。
上下関係の力学に代わる新たな力学は、人々をより強固に結びつけ、かつ、各人が過度な無根拠によって他人に制約されずに自由に振る舞えるようなものだ。
これを見つけない限り、このバラバラになった日本の世界は収集がつかなくなるだろう。
おわり
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
