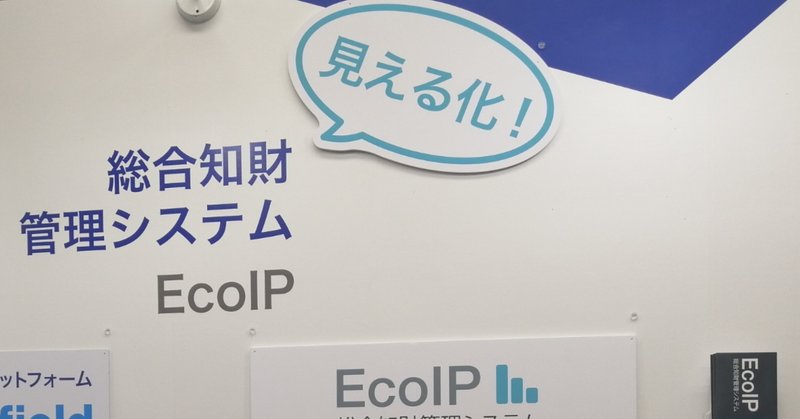
知財×財務×経営者目線の管理システムがほしかった!
私が6年前ぐらいから馬鹿らしく諦めずやっていることが1つあります。
それは、EcoIPと言う総合知財管理システムを開発することです。
2014年の時点で、世の中には、立ち上げて1年未満の一零企業が気軽に使える知財×財務×経営者目線の管理システムがありませんでした。
あったら、私は絶対こんな馬鹿らしいことをしなかったと思います。
このシステムを開発するために、私は、本業で稼いたお金を、全てこのシステム開発に打ち込んだと言っても過言ではありません。
因みに、私は未だにも、日本にはこんなシステムが市場で流通されていないと思います。(とっちかの大手が物凄くいいシステムをこっそりと開発して自社だけ使っているところはあるかも知りません)
それでは、私がEcoIPの開発した経緯を振替えてみたいと思います。
2014.09 開発のきっかけ
下記は、2014.09.22の私のFacebookの記録です。

私は、2014.07.01に私の最初の会社であるTRY㈱を起業し、その2ヶ月後の9月に自社用のシステムを開発し始めました。
自前でシステム開発に取り組んだ理由は、主に以下の3つでした。
(1)前職で使っていた***DATAと言うシステム、当時、特許事務所向けに一番いいと言われていたシステムがあったんですが、実際使って見たら、非常に使い勝手が悪く、カスタマイズもしてくれなかったので、前職では、しょうがなく、自前でこのシステムを補充するExcelマクロを開発して、組み合わせて使っていました。(実際のところ、この会社2014年10月に潰れました)
(2)IT派遣会社を経営している私の大学先輩(図2の左側の人)から、自社の一番優秀な開発者(図1の後ろに立っている人)を付けてくれるから、自分で開発してみたら?と言われました。
(3)話してみたら何でもできそうな、賢い開発者と偶然巡り会いました(私の隣の人)
言わば、既存の市販のシステムは気に食わず、周りの人からお前自分で作ってみたら?!と言われたからです。
その時の開発のスケジュール感としては、3ヶ月ぐらいで出来上がり、その後、3ヶ月ぐらい掛けて微調整すれば完成されると思って取り掛かりました。
それが、今まで6年間立っても、完成されておりません。
最近私はもうシステム開発って完成はできないと思っています。
私が求めるシステムとは、永遠と完成型で存在しないと思っています。(笑)
2015.02 失敗後、再チャレンジ
2014年の年末まで完成させようとしたところ、12月の中旬になっても、1%も作れず、ずっと、基礎工事をしている状態でした。
私としては、前職でいろんな苦労をしていた、非常に具体的な要望を出せる訳で、それを開発者2人体制で、半年ぐらい掛けてさっさと作れると思ったのに。。。
半年ぐらいで3階建ての別荘を作れると思ったのに、
3ヶ月だっても、未だに土地を掘っている感じでしたね。
開発者2人掛かりで3ヶ月やったけど、目に見えるものはなんもありませんでした。
そこで、大学先輩にずっとご迷惑掛けるのも申し訳ないと思い、さっさと開発を諦めました。
その後の展開が面白かったんですが、
先輩の会社の一番優秀だった開発者、その時既に15年間の開発歴を持っていた方が、2ヶ月間、私が作ろうとするシステムの未来像について物凄く洗脳されたせいか、「今、このプロジェクトを諦めるのは絶対ダメ!」言い出して、あの会社を辞めて、無給でもいいから、是非引き続きこのシステムを開発をやらせてほしい、と言った訳です。
それだけではなく、彼は、このシステムの構築思想の提案者でもあった「なんでも屋さん」も説得してくれ、結果的には、「なんでも屋さん」もIT会社を辞め、このシステム開発し始めてから半年後、開発中止してから2ヶ月後の2015年2月に、LTASSと言うシステム開発会社を立ち上げることになりました。
そのときの記録からの抜粋。
我々のシステム開発をメイン事業としている会社---LTASS株式会社、について記録しておこう。
︙
いつ潰れるか、或いは、どこまで上手くいくか、全く分からないが、できるところまで、頑張ってみる!
このように、会社を作って、そこで、開発再開することになりました。
この二人は、未だに私と一緒にこのシステムの開発に邁進しています。
2015.06 目処が立ってきた
彼らは生活費しか貰えない状態で4ヶ月頑張って、2015年6月頃になって、なんとなく基本的な情報が管理できるシステムが出来上がりました。この時のシステムは本当にシンプルで、
(1)依頼人、出願人、発明者、外注者(現地代理人)などの人的資源の管理(我々内部ではCRM管理と言います)
(2)出願番号、出願日、登録番号、登録日、自社整理番号、依頼人整理番号などの案件基本情報の管理
(3)法定期限、指定期限、顧客期限を、全て手入力による管理
だけでした。本当に、Excelマクロで開発したレベルのシステムで、データのバックアップ、改ざん防止のメリットしかなかったものでした。
それにしても、一応、可能性は見えたし、知財について素人だった開発者達も1年近く私の教育を受け、知財業務の流れも分かって来たし、兎に角、この開発チームが長続きできそうだったので、本格的に外にも売ろうと思い、システムに名前を付けようと思い、Ecoと言うワードに辿り着きました。
システムの名前を考えながら書いたのがこちらの記事になります。(2015-06-05 21:46:18発表)
記事からの抜粋は以下の通り。
引用1:
eco(エコ)という言葉は、ecology(生態系)とeconomy(経済)の両方の接頭語です。この eco という言葉自体の由来は、ギリシャ語で house(家)という意味だそうです。
引用2:
エコノミーとエコロジーという語はいずれも、ギリシャ語で「家」を意味するoikos(オイコス)に、それぞれ「規則/規範」を意味するnomos(ノモス)と「論理/学問」を意味するlogos(ロゴス)が付いてできた合成語です。
多分、経済的で、生態系的な存在、プラットホーム的な存在になってほしいと思ったんでしょう。
その3日後の2015-06-08、日本特許庁にEcoIPと言う商標を出しました。

今現在でも、日本では全区分で見ても、EcoIPと言う文字の組み合わせの商標は1つしかありません。我々LTASS㈱が持っています。
2016.11 世の中に出せるまで、また1年半
私がニーズを整理し、彼ら2名が開発をする、この3人チームでコツコツと開発して1年掛かった2016年6月、ようやく世の中に出せそうだったので、11月開催される特許情報フェアに申し込みました。それに間に合わせるために、9月、10月は、ほぼ毎日夜遅くまで開発に邁進しました。


2016.11展示会出展の写真
ご覧の通り、非常にオンボロの装飾でした。
三日間の展示会で、システムについての有効相談数はゼロでした。
但し、偶然(じゃないかも?)ながら某中小企業と知り合いになり、その会社は未だに我々にグローバルレベルの知財権利化業務を依頼しています。その中小企業は中国人の発明者も多く、中国にも研究開発チームがあるため、確かに我々みたいに、東京に在籍している中国実務ができる弁理士チームじゃないと対応難しかったと思います。
その時に書いた記事は下記の通り。
2016-11-08(21:07) に書いた記事。
この記事は、特許情報フェア開催日の前日の夜に書きました。
午後には会場に行って、装飾の手伝いをし、それが終わってから事務所に戻って書いた記事です。
一部抜粋は下記の通り。
プラットフォームを目指す、このシステムに登録したデータを利用するいろんな便利ツールを開発予定
社内サーバー版およびクラウド版を設け、担当者毎の業務量を俯瞰的に把握することができ、業務の流れを効率的に管理することができる
案件管理、期限管理、顧客管理、財務管理などの充実な機能が標準搭載
基本費用に含まれる機能や件数の制限が一切ない
クラウド版の場合、初期費用がゼロに近い
EcoIPの料金表
未定
料金表も決めてない状態。(笑)
取り敢えず出してみようか?と言う気持ちで、出展しました。
結果は、成約者 0!
2017.11 パートナーと組んでみよう
このように、2016年11月に一応市販できるようなものを作ってから、知財関連業者にアピールし続けました。
そこで、2017年は、日本進出を検討中であった特許DB業者である「Patsnap」さんと組んで、共同出展しました。
この時、Patsnapさんは既に海外では有名な大手特許DB業者であって、日本だけあんまり知られてない状況だったんですね。
今現在は、Patsnapさんは日本に代理店も持っているし、それとは別途、拠点も置いて、自社社員を日本で採用しています。

2017.11展示会出展の写真
この年は、稲畑産業さんからも応援してもらいました。
但し、この年も、メインはpatsnapさんになってしまい、私としても、EcoIPのアピールよりは、Patsnapさんを広げることに熱心になりました。
この時、感じたのは、既に大きくなったDB業者とは組める部分があんまりないことでした。例えば、APIなどでのデータのシームレス的なやり取りができるようになれば組むメリットがあったかと思いますが、そのようなことをするには、我々EcoIPの魅力って非常に限られていたかも知りません。
2018年 時の流れに身を任せ
2018年になってからは、システムを市販することに焦らず、取り敢えず、自社が満足できる機能を盛りだくさん入れることに専念しました。
また、私自身も本業である特許関連会社のほうが忙しくなり、月に半分は中国に行っていたため、この年は、特許情報フェアも出ませんでした。
その代わり、2018-10-05(18:22)の時点で、下記のような記事書いていました。
一部抜粋すると。
知財業界の組織管理を標準化する
作業効率をアップさせ、人件費削減を図る
業務フローを記録し、社員の実績を見える化する
ある意味、自分のシステムを非常に偉そうに見ていました。(笑)
一部抜粋は、下記の通り。
事務効率アップ
Login型のWEB基盤の管理システムのため、全社員がシステム利用可
全社員が自らシステムにアクセスして閲覧するため、事務員からの一々アシストが不要
情報の一本化管理ができ、誰か一回入力したデータは、全社員が自由に使い回せる
期限管理がめっちゃ楽
自動的・強制的に期限を担当者宛にプッシュ
プッシュは、メールによる通知に加え、Slackによるスマホへのプッシュも可能
財務管理が楽ちん
特定社員のみ閲覧可能で、請求書発行状況、未入金状況が一目瞭然
複雑な検索が可能であるため、いろんな観点から財務状況を絞ることができる
データベースでデータ管理するため、データ紛失の恐れがない
請求書管理、入金管理、送金管理、庁費用管理、口座情報の管理が可能
売上、売掛金、外注費などを複雑な検索式により検索し、統計取ることができる
JPO対応
XMLファイルを解析することで、出願端末とシームレスに連携
庁への提出書類、庁からの発送書類、庁費用引落状況の自動取り込みが可能
出願端末からのXMLファイルを解析し、各データを自動的に整理し、システムに取り込むことができる
検索&抽出が楽ちん
いろんな項目で、過去登録されている案件を検索することができる
定型文
定型文の新規作成・編集・蓄積が直感的にできる
個別定型文と、包括定型文のテンプレートを簡単に編集・登録できる
登録した定型文テンプレートを利用して定型文を作成することができる
dashboard
充実したタッシュボート機能
売上、未回収金状況、業務受注量などを、いろんな観点から経営状況を一目瞭然に把握することができる
この時期は、一時的に、他人に売るよりは、自分が育てた子みたいなシステムを、自分だけ独占したい気持ちもありました。
このシステムがあってからこそ、あり得ないぐらいの物凄い業務量を少人数で回していた訳です。
これは、同時期に書いた別の記事です。
2018-11-06(19:17)の記事。
全日本で第8位にランクインしたよ!との自慢話です。(笑)
一部抜粋は下記の通り。
今年、TOP10には確実に入れると思います。
因みに、
日本で商標出願件数がTOP10に入れる特許事務所ですが、
何人チームでこなしていると思いますか?
当ててみてください(笑)
2019.11 特許情報フェアへの3度目チャレンジ
2019年度は、Patentfieldさんとも付き合いが始まり、API提供を含め、いろいろとご協力してくださったので、特許情報フェアに共同出展しました。
Patentfieldは、2017年よりAI特許総合検索・分析プラットフォーム https://patentfield.com の開発・運営をしています。データ可視化、およびAI・機械学習を活用し、特許、技術調査にかかるコストを削減、難易度を低減させることにより、特許情報・知財情報の有効活用機会の向上、イノベーションの促進化を目指しています。
LTASSは、2015年より知財総合管理システム「EcoIP」http://www.ltass.co.jpの開発・運営をしています。知財サービス業者の組織管理を標準化することにより、業務効率のアップと人件費削減を図り、会社経営への貢献を目指しています。
Patentfield社は非常に若いベンチャ企業で、創業者も私と同年輩で話しやすかったので、組むことにしました。
現在もPatentfieldの経営層が我々の顧問になっています。

2019年特許情報フェア出展写真(右側がEcoIP)


売りポイントは、経営者目線、見える化、業務効率化でした。
今現在、我々は毎月200件前後の新規業務依頼を受けています。
ここ一年間は、このような大量受注に対応できるように、一括生成や、一括変更、一括発送などの機能に力を入れており、メール自動化機能もかなり進化されました。
私の夢
私は前職で、独立開業のための全ての訓練をしたと思います。
その時に、我々が打ってきたのは、業務効率のアップを通じて、サポーターの人件費を下げ、アウトプットに直結する弁理士への支払い額を業界平均の1.5倍にすることでした。
我々の業界は、単純に頭数で5割はサポーターです。事務、経理などの周辺人員ですね。
私は、自社にピッタリのシステムが構築できたら、この頭数を2割以下に下げれると思っています。
そうなると、経営コストを格段に下げることができ、お客様への請求金額が高くないにも関わらず、社員への支払いは他所より高くすることができ、このシステムを使っている会社にいる方は、仕事が楽ちんでありながら、収入は他所より高くなると、思います。
これからも、特許DB業者との連携だけではなく、マネフォワードやフリーみたいな異業種の優れたシステムとも連携できるように積極的に働きかけ、より一層このシステムの価値を高めたいと思っています。
プロフィール

TRY㈱、LTASS㈱の代表取締役。twitter: @TokyoTigerAniki
東北大学(CNIHA)工学部、東京理科大MIP卒。2007年来日、東京の特許調査会社と特許事務所を経て2014年に起業。知財重視型経営を支援。ゼロから開発した総合的知財管理システムECOIPは日中韓の多数の企業や特許事務所に採択されている。現在、日本でIT会社、知財会社を経営しつつ、韓国・ソウルにある特許事務所、中国・北京にある特許事務所の経営にも参画し、日・中・韓の知財業務をシームレスかつダイレクトに支援している。
よろしければサポートお願いします!いただいたサポートは価値のある情報収集に使わせていただきます。
