
【1】職業選択の際に重視すべき2つの視点
この記事は、元ネイリストが診断士になるまでに加筆修正を加えたものです。
高卒で事務職になってみた
本当は、大学に行きたかったんです。でも、ほぼ無勉強で志望校に受かるほど、大学受験は甘いものではありませんでした。
ファストフードチェーンでアルバイトをしながら浪人生活を始めたものの、勉学への意欲がまるで湧かず、ある日突然「就職しよう!」と思い立ち、大手旅行会社で働き始めました。高い予備校の学費を負担してくれていた父に対してなんの相談もしなかったので、きっと腹立たしかったことでしょう(親になった今ならわかる)。旅行会社の倍率はとても高かったようですが、面接官の中にたまたま中学時代の友人の父上がいて、半ばコネ採用みたいなものだったのかもしれません。
いわゆる事務職で、企画・販売される商品が直営店や代理店で予約可能な状態にするためのデータ入力が担当業務でした。発売日前にデータを更新する必要があるため、繁忙期(連休向け商品が立て続けに発売される前など)には連日の残業。
私は、アシスタントとして先輩の仕事のサポートを行なっていましたが、ただひたすらキーボードに数値化されたデータを打ち込んだり、そのデータをプリントアウトして誤りがないかどうかを確認する作業をしたりといった業務内容については、先輩とそれほど違いはありませんでした(将来性は見出せなかった)。
この仕事を誰かがやらないことには企画した商品が販売できないという点では、やり甲斐がなかったわけではありません。でもある日、こう思ってしまったのです。
「つまらない。誰かに喜ばれる仕事がしたい」
ワクワクしない仕事に日常を差し出すことが、虚しかったのです。
「人をきれいにする仕事がしたい」
との思いから、迷わず美容業界を選びました。
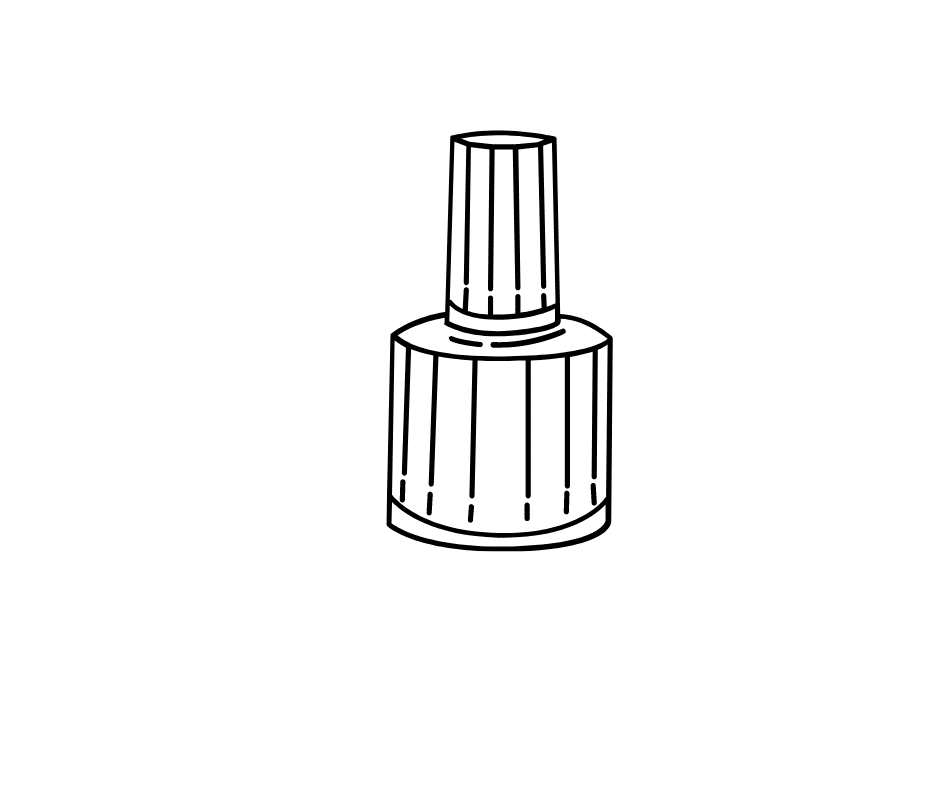
美容業界の職業の中で、なぜネイリストを選んだのか?
美容業界の職業といえば、美容師・エステティシャンなど別の選択肢もありましたが、当時の私は、ネイリストを選びました。
理由は、以下の3つです。
自分の友人・知人には存在しなかったこと
国家資格ではないため、半年程度で“手に職”が実現できること
これから成長していく業界であると見込めたこと
この時もそうでしたが、私は職業選択の際に重視すべき視点が2つあると思っています。
短期的に、ちょっと頑張れば手が届く興味が持てる分野の職業であること
中長期的に、ライバルが少なく今後一定の需要が見込める職業であること
当時のネイル業界は、まさに成長期にあり、就職活動も比較的スムーズにいくのではないかと考えたのです。ハタチで世間知らずを絵に描いたような私でしたが、自信のなさから、無駄な競争に巻き込まれたくないという危機感を持っていたのです。
会社で働きながら、夜はファストフードでアルバイトをして学費を稼ぎ、ネイルスクールに通って、半年程度でディプロマ(修了証)を取得しました。
仕事にのめり込んだネイリスト初期の失敗経験
知人友人などの伝手でお客様を開拓し半年ほどフリーで活動した後、就職活動をしました。幸いなことに、最初に技術試験と面接試験を受けた化粧品の輸入商社に、ネイリストとして採用してもらうことができました。最初は東京日本橋の百貨店内に立地していた店舗に配属されましたが、接客がすきだったこともあって、どんどん仕事にのめりこんでいきました。
就職前には既に、スチューデントサロン(学生が通常の半額程度でサービスを提供するサロン)や美容室でのネイリスト経験もあったことから、入社2か月目には新規店に配属され、4か月目には店長になり、それをきっかけに売上をつくっていくおもしろさに目覚めました。
当時の私は21歳でしたが、マネジメントのことなんて何も分からず、自己流のやり方で売上をつくっていきました。
とにかくお客様から要望があれば、技術的に難しいことだったとしても、何でもやりました。「できません」という一言を言うのが、嫌だったからです。ただ、誰に教わったわけでもなく、採算性だけは何となく気にしていました。
店長になった当月には、売上・利益ともに、当時営業していた4店舗中No. 1を達成することができました。その後、3年間その店舗に勤めながらも、売上・利益の最高記録を更新し続け、ネイリストとしての腕を磨いていきました。

ただ当時は、勢いだけで売上をつくっていて、緻密な計算なんて何もありませんでした。
予約をなるべく効率よく詰めて、忙しい日は休憩をいっさいとらず、毎日「どこまで売上を上げられるか?」という、限界にチャレンジしていました。
もちろん、努力は惜しみませんでした。自腹をきって外部講習にも参加しましたし、自社では取り入れていなかった高度な技術がいるものの採算性の高いメニューも取り入れるよう本社に掛け合って、導入するような働きかけもしていました。
営業時間という制約がある中で、売上記録を出し続けるには、技術のスピードアップを図るしかないと考え、休日には猛練習しました。おかげで、技術のスピードは格段に上がり、普通の人が2時間かけて提供する技術も、1時間程度で仕上げられるようになりました。
提供技術のスピードの速さも、私にお客様がついた要因だったように思います。個人売上は、全スタッフ平均の3倍ぐらい稼いでいました。
この時点では、肩書きは店長だったものの、単なる個人プレーヤーとして売上を上げていたに過ぎませんでした。右腕となるスタッフもおらず、孤独な戦いでした。売上至上主義の私と働いていた当時のスタッフは、大変だっただろうなと思います。なのに、当時の私は大いなる勘違いをしていました。
「私は結果を出しているのだから、これでいいんだ。文句を言いながらマイペースで働く子たちが、理解できない」
なんとも、傲慢で恥ずかしい限りです。
いつの間にか、系列店は8店舗に、入社当時は10人にも満たなかったスタッフの数も、30人以上に増えていました。ただ、驚くべきことに、黒字店舗は私が店長を務める1店舗のみでした。
ネイリストとしての転換期をもたらした究極の選択

そんな折、新しい部長が入社してきました。
私が店長を務めていた店舗は、都内でありながらも僻地だったので、本社の人間がくることは殆どありませんでした。それなのに、その部長は2週間に1回ペースで通ってくるようになりました。一緒に昼食をとったりお茶したりしながら、仕事に対する熱い思いを語り合っていたように、記憶しています。
見た目が派手だったからか、どんなに売上を上げても、本社の人間に褒めてもらったことなんて一度もありませんでしたが、ようやく自分の頑張りを認めてくれる上司に出会えて、嬉しかったのを覚えています。
部長がきて半年程たったある日、まさかの究極の選択をせまられることとなりました。
「ネイルサロンはサービス業だから、店舗としてのブランド価値を上げることが重要だ。そのためには、(一等地に立地する)銀座店をフラッグショップ(モデルとなる旗艦店)にしていきたい。ただ現状は、毎月100万円の赤字だから、まずは黒字にもっていかねばならない。俺はおまえならできると思っている。銀座店に異動してみないか?」(注:時代背景的に言葉遣いは乱暴ですが、パワハラではありません)
正直、相当迷いました。
銀座店は、私が当時店長を務めていた店舗よりもスタッフ数が多いにもかかわらず、客数も売上も半分でした。端的にいうと、暇な店舗に行きたくなかったのです(浅はか)。既に24歳だったにもかかわらず、まだビジネス感覚もなく幼稚な発想しかできなかった私は、これまで貫いてきた売上No. 1の座を退き不採算店にいくことが、自分にとってはマイナスであると捉えてしまったのです。
それでも、部長の真剣な思いが痛いほど伝わってきたため、暫く考えてみることにしました。なぜ、部長が半年間人事をいじらずに様子を見ていたのかというと、新しい環境において正確に現状把握を行い、今後の方向性を決定するにあたっては、「人事・組織は半年はいじらない」のがセオリーだからということでした。
1週間ほどじっくり考えてみましたが、「不採算店を短期間で黒字化できたらかっこいいよな」という単純な発想から、銀座店の店長を引き受けることにしました。
このことが、自分がビジネスパーソンとして物事を捉えることの大切さを学ぶ、きっかけとなったのでした。
職業を選択する際には、短期的な視点と中長期的な視点で判断すべき
どんなに結果を出していても、ワンマンプレーでは満たされないし、周りに認めてはもらえない
管理職でも、現状把握ができるまでは、組織・人事を闇雲にいじらない
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
