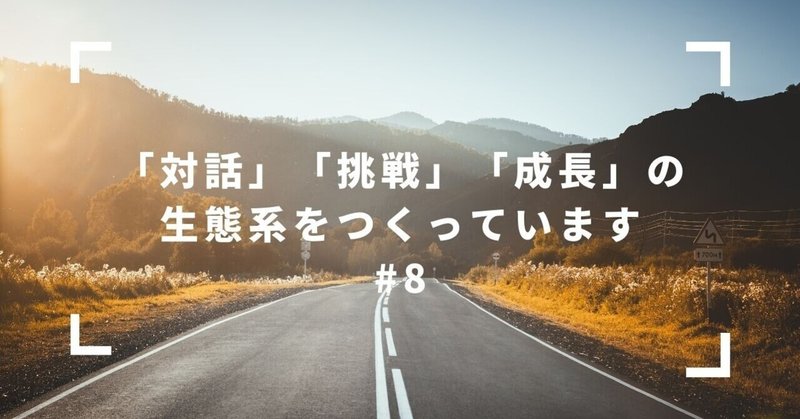
対話とは、「わかり合えなさ」に気づくこと?
イントロダクション
「対話」「挑戦」「成長」の生態系をつくっています、シリーズの8回目です。
前回まで3回に渡って、対話の場、「ソシャり場!」の運営メンバー「世話(焼き)人」についてお伝えしてきました。
今回からは、ソシャり場!で行っている「対話」というものについて、何回かに渡ってお伝えしてみたいと思います。
まずは
「対話」とは何か、と、
なぜ「対話」のコミュニティを運営しているのか、
から。
対話とは「新しい関係性を構築する継続的な相互作用のプロセス」
対話とは何か、をお伝えする前に「コミュニケーション」という概念について少し考えてみたいと思います。
学校や職場では「コミュニケーションが足りない」とか、「コミュニケーションを活性化しよう」みたいな言い回しをよく聞きます。
また、「コミュニケーションスキル」なんて言う言葉も日常的に使っているかと思います。
私自身、過去にコーチングやカウンセリングを学んだ際に、コミュニケーションとは何かを理解し、そのスキルを身につけていたつもりでしたが、この「対話(ダイアローグ)」と言う概念に出会い、コミュニケーションの意味を本当に理解できていなかったと気づきました。
と、言うのもこのコミュニケーション(という行為)を「導管」の様に捉えていたからです。
この「導管」とは何でしょうか?
Aさんが伝えた言葉が、Bさんに一言一句間違いなく“伝わり”、その証拠として、Bさんが復唱できたとします。
確かに、Aさんの言葉が損なわれたり、改変されたりすること無く届いたのだとしたら、あたかも100CCの水が減ったり濁ったりすること無くA地点からB地点に辿り着く「導管」として機能したと言えるでしょう*。
しかし、仮にそうだったとして、そこに込めた意味や想い、もしくは熱量のようなものは「伝わる」のでしょうか?
対話を理解する第一歩は、コミュニケーションや情報伝達を「導管」とみなすこと(=導管メタファー)を捨て去り、「新しい関係性を構築する継続的な相互作用」と再定義すること、です。
そしてこの「新しい関係性を構築する継続的な相互作用のプロセス」こそが
「対話」
なのです。
「対話」を理解するには、それ以外のコミュニケーション方法と比較してみるとわかりやすいでしょう。

「対話」の特徴
・お互いの意見や考えの違いを認め、尊重し、相互理解に至る
・場合によっては、「第3の考え」が産まれる
・話の主体は「私達」(win-win)
「議論」の特徴
・お互いの考えをぶつけ合い、最終的に一つの正解や、答えを導く(二項対立)。
・話の主体は「私」(win-lose)
(大学での講義の際に作成したスライドより)
スライドに書かれていない部分をもう少し補足すると、
「議論」は所謂正解や共通解を導くためのプロセスであり、合理性や妥当性が求められます。
対して「対話」は、自身の経験や、体験に基づく価値観や感情など、「異なって当然のもの」や「正解や間違いのないもの」をその場に出すことから産まれる営みであり、合理性や妥当性とは対極ともいえます。
「ソーシャルイシュー(社会課題)」を扱うソシャり場!に対話というコミュニケーションが用いられるのは必然と言えるでしょう。
続いては、私がなぜ「対話」のコミュニティを運営しているのか、を対話の特徴として挙げた「相互理解」を切り口にお伝えします。
わかり合えない、に「それでも」と言い続ける
この「対話」において、一つ誤解を解いておく必要があるかも知れません。
「対話?お互いの違いを理解し合うことだよね」
「対話を積み重ねていくことでわかり合えるよね」
この様な言葉を聞きます。
この言葉を発している方は対話の可能性を信じている方であり、自身も対話的コミュニケーションを行っている方なのでしょう。
しかし、本当に「対話」によって「相互理解」は得られるのでしょうか?わかり合えるのでしょうか?
せんだいメディアテークの館長であり、哲学者の鷲田清一が、『対話の可能性』と題したテキストの中でこのように述べています。
対話は、他人と同じ考え、同じ気持ちになるために試みられるのではない。語りあえば語りあうほど他人と自分との違いがより繊細に分かるようになること、それが対話だ。「分かりあえない」「伝わらない」という戸惑いや痛みから出発すること、それは、不可解なものに身を開くことなのだ。
(『対話の可能性』鷲田清一 より)
「わかり合いたい」
「伝えたい」
対話とは、そんな想いや願いを持って行われる行為ですが、同時に、話せば話すほど、聴けば聴くほど、他者とは異なる自己、自己とは異なる他者を直視することになる。
寧ろ、安易な同調や共感を示して「わかり合えた」と思い込みたくなる誘惑に毅然と立ち向かわなくてはならない。
また、鷲田は上記テキストの中でバーナード・ショーの”何かを学びましたな。それは最初はいつも、何かを失ったような気がするものなのです”という言葉を引いた上で、こうも述べています。
何かを失ったような気になるのは、対話の功績である。
(『対話の可能性』鷲田清一 より)
私が持ち合わせていない何か。
それが他者の中に在ると知ることは、自身の中に「私が持ち合わせていない何か」の空白に気づくことです。「十分に『足りて』いると思っていたが、まだ空白があった」と気づくこと、すなわち喪失感を覚えることです。
これは辛い。
対話を重ねていくことは、喪失感が無限に続くことでもあるのです。
だけれども。
いや、だからこそ私は
「それでも」
と言いたい。
それでも、
「わかり合いたい」
「伝えたい」
「私が持ち合わせていない何か」に出会い続けた先に、つまり、"「分かりあえない」「伝わらない」という戸惑いや痛み"の先に、「相互理解」があることを信じているからです。何故なら、私が現実的楽観主義者だから(笑)
それが、「対話」のコミュニティソシャり場!を運営する理由です。
まとめ
対話とは、「新しい関係性を構築する継続的な相互作用のプロセス」。
そして、その対話のコミュニティを運営している理由は、
現実的楽観主義者として、他者と
「わかり合える」
「伝わる」
と信じ続けたいから。
今回は「対話」とは何か、と、なぜ「対話」のコミュニティを運営しているのか、をお伝えしました。
実験はつづく
(2021/03/02時点のソシャり場!の実施回数 14回)
*文中でご紹介した「導管」のメタファーについては、「ダイアローグ 対話する組織」から引用しました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
