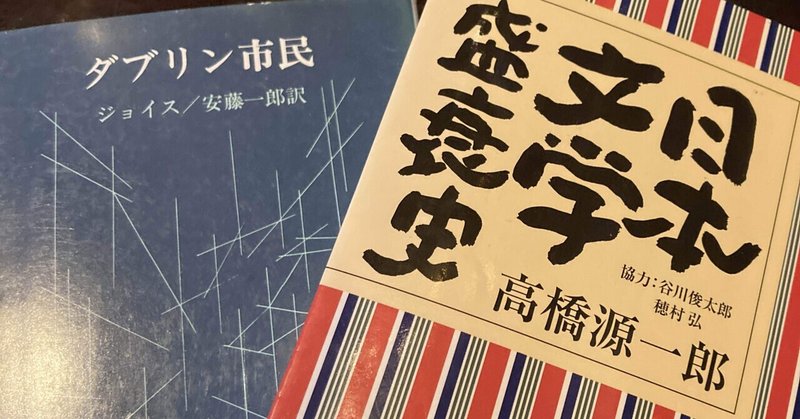
【39冊目】日本文学盛衰史 / 高橋源一郎
1/4です。
本日17時-24時半です。
三が日も終わり本日から通常営業となります。みなさまにおかれましても、本日から仕事初め、あるいは本日までお正月休みという方が多いのではないかと思うのですがね。そう考えると、この1/4という日はなんとも狭間に存在することになる。お正月というハレの日から、日常のケの日々へと狭間に存在するのがこの1/4という日で、なんとも奇妙な感じである。しかして、当店なんていうのは本日から通常営業なわけですから。つまりは通常、日常の生活を取り戻さなくてはいけないわけなんですが、そうなると当店が月初に何をやっているかというと、そう「ウィグタウン読書部」ですね。
というわけで、昨年12月の課題図書は高橋源一郎『日本文学盛衰史』。タイトルだけ聞くと、何か堅苦しい文学史なのかと思いますがね。実際にページをめくってみると、この本は二葉亭四迷の死から始まる。四迷の死を当時の文壇がどのように捉えたか、直接間接と関わらず、関わり合いのあった文人がその死に何を思ったかが、文語、旧仮名交じりに描かれ、なんともブンガク的な幕開けとなり、その描写はさながらドキュメンタリーのようですらある。これを受け読者は、なるほど、二葉亭四迷といえば言文一致の発明者だと国語の教科書で習ったことがある。その死から始まるこの本は、明治から大正、昭和の初頭までの近現代文学をめぐる、文学者たちの苦悩が描かれるのだな、など思う。作中では四迷の葬儀に参列した文学者の名が連ねられ、曰く〈坪内逍遥、池辺三山、夏目漱石、徳富蘇峰、広津柳浪、内田魯庵、半井桃水、島村抱月、泉鏡花、小栗風葉、後藤宙外、小川未明、徳富蘆花、福田英子、森鴎外、饗庭篁村、上田万年、小杉天外、相馬御風、高瀬文淵、田山花袋、長谷川天渓、正宗白鳥、他文壇内外の二百数十名が出席した〉と。こうして連ねられた名前を見ているだけでもテンションが上がるのだが、ところがどっこい、きちんとドキュメンタリーしていたのはものの十数ページで、葬儀に参列した漱石と鴎外が人の輪から離れた場所でそっと会話を始める。四迷の死に対して、今では知らぬものがいない文豪二人が何を語るのか、と読者は期待するのだけれど、その実その場で交わされる会話といえば、漱石が鴎外に対して〈『たまごっち』を手に入れることができませんか?〉と訊ねて、それに対し鴎外が〈娘のマリが持っていたと思います。確か新『たまごっち』の方も持っていたようだ。どこで手に入れたか訊ねてみましょう〉と返すという、なんともズッコケてしまうようなやり取りで、そうかと思えば、弔問客を相手にしていた受付の石川啄木は、退屈しのぎにしょうもない歌を詠んでは暇を潰していたりする。これをして読者は、あぁ。これは、ドキュメンタリーではなくギャグなんだな。ギャグ版の文ストなんだな、と理解するに至るのだけれど、いやはや、この緩急といいますか、今作の書かれた平成の文化風俗をたんまり盛り込んだ上で、実際に描いているのは近代作家の苦悩だったりするので、大変に面白い。私なんかはやはり平成を生きていたので、ある種の平成ポップ的ノスタルジーが乗るのであって、そういう意味でも大変面白かったですね。そう考えると、二葉亭四迷というのは「くたばってしまえ」ということですから。その四迷がくたばってしまうところから始まる本書は、冒頭からメタ的なネタをたくさん放り込んでいるとも言えますね。いいですね。ナイスですね。読んでいきましょう。
本作最大の魅力は何かというと、真面目なブンガクの話が平成風俗にまみれて行われているという緊張と緩和で、そのミックス具合がなんとも最高である。本作はいくつかの章立てから成り立っており、短編集としても読むことができるようになっているかと思うが、例えば四迷の死を描いた冒頭に続く、次章の主人公は石川啄木である。ページをパラパラとめくっていくと、なぜか英語で埋め尽くされているページがあり、これまた、など思いよく読んでみると、それは英語ではなくローマ字で書かれている。つまりKouiu guaide subete ga ro-maji nite kakareteiru nodearu。しかもその内容たるや、"マルキュー前”で待ち合わせした”ミキちゃん”と”渋谷のラブホテル”で”エンコー”したという告白で、私なんかは、読みづらいローマ字で書かれたミキちゃんとのやりとり読んでいて、あまりのバカバカしさに失笑してしまったのだけれど、その実、実はこの「ローマ字日記」というのは実際の啄木も試みていた自然主義的な内面の告白であって、ブンガクの徹底と真実を内面の告白に求めたものとして実際に行われていた実験だったんですね。内容こそ作者の創作ではあるが、当時の文学者にとって「内面の発見」と「真実を描くための美化の否定」というテーゼがいかにセンセーショナルなものだったか。ミキちゃんと売春して、伝言ダイヤルにはまり、ブルセラショップに通い詰めている性獣と化した啄木が描かれる一方で、その姿を美化せずに語る自然主義的な真実への到達をローマ字にして綴る。与謝野鉄幹、晶子とも交流し、私生活をブンガクに落とし込んでいく告白には、その内容のグロテスクさを切り分けても、ブンガクを成そうとした啄木の熱量を感じずにはいられない。
全てがこの調子で、透谷の文学的苦悩を伝えたかと思ったら、そこからシームレスにドアーズの「ハートに火をつけて」が流れ始めたり、大逆事件による死刑執行の様子を厳かに描写したかと思えば、そのニュースを伝えているのが「ニュースステーション」だったりと、見事なまでに平成風俗と文学者の苦悩が接続されている。病弱の詩人、横瀬夜雨を取り巻く女性たちとの関係は、電子掲示板BBSの形式で横書きで書かれ、芸術と娯楽の狭間で苦悩する啄木には『もののけ姫』を観に行かせ、独歩は武蔵野の地を歩きながら女子高生のスカート丈の短さに言及したり、北野武映画を観に行ったりする。その平成と明治のメガミックスが極まるのが田山花袋が主人公の章で、この章で花袋はアダルトビデオの監督になる。花袋の代表作である『蒲団』を下敷きに『蒲団 '98・女子大生の生本番』というAV作品が撮られることになる。戸惑う新米監督である花袋と、百戦錬磨の現場スタッフ兼男優、メイン女優、ベテラン女優、そして「ナイスです」が口癖のプロデューサーまで現れて、まさに平成のアダルトビデオの空気感そのままのアングラポップな展開が巻き起こる。花袋の『蒲団』や『露骨なる描写』に観られる自然主義的内面の追求と真実の吐露が、あけすけな性の現場で軽々に扱われる。己の内面を見つめ、私生活をも開陳して、実在するモデルの人生をも変えてしまうような作品を書いた花袋に対して、AV制作陣は「穴があったら竿を刺せばいい」といったシンプルな論理で説得する様などは、もはや痛快ですらある。この章の中では様々な文学タイトルをAV化した「トンデモ」なAVが複数現れたり、撮影の現場にいたはずがいきなり作者の独白がはちゃめちゃな口語で流入してきたりと、どんどんと文章がドライヴしていくのも面白かったですね。しまいにゃブルセラショップで働く啄木と花袋が語り合ったり、『全裸監督』でもおなじみの村西とおるさんが出てきたり、『ラブ&ポップ』を撮影した庵野秀明がAV撮影の現場にやってきたりと、そのメタコラージュがどんどん加速する。そんなめちゃくちゃな章の中において、島崎藤村の『破戒』に対して花袋が「告白専用の内面なんて、カッコ悪い」と正鵠を射るようなことを言ってみたり、啄木は、四迷の発見した新しい言語による詩作が、結果として詩本来の役割を奪い、二葉亭四迷が文学者として降りざるを得なかった境地に至ったりと、ブンガク的な葛藤はどんどんと放り込まれていく。啄木も藤村に対して「製図家だなぁ」という感想を漏らし、つまりは本当の本当の自己は隠して、告白専用の内面を描いているに過ぎないと言う。鴎外に対しても「ぼくらはみんな二重生活をしている。けれども彼らはそのことを決してお書きにならない」と批判する。ブルセラショプの店長である啄木は、AV監督になった花袋に非常にシンパシーを抱いており、それは真実の告白と自己の内面を見つめると言う、紅露逍鷗時代以後の自然主義へと決着していく。一見はちゃめちゃなエロ描写しかない章ながら、きちっと近代文学の流れを追っていくこの展開には痺れましたね。
しかし、この次の章をもって今作はさらにはちゃめちゃな方向へと進んでいく。作中に作者本人が登場し、救急車で運ばれている間にその車は時空を超え、なぜか作者は同じ病室で同じように療養していた夏目漱石と出会う。ついに平成が明治に「追いついた」と言う感じで興奮しますね。ここからは、作者本人の胃カメラの映像を交えて、腫瘍が消滅していく様を一緒に眺めたり、見舞いに来た糸井重里が「日本語の特徴は改行だ」と言うので
こうして改行をすると
それがなんだか
詩のように見えてきて
つまり詩人になるとは
改行だったのだ
改行にこそ情緒は宿る
みたいなことをやってみたりと、やはり面白い。続く章ではJ-POPとカラオケの前口上付きで若菜集が重なり合ったりもして、口語と文語の端境期にある近現代というものを生きた作家の葛藤を描き出す。
その後に続く「WHO IS K ?」の章は、日本近代文学史上最もポピュラーな謎である、夏目漱石『こころ』内の登場人物「K」とは誰か、に迫る文学研究で、その帰着こそが、ブンガクの新しい潮流を求めた啄木らと、それを黙殺した漱石や鴎外との対立に至るなんていうのは、なんともカタルシスがある。そこに大逆事件などの思想弾圧も加わり、果ては自由主義や自由民権運動が日本社会にどのように馴染んでいくか、という大きな潮流となっていくさまは、いやはや。『日本文学盛衰史』のタイトルに一点の偽りなしという感じでしたね。すごく面白かったです。余談ですが今月、吉祥寺シアターで青年団による『日本文学盛衰史』の舞台があります。令和の時代にこの作品がどのようなマッシュアップを見せるのか、楽しみですね。
というわけで昨年12月の課題図書は高橋源一郎『日本文学盛衰史』でした。今月はジェイムズ・ジョイズ『ダブリン市民』です。タイトルは知っていても読んだことない作品の筆頭ですね。やってみましょう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
