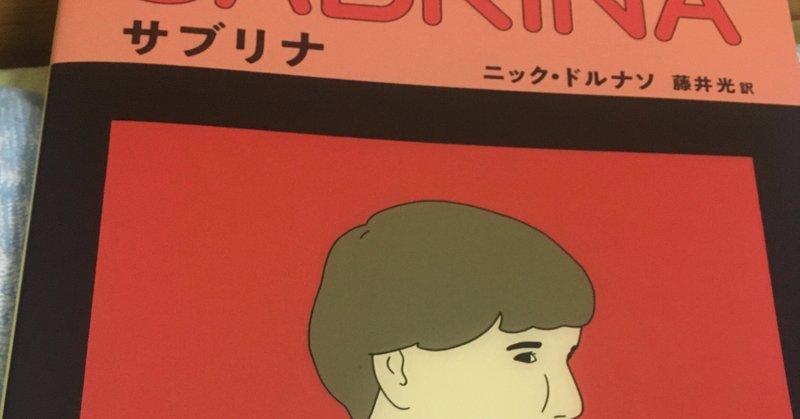
【3冊目】 サブリナ / ニック・ドルナソ
華の月曜日、通称"華月"です。
お正月休みも終わって今日から稼働という方も多いですかね。仕事初めってことで、さっさといつものペースを取り戻したいところですね。日々のルーティーンを、正確な時計の秒針のような動きでこなしていくなんていうのが、永遠にも思える日常を進み続けるための唯一の手段ですよね。そしてその秒針が進む先の未来へと。私たちは知っている。継続こそが力になるのだということを。「やればできるをやったってつまらない」と嘯いた十代を経て、「誰でもできるを誰よりやる」。それ以上の近道などないということを知っている。日々の継続こそが、日常の獲得こそが、最も偉大で、最も得難いものであるということを知っている。そんな当店の月初の日常といえば、そう、ウィグタウン読書部ですね。続けていきますよ。
というわけで、今月の課題図書である『サブリナ』ですね。例によってここからは完全に【ネタバレ注意!】となるので、その辺りをどうかお気をつけくださいませ。まぁ、この作品の場合、いわゆるネタバレというか、どういった解釈が与えられるかが面白い作品だったりする気がするので、こうして私の考察をダラダラやるなんていうのにはぴったりの課題図書ですね。やっていきましょう。
まずは、小説ではできない、グラフィックノベルでしかできない表現について、ちょっとお話ししたいんですがね。
今作において、作者のニック・ドルナソは、我々読者を、徹頭徹尾観客でいるように強制しているように思うんですね。
小説なんていうのは、魅力的で親しみやすいキャラクターに感情移入したりすることで、その作品をより味わい尽くす、という手段が取られることも多いわけなんですね。ですから、一般的な作品レビューなんかを見てみると「主人公に感情移入できない」とかの見出しがついて星一つの評価がついたりするわけですよ。読者を、視聴者を巻き込むために、キャラクターを魅力的で、感情移入しやすい人物に生き生きと描く、なんていうのは、エンターテインメントの基本かとさえ思うわけなんですがね。ドルナソは完全にその逆。感情移入をなるべく排そうという意図で今作を書いているんですね。まずキャラクター。一見して表情が読みづらく、コマによっては単なる点と線のみで描かれている人物さえいる。奇妙な違和感を与える描き方ですよね。中でも、読者が最初に出会う強烈な違和感といえば、カルヴィンの元に身を寄せたテディが悪夢を見てパニックに陥るシーンですね。「あああああ」という画一的な叫び声と、ブリーフ一枚で直立しながら微動だにしないテディの姿に共感する人はまずいないでしょう。描かれる表情など、もはやロボットのそれのようで、カルヴィンになだめられて再び眠りにつく様などは、さながら電源を切られたロボットのようです。この手の「感情が爆発するシーンをわざと距離感を持って描く」という手法は、この後にもまま見られる。例えばカルヴィンがテディに「サブリナの定期券が実家に届いたこと」を伝えるシーン。公園のブランコに座っているテディの元へカルヴィンが行き話をするのだが、その様はすべて遠景で描かれ、会話の内容もすべて「ーーーー」で描写される。詳しい内容が描かれないので、次のコマで卒倒してしまうテディの姿は、読者の目には滑稽にすら映る。また、サブリナの妹、サンドラが身を寄せた友人、アナの元でパニックに陥ってしまうシーンでは、サンドラは髪で顔を隠して表情を読むことが出来ず、ついに叫び声をあげるコマでも、描かれるのはサンドラの背中だけである。
この「読者を観客であることに強制する力」は、その非常に画一的で静的なコマ割りにも現れている。コマは躍動しない。読者は、スクリーンやyoutube画面を見るような感覚で、登場人物たちを見ることになる。「これは"作品"で、ここに描かれている人たちは実際には"存在しない"のだ」と。フィクションの世界をフィクションとして描いている。この構図が、作品を読み進めていくに従って、特別な効果をもたらしていくことになる。では、内容に触れていこう。
私は、今作を「ネットというフィルターを通すことで歪曲する現実の恐怖」を描いた作品ではないかと思う。
「隣人がどこの誰だか分からない」という恐怖を抱く時代は終わった。いまや「よく知っている人物でさえ、ネットを通すと全く知らない人物のようになってしまう」という恐怖が蔓延している時代である。作中の陰謀論者のラジオを引用すると「悪人どもはマントの下に隠れているのではなく、雑誌の表紙を飾っているのだから」というやつである。サブリナを殺したティミーは、彼女の住む家からわずかワンブロック先に住んでいた。カルヴィンの同僚コナーは、陰謀論に染まっている。カルヴィンが最後に見る夢の中で覆面を被った男の吐くセリフは、全てカルヴィンが実際に会った人々のセリフである。そのセリフを言った人々に悪意はないし、そもそもそのセリフにそれ以上の意味などない。ただ、それが覆面を被った男のセリフになると、それが最後の一コマ「俺がこんなの楽しんでるわけないだろ」というティミーのセリフに重なると、周りの人が全て不可解で信頼の置けないものになってしまう。そして、そんな悪夢からカルヴィンを現実に引き戻したのは、部屋を間違えた酔っ払いが叩くドアの音だ。悪意も他意もなく、人は人を傷つけるし、そこには「他者と干渉した」という実感さえ伴わないことさえある。酔っ払いの無意識のノックはカルヴィンを悪夢から救ったが、やっていることは「真実の闘士」を自称してカルヴィンに脅迫メールを送り続けていた男と変わらないのだ。我々はそんな「無意識の悪意」にさらされ続けている。
しかし、ここまで書いてアレなんですけど今回のはなかなかまとまらない気がしますね。これ以降は小見出しをつける形で、気になったところを箇条書きしていこうかと思います。
【脅迫メールの差出人は、コナーではなかったか】
カルヴィンの同僚、コナーですが、作中で最も不気味な人物の一人ですよね。彼の登場シーンを順に追っていくと、作者がいかに彼を恐ろしく描いているかが分かるので、ちょっとやってみましょう。
初登場時、彼はカルヴィンに「何か笑えるニュースをくれ」と言われポルノ女優のステルスマーケティングに関する記事を読む。この際、彼は「陰謀」という単語を口にしている。/次のシーンではタバコを吸いながら韓国人同僚についての話をして「韓国語で俺のことを馬鹿にしてた」と被害妄想を愚痴る。/カルヴィンとコーヒーを飲んでいたはずがいきなり姿を消す。/次のシーンでは、カルヴィンにサブリナの事件発覚のニュースを伝えるという地味だが重要な役割をしている。/ロッカールームで事件の成り行きをカルヴィンと話しながら、特別捜査局の話をする。/仕事中にパソコンでサブリナの動画を見ようとしている様子が描かれる。/他の同僚から「コナーが特別捜査局の面接を受けた」と知らされたカルヴィンが、彼の席を見遣ると、コナーはディスプレイと向き合って"普段と変わらぬ様子で"仕事をしている/サブリナの次の事件「デンヴァー銃乱射事件」が起きた際も、コナーの机を中心に同僚がその話題を口にしている。/そして問題のサーバールームでのやり取りである。陰謀論を口にし、カルヴィンの心を揺さぶる。その後部屋に戻ってからは、またいつもの顔でディスプレイに向き合っている。カルヴィンはメンタル調査票の「今の気分」の項に、最高を意味する「5」をつける。/4ヶ月後、シカゴへ向かうカルヴィンの引っ越しの手伝いをする。最後にダイレクトメールだらけのポストの中身を取ってきてくれる。そして「俺が言ったことを忘れるなよ」という意味ありげなセリフを吐く。そしてシカゴへと向かう途中で、それらのダイレクトメールを確認していたカルヴィンが発見するのは「私たちを裏切るな」という封筒と、そこに同封されていたシカゴのスーパーのディスカウントクーポンである。どうでしょうね。私は、最初にこのクーポンを、誰とも知らない陰謀論者による脅迫と取ったのですが、こうして読み返してみると、これはコナーの手によってもたらされたものである、と取る方が、むしろ自然な気がしますよね。「よく知っている人物が、全く分からない人物になる瞬間」ですよね。怖いですね。
【猫を探しに出たテディは何を取り戻そうとしていたのか】
恋人の死というショックから無気力になり、陰謀論者のラジオにはまった彼が物語の終盤、いなくなった猫を探しに外に出るシーンがある。この「猫を探す」というムーヴを作中で行なっている人物がもう一人いる。サブリナその人である。冒頭の彼女のムーヴと、終盤の彼のムーヴとをシンクロさせることで「まだ事件が始まる前の日常」を彼に取り戻させようとしたのではないか。これは、物語のラストで、作中唯一サブリナと直接的な会話を持っている妹のサンドラが、その会話の中に出た自転車旅行に行っている描写でも同じことが言える。事件以前以後で分断されたかのように見える彼らの日時は、それでも一定の速度で続いていくのである。
あとはなんでしょうね。カルヴィンの別居中の妻娘と、その持ち物であった絵本の内容とかでも、なんか言えそうな気がしますね。ただ、ちょっとまとまりそうもないので、この辺にしときましょうかね。冒頭で話した「他者であることを強制する力」も、作品の内容と併せると、我々は傍観者であり、監視者であり、同時に当事者になり得るのだ、という効果をもたらしますよね。だらだら書いた割にちょっとまとまりが悪すぎますね。反省しております。
というわけで、謹賀新年な今月の課題図書は阿部和重『ニッポニアニッポン』です。お正月っぽいですね。毛色を変えていきたいですね。やっていきましょう。
(posted on Facebook on the beginning of January)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
