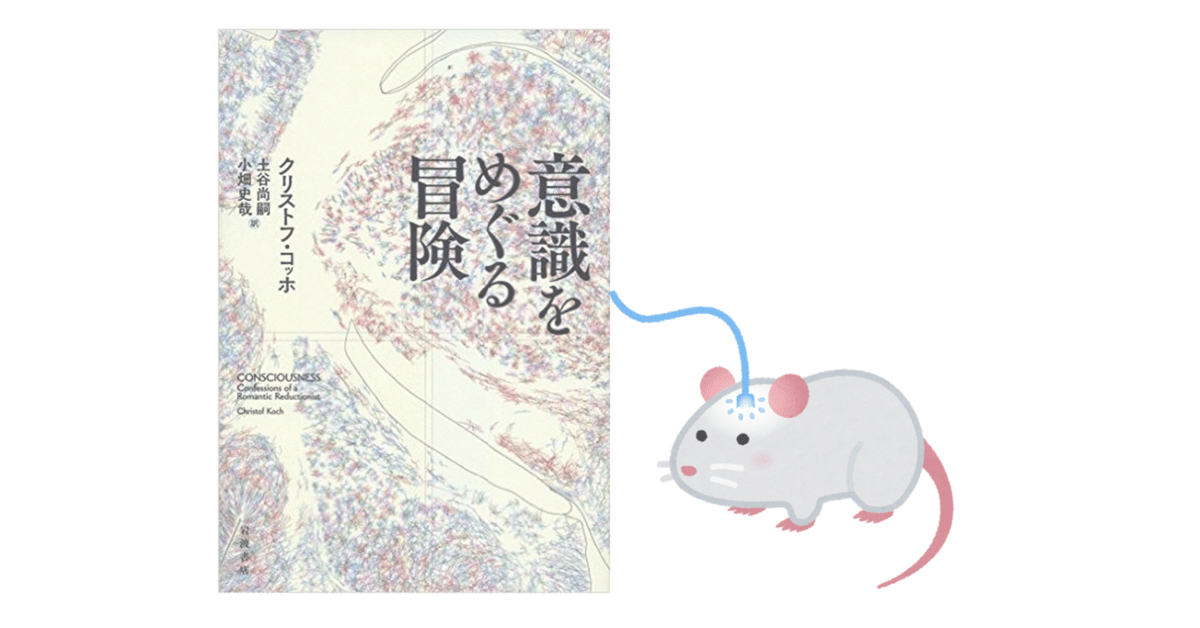
意識とは何か?意識をめぐる冒険(クリストフ・コッホ著)
以前に別所で書いたものを移行(アーカイブ予定)
表題の通り、「意識をめぐる冒険(クリストフ・コッホ著)」を読みました。

とても素晴らしい本でした。読んだ後も数日は読後感の余韻に浸っていたような気がします。科学者の知性を分かりやすく咀嚼し、わたしのような素人・一般向けにおすそ分けするよう配慮された文章にも感銘を受けました(翻訳者の超訳が非常に秀逸だったのかもしれません)。
クリストフ・コッホとは
クリストフ・コッホ氏はカルフォルニア工科大学(通称カルテク)とアレン脳科学研究所で所長を務める著名な脳神経学者です。DNAの「二重らせん構造」の発見で有名な故フランシス・クリックと意識研究において長年パートナーを組んでいた経歴を持ちます。また日本人の意識研究者である土谷尚嗣さんの指導教官でもあるようです(土谷さんはこの本の翻訳者です)。
意識のハード・プロブレム
そしてこの「意識」についてですが、脳科学において「ハード・プロブレム」と呼ばれる領域があります。ハード・プロブレムとは「クオリア(感覚質)」と呼ばれる意識体験がなぜ創発されるのかを(現時点では)科学的に説明できないことから、このように呼ばれています。
意識のハード・プロブレム - Wikipedia
私たちは意識体験というものを自覚しています。しかし自分の意識体験は自覚できるものの、他人の意識体験を証明することはできません。他人が意識を有していることは脳内の電気信号などの状態と「私は意識を持っています」という当人からの申告でしか確認することはできず、これは意識を有しているだろうと推測しているに過ぎません。
現時点では、どんなに脳イメージングの観測技術が発達し、脳の分子的な状態遷移と複雑なネットワークのメカニズムが完全に解明されたと仮定しても、他人が有する意識体験はその当人にしか自覚できないということがこの問題がハードである理由です(*1)。
哲学的ゾンビ
なぜこれが問題であるか。それは「哲学的ゾンビ」という概念があるからです。哲学的ゾンビとは、一見私たちと同じように意識や知能(思考)があるように見えるが、その当人には主観的な意識体験が存在していないことが成立するという考え方です。つまりは「クオリア(感覚質)」を持っていないということです。
私たちがイメージするSF的な機械(ロボット/アンドロイド)では、わたしたちと同じ意識を有しているように描かれています。たとえば鉄腕アトムやドラえもんなどが代表例です。しかし現実のロボットに知能があると感じても、意識まで有していると考える人は多くはないかもしれません(ただ、愛着が湧くことでロボットが生きていると感じることはありそうです)。
また「虫に意識はなく、ロボットのように反射をしているだけだ」と考える人は多そうです。同様に魚類に意識は無いと考える人もたくさんいるでしょう。では爬虫類はどうでしょうか。マウスや猫はどうでしょうか。さらにサルは、チンパンジーやゴリラなどの類人猿は・・・と人間に近づくにつれて境界が曖昧になってきます。
この「意識をめぐる冒険」は上記のような事柄や著者の研究者としての人生を踏まえて、「意識」という不可解な事象に挑戦するクリストフ・コッホの物語です。
脳神経学についての基礎的な説明だけでなく、コンピューターや人工知能、遺伝子や宇宙論、量子力学、カオス理論、自由意志と決定論、哲学や宗教(魂)と多岐に渡る分野に言及しながら物語は進みます。
後半では意識研究で主流となっているIIT(統合情報理論)についての説明があります。IIT(統合情報理論)はイタリアの神経学者であるジュリオ・トノーニ氏が提唱した理論です。トノーニ氏の著作「意識はいつ生まれるのか」も拝見したので機会があれば別途書きたいと思います。
意識はいつ生まれるのか――脳の謎に挑む統合情報理論(著者: ジュリオ・トノーニ,マルチェッロ・マッスィミーニ)

「意識をめぐる冒険」では、コッホ氏は人工意識について肯定的に捉えています。Googleなどが行う人工知能のカンファレンスなどに出席し、意識研究をリードする著者が肯定的なことはとてもエキサイティングに感じました。
意識と死生観
最後に著者は「死」について肯定的に捉えていることを述べました。コッホ氏は元々は敬虔なクリスチャンでしたが、本書最後には死生観が変わることを示唆しています。わたしもこの本を読んだ後に「死ぬこと」とは「意識がなくなること」ではないかと、ほんの少し考えられることができるようになり、すごくホッとした気分になりました。死の間際に苦痛がなければ、本当に眠るように死ぬことになります。まだまだ死ぬつもりはないですが、将来的にはそのことが死の恐怖を和らげてくれるような気がしています。
アラヤ・ブレインイメージング代表(兼ニューロサイエンティスト)の金井良太さんが「意識の解明は死生観を変える研究とも言える」(確かこんなニュアンス)とTwitterで呟いてことに共感しています。
子どもの頃から、あるときふと「いつか死ぬ」を思い出して、なんだか怖くなっていたことがあります。そのことを意識すると今でも怖いのですが、ただ本書を読むことで「生」と「死」の境には意識の「創発と消失」と捉えることもできるのだな、と考えるようになりました。明確な違いとしては「目が覚めることがない」ことを認識しているかどうか。
意識の創発は(自分にとっての)世界の始まりであり、意識の消失によって世界は幕を閉じるという哲学的な考え方に共感しています。
おわりに
死生観については深く考えているわけではないのと、また、これは年齢を重ねることでまた変化するかもしれませんが、幸いにも「意識」の研究は数十年をかけてさらに進んでいくように思います。そしてその研究成果と一緒に年齢を重ねることができる時代に生まれたて本当によかったなと改めて感じます。
意識研究が人々から誤解を受けることなく進んでいくことを願っています。
(*1) とはいえハード・プロブレムを攻略する取り組みとして、アラヤ・ブレインイメージングCEOの金井さんの公開文献「意識の謎に挑む(PDF)」を拝見しており、6章の「クオリアに挑む」の内容が面白いです。ただ「意識の謎に挑む(PDF)」は2013年頃の内容ですが、アップデートを踏まえた最新の記事がnoteに投稿されています
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
