
マラドーナ。
最初に心躍らされたフットボーラーは
1988年ヨーロッパ選手権の " ファン・バステン " 。
初めてテレビで観たW杯の
1990年イタリア大会で惹かれていたのは
ベルギー代表の10番 " エンツォ・シーフォ " 。
それからはずっと
" ペップ・グアルディオラ " でした。
そう、じつは
自分のフットボールライフの中で
" ディエゴ・アルマンド・マラドーナ " は
ど真ん中にはいなかったのです。
でもずっと
彼を知ってから今の今までずっと
気になり続けている存在で。
そんな選手、他にはいませんでした。
「 アンタッチャブル 」な存在。
プレーや佇まい
言動、ストーリーなどすべてにおいて
そのときの自分の想像を
軽く超えてしまっていることに
アンタッチャブルさを感じて
気づかないうちに「 畏れ 」に近い感情を
抱くようになったのかもしれません。

でもその感情は、次第に変化していきました。
それはたぶん
自分が19歳でブラジルにサッカー留学したり
バックパッカーでいろいろな国を旅したり
コスタリカへサッカーチャレンジに行くなかで
たくさんの人や生き方に触れていくことで
自分の中でアンタッチャブルだと感じているものが
じつは世界の視野で考えたら全然そんなことなくて
むしろ、とてもとても欲しいものなんだと気づいて。
そして同じ経緯で
岡本太郎やブルーハーツも
大好きになっていったのでした。
で、マラドーナに関しては
絶版となった幻のこの名著との出会いで
さらに特別な存在へと変化していきました。
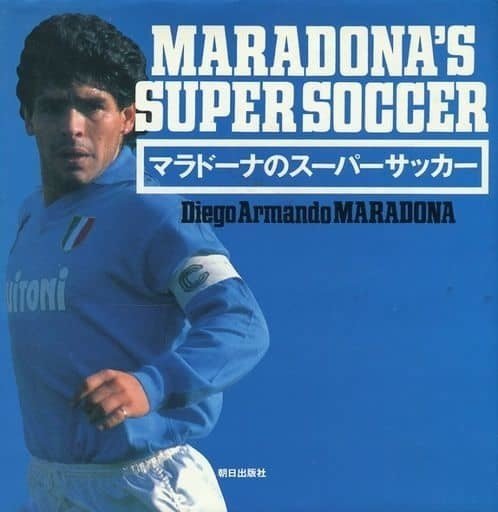
序文のこの文章からしてサイコーなのです。
「 サッカーを今現在
実際に楽しんでやっている君たちに向かって
ボクがあらためて
(自分のプレーを解説するとは言っても)
サッカーのテクニックについて
あれこれ言おうとすることに
最初はボクも気乗りしなかった。
だって君たちは君たちなりに
十分サッカーを楽しんでいるんだし
それ相当のレベルに達していると思うからだ。
たとえそのボールの扱い方や、
ゲームに対する考え方が
ディエゴ・アルマンドという
一個人と違っていたからといって
それは間違っているとか、
直さなくてはいけない
とかいった
レベルの問題ではないと思ったのだ。 」
「 たとえば極端な話
ボクの蹴り方はフリットとは違うし
プラティニなんかとも違う。
弟のラウールやウーゴは
ボクと似ているかもしれないが
それでも全く同じように
蹴るということはない。
それぞれが、自分の好みや
考え方に合うように
ボールを扱っているのだ。 」
「 そう考えながらも
カメラマンの “ タカ ” や
構成者の “ ヨウイチ ”
それに出版社の並々ならない熱意に
負ける形になったのは
ボクのサッカーのスタイルややり方
考え方を < 決まり > としてではなく
ひとつの < モデル > として出すことによって
これを見る人に、ボクが
サッカープレーヤーとして感じている幸福感を
わかってもらえるような気がしたからだ。 」
「 だから、この本の最初に当たって、
ボクが君たちに期待するのは、とにかく
サッカーの素晴らしいシーンを楽しんでほしい
ということ。
そして、ボクのプレーで
参考になることがあったら
君たち自身のサッカースタイルに付け加えて
もっともっとサッカーをやることを
楽しんでほしいということなのだ。
幸運を祈る! 」
これを読んであらためて気づいたんです。
自分は「こうしろ」と押しつけられるのも嫌だし
周りに対して押しつけるのも嫌なんだと。
マラドーナを知ってすぐのときの自分は
周りに合わせて評価されることを良しとしていたから
周りとは明らかに違う彼に対して
妙な違和感しかなかったんですよね。
けど、海外に出てみて
本当は自分も周りの目とか空気とか関係なく
自分自身の心に応えて生きたいんだ
と気づいてから、見方が変わっていった。
たぶんこれからもずっと
いや、これからもっともっと
スペシャルな存在になっていくんだと思います。

このマラドーナの
スーパープレーTOP50動画オモシロイです。
個人的には、#20 と #26 が特にヤバかった…
たくさんのインスピレーションをありがとう。
R.I.P Diego.


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
