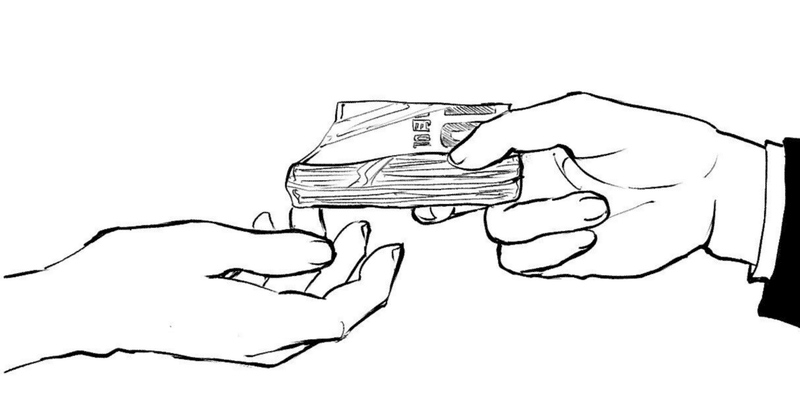
手の役割分担を考える~手の発達を促すために必要なこと~
手の役割分担が意味すること

手指は、全部で5本ありますが、日常生活動作の違いによっては指の役割は違います。
その役割とは、機能性と固定性です。
親指、人差し指、中指までは機能性の役割を担う

親指・人差し指・中指は機能性(道具を操作するために動く役割)を担います。
薬指、小指は固定制の役割を担う

薬指・小指は固定性(手を安定させるために固定する役割)を担います。
手の役割分担を日常生活動作に当てはめて解説する

日常生活動作のハサミ、箸、鉛筆の持ち方を例に挙げ、指の役割分担について解説していきます。
ハサミをもつ

画像では、機能性の親指と人差し指が支点となっています。
親指の開閉運動(外転と内転)を繰り返しながら、
人差し指は紙を切る方向性の安定性とハサミの開閉運動のために動かします。
薬指と小指は、ハサミ本体を安定させるために固定されています。
下の記事には詳しくハサミの使い方が書かれています。
箸をもつ

箸の操作は、特に巧緻性の高い指の操作を必要とします。
下箸は薬指の側腹で固定させ、小指は固定性をさらに強化させるために関節を曲げて固定しています。
親指も下箸を抑えるために固定性に作用しています。
親指と人差し指、中指は上箸を動かします。
箸の動きが特に難しい理由は親指にあると考えられます。
親指は機能性と固定性の両方を担っているからです。
上箸を動かす時は、親指の関節(IP関節)の曲げ伸ばしの運動を行いながら、親指の付け根で下箸も固定しているため、親指が忙しいです。
鉛筆を書く

鉛筆で細かく字を書く時は、親指、人差し指、中指の3本指で鉛筆を動かします。
薬指と小指は、安定性を付与するためノートに押し当てています。
下画像のような握り方で鉛筆やシャーペンを把持している方もいますが、一番機能しないといけない親指が固定になっているため、細かい字を書くことが難しくなります。
安定性は高くなりますが、この握り方では親指を固定してしまっているため、親指側の筋肉を動かす機会が減り、手の筋肉の発達を促す事が難しくなってしまいます。

正しい鉛筆やクレヨンの握り方については下の記事に書かれています。
おわりに
遊びの中でも、指の役割分担を意識した指の使い方をすることで、手の発達を促すことができます。
子供が集中して楽しめる遊びの中で、手を動かす事はとても良い事だと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
