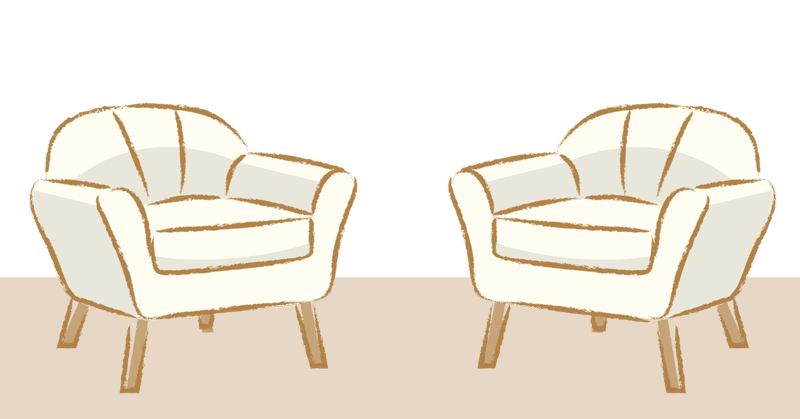
自己紹介に代えて 〜対話をめぐる話〜
4月から沖縄のとある共同売店で働きはじめた。
共同売店とは、住民が出資しあって運営するお店のことで、明治末期に沖縄で生まれたらしい。現在わたしがかかわっている売店は、地域で運営されているが、住民が出資しているわけではない。だから、本来の共同売店ではないが、昔ながらの共同売店的な要素を持ったお店であり、小さな集落での暮らしを支えるインフラとしての役割を担うものとして、地域住民からは認識されているように思う。
じつは、今回この職場で働くのは2回目だ。3年前に3ヶ月間だけ働いていたことがある。
辞めた理由はいくつかあるが、表向きには、「他にやることができたから」ということにしている。だが実際のところ、地域のおばさんたちと衝突してつづけられなくなった。おばさんといっても、60代後半~80代の方たちだ。
どこの地域もそうかもしれないけれど、ここでも、年長者の、特にこの土地に長く住んでいるひとの意見ほど重んじられる。わたしみたいな移住者の意見は、跳ね返されることの方が多い。だから、いくら戦略を立てて会議で説得を試みたところで、ことごとくダメだった。
しかも、人口100人程度の小さい集落だ。地域の有力者の言うことは絶対、みたいなところが少なからずある。ただ、頭ではそういう現実があるとわかっていたとしても、からだは受け入れられなかったのだろう。ちょっとした認識のずれやコミュニケーション不足が誤解を招き、そこからさらにヒートアップして対話ができなくなったときには、すでに精神的なバランスを崩していた。燃え尽きてなにもしたくなかったし、なにもできない感覚に飲み込まれていた。文字通り、動けなくなってしまったのである。
いま振り返れば、売店に対するそれぞれの思いが強かったがゆえに、やる気が空回って、うんともすんともいかなくなっていたことがわかる。自分に対しても、あのころ正面突破しようとしていたのを、なんて不器用だったんだろう、と思えるくらいの心の余裕はできた。
だが、そう思えるようになるまでに、それなりの時間を要した。地域のさまざまな行事や集まりに参加することを通して、年長者への感謝の気持ちを忘れず、また意見を尊重するだけでなく、ときには根回しをするのも大事だとまなんだ。それは、長いものに巻かれろということではない。この状況を変えていくには、ここで生き抜いていくには、それなりの作法を身につけて、したたかにやっていくことが求められるということだ。
想像してみてほしい。それはきっと息の長い挑戦になる。前みたいに、また放り投げたくなることもあるだろう。
それなのに、なぜそんな職場にもう一度戻ってきたのか。一言で言えば、それは地域の未来をつくっていくプロセスに興味があるからだ。共同売店は、地域の交流の拠点であり、一番近いコンビニまで車で30分、スーパーまで1時間の集落では、買い物支援の役割も担う。実際のところ赤字経営がつづいており、どうにかするには観光客を相手に外貨を稼ぐ必要はある。だが、ここは地域住民にとって「第二の公民館」のような場所だ。そういう大事な場所として、ここをまもっていくにはどうしたらいいのか。
必要なのは、「対話」ではないかと考えている。新しいことを導入しようとしても、昔ながらのものに引き戻そうとしても反発が起きるのなら、なおさらたがいの話を聞くということが大事になってくるだろう。特に、多世代間でその機会を持つことが、不可欠になってくるはずだ。
簡単に分かり合えないからこそ、ことばを紡ぎ、違いを浮き彫りにするのであり、向かうべき方向を定め、どうやっていくかいっしょに考えていくのだ。その対話を通して、なにがどう変わっていくのか、わたしは見てみたい。
ここで、なぜ対話にこだわるのかということを少し話しておこう。対話を考えることは、わたしにとって、沈黙をめぐる問いを握りしめ、また解いていくことを意味する。先に暫定的な結論を述べておけば、沈黙するのは、抑圧され、語れない状態であると同時に、自分をまもる能動的な行為でもあると思っている。
そう考える背景には、盲目的なキリスト教徒だった母との関係がある。神の律法を重んじる母の価値観に合わせるしかない家庭環境下において、わたしは秘密をつくり、沈黙をまもることで、自分をまもろうとしていた時期があった。そして、家の外でもそういう反応をくりかえしていった。自分の意見を言ったら批判されるのではないか、攻撃されるのではないかと過剰に防衛するようになり、気づいたころには、ことばを飲み込んで沈黙することが、生き抜く術として定着していたのである。
しかし、それではいつまで経っても自分はだれかの支配下で操られているのではないか。そんなのはごめんだ!沖縄に足を運ぶようになってから、そんなふうに考えるようになった。
詳しい話は省略するが、沖縄は「戦後」ゼロ年(目取真俊)と言われてきた。軍事基地が集中し、基地関連の事件が相次いできたほか、近年は有事の備えとしてシェルターがつくられたり、ミサイル攻撃に対する避難訓練が導入されたりしている。
そうしたいのちが危険にさらされた状況下で、危機を察知した人びとがつぎつぎに姿をあらわし、いのちをまもり、生きのびていくにはどうしたらいいか考え、ことばを発してきた。しかしながら、なにを言っても、その声は聞きとられず、状況は変わらないどころか悪化していくことの方が、圧倒的に多い。それでも人びとは生きのびようとことばを紡ぐ。
わたしは、そうした人たちとの出会いを通して、ことばを紡ぎだすことを通して生きる営みが確保され、維持されてきたことと、いまにつながる長い歴史を知った。
抑止論や同盟関係の強化をはじめ、だれかにとっての「正しさ」をそのまま鵜呑みにしていては、殺されるかもしれない。自分はこの状況をどう感じているのか、どうしたいのか、なにがイヤなのか。感情や意見を外に出して、表現していくことで、生きのびようと試みるのだ。
そうして、それまで自分のなかに抑圧されてきたものを、言語化して、この世界に「ある」ものにして、だれかとわかちあう。それは、大げさに聞こえるかもしれないが、いまわたしたちが生きるこの場所の運命を変えていく、そのような営みだろう。
この流れでする話ではないかもしれないが、わたしはつい数年前まで、人びとの経験してきたことを聞き、書き起こしていく過程を、対話の場として設定し、どのように関係性や立ち位置、生き方、価値観が変化してきたか、大学で研究していた。アカデミアに留まらない選択をしたのは、なにかを論じることよりも、生きることそのものにひかりを見たからだった。
だが、これは言い訳に過ぎないのかもしれない。実力もないのに、カテゴリーさえはっきりしない変な研究テーマに取り組めば、当然評価されるわけがない。側から見れば、いじけてやめたように見えていたことだろう。
大学から離れたいま大事にしているのは、くりかえしになるが、日々の暮らしのなかで、ことばを紡いでいくことであり、対話していくということだ。対話を通してなにかを変えていくには、時間もかかるし、多くの困難を伴う。だが、なによりおもしろそうではないか。
わたしは、対話を通してなにかがはじまることに賭けている。
共同売店は、そのはじまりの場所になるにちがいない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
