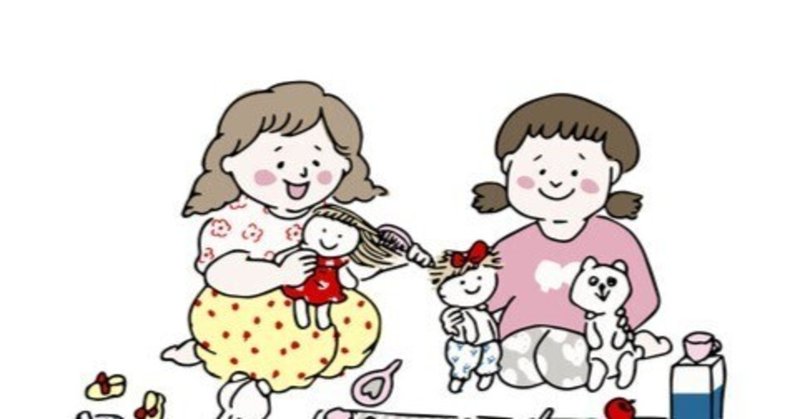
子どもと人形
穢れの祓いだったり呪いだったり人形には多くの活用方法がありましたね。
幼児を守るための人形だった天児というものがありました。

実際に貞丈雑記にはそのことが書かれてあります。
天児は3歳くらいまでの子供に与えられており、今で言うところのぬいぐるみのようなものでした。
室町時代に入ると這子と言って子供がハイハイをしたような形の人形となりました。

元々、這子は赤色で作られることが多かったのです。
これは恐ろしい病である天然痘の疫病神が赤を好むために、子どもではなく這子に病が移るようにという願いから赤色となりました。
また、這子は逆さまにして猿の人形に作り、庚申の日の呪物にも使われました。
撫物として簡単な作りだった人形も、時代とともに洗練されてきます。
流し雛が生まれたのはそういう背景でした。
現代でも、一部の地域では流し雛が行われています。
オリジナルの形代もあります。
また、菅で作った人形は古くは、草人形と呼ばれていました。
中国では、死者が寂しくならないように供として一緒に埋葬していました。
こうしないと死者は妖怪になってしまい、生きている人間を黄泉へ連れて行こうとしてしまうからです。
ちなみに、草人形は日本では垂仁天皇の時に、神々の怒りを鎮めるために使われたのが最初だと言われています。

子供の遊び道具として使われる人形も歴史が長くありました。
そこには見えない世界に関するものもあるわけです。
歴史的な背景があり、そのような部分も合わせて学んでいきたい方は、ぜひ一緒に頑張りましょう。
これからも良い記事を書いていきます。
