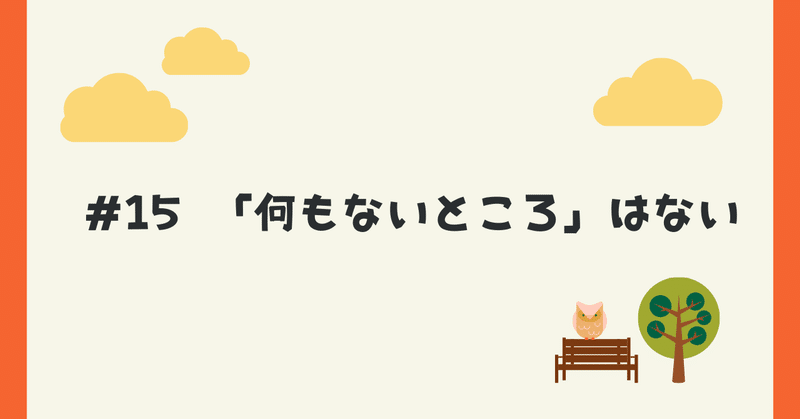
#15 「何もないところ」はない
「ここは何もないところだから・・・」
この言葉を私は地方部や中山間地に行くたびに何度となく耳にしてきた。
ところがそんな地域を歩いてみると面白いものを発見することが多々ある。
確かに地元の人にしてみれば、何のことはないのだが、外から来た人には珍しいことが多々あるのだ。
それどころか、地元の人さえ気づかない魅力を発見することさえある。
長野によく往復するようになって、発見したことがある。
向こうの家のまわりにはたくさんのオニグルミの木が生えている。
実が落ちるとすぐに果肉が腐るので、最初は「汚いなあ」くらいにしか考えていなかった。
オニグルミは一般に市場に流通しているカシグルミに比べて実も小さくて殻も固いため、ほとんど市場には出回っていないようだ。
ところが煎って、食べてみるとカシグルミより格段においしい!
生のオニグルミと市販のカシグルミを比べてみると、まるで香りも味も、生ラーメンとインスタントラーメン程の違いがある。
それだけではない。クルミの木の枯れ枝は燻製をつくる時には、良い香りのする恰好のチップになると知った。もうわざわざ燻製チップなど買う必要はない。
さらにさらに、なんと冬の間に幹に小さな穴を空けて樹液をためて煮詰めるとメープルシロップならぬクルミシロップをつくることもできることが判明した。ちょっと酸味があって独特の味わいだ。
今では家を建てた後にオニグルミの木を何本か切ってしまったことを心底後悔している。
「生活に井戸水を使っている」
「薪で風呂を沸かしている」
「家でニワトリを飼っている」
といった、かつては日本の田舎であたりまえであったことに、触れることなく育つ子どもが現在ではほとんどだ。
工夫次第でこれらはきっと新鮮な価値をもつに違いない。
「何もないところ」はない。
そう思うのはただ自分たちが何も見えていないだけだ。
