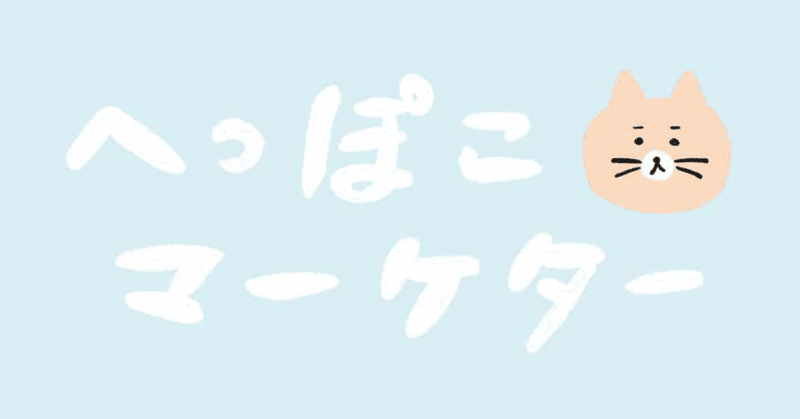
“代案”の存在の有無が、施策の実行度を左右する、という話
「へっぽこマーケターの日々」第37回(前回は3/9更新)。
マーケ施策をいろんな人をまきこんで実行するには、どうしたらいいかを引き続き考える。今回は施策の準備が進まない原因や、施策自体が立ち消えになる原因の対処法について。
目的達成が重要なのだから、「不確定要素」によってプラン(手段)がグラついて実行が担保されないことは避けるべきだ。自分なりの「コトの進め方」をこれまでの経験を踏まえて書いてみる。
***
複数チーム連携して、戦略を施策(プラン)に落とし込んだものの、数日後に進捗を聞くと「なかなか進まない」「いつのまにか施策がなくなっていた」ということが起きたことはないだろうか。
もちろん、そこですぐにやる気の有無を問うのは尚早である(自戒)。大抵の場合、やる気はあるのにそれを阻害する事象が発生しているのである。
たとえば、「◯◯が決まらなくて」「外部との調整がいつ終わるか目処が立たない」と困っているという事象が周囲ではよくある。
この状態はつまり、「不確定要素のせいで進められない」し、最悪の場合「不確定要素が確定せずに消えてしまい、施策自体が成立しなくなる」ということを招く。
過去に自社運営のwebサービスのUIデザインとHTML/CSSコーディングをやっていた5年半では、この不確定要素が決まらない間の「待ち」や「宙ぶらりん状態」を避けるようにしていた。自分のコントロール外の要素が増え、他者に成功が左右されるからだ。
そんな他者に委ねた状態を回避するためにやっていたことが、アウトプットの「松竹梅」のバリエーションを用意することだった。不確定要素がいつ確定するのかを関係者に確認し、その期日までに決まるかどうかで「松竹梅」のどれを提出するのか、進め方として関係者と事前に握っておく方法である。
プロマネもディレクションも重要なことはそれと似ている。「松竹梅」の選択肢を作りながら意思決定を重ね、「不確定」なままにしないようにするのだ。
松竹梅≒プランBをつくる
ここまで書いたことは、要するにプランBを用意しておくということでもある。不確定要素を含むプランAと、不確定要素のないプランBの両方準備するのだ。
そうは言っても、2つも準備するのは大変ではないかという声もわかる。たしかに、つつがなくプランAが実行できればBは無駄になる。
しかし、プランAがリリース直前で使えなくなってしまったらどうするか?
特にプランのコア(ウリ)となる部分を、外部の企画やコンテンツに頼った場合がおそろしい。まずあちらの大小様々な変更に、こちらのプランが変更のたびに対応をするコストがかかる。
そして変更を重ねていくうちに、当初の素敵なプランがだんだん味気のないものに変わっていく...なんていうことも有り得るのだ。最悪の場合、あちらのコンテンツがなくなり、プラン自体が成立しないリスクもある。
そうなったときの直前の対応によるバタバタや、「どうしてこんなのやろうと思ったんだっけ?」という虚しさを思えば、確実に実行可能なカードを用意しておくことが意味があると思えるのではないだろうか。
手間の量ではなく、手間に見合う結果かどうか
施策を考えるときに、風呂敷を広げることは素晴らしい。実現可能性ばかり気にしてると、おもしろくならないのもわかる。
けれど、風呂敷は手段でしかない。肝心なのは目的を達することだと思い出すことさえできれば、1つのプランに固執せずプランBに切り替えることのメリットがわかってもらえるのではないだろうか。
さらに重要なのは、かけた手間に見合う結果を安定的に出せるかという視点だろう。
土壇場のプランAの大変更よりも、プランBを予め用意している方が結果にコミットできるはずだ。
結局、リソースをうまく使ったものが勝つ。
わたしをサポートしたつもりになって、自分を甘やかしてください。
