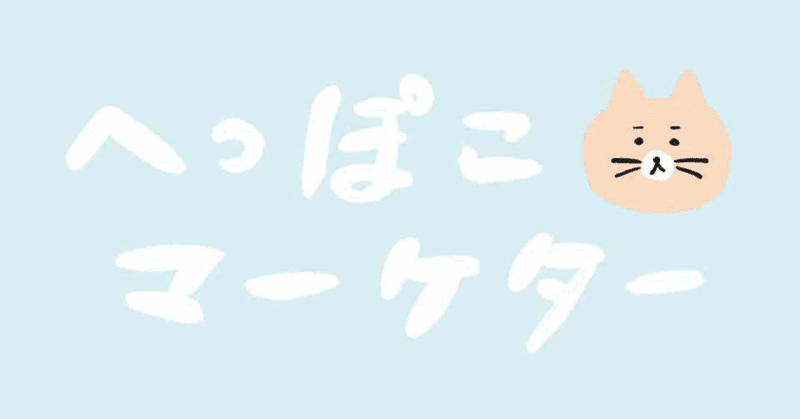
“売れる”ためのチームのあり方、という話
「へっぽこマーケターの日々」第33回(前回は3/4更新)。
今日は、同僚が共有してくれたTipsをきっかけに、“売れる”作品をつくるために、“誰が”、“どんなこと”をすればよいかについて、最近考えていることを書いてみる。
つい先日、コルクのマネジメント作家の新刊が発売即重版となった。重版というのはなかなか起きないし、たくさん刷ることはリスクなのでそれ以上のメリットがないと刷ってもらいにくい。なのでこの事態は“うまくいってる”と言える。
概観としては、①作るとき②届ける(売る)ときに一貫性のあるアクションが起こせたケースだ。
①作るでは、コアファンをまきこんだ魅力の言語化と、そのキーワードを基に改稿を重ねたこと。②届ける(売る)では、マスとインフルエンサーとオンラインコンテンツをうまく使い分けたプロジェクトだったように思う。
今回の件について詳しくは割愛するが、重要なポイントはとてもシンプルだ。“作り手と売り手(届け手)が、共通のキーワードを共有すること”である。
※キーワードというのは、物語のコアとなる要素のこと。これをフックとして世間に作品をアピールしていく。
上記の要点を聞いたとき、世間のトレンドや、作家との日ごろの会話に触れる度、“いい作品”と“売れる作品”は違うのだな、と日ごろから感じていることを思い出した。
作り手である作者とともに、“作る”“届ける(売る)”ことに二人三脚でとりくめるのが、エージェントとしてのコルクの価値だ。そうして作家がやりたいことと、時代性をマッチさせ、世間の興味関心と作品のブリッジをつくることに尽きるのではないだろうか。
今回の同僚のケースは、そこへさらに、出版社の“売る”現場のメンバーが初期から関わってくれていたことも大きいと言う。出版社とコルクの互いに異なる強みを出し切れる、まさに“強いチーム”だったのだ。
失敗したときに矢面に立っているのは…
SNSのおかげで、作品の感想も本当に多様化していると思う。しかし、それと同時に、“何を作っても誰かが叩く”という不安もつきまとうようになったのではないだろうか。
たとえば、直近で起きているメディアのオリジナルコンテンツなどがそうだ。
媒体自体にオーディエンスが持つ期待値(たとえば“新しい”、“おしゃれ”、“先端”などのイメージ)と、作品の作り手のスタンスや伝えたいことが、一致しないことが少なくないように見える。
しかし、いざそういう作り手と売り手のズレが起きたときに、オーディエンスの感想の矛先が作り手に集中してはいないだろうか。そんなことが頻発したら、怖くて作れなくなってしまうと思う。
目指したい状態
そういう視点でも、“作る”ことと“届ける(売る)”ことは担う人が異なることを意識したい…(もちろん一人ですべてやる、と場合もある)。
作り手と届け手(売り手)がワンチームとなってキーワードを考え、共有し、作品とのよい出会いの場を提供していく。そんな機会を増やせるようにしたい。
補足
今回の知見の基となった作品はこちら。
『茶聖』伊東潤(幻冬舎)
https://www.amazon.co.jp/dp/4344035690/
発売即重版は、本当にめでたい。
知見自体はまた機会があれば話せたらと思う。
(ケーススタディとしてぜひ主担当の同僚に話してほしいと思っている)
わたしをサポートしたつもりになって、自分を甘やかしてください。
