
時 論
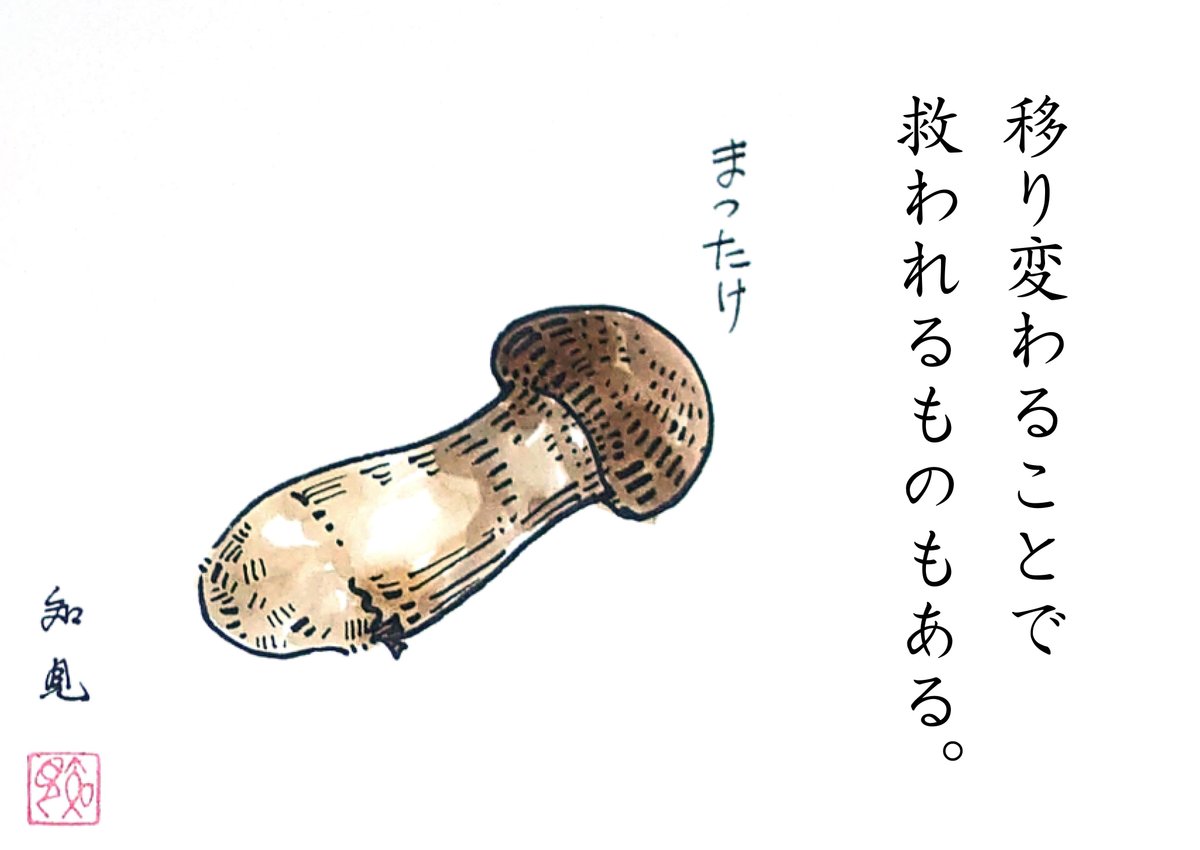
ナァ、時と云ふものは、と、彼は言った。
「ハァ、時と云ふものは」
と、私は言う。此の後に何が続くのか、私は全く期待なぞしていない。其れでも会話には付合いと云ふものがあつた。
「時と云ふものはだ、ナァ、君。まるで川の流れのやうなものだと思ふかね。其れとも、クルクル廻る風車(かざぐるま)のやうなものだと思ふかね、どうだい」
「ハァ、時と云ふものは、川か、其れとも風車か、ですか」
「そうだ。僕はだね、君。どちらとも、間違つてゐると思ふのだよ」
彼は、私が考える間も無くそう言つた。これだから、彼と話すのは嫌なのだ。彼は何時も答を待たぬ。此れでは、壁に向かつて話しているやうではないか。つくづく私を巻き込まないで欲しいものだが、彼の会話の相手は今の所私しかいないのだから仕方ない。今日も又、私は彼の壁になる。
「時と云ふものは、だ。屹度、此の中庭に咲く花の、花弁のやうに儚きものだ。ウム、其れ以外に考えられまいよ、君」
彼はしたり顔で低い鼻をぶうと鳴らした。私は伏せていた頭を擡(もた)げて、我が家の狭い庭を見た。主人が手間を惜しむ所為で、客の世辞にも美しいと云ふ言葉が出て来ぬほどの庭だ。其の中から、咲いて居る花を見つける事は、意外に容易であつた。丁度金木犀の季節なのだらう。今朝方から、甘い匂ひが私の鼻――此の鼻が、彼よりも高く鋭い事を秘かに自慢に思つてゐる事は誰にも内緒だ――に届いてゐる。
「見て御覧。此の金木犀達は、明日になれば風に吹かれて散つてしまふ。僕達だとて、後十年もすれば、屹度此の花のやうに散ってしまふだらう。其れを、人は死と云ふらしいがね」
「ハァ」
「時と云ふものは、其れ程に儚く、侘しいものなのだ。皆、其れと知らずにあくせくとしてゐる。マァ、何んと面倒な事だ」
そりやあ、貴方はさうでしやうよ、と思つたものの、懸命な私は、ハァ、と応えるのみに留めた。彼の話は眠くなる。こんな温かな日に、彼の話を聞いてばかりは居られぬのだ。早く壁から解放されぬものかと、私は辛抱強く待つた。
「一瞬、刹那の過ぎ去るものだと、分かつてゐたら、人は皆、時を掴もう等とは考えまいに。ナァ」
「ハァ」
「そうは思わぬかね。刹那のものを、掴む事は不可能なのだよ、君。試みること自体が愚か者のする事だ。ナァ。知つてゐたら、そんな真似はせんだらうよ」
「知つてゐて、其れでも試みてゐるとしたら」
私の大きな口から零れた言葉に、彼は髭をピクピクとそよがせた。気に入らぬ事を言ったやうだ。忙しなく、彼の髭は動いた。
「其れは君、思ひ違いと云ふものだよ」
「ハァ」
私は金木犀を見た。風が吹いてゐるのだらう。先程よりも強く花が香つてゐた。
足音が聞こえる。自慢だが、私の耳は彼の其れよりも良い。あれは、主人の一番上の娘のものだ。
「マァ、オマエ。こんな所に居たの」
「居たら悪いか」
「アラ、金木犀。此れを見て居たの。風流なのね」
「当り前だらう。僕は非常に賢いのだ」
「お出でなさい。お母様がお菓子をくださるさうよ」
「ウム、行(ゆ)こう」
彼は、娘の赤い着物に抱かれて、奥へ入つて行つた。私はフゥと鼻を鳴らし、顎を冷たい石畳の上に置いた。此れでやつと昼寝が出来る。私は、鼻の次に自慢の耳を立て、警戒だけは怠らぬやうにしながら重たくなつた眸を閉じた。
彼は、人は賢しい者と信じてゐるが、其れは間違つてゐると思ふ。彼らは己の力を過信し、我々がこうして言葉を解し、又、彼らと劣らぬ程の議論をする等とは思わない。一寸考えれば分かりそうなものだが、彼らは彼らが最上の智慧を持つた動物だと頑なに信じてゐる。此れが、私が人は愚かであると思ふ所以だ。
彼は何時も人に抱かれ、其の言葉がゴロニヤアとしか聞えておらぬ事を知らぬ。否、あれは知ろうとして居ないのだ。私のやうに、どんな嵐の夜にでも、泥棒がやつては来ぬか見張つてゐる身になれば、人の愚かさは直ぐに分かるだらう。
イヤ、此れは、菓子が貰えぬからと拗ねているのでは決してない。真理と云ふものである。私が、そんな事をするものか。
「オイ、オマエ。何時もご苦労だな」
主人に仕えてゐる書生が、顔を覗かせた。墨が顔に付いてゐる。大方、勉強中に居眠りでもしたのだらう。全く、人と云ふものは愚かで仕様がない。眠いのなら、私のように寝れば良いのだ。
「ホラ、此れをやろう。貰ったのだが、俺は餡子の入った餅は好かんのだ」
私は甘いものが好きだ。お言葉に甘えて、ぱくりと餅を頂くことにする。歯に付いて難儀だが、中の餡が美味だつた。私のフサフサの尾が、左右に忙しなく揺れた。
「そうかそうか、美味いか、良かつたな」
書生は、私の頭をぐりぐりと撫でると顔を洗いにか、井戸の方へ去つて行つた。
マァ、人もそう捨てたものではないかもしれん。
私は、見張りの役目を全うするために、手早く餅を平らげた。
金木犀の香りが、庭に満ちてゐる。雑然とした庭から侵入する者は私が食い止めてやらう。起きあがつた私は、ピンと凛々しい背中を伸ばして、完璧な見張りの体を整えた。
庭のどこかで、失敬な黒い烏が阿呆と鳴いた。
終
あとがき
小説はどこまで旧仮名遣いが許されるのかにチャレンジした短編小説です。
まじめな話に見せかけて、犬と猫の話、というのが書きたかった話でもあります。お楽しみいただければ幸いです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
