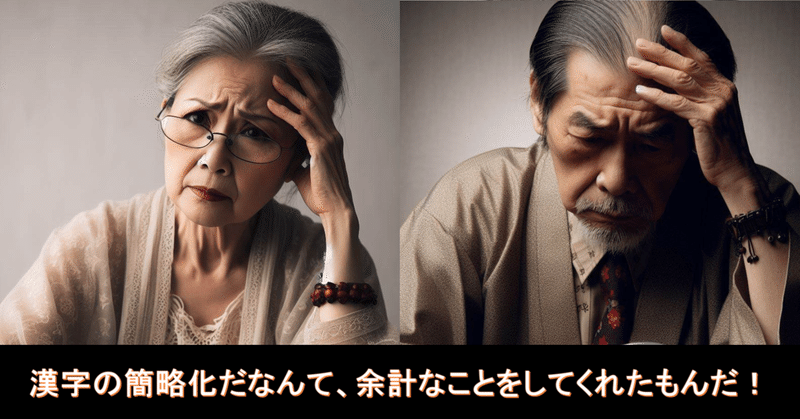
漢字の画数問題は占い師を悩ませたか?
●主要五流派の画数の取り方
漢字の画数問題は少々込み入っているので、まず全体像を把握しておきましょう。話を進めやすくするため、画数の取り方の違いによるグループ名として、以下の仮称を用いることにします。
新字派・・・新字体の画数を用いる
旧字派・・・旧字体の画数を用いる
康煕派・・・旧字体の画数を用い、「へん」や「つくり」を特別に数える
常用派・・・日ごろ使っている字体の画数を用いる
戸籍派・・・戸籍に登録した字体の画数を用いる
[注] 康煕派
この流派は漢字の字書として康煕字典(中国の清朝時代に編纂)を至上とする。康煕字典では「さんずい」が「水」の部に分類されている。だから、「さんずい」は3画だが「水」は4画なので、見かけに騙されずに4画と数えるべきだとする。
●画数問題の変遷
明治の中頃(1890年代)、現在も使われている数霊法の原型が、初めて占い本の形で世に現れます。それ以降、大正末期までの約30年間に、確認しただけでも60人以上の占い師が、100冊以上の姓名判断書を著しています。[注1]
この頃の漢字といえば旧字体のことで、大半の占い師は画数のよりどころとして、江戸時代から使われていた康熙字典を用いたようです。占い本に掲載してある漢字画数の一覧表からも、占い師の多くは旧字派だったと考えられますが、少数ながら常用派や戸籍派もいました。
ついで、昭和に入ると、まもなく康熙派が現れます。この特殊な画数の数え方が、現代の姓名判断で主流となっている数霊法に持ち込まれたのは、このときが最初と考えられます。
旧字派と康熙派は、同じ康熙字典を用いても画数が異なる場合があるので、両者の対立は必至となります。[注2-3]
昭和20年〔1945年〕に終戦を迎えると、漢字の一部が簡略化されて、新字体が内閣告示されます。昭和21〔1946年〕~昭和24年〔1949年〕のことです。画数問題に新字派が参入するのはこの時期からで、いよいよ五流派が入り乱れての複雑な事態に発展していきます。
●新字体の登場で占い師はどうした?
漢字は、新字体と旧字体のどちらを用いるかで、姓名判断の結果が正反対になることがあります。戦前は旧字体しかなかったので、漢字の字体を気にする必要はありませんでしたが、戦後に内閣告示された新字体は占い師にとって大問題のはずでした。
そこで、こう考えました。「法律で人名用漢字が制限され、そのうえ旧字体が使えないとなれば、さぞや当時の占い師は狼狽しただろう」と。[注4]
試みに、新字体が世に出た前後の時期で姓名判断書の出版にどんな変化があったか、独自に集めた占い本データを使って調べてみました。すると、1940年代の10年間に出版点数が激減していたのです!これこそ占い師が字体問題でいかに悩んだかを示す、厳然たる証拠ではないか?

ところが、さらに調べてみると、どうもそうではなかったようです。実は昭和16年〔1941年〕、政府が内務省を通じて暦の出版を禁じ、次第に占い書全般を取り締まるようになったのです。占いは迷信であり、人心をいたずらに惑わすから、というのが理由のようです。
●まずは旧暦の廃止から
暦がなぜダメかというと、大安とか仏滅などの「日の縁起」 や、一白水星、九紫火星などの九星による吉凶判断は暦に付随したものであるから、迷信の温床になっているというのです。
旧暦(陰暦) を廃止し、新暦(太陽暦) を普及させて、「非科学的な因習」(当局の表現) を一掃しようとの狙いだったのです。
昭和16年5月3日の読売新聞(東京)夕刊には、大見出しで次のように出ています。
“九星”や縁起を抹殺 太陽暦一本槍に 迷信打破・陰暦は一切認めず
この記事に続いて、高島易断総本部の高島象山氏による政府批判が掲載されています。当時の占い師の反応を代表するものとして、参考に見ておきましょう。
・・・ 陰暦をなくすることになれば・・・ 易断のほうも一応成立しないこととなりましょうが、だからといって世の中から易断がなくなるものではありますまい。
当局の考えは迷信打破の目的で行うのでしょうが、そんなことをすれば却って訳の分らない迷信が新たに生れ、社会に害を及ぼすような結果になりはしないでしょうか。
易断は社会に益するものです。益するものを廃することは悪いことであって、これはいわゆる官吏の机上論というものでしょう。(旧字を新字に改め、句読点の一部を追加修正)
この時点では、まだ旧暦の廃止に重点が置かれており、占いそのものは規制の対象になっていないようです。しかし、わずか1ヶ月後には、その範囲が占い全般にまでおよびます。
●政府の取り締まり強化
昭和16年6月3日の東京日日新聞(現在の毎日新聞) 夕刊には「でたらめ占師追放」 と題して、次のような記事が載っています。
・・・ 警視庁保安課は内務省通達の「擬暦記事掲載出版取締りに関する件」 にもとづいて戦時下迷信打破のために検閲課と協力、近くこれが粛正に乗り出すことになり、具体案を練っている。
現在、帝都の占師は約五千名に達し、ますます激増傾向にあるが、中には殆どでたらめに近いことをいい、当るも八卦、当らぬも八卦とばかりうそぶいているものや、客から過去の大半を聞き出し、それを占いから出たように客に告げ、預言を信じさせているものなど、悪質なものが相当いるので、擬暦にもとづく占は勿論、これに類似する占は禁止するとともに、でたらめのひどい占は詐欺罪として検挙する方針。(句読点を追加、旧字を新字に改め)
それからおよそ3ヶ月後の8月28日、同じく東京日日新聞の夕刊は8月中旬の一週間だけで5件の占い書籍が「迷信的出版物」 として発禁処分を受けたと報じました。
この記事の中で、以後の取り締まり強化につき、当局の担当課長は次のように気炎をはいています。
迷信書や風俗壊乱の小説の殖えて来たのは警戒を要する。何れも国民の心を毒するものであり、今後は厳重取締り、どしどし発禁処分に附すると同時に、出版文化協会とも連絡をとり、各出版業者の指導に万全を期するつもりです。(句読点を追加)
その後も、二十八宿、九星術、陶宮術、家相、夢判断、まじない、米相場必勝法など、占い系の書籍が続々と摘発され、発禁処分を受けることになるのです。
●占い師にとっての大氷河期
発禁理由を見ていくと、「時期のいかんを問わず、吉凶、禍福、運勢等を知る方法を掲げているので、万年暦の一種である」「皇室に関する不敬記事を掲載している」「いたずらに恐怖心をあおっている」などというのがあります。これらの理由はどう考えても旧暦とは無関係です。[*1-2]
こうなっては占い師も出版社も戦々恐々でしょう。その気になれば、当局は発禁理由などいくらでもひねり出せるのですから。危なくて、新たに占い本を出版するどころの話ではありません。[注8]
かくして、大正期から昭和初期にかけての姓名判断ブームは、すっかり冷めてしまいました。占い師にとっての大氷河期がやってきたのです。
●姓名判断の復活
ところが、昭和20年〔1945年〕8月15日に太平洋戦争が終結し、昭和22年〔1947年〕5月3日に新憲法が発布されると、思想・信仰・出版等の自由が保障されることになりました。おかげで、姓名判断書は再び日の目を見ることができたというわけです。
1940年代の出版点数の減少には、こうした背景があったのです。戦時下でもあり、書籍・雑誌の印刷用紙が割当制になるなど、出版物の絶対数が制限されたことも影響したでしょうが、それにしても漢字の字体変更とはほとんど関係がなさそうです。[*3-4]
どうやら漢字の新・旧字体で一番悩まされたのは、姓名判断を商売にする占い師ではなく、私たち利用者だったようですね。
==========<参考文献>==========
[*1] 『禁止単行本目録(Ⅰ~Ⅲ)』(湖北社)
[*2] 『発禁図書目録』(国立国会図書館)
[*3] 『戦時の出版統制』(布川角左衛門著、『文学』29巻5号所収)
[*4] 『戦時中の出版事情』(布川角左衛門著、『文学』29巻12号所収)
==========<注記>==========
[注1] 姓名判断の創始者
現代的な姓名判断の創始者が誰かについては、機会を改めて取り上げたい。というのは、「創案者」「秘術の伝承者」を名乗る者が10人以上も存在するからで、ここでそれらを検討する余裕がない。
[注2] 康熙派に対する批判
旧字派からの批判はこちら ⇒ 『漢字の画数問題(1):旧字派と康煕派』
[注3] 康熙派の源流
漢字の「へん」 や「つくり」 を康煕字典の部首分類に従って数えるやりかたは、実は江戸時代にもあった。
たとえば『名判集成』(赤頬氏著、文政5年〔1822年〕)には、「字の画数は、字書のとおりを用ゆ。・・・サンズイ〔3画〕 は水で4画、リッシン〔3画〕は心で4画・・・」 などとある。また、明治初期の『通俗名乗字解』(青木輔清著、明治8年〔1875年〕)にも同様の記載がある。
ただ、これらの書は字画数にもとづく易や、反切(現代では廃れた技法) を用いた古式の姓名判断であり、数霊を使った現代の姓名判断とは異なる。
なお、古式の姓名判断(易や反切を使った姓名判断)については、『「姓名判断は我が国百年の歴史」が本当だ(1)』を参照。


[注4] 新字体の登場
新字体がこの世に現れたのは1946年〔昭和21年〕11月以降である。このとき国語の簡易化方針による「当用漢字表」が内閣告示された。
続いて1948年〔昭和23年〕1月、戸籍法50条と戸籍法施行規則60条が施行され、人名用漢字が「当用漢字表」の範囲に限定されることとなった。
そして1949年〔昭和24年〕には「当用漢字字体表」が告示され、「当用漢字表」で旧字体のままだった文字も新字体に置き換えられた。
<参考> 『現代の名前についての法律問題』(家永登著、『名前と社会』所収、早稲田大学出版部)



[注8] 姓名判断書の発禁処分
姓名判断書の発禁処分は意外に少なく、『今すぐ役立つ幸運姓名の付け方』(根本圓通著) の一冊だけのようだ。
発禁理由は「両陛下の称号を姓名学的に解釈し、不敬にあたる」 ことと、「天皇陛下・大正天皇の御諱を使用することにより凶運に見舞われるとして例示し、不謹慎きわまる」 からという。
諱とは生前の名前のこと。この書は昭和18年6月に発禁処分を受けた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
