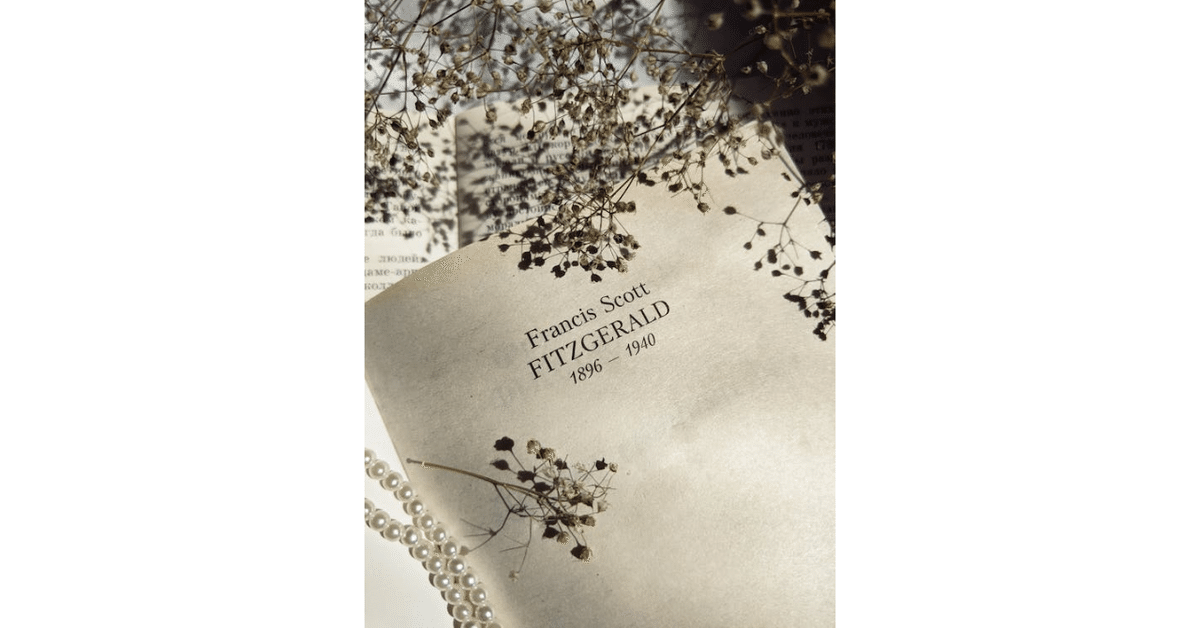
F・スコット・フィッツジェラルドについて
手のひらで雪を感じたあの冬の心もとないグレート・ギャツビー
甘いなあと思う。冒頭歌は、拙著『The Moon Also Rises』中の一首だが、いかにも初期作品らしい青臭さがある。詩情の強度という点ではあまりに脆く、あえて言うなら、「あの冬」の「あの」というところがすこぶる心もとない。
それはさておき、今回はそんな『グレート・ギャツビー』の作者、F・スコット・フィッツジェラルドについて。
♭
フィッツジェラルドは贔屓の作家だが、学生時代に最初に手にしたのが彼の代表作、『グレート・ギャツビー(The Great Gatsby)』だった。著者生前にはあまり日の目を見ず、一時は絶版という憂き目にあいながらも、死後に再評価が進んだ本作。現在では20世紀米文学における最高峰と見なされ、今後その評価が揺らぐことはないとされている。
〈失われた世代〉だとか〈狂乱の20年代〉だとか、ギャツビーを読む上での云々はもちろんあるのだけれど、あえてここでは触れないでおく。初読時に抱いたのは〈廃れゆく男の美学〉という所感なのだが、あながちこれは的外れでもなかったように思う。自己肯定的なある種の美意識と、それとは相反するような深い内省と自己への冷徹な眼差し。そんな両義性こそフィッツジェラルド作品の多くに通底する核であり、また大きな魅力でもある。
ギャツビーに関してもう一点だけ述べると、これも衆目の一致するところなのだが、冒頭と最後の数ページは特に格調高い名文として知られている。フィッツジェラルド最大の特徴はその絢爛また流麗な文体なのだが、拙い英語力で原文にあたった当時にも、息を呑むような音感的な美しさは肌で感じられたことを覚えている。
なお、フィッツジェラルド作品に関しては、近年の村上春樹新訳が話題となったけれど、好みで言えば圧倒的に、野崎孝訳をお薦めしたい。『ライ麦畑でつかまえて』の名訳で知られる野崎訳は、半世紀前の訳文とは思えぬほどに今読んでも鮮やかで、原文の美しさに勝るとも劣らぬ美しさを味わうことができる。
さて、フィッツジェラルド作品には折に触れて読み返してきたものも多いのだが、長編で言えば『グレート・ギャツビー』よりも『夜はやさし(Tender Is the Night)』の方が好みだろうか。(ちなみに、このnoteの表題は、『夜はやさし』の原題から拝借している。)
完全無欠の比類なきギャツビーに対し、ときに失敗作とも評される『夜はやさし』はどこか隙を感じさせるけれど、そこに何とも言えない哀感が表れている。〈人生とはみな崩壊の過程である(all life is a process of breaking down)〉というフィッツジェラルドの名言は、この物語にこそ最も体現されているように思う。
個人的な好みとしては、フィッツジェラルドは短編がいい。玉石混交、生活苦から金のために書き飛ばしていたと専ら芳しくない評価のつきまとう短編作品だが、そのなかには紛れもない傑作も数多くある。
その筆頭は『金持ちの御曹司(The Rich Boy)』だろう。生まれながらの上流階級を憧憬と揶揄をもって、繊細かつ鋭い筆致で描く本作。誰よりもエゴイスティックかつロマンティストな主人公を評した友人(語り手)の傍白に次の一行があって、この一文の美しさが初読時より忘れられない。”I don’t think he was ever happy unless someone was in love with him…”
その他の短編では、『冬の夢(Winter Dreams)』や『バビロン再訪(Babylon Revisited)』などが名高いけれど、小ぶりな作品にも趣のある良品はある。
『乗り継ぎのための三時間(Three Hours Between Planes)』などは、何とも忘れ難い余韻を残してくれる。32歳の男、ドナルドは、飛行機の乗り継ぎのわずかばかりの時間に故郷の町へ降り立ち、かつて恋心を抱いていたナンシーのもとを訪れる。20年ぶりの再会に、二人の気分は高まるのだが、当時を写した一枚の写真から、両者は思いがけぬ事実に気づいてしまって・・・。
予想外の結末は、ほとんどブラックユーモアと言えるようなペーソスに溢れているのだが、この軽妙さがかえって人生の残酷さを痛切に感じさせる。
「歯医者の待合室で待たされる三十分の時間をつぶすには恰好な作品」と、フィッツジェラルドその人は自身の短編をこんなふうに自虐的に位置づけていた。けれども、そんな短編こそ、時代の空気感や当時の若者の姿をヴィヴィッドに描き出さすとともに、鋭い批評的眼差しが注がれており、実に魅力的である。
♮
そんなフィッツジェラルドにちなんだ短歌作品といえば、次の一首が思い出される。
寝て覚めてこの暁のF・スコット=フィッツジェラルドわずかな光
堂園昌彦
意味よりもイメージに重心の置かれた一首には、なによりも三句目以降の音感的美しさに惹かれてやまない。その流麗な韻律はフィッツジェラルドの文体を大いに想起させるところだが、改めて一首を読むと、結句の「わずかな光」が決定的に効いている。
この「わずかな光」は、直接的には「暁」という時間帯を示すのだろうが、そこには『夜はやさし』やあるいは晩年のいくつかの短編が描く諦念や哀感が思われる。どこか隙を感じさせながら、しかしながらそこに滲み出るような慈愛の表情。それは、飽くなき野心と意志の強さゆえにやがて夢破れてゆくギャツビーとは、似て非なるロマンチシズムなのだと思う。
そう考えるとき、冒頭の拙歌においては「心もとなさ」こそが鍵だったのだと思う。若かりし日に読んだ『グレート・ギャツビー』はあまりに比類なき傑作で、だからこそ当時の僕は、自身の未熟さに心もとなさを覚えたのだろう。
その感覚は、短歌という表現の世界に足を踏み入れてまだ間もなく、手探りだった頃の心境ともどこかで共鳴していたのかもしれない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
