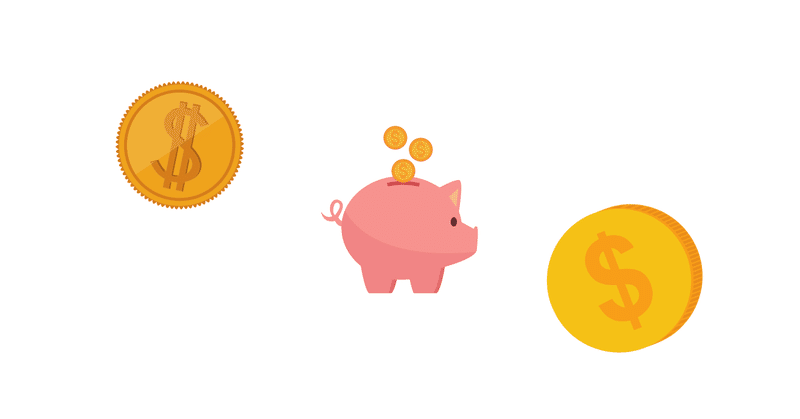
給料明細を見よう!
なぜ給料明細といいますと、自分が働いて得たお金から、社会保障の金額、税金が記載されているからです。
個人営業主世帯では常に気にしているところも、サラリーマン世帯では天引きのため、「お金を引かれている感覚」が鈍くなっているようです。
明細を見たことがない。
さらっとみて捨ててしまう。
など私にしてみたら、びっくりするようなことを言う人もいます。
投資で資産を増やそうとしている人、お金を使わないで貯金をする人は、ただ貯金しているだけでいいのでしょうか?
給料明細は、最低限知っておくべき情報が入っている
給料明細には、必要最低限知っておいた方がいい、「お金の情報」が記載されています。
給料の基本報酬のみならず、保険、年金、税金の記載があり、家計簿をつけるような知識で、理解が出来ることだと思っています。
一般のサラリーマンでは、個人営業主のような細かな経費が記載されているわけでもない、シンプルな給料明細です。一度、じっくり確認してみてください。
給料明細公開!
これはある年の私の給料明細です。(勇気を出して公開!)
行政の臨時職員をしていた時の明細です。
◎給料・基本報酬 170,982円
◎雇用保険 513円
◎健康保険 6,958円
◎介護保険 1,278円
◎厚生年金 12,993円
◎課税対象額 149,240円
◎所得税 2,950円
◎控除合計 24,692円
差引支給額 146,290円
正職員ではないため、各種手当、積み立てなどはありません、ごくシンプルな明細です。
たったこれだけなのですが、生きていくうえで知っておいた方がいい情報だと思っています。
無知だったことが良かった
私が給料明細(以下、明細)を見るようになったきっかけは、経理による計算ミスがあったからです。
ものすごく昔のことですが、明細を見なかったばかりに、計算ミスにも気づかず働いていました。
ある時、投資と節約を生きがいにしている(笑)同僚が、給料の計算が違っていると教えてくれ、慌てて見てみると、確かに違っていました。
パート勤務で時給制だったために、計算は簡単でした。
一日分が計算されておらず、その上、交通費も全く違う金額が記載されていたのです。
人間も機械もミスはある。
その時から、明細を確認するようになりました。簿記、税理士、会計士の資格なんてありませんし、勉強もしたことはなく数字は大嫌い。
それでも明細に記載されている内容は理解できます。たかが明細、されど明細です。
家計を預かる主婦は把握しておくべき
2000年だったでしょうか?内閣府が消費税10%引き上げに低所得者、子育て世帯の影響を緩和して、地域における消費・喚起する目的として「プレミアム商品券事業」がありました。
購入対象者
・2019年度住民税非課税者
※住民税課税者と生計同一の配偶者・扶養親族、生活保護被保護者等を除く
・学齢3歳未満の子が属する世帯主
この時、この事業を担当する課に属していました。
事業が開始されるや否や、電話が鳴りやまず対応に追われました。
そのほとんどが、
・非課税世帯とはなにか
→ 一定の収入以下の世帯で、所得税・住民税が免除されている世帯
・生計を一とするとはなにか
→ 同居をしていなくても、生活費の送金をしていたり、休みには一緒に 過ごしたりしていれば、生計を一にしています。
・扶養という意味の取り違え
→ 税法上の扶養ということと、子供などから生活費をもらうということ の扶養(よく使われる「子供から面倒なんかみてもらってない」というのがこれですね)
・住民税を支払っていないのに、購入できないのはなぜか
→購入できないのは、理由があります。引かれているのです。明細を見れば引かれているのが分かるはずですし、納付書はどうしました?ということです。
もっとありましたが、大まかにいってこういうことでした。
質問内容は、明細を見ていれば分かることばかりだと思いませんか?
住民税は支払っていれば明細に記載され、記載されていなければ、納付書が郵送されますしね。
高齢者はなんとなく理解が出来ますが、首をかしげるのは、若い世帯。
子育て中の若いお母さんでも、社会人だった時期はあるはずです。
「扶養されているのに、商品券が買えない」
「住民税ってなに?」
などなど・・・。
制度そのものの条件が複雑だったこともありますが、なんとも嘆かわしい。
教科書は役所にあり!
がむしゃらに働いた給料が、どのような保障に引かれているのかくらいは、把握していたいものです。
そこでおすすめなのが、役所が作っている「税に関するガイドブック」です。自治体によっては呼び名が違うと思いますが、税金を扱う課には置いてあると思いますので、読んでみてください。
住民税の算出方法、固定資産税、自動車税、国民健康保険など必要な税金の情報が冊子になっています。
この一冊があれば、支払う税金に対して、いくらまで働けるのかなど詳しく書かれています。
また、自治体では無料の税金相談などしていますから、そういったサービスをガンガン利用しましょう。
税金を支払った分、情報を対価として受け取る。
投資をするにしても、貯金をするにしても、相続や譲渡をするにしても、税金がかかってきます。
出来るところから、賢く節税です。
資産を増やすのは、それからでも遅くはないと思います。
明細を見るところから、給料の使い方を見直してみてはいかがでしょうか?
★最後までお読みいただきありがとうございました。
★専門家ではありませんので、用語等の使い方に間違いがございましたら、ご報告ください!勉強させていただきます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
