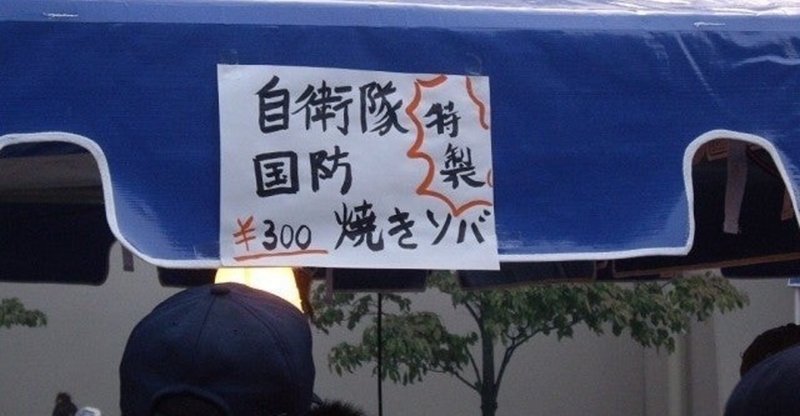
現代人は「正戦」がお好き(悪の軍団の政治学 その四)
※ 有料になってますがぜんぶ無料で読めます。余裕のある方はサポートしていただければありがたいです。
「悪の軍団の政治学」シリーズの最終回。
長っ尻の仮面ライダー
1911年に漱石は書いている。
夜番の為に正宗の名刀と南蛮鉄の具足とを買うべく余儀なくせられたる家族は、たくあんの尻尾をかじって日夜あくせくするにもかかわらず、夜番の方では頻りに刀と具足の不足を訴えている。われらは渾身の気力を挙げて、われらが過去を破壊しつつ、たおれるまで前進するのである。(「マードック先生の日本歴史」)
われらが仮面ライダーがだんだん長ッ尻になってきたのはこの頃らしい。大正デモクラシー期と戦後にちょっと断絶があるが、昨今はまた、茶を出せだの飯がまずいだの、要求が図々しくなってきている。しかし、われらの安全を脅かす悪の軍団があるかぎりは、この居候を追いだすことを躊躇する。ここは、まずは落着いて、悪の軍団がどこから登場してきたかを考えないとならない。
残念ながら、悪の首領はあまり自分史を語るのが好きではないらしく、彼らのことを知るには資料が不足している。しかし、彼らが歴史上の征服者の後継者を自認しているかぎり、その歴史上の人物を世界征服に駆り立てた思想も引き継いでいると仮定できるだろう。
民主化は戦争をなくさなかった
およそ戦争は種々雑多な目的で遂行される。権力者の支配欲、資本家の物欲、軍人の野望、武器商人や軍産複合体の利益なんてものが戦争の原因として指摘されてきた。しかし、現代戦は総力戦である。一般市民の協力なしには戦えない。悪の親玉の意図が何であろうとも、少数者の趣味や私益のために生活を犠牲にして殺人計画に協力しろと言ったところで、付き従う者は多くない。
だから、戦間期のリベラルたちは民主化が進めば戦争はなくなると考えたのだが、現実には戦争は回避できなかった。むしろ、民主化の進展に伴って戦争もまた激化したような面がある。そして、反戦勢力であると思われた一般市民が戦争に進んで協力した事実がある。それも大衆だけではなく分別ある知識人の多くもである。
この謎を解く鍵は既に与えられている。前の記事にも書いたように、積極的に戦争を善とみなす思想があったのであり、今日でもそれが廃れたといえるかどうか怪しい。復習すれば、それは特定の国や階級の利益ではなく、人類の名をもって戦われるような戦争である。自国領土の防衛やら市場確保なんていう狭い目的ではなく、世界によりよい秩序をもたらすための組織的暴力である。病んだ人類に健康をもたらす浄化としての流血である。
たとえば、満洲事変の首謀者である関東軍作戦主任参謀の石原莞爾は、「国運転回の根本国策たる満蒙問題解決策」と題された文章でこう述べている。
日本のために必要なるのみならず、多数支那民衆のためにも最も喜ぶべきことなり。すなわち、正義のために日本が進んで断行すべきものなり。
満洲の武力による領有を正当化するために、正義が持ち出されている。
無論、現実の戦争は首尾一貫した思想に基づいて戦われるものではない。それは多種多様な利害を持つ人々によって支持され、多種多様の思想のごった煮によって正当化される。しかし、遅くとも戦間期までには、戦争による人類救済がありうるという考えが世界的に流布され、また受け入れられたように見える(もとよりそのような思想には前史があるが)。それが恒常的な大規模殺人計画を正当化することに一役買ったのではというのが自分の仮説である。
進歩史観と戦争
戦争を正当化する種々雑多な思想のごった煮をより分けていくと、現代戦争に道徳的意味を帯びさせるものとして、少なくとも二つの近代的な思想的要素が結合しなければならないと思う。
第一にある種の歴史哲学がある。歴史は人間が意識せぬ法則によって律せられており、ある目的地、あるいは一定の方向に向かって進んでいる、という考えである。マルクス主義の唯物史観が一つの例であるが、社会進化論や他の雑多な進歩主義なども同じような機能を果たす。この歴史主義にイヴァーノフ=ラズームニクが「時間におけるシガリョーフ主義」と呼んだような論理が結びつくと、歴史的必然に与する暴力が肯定される。
シガリョーフ主義は、人類の選良の一割のために残り九割が犠牲になるべきという思想であった。これは同時代に生きる人間たちについてなのであるが、この関係を時間軸上に配分することもできる。つまり、今日を生きる不完全な人間たちは、未来の理想的人間のための肥しであると考えるのである。
これが「時間におけるシガリョーフ主義」である。人類の完成のためには、現在の劣った人間はよくても理想の人間を生むための素材にすぎない。邪魔になるようであれば掃討すべきである。進化という規準から見れば、殺人は罪であるどころかむしろ神の計画や自然の摂理に沿うたものである。そうなれば、階級闘争とか優等者が劣等者を淘汰する過程を加速するような暴力は、病ではなく健康の証しとなる。『罪と罰』のラスコーリニコフは、この思想にもとづいて高利貸しの老婆を殺害したのである。
レーニンの伝記などを読んでみると、この時間におけるシガリョーフ主義が明瞭に見て取れる。彼はナロードニキのテロリストを尊敬しており、国家権力を掌握してからもテロを積極的に使用した。彼の机には人間のしゃれこうべを調べる猿の青銅の置物が置かれていて、進化論へ好感を抱いていたことが知られている。これがどうも悪の首領の先輩の一人である。
人種思想と戦争
こちらはどちらかというと進歩派、革新派の思想であるが、第二の要素は、この進歩主義に対する反動として出てくる。つまり、反近代思想における概念の人種化が挙げられる。都市-農村、文化-文明、資本主義-社会主義、農業・産業-商業・金融といった社会的範疇が特定の人種・民族集団に結びつけられ、人種や文明の間の衝突といったものに置き換えられる。典型的なのは、ユダヤ人が都市生活、文明、資本主義、金融などと結びつけられ、ドイツ人が農村、文化、社会主義、産業などと結びつけられた例だ。
さまざまな社会的対立項が人種化されて、さらに上にあげた進化論と結びつくと、進化のための人種間闘争が淘汰の過程として肯定される。優れた人種が劣った人種を淘汰することによって人類は進歩する。これが自然の摂理である。この進化論は実在の人種間の社会経済的不平等を正当化する現状維持思想としても用いられるが、現状の人種的序列をひっくり返す革命思想にも使える。なんとなれば、進化論においては、勝った人種が優れているという事後的な正当化は原理的には否定できない。勝てば優等人種である。
そうなると資本主義の産みだす悪などを滅ぼすためには革命などではなく、人種戦争を最後まで戦い抜かなければならぬということになる。言ってみれば、人種化という操作で、時間におけるシガリョーフ主義と空間におけるシガリョーフ主義が止揚される。歴史哲学が地政学化する。それで階級闘争や革命が避けられるのかもしれんが、その代償として、戦争の意味は国防や植民地獲得とは全然別の次元に移される。革命家は「資本家を打倒せよ」のかわりに「鬼畜米英」などと叫ぶことになる。
この二つの思想が結び付くと戦争が国益の衝突以上の意味をもち、聖戦の性格を帯びるようになる。一部の国では、その思想が政策決定自体に影響を及ぼすほどに強くなった。ナチス政権下のドイツがその典型例である。ドイツ人が世界を征服するのはドイツ人だけのためではない。それは世界人類のためなのである。
わが国においてもまた、先の戦争は日本人ではなくアジア人のための戦争であり、少なくともそれを信じた人が多くいた。右翼思想においては、階級対立より民族対立が重視されたのだが、それはまた国際的な階級闘争(支配民族対被支配民族、白人対有色人種)とも呼ばれる側面をもっていた。
まだ調べることができないでいるのだが、労働者階級の国際的連帯を標榜するソ連では人種化の側面は表面には出ない。でも、社会主義の未来がロシアの国益と同一視される程度において、やはり戦争が人類の未来を左右するという考えが出て来たのではないかと考えている。
悪の軍団同士の対決
世界征服には国防以上の軍備がいる。そうして世界征服をたくらむ悪の帝国が現われれば、正義の味方もまたそれに見合った軍事力を装備しなければならない。最後には正義の味方も悪の首領と同じだけの武装をする世が到来する。平和を望むが故に戦争を拒否できない。国際政治の悲劇と呼ばれるような事態である。
しかし、思い返せば、悪の軍団が悪であるならば、ヒーローとその仲間もまたも悪でありえた。共産主義や人種主義は真空から生まれたのではない。日独伊やソ連だけが悪の軍団であったとは言えない。英仏にその思想の先触れになるものが既にあったし、そのかなりの部分は植民地支配のなかで培われてきた経緯がある。その植民地主義には批判的であるはずの米中という今日の大国の行動を見ても、無意識のうちにも、自分らこそが未来の人類のご先祖として選ばれた者であり、世界は自分たちの安全のためにこそ作り直されるべきだと考えているような節がある。
前回も書いたが、これは国家道徳の衰微(もしくは逆説)とも解せられる現象である。近代政治理論は、今生きている人々の安全と便宜のために作られたものとして近代国家を正当化した。政治と宗教は分離され、楽園浄土をこの世に実現することは国家の役割ではなくなったはずであった。しかし、現実には、あの世でしか実現されないような理想をこの世で実現しようという欲求が政教分離の壁を超えて、政治の場に溢れだすことになる。
そうなると、宗教特有の情熱が国家の行動を左右するようになる。社会進化論やら唯物史観やら人種主義やら民族主義やらが習合して、宗教と同様にユートピア像とそこへ至る道筋を示し、戦争を通じてそれを実現しようという政治運動を生んだ。今日の国際テロにも通ずる現代紛争の宗教的側面である。イスラム過激派ばかりが宗教と国際関係をつなぐリンクではない。
逆説的な話であるが、世界の民主化や普遍的人権観の普及もまた、この戦争の理想化に貢献するところがありそうだ。民主化された社会では、少数のものの私益のために戦争は行えない。そうなると、多くの人々に戦争の利益を売り込まないとならない。
さらに人権思想が普及すると、そもそも国益のために戦争をするということ自体が怪しからんということになる。そうなると、戦争はより崇高な宣伝を伴って売り込まれることになる。人権のため、民主主義のため、悪を滅ぼすため、というプレミアをつけないと戦争は行えない。そして、平均以上の道徳心をもった人であればあるほど、そんな口実を必要とする。シリーズ第二弾で話したテロリストの倫理と相似の関係である。
言ってみれば、俗なる領域の日常を律する倫理を、そのまま聖なる領域に適用しようとしたことによって生じた矛盾である。国内政治において悪を憎む人ほど、国際政治においては悪の首領の支持者となりやすいという逆説である。この自覚がわれらに欠けておるかぎり、悪の首領は倒されても何度でも甦る。
してみると、ライダーたちの居直りは、われらの善人にも付け入られる弱みがあった。漱石が百年前に嘆いたように、「われらは渾身の気力を挙げて、われらが過去を破壊しつつ、たおれるまで前進するのである」か、それともこの弱みを克服することができるのか。それが人類の存亡をかけた課題となった。
国際政治を勉強する人のためのおまけ
ちょっと専門的な話になって恐縮だが、つけ足しておく。国際関係論における古典的リアリズムというのは、戦争の目的をあくまで実現可能なものに限定することにより、終末論的戦争を避けるという倫理的意図をもって唱えられたものであった。
主権国家が互いを警戒して武装する世界は平和からはほど遠いものであるが、世界征服よりは小さい悪なのである。しかし、それは放っておけば自然にそうなるというものではない。次善の策とはいえ、国家指導者が熱狂しやすい民衆のナショナリズムに抗するだけの強さを持たないと覚束ない目標なのである。そして、長い目でみると有権者が国際政治の悲劇性を理解するようにならなければこの不安定な平和もおぼつかないであろう。エリート以外にも国際政治に関する教育を施す必要が唱えられたのも、それが理由であった。
それが後にネオ・リアリズムなんて呼ばれる米国の国際関係論学者の一派の手によって、機械論的自然主義に基づく科学理論にされてしまった。社会科学者の自然科学コンプレックスを癒すためだけの社会科学が、いかにバカげたビジネスに堕するかという典型的な事例を提供することとなった。
そんなガラクタのためにどれだけの若い才能が浪費されたかわからない。それだけではない。国際政治が一般の人には縁のない「科学ごっこ」によって囲い込まれてしまって、教育の普及を妨げている。これからやって来る人たちには、もうそんな無駄をしてほしくない。こんな文章を長々と書いてきた理由のひとつもそれである。
(2019年5月7日執筆したものに加筆した)
ここから先は
¥ 100
コーヒー一杯ごちそうしてくれれば、生きていく糧になりそうな話をしてくれる。そういう人間にわたしはなりたい。とくにコーヒー飲みたくなったときには。
