
2020年マイ年間ベストアルバム20
今年特に好きだと思ったアルバム作品を20枚選びました。去年と同じようにその内訳は2020年に発表された作品が10枚 + それ以外の作品が10枚。そしてそれらを交互にカウントダウンすることで、2軸綯い交ぜとなり、私自身も皆様にも、これまで見えていなかった景色が浮かび上がってくるようなランキングになっていてくれればいいなとひっそり期待しています。
振り返ると一人孤独なディグを続けていた印象の強い2020年でした。
10. Marcia Marie Rhoads『The Valley and The Mountain』 (1977)

70年代、ペンシルバニアで作られた女性SSWの自主制作盤。私が持っているレコードの中でも極端に情報が少ない、というかほぼ皆無で、私が買ったHMVとアメリカのオンラインレコードストア1軒に作品名とアートワークが載っているくらい。内容はざっくり言うとジョニ・ミッチェル直系のアコギ弾き語りを基調としたSSWアルバムなんですが、アルバムの半分程度を占めるカバー元がほとんどクリスチャン・ミュージックなのが最大の特徴でしょう。A-5「Would You Crucify Him?」ではJudee Sillに勝るとも劣らないホーリーな弾き語りが聴けます。静謐なホワイトゴスペル的要素が中心にありながらも、パイプっぽいハーモニカの使い方なんかで、タイトル通り高地の風景が浮かんでくるところも素敵です。
10. Sam Amidon『Sam Amidon』

Sam Amidonと言えば、幼いころからのルーツであるトラッド/フォークナンバーを、現代的な解釈で演奏する人で、例えばニコ・ミューリーだったり、初の全曲オリジナルとなった前作のMilford Gravesだったり、コラボレーターによってサウンドをアップデートしていく印象だったんですが、今作はトラッドのカバー中心の構成に回帰しつつ、これまで培ってきた要素が整然とまとめられて、我がものとなっている印象がすごく強いです。「Folk Roots, New Routes」という3年前のディスクガイド内のインタビューで、本人が「フォークミュージックはサウンドとフィーリングが重視される」と語っているのがすごく印象的で、この作品というかSam Amidonの作品全般を聴きながら、ルーツを掘り下げることと(サウンド的に)先鋭的であることって少なくとも対になる事柄ではなく、むしろ同符号のベクトルとなるようなシチュエーションも多いのではなかろうかと、そんなことを考えたりしました。
9. 歌島昌智『ゆにわ』 (2012)

寺尾紗穂さんの「わたしの好きなわらべうた」シリーズで出ているヤバい音は誰が出しているのか調べに行ったら、ほとんど全てこの方でした。情報は少ないですが、出雲在住のピアニスト、民族楽器奏者、作曲家、身体調律師だそうで、神巫音楽「あわのうた」を始め、日本古来の伝承音楽をポップスでは聴き慣れない音色の楽器を駆使しつつ、非常にコンテンポラリーなサウンドデザインを鳴らしているのがおもしろい。特にパーカッションの響きがすこぶるいいですね。2曲目の「たたらうた」という曲は、このワードだけ検索すると久石譲作の『もののけ姫』の劇中歌が出てくるんですが、そちらも改めて聴いてみるととてもよくてびっくりしました。歌島さんのアルバムの「たたらうた」と聴き比べてみると、ちょっとオブスキュアなアンビエンス、太鼓の縁打ちのようなパーカスと、アレンジに共通するところが見えてきます。なんだか「たたらうた」という種のうたの性格が見えてくるようで興味深いですね。
9. John Carroll Kirby『My Garden』

Solange、Frank Ocean、Blood Orangeといった錚々たる面々の作品に参加するピアニスト、作曲家。表面的なコラボレーションの経歴や活動拠点(LA/NY)を踏まえるとちょっと意外かもしれないですが、ソロ名義の本作は一面として、西洋のポップス的なところから離れていく無機質なエキゾ感があるのが抜群に気持ちいい。M9「Wind」なんかは、このランキングで後に出てくるある南米のアーティストにインスピレーションを受けたのが、モロに出ていて面白かったりします。このランキングを見渡した時に、上位に出てくる様々な年代の非英米圏のジャズ/室内楽/アンビエント/フォーク的な音楽と、英米圏のポップミュージックとをさりげなく橋渡ししてくれるような作品であるように思います。
8. Rafael Martini Sextet + Venezuela Symphonic Orchestra『SUITE ONIRICA』 (2017)

今年初LP化されたタイミングで知ったブラジルのピアニストRafael Martni率いるセクステットが、ベネズエラのシンフォーニーオーケストラとコラボレーションした大作。B-1で大活躍するコーラル(賛美歌)隊を始め、大オーケストラの数の力と、インプロとオーケストレーションがせめぎ合う厚く緻密な楽曲構成とでねじ伏せられる密度ギチギチ、壮大なモダンオーケストラ作品です。結果年代不詳な音にできあがっているところが最高。とても古くもつい最近のものにも聴こえるという。ちなみに、今年出たLP盤は、なかなかインパクトあるこの国内盤アートワークとはかけ離れているすっきりした輸入盤アートワークベースのものとなっています。
8. Wilma Archer『A Western Circular』

ロンドンベースのマルチ奏者の本名義での1枚目。家にずっといた春先にフィーリングが合ってよく聴きました。ジャズ、R&B、室内楽、ソフトロック、ヒップホップ、エレクトロをどろどろ溶かして、スイートで妖しい異形のトリップポップとしてアウトプットしたような作品。アレンジとしては豊富な楽器のレパートリーの中でも、ストリングスが中心となって引っ張っていくイメージがあります。そこで中核と言えるプレイヤーは誰かクレジットを調べてみると、Cliona Ni Choileainというプレイヤーが半分以上の曲でチェロを弾いていることが判明したんですが、フォロワー121人の本人のTwitterアカウントしか見つけられず困惑しています。ストリングスといえば、Wilma Archer本人も二胡を弾いていたり、他にもアルトサックス、ドラム・パーカッション、ギター、ベース、ピアノを自ら演奏していたりと多彩。未だになんだか得体のしれないミュージシャンという印象が強いですね。
7. Margo Guryan『Take a Picture』 (1968)

68年に作られた唯一のフルアルバム。ビーチボーイズ「God Only Knows」に感銘を受けてポップスのSSWとして活動を始めたというバックグラウンドどおりのソフトロック/ソフトサイケ サウンド、そしてふわっふわのウィスパーボイスととどめのアートワークまで、日本人に刺さりに刺さりそうな要素で身を固めてきている割には、日本での知名度が低すぎるような気がします。それこそRoger Nichols & The Small Circle Of Friendsくらいの知名度はあってもいいような気がしますが。最初聴いた瞬間から特に惹かれたのは、ミックスの塩梅で、エコーがしっかりかかって広がりのあるドラム・ボーカルと、ペラペラで軽いギター・ストリングスの対比、バランスが絶妙な "抜け" を生み出している。そういえば、柴田聡子さんの去年のライブ盤にも同じ "抜け"を感じているんですよね。
7. Joel Ross『Who Are You?』

NYベースのビブラフォン奏者のブルーノートからの2作目。今年はこのランキングにはそこまで反映されていないとはいえ、ジャンルとして一番聴いたはジャズだったと思うのだけど、新譜で特に好きだったのはこれです。ときに名盤と名高いジャズアルバムの中でも、特に管楽器のプレイヤーがディレクションを務めるものは、全体のアンサンブルよりもソロを重んじているような、どうもそれは弾き過ぎじゃないかと苦手に思うようなところがあり、私は未だジャズにおいてもアンサンブル、サウンドプロダクション、メロディとおよそ他ジャンルと同じような尺度で聴きがちな中で、このアルバムはアンサンブルへの意識の高さがひしひしと伝わってきて特別でした。ヴィブラフォンという担当楽器の性質がそうさせるのか各パートが主張し過ぎず、有機的なアンサンブルを聴かせながらも実にあっさりしています。とはいえ実はヴィブラフォンが主役を担っている時間は必ずしも多くなく、ピアノや管楽器などあくまでもスタンダードなジャズに根差した演奏をしているところがさらにおもしろく、プレイヤーというよりはプロデューサーとしての懐の深さに聴くたびに圧倒されてしまう作品でした。
6. Keith Jarrett『The Köln Concert (Live)』 (1975)

最も売れたジャズのソロ・アルバム、最も売れたピアノ・ソロ・アルバムです。今年は夏以降ジャズの名盤と名高い作品や、ECMの諸作品を結構な時間聴いていたんですが、どうやら一番有名なやつが一番好きだったようです。もちろんリズム楽器は入っていないのに、とにかくリズムが素晴らしいのがツボ。キース・ジャレットを語るときによく用いられる、「ジャズ以外にもさまざまなジャンルの素養を感じるスタイルで…」というのを分かるような分からないような感じだなーと『Facing You』なんかを先に聴きながら思ってたんですが、これのA面を聴いてようやく、その真の意味、彼の素養、エッセンスがどういうものかつかめた気がします。B,C面の片手はずっとコード弾き続けるところなんかも、平時ではこうはしないんだろうなーという、語り草となっているこのコンサートのバックグラウンドによる要素がことごとくベストな方向に転がっている。完璧!!
6. Meitei『古風』

広島在住のプロデューサーによる3rd。自分の言葉で書くのが道理という気もしますが、柴崎祐二さんのインタビューでの一節をどうしても引用したい。させてください。
「僕は基本的に洋楽ばかりを聴いてきた人間なんですけど、ふと国内に目を転じると、どうもいびつな状況があるような気がしたんです。“日本の音楽”でありながら、そのほとんどがおそらく無自覚に“東京の音楽”になってしまっている。海外の音楽を聴くと、その土地ごとの要素が少なからず溶け込んでいるように感じるけど、日本の音楽は、たとえアーティストが東京に住んでいなくても頭の中で組み立てられた“架空の東京の音楽”ばかりを鳴らしているという気がしてしまうんです。邦楽のルーツをさかのぼるにしても、あくまで“西洋のポップス”の枠組みばかりで、それが時に“日本らしさ”だと考えられてすらいる。たとえば雪をかぶったお地蔵さまとか、田園の水面に月が映る様子とか、僕達の世界に本当は今も実際に現存し続けている本源的な風景だとか記憶の階層には意識が向いていないように思えてしまって。
https://tokion.jp/2020/09/26/meitei/
今はそれぞれが自分の"フォーク"とはなにか、それをじっくりと見つめてみることが、日本に住む我々には殊更必要な時期なのではないか。それは分断や後退を意味するのではなく、いまよりもっと自由である緩やかなつながりを生むのではないか、そんなことを時々考えたりしている結果が、このランキングにも反映されていると思います。
5. Elizabeth Cotten『Freight Train and Other North Carolina Folk Songs and Tunes』 (1958)

1893年、ノースカロライナ生まれの彼女が、フォークリバイバル文脈で重要なシーガー家のメイドとして働いているうちに、一家に影響されて40年近く離れていたギターを再開し、58年に63歳で録音したファーストアルバムが本作。録音に至るまでのエピソードだけでも濃すぎますが、右利き用のギターをそのまま逆さに左利きの構えでもって弾くオリジナルのフィンガー・ピッキングが売りだということも触れておきたい。聴くたびに「弦が弾かれて生まれた振動が筐体に共鳴し、空気を揺らす」というギターという楽器の出音原理一連をわざわざ思い浮かべてしまうような身体的で暖かいピッキングはプリミティブなアメリカンフォークミュージックとしての魅力に溢れています。よれ気味のピッチも、彼女しか持ち得ない"間"と捉えたくなる境地に昇華されている。
5. Fleet Foxes『Shore』

Fleet Foxes名義でありながら、フロントマンのロビン・ペックノールド以外のメンバーは一切参加せずに作られた4thアルバム。Fleet Foxesと言えば、今年の春頃は前作「Crack-Up」から感じる清廉であり続けようとする気高き姿勢みたいなものが響きに響いて聴きまくっていたのですが、その「Crack-Up」について「7割が海で、3割が陸」と答えていたところから、本作「Shore」ではさらなる大海に漕ぎ出し「8.5が海で、1.5が陸」くらいのバランスとなっているように思います。「海」というところをイメージするのは、明らかにこれまでより柔らかくなった演奏や、多彩なパートに分離を利かせず水に溶かすようにまとめた (まとまっているのに奥行きがすごい!)ミックス、前作からより顕著になった南米をメインとしたエキゾチックな香り、逆にある側面ではビーチ・ボーイズ的なところに回帰しているようでもあり…
Fleet Foxesはここ2作が過渡期、むしろここからが面白いバンドのような気がしてなりません。
4. Blind Willie McTell『The Early Years (1927-1933)』 (1968)
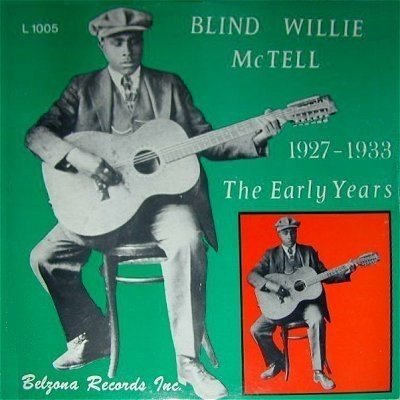
今年のちょうど長い梅雨頃には戦前のブルースをよく聴いていた。これはレコ屋また回れるようになったら実際にディグりたいなーと思っていたら、なじみのレコ屋には軒並みブルースのラインナップは少なく、しかもジャケでは良し悪しを判断しづらくて(というかよさそうに見えるやつがぶっちゃけあまりない…)、ちょっとここら辺への情熱は下火な最近ですが。そんな中で現時点の私のベスト・ブルースマンはこのBlind Willie McTellです。盤としてご覧のアートワークで発売されたのは68年ですが、収録曲が実際に録音されたのはタイトル通り1927年~1933年となっています。まさにデルタ・ブルースの面々と同時代を生きながら、その時代のブルースマンらしからぬ鼻から抜くような軽くて伸びのある歌唱スタイルが大好き。だらだら歌ってる中で一気に声を張るところで喉を締めて声が割れる感じとか、とにかくこの歌声が好きで聴いています。これからはベストボーカリストを尋ねられたらBlind Willie McTellと答えるつもり。
4. Alabaster Deplume『To Cy & Lee: Instrumentals Vol. 1』
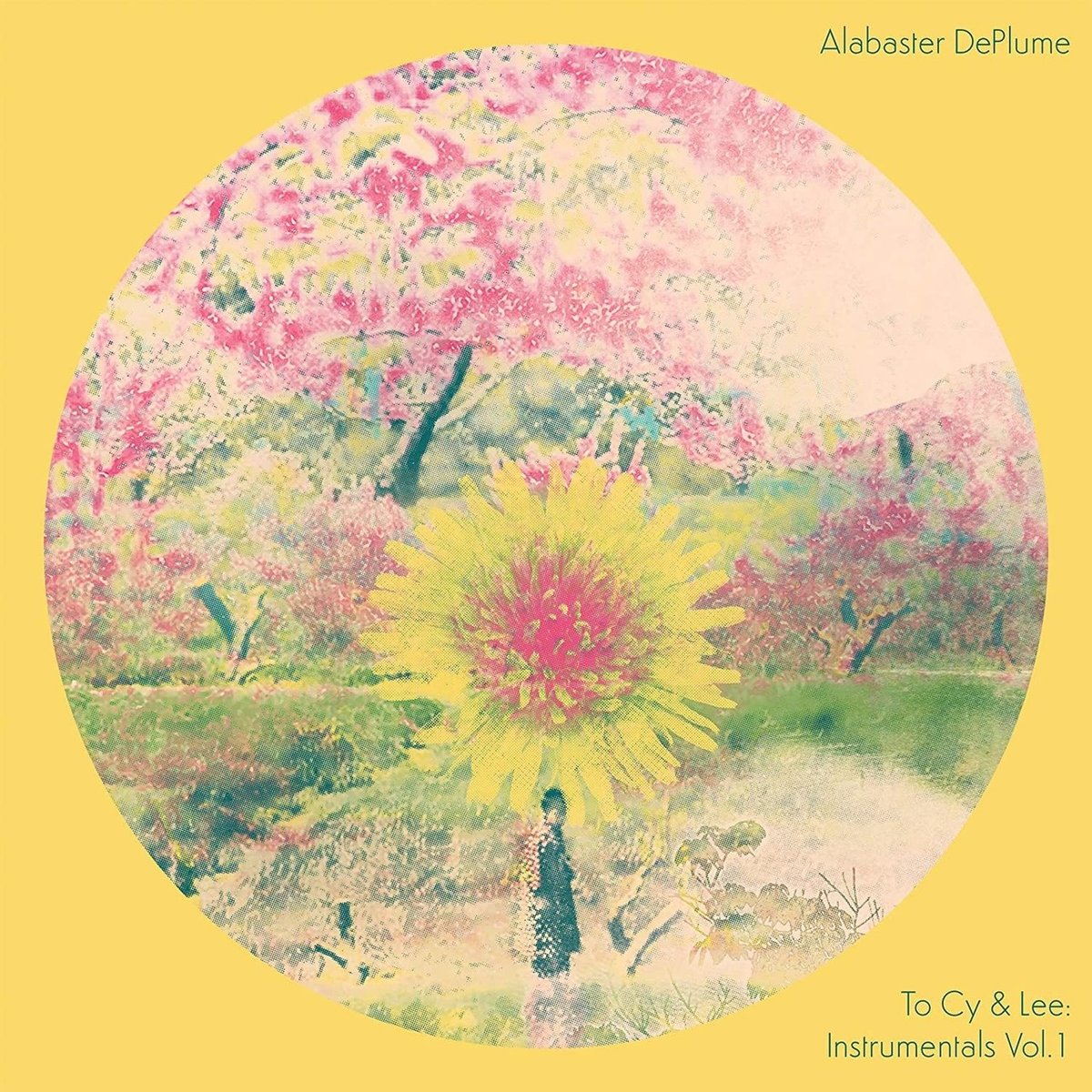
ロンドンベースのサックス奏者が近年発表済みの中からセレクトした楽曲と若干の新曲をまとめた作品。ストリングスとサックス中心のアンサンブルと開放感のあるサウンドデザインが抜群に美しい、ドリーミーでオブスキュアな室内楽/ジャズアルバムとなっています。日本の民謡やケルト民謡からアーサー・ラッセル、さらには「天空の城ラピュタ」など日本のアニメのサントラとこのランキングそのもののようなバックグラウンドを持つようで、確かに特に日本と特定してしまうと少し違う気もするが、東洋的なニュアンスを含んだアンサンブルを随所に響かせているのが窺えます。尺八のように震えるオブスキュアなサックスは特に印象的でサウンドの中核を成していると感じました。ちなみにここまでランキング中でアーサー・ラッセルからの影響を公言していたミュージシャンとして、Sam Amidon、Wilma Archerがいます。Fleet Foxesのロビンもきっと相当影響受けているだろうし、何か耳を澄まして音楽を聴くその対象の背後にはアーサー・ラッセルを感じる1年だったような気もします。
3. Yoshiharu Takeda『Aspiration』 (2018)

作編曲家 武田吉晴によるファーストアルバム。リリースは2018年ながら、今年ディスクユニオン内の「Silent River Runs Deep」という新興レーベルから初LP化されたタイミングで知りました。Silent River Runs Deepレーベルの作品はまだカタログがこれを含めて4枚 (Mono Fontana「Ciruelo」、Edson Natale「Nina Maika」、濱瀬元彦「樹木の音階」すべてLP)しかないんだけど、そのどれもがオブスキュアで、土着的で、室内楽的とまさに今年私が聴きたかった音を鳴らしていて夢中になってしまいました。Mono Fontana再発ここから出てたのか!というのは答え合わせ的な興奮もありましたね。武田吉晴の作品で特に興奮したのはサウンドプロダクションの面。クラリネットやオルガンが演出するドリーミーでオブスキュアな音響空間を、解像度の高いピアノやパーカッションが突いて穴をあけていくような、はたまた切り裂いていくようなアンサンブルの組み方がなんと刺激的だったことか。
3. Bob Dylan『Rough and Rowdy Ways』

このアルバムを聴くと、前述のSam AmidonやMeiteiへのコメントで私自身が書いた
ルーツを掘り下げることと(サウンド的に)先鋭的であることって少なくとも対になる事柄ではなく、むしろ同符号のベクトルとなるようなシチュエーションも多いのではなかろうか
今はそれぞれが自分の"フォーク"とはなにか、それをじっくりと見つめてみることが、日本に住む我々には殊更必要な時期なのではないか。それは分断や後退を意味するのではなく、いまよりもっと自由である緩やかなつながりを生むのではないか
という問いがよりクリアになっていく気がしてならないです。
今作までのオリジナルアルバムで見たら8年存在するブランクには『Shadows In the Night』、『Fallen Angels』、『Triplicate』とフランク・シナトラのレパートリーなどアメリカンクラシックをディラン流に解釈した、グレイト・アメリカン・ソングブック3部作を鋭意制作していたのは私が説明するまでもないですね。新作『Rough and Rowdy Ways』に戻ると、そのグレイト・アメリカン・ソングブック的なエッセンスと、戦前のブルースといったアメリカローカルな表現を捉え直した作品に聴こえます。さらにコラボレーターとして参加しているブレイク・ミルズやフィオナ・アップルといったアメリカンロックの(ディランと比べれば)新鋭の貢献度も高そうで、M5『Black Rider』のマンドリンとパーカッションの響きなんかにはブレイク・ミルズらしいアンビエンスを確かに感じるような気がします。(実際どこで参加しているかはクレジットされていませんが。)
アメリカにはボブ・ディランがいる。それを思うだけでいつもなんだか羨ましくなってしまうな。
2. Juan Fermin Ferraris『35 Mm』 (2019)

アルゼンチンの現代フォルクローレを更新するグループ、Cribasのピアニスト Juan Fermin Ferrarisの初のソロアルバム。リリースは去年で、私が初めて聴いたのは去年暮れの年間ベストを出した後だったと思うのですが、そこから1年間何度も繰り返し聴いたこの作品は、今振り返ると今年の私が音楽を聴くときの指針のように存在していたといえるかもしれません。Juan Fermin Ferrarisのピアノを中心とするカルテットの土着的で軽快、陽だまりのように暖かいアンサンブルに、グループ名Cribasの引用元となっているMono Fontanaを彷彿とさせるミュージックコンクレートが導入された結果、映像的で郷愁に胸をぎゅっと締め付けられるような不思議な愛着を植え付けられる音楽となっています。しっとりとした泣きのピアノジャズ。その不思議な郷愁を覚える土着的な旋律からは、RPG系の架空のゲームサウンドトラックみたいな雰囲気も漂ってくるのも、おもしろいポイントかもしれません。
2. ROTH BART BARON『極彩色の祝祭』

これで3年連続のオリジナルアルバムリリースである。毎年秋になるとROTH BART BARONの新作が聴けるとはなんと幸せなことか。
一緒に踊ろう 終わりがくるまで
とは、デビュー作で日本古来の"祝祭"について歌った「盆ダンス」のメインフレーズですが、「極彩色の祝祭」においても"祝祭"がもつ始まりと終わり、もっと意味を広げて時間的な断絶や繋がりが歌われているように思います。繋がりというところで言うと、印象的なのは「ループ」というモチーフ。リリックにおいてはDNAの二重螺旋がモチーフとなっている「ひかりの螺旋」、「000Big Bird000」では「どれだけループを繰り返したら このふざけた話は終わるの?」と直接的な表現も登場したりしますが、もっと面白いのはその「000Big Bird000」から始まるB面サウンドに注目してみたときで、「000Big Bird000」、「BURNHOUSE」、「ヨVE」とループするギターリフが前面に出てくるような、これまでのロットには珍しい3曲が並んでいます。
今この瞬間が当たり前のように続くと思っているから、断絶を迎えたときのインパクトはより鮮烈となる。「ヨVE」の当たり前のように続くと思った'音が止んで'「NEVER FORGET」へ。何が起こってもおかしくない時代、きっと私たちと同じように惑いながらも、三船雅也は決意の火を灯し続けている。
※追記ですが、アナログバージョンでは「ヨVE」はフェードアウト、緩やかに「NEVER FORGET」と繋がるマスタリングとなっています。さらにバンド初のドイツプレスによる効果なのか、音圧みっちみちのリッチで特別感あるサウンドとなっていて、「極彩色の祝祭」はアナログで聴いてこそ完成する!と思わず言いたくなる代物。まだの人はぜひLP盤、お勧めします。
1. Tsegue-Maryam Guebrou『Ethiopiques, Vol. 21 : Piano Solo』(2006)
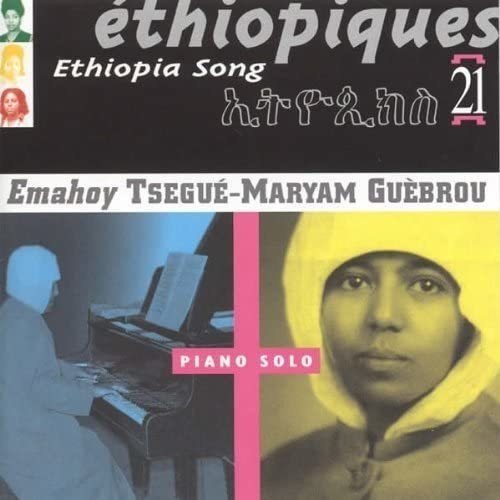
エチオピアの修道女であり、ピアニストであり作曲家であるTsegue-Maryam Guebrouがドイツやイスラエルでリリースしたレコードから曲を集めた編集盤。エチオピア音楽のリイシューシリーズ「エチオピークス」のラインナップの1枚です。16曲中M1~9が1963年、M10~12が1970年、M13~16が1996年に録音されたよう。現在ディスコグラフィの中で気軽に入手できるのはこの編集盤だけとなっています。ヨーロッパに留学してクラッシックを学び、その後エチオピアに戻って修道女となった経歴が音にも出ているように思う。エチオピアの伝統的な宗教音楽と思われる要素と、欧米のクラシック・ジャズなどの要素が綯い交ぜになった結果、禁欲的な緊張感がありながらも、郷愁や慈愛の心が零れ落ちてくるような、圧倒的なピアノソロスタイルに至っている。そのピアノスタイルの基本は、細かなタッチで爪弾かれる短いフレーズを少しずつ形を変えて繰り返すことにあり、それはまるで車窓から過ぎ去る景色を気まぐれに描写するような瑞々しく、オブスキュアな感覚へと聴くものを誘ってくれます。
この作品に出会ったのはつい最近なんですが、聴いた瞬間に今年一年音楽を聴いてきた集大成であると確信するサウンドでした。きっかけは新譜9位のJohn Carroll Kirbyの「Wind」という曲の影響元として挙げられてたから。さらに、Fleet Foxesのロビンも今年の新作の影響源としてセレクトしていたり、どうやら音楽って私が思っていたよりずっとフレキシブルで、いろいろな境界を越えていく繋がりを生むポテンシャルがあるようです。土地や年代、商用のジャンル分け(は便利だけど)、そこに固執してしまうことが如何に視野を狭めるか、つくづく実感することとなりました。
1. 寺尾紗穂『わたしの好きなわらべうた2』

今年の寺尾紗穂さんと言えば、アルバム「北へ向かう」から「光のたましい」があって、今作と常に別格でしたが、ベストとしてはこれを選びたいと思います。全国各地のわらべうたを発掘、コンテンポラリーなアレンジを施す「わたしの好きなわらべうた」の4年ぶりの続編。篠笛、能管他聞いたこともない楽器の数々を操るわらべ歌シリーズのサウンドの核である歌島昌智、わらべ歌シリーズ以外でもおなじみのベース 伊賀航、ドラムス あだち麗三郎と中心メンバーに大きな変化はありませんが、 そのアレンジ・演奏は前作をはるかに凌いで、あまりに鮮烈なアップデートを遂げています。わらべ歌/こもり歌という土着的な題材にインスピレーションを受けるとかそういうレベルを越えて、何かDNAレベルで刻まれた獣としての記憶がよみがえるように、寺尾さんのピアノも歌唱も、バンドメンバーの演奏も、よりトライバルで、肉体的な質感を伴って聴こえてくるような気がします。
この作品なくしては、近ごろ音楽を聴きながら漠然と考えていたことを、(まだまだ不完全ながら)ここまで言語化できてはいなかったでしょう。
2度目のセルフ引用となり恐縮ですが。
ルーツを掘り下げることと(サウンド的に)先鋭的であることって少なくとも対になる事柄ではなく、むしろ同符号のベクトルとなるようなシチュエーションも多いのではなかろうか
今はそれぞれが自分の"フォーク"とはなにか、それをじっくりと見つめてみることが、日本に住む我々には殊更必要な時期なのではないか。それは分断や後退を意味するのではなく、いまよりもっと自由である緩やかなつながりを生むのではないか
2020年にこれが聴けてよかった。
どうぞお気軽にコメント等くださいね。
