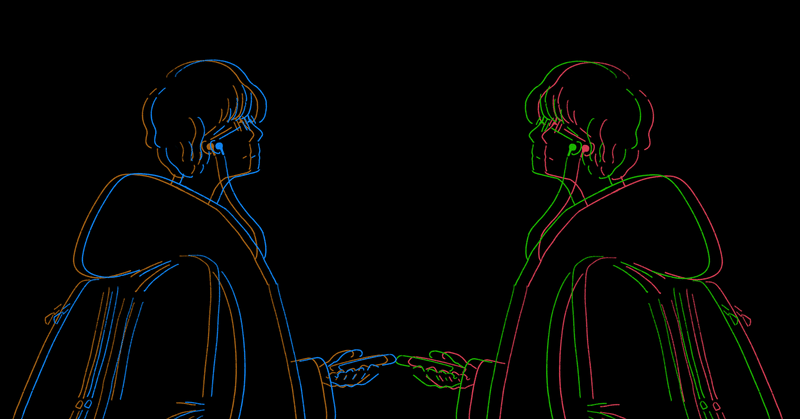
かび臭い学校のB階段で聴いたラフメイカー
薄暗くてかび臭い学校のB階段で聴いたBUMP OF CHICKENのラフメイカー。今、高校の卒業文集を書き直すなら、こうタイトルをつけたい。
部活動、文化祭、楽しいことが溢れんばかりの高校生活を過ごしていた僕にとって、大学受験は憂鬱以外の何ものでもなかった。というのも、大学3年生まで尽く勉強をさぼってきたから。そのツケはあまりに大きかった。
家庭の事情から浪人できない僕は、すでに浪人している年後の兄に対し、負けまいという対抗心と余裕たっぷりで見下してくることに対する怒りを
ボイラー室に詰め込み、毎日がむしゃらに勉強していた。
ランナーズハイに近い現象だろうか。
勉強を必死にしていると憂鬱は段々と心地よさに変わっていった。
カビ臭かった校舎に制汗剤の匂い漂う頃には毎日自習室で最低12時間のノルマをこなし、帰路でもベッドでも単語帳やノートを開いていた。
セミの声が聞こえなくなっても、そのペースが落ちることはなかった。
ーーーーー
現役生は最後まで伸びる。
擦られすぎた歌い文句だと斜めに捉えていても本当にそうなったから驚きだ。E判定はC判定へ。C判定はB判定へと、段々と努力が結果に表われてきた。
587点。
今でも覚えているセンター試験の結果。本来必要な点数は720点。大きすぎる失敗だった。僕は当時よくしてくれていた美術教師のもとに向かい、2次試験を受けたとしても点数的に合格の見込みがないことを話した。
「水口、美術受験受けろよ」
突拍子のないことを言うことで有名だった先生。豆鉄砲を食らった僕をよそに先生は淡々と続ける。
「2次試験が400点満点で、普通に受けたら1次2次合計900点ないと合格できないからお前にはムリ。でも、美術受験なら合わせて800点で受かる。おまえが行ける可能性はそこしかない。それか諦めて滑り止め。」
「諦める」という言葉に敏感だった僕は、二つ返事で美術受験を受けることに決めた。
とはいえやっぱり現役で大学に行って欲しいと思っている親とは喧嘩になった。根拠のない自信と熱意だけで押し切り、親をなんとか説得した。
「わかった。ただ、併願している大学の受験には必ず行くってことだけは守って欲しい」親から告げられた心配と信頼が入り混じった言葉に、胸が熱くなった。
自習室に通う日々は、美術室へ通う日々へと変化した。
すでに進路が確定している友達を呼び出して、デッサンのモデルをしてもらいながら毎日絵を描く。鉛筆を削ったときの墨と木の匂いが、だんだんと身体中にこびりついて離れなくなっていった。
「水口、筆が遅いね」
「もっと線を丁寧に書きなよ」
「密度が足りないね」
「形取れてないな〜」
「ここに球体があるのを想像できない?」
「まずは面で見て」
先生は毎日、ちょっと強いけど的確な指摘を浴びせながら、必死に向き合ってくれた。僕はヘラヘラしながら、謝ることしかできなかった。
とはいえそんな指導のおかげもあって、少しずつ絵が上達していった。
試験前日には「もしかしたら受かるかもしれない…」そう希望を持てるようになっていた。
ーーーーー
いつものようにストーブが弱々しく燃えている美術室、
箱椅子の上で絵を描いていると、先生がやってきた。
「お前、変わらないな〜」
絵を見て一言目に発した先生の言葉が、なぜかは分からないまま、やけに響いた。
「すみません、ちょっと、トイレ行ってきます…」
鼻を啜る様子からして明らかにバレバレな嘘をついて美術室を飛び出す。
先生にも、受験が終わって浮かれている同級生にも見つかりたくなかった僕は、誰も使わない埃まみれのB階段に一人蹲る。
自分の絵は変わった。うまくなってきていると思っていた。
これなら合格できるかもしれないと思っていた。一方で同時に抱えていた合格できるかわからない不安。模試のようにわかりやすい結果がない不安が知らず知らずのうちに募っていたのだと思う。
さっき先生に言われた「変わらない」は、僕にとって「受からない」と同義で、その事実に耐えきれなかった。
こういう時に限って浮かれている同級生は現れる。
「お〜う、水口じゃん、新しくギター買ったんだ〜いいだろ〜」
「…いいね」
「めっちゃいい音だからさ、弾いてもいい?」
僕が答える前に、そいつは弾き始めていた。
「涙で濡れた部屋に、ノックの音が転がった。誰にも会えない顔なのに もう なんだよ どちら様?『名乗る程 たいした名じゃないが 誰かがこう呼ぶ"ラフ・メイカー" アンタに笑顔を持って来た 寒いから入れてくれ』」
そいつが歌ったBUMP OF CHICKENの「ラフメイカー」に、笑顔ではなく泣き顔を連れ戻されることになってしまった。
結局僕は、志望校に合格することができた。
後々先生に聞くと「変わらず今日も描いているね〜」という意味で言っていたと、発言の真意も判明した。
ーーーーー
いつ振り返ってみてもこの思い出が鮮明に輝き続けているのは、僕の優しさの物差しを広げてくれたからと思う。
「泣いているけど、どうしたの?」
「何かあった?」
「辛かったね」
たくさん話を聞いてくれる優しさだけじゃない。
ただ隣にいて、ただ自慢げに一曲弾いて歌っただけ。その後満足して去っていく。辛い時に隣にいて、歌を歌うだけの優しさがあってもいいのだと知ったからだと思う。
言葉の企画を通して自分らしい生き方を見つける講座「言葉の企画2020」の第二回。ゴールデン帯に見られるテレビ番組を企画するという課題に取り組む中で、僕は今まで生きてきた道のりを、ノートの上で一つ一つ辿った。
僕という人間は、僕を僕にしてくれた、生まれてから今日までの間に出会った全ての人や出来事によって成り立っている。
それを知ることが、企画の源泉になると感じた。
今日まで何を面白いと感じ、何を喜びと感じ、何を優しさと感じてきたのか、それらを踏まえて、今何が面白くて、何に喜び、何が優しさなのかを言葉にしなくてはいけない。
自分を知ることができたらさらにその輪を広げなければならない。企画に出演してくれる人、関わってくれる人、企画を評価してくれる人、そして企画を体験してくれる人。
こんなこと今まで一度も考えたことがなかった。熱を持って知りたいと思うことなんて滅多になかった。
でも今は、知りたいと言う気持ちが、少しずつ頭をもたげてきている。
サポートは、スシローのお寿司をいっぱい食べることに使わせていただきます。
