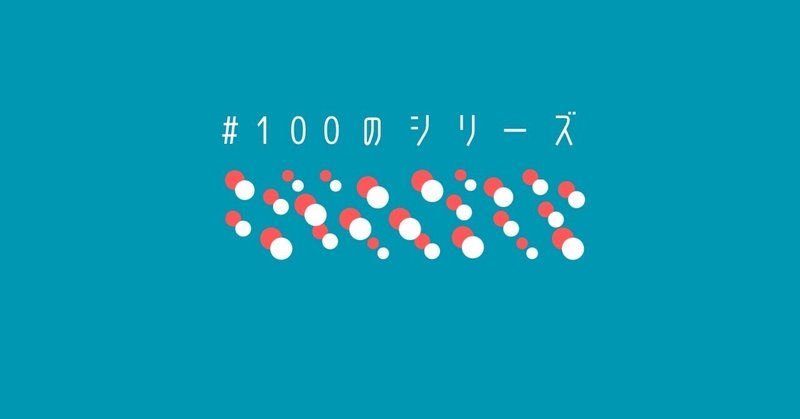
【71気持ち】#100のシリーズ
「今から『気持ち』を預からせていただきます」
自分たちの前にそれぞれひとりずつ、宇宙服にも似た服を着た係員が立つ。
アナウンスが「利き手を前に」というのに合わせて係員はボックスを差し出す。
自分たちはそのボックスの中央にある穴に利き手を入れる。
「それだけ?」
「うん。それだけ」
頷きながらクヌギハラはメロンクリームソーダのアイスを突く。
透明な緑色のメロンソーダの中の氷がキラキラ揺れる。
「それで気持ちがなくなっちゃうの?」
オオツガワが前のめりになる。
「なくなるというか落ち着くというか…感覚はあるし、記憶もあるけど、感情だけがないんだよね」
クヌギハラはアイスが氷に接して凍っている部分を、慎重にスプーンで削り口に運ぶ。
「この食感が好き」
クヌギハラは嬉しそうに言う。
「好きも嫌いも。楽しいも辛いも。なーんにもない」
「でも何をしたかは覚えているんだ」
「まあね」
クヌギハラは今度はメロンクリームソーダをストローで吸った。
「でもね。何の感情も伴わない記憶って、すぐ抜けちゃうんだよね。俺、相手の顔とか全然覚えていない。相手もそうなんじゃないかな?」
「ふうん」
オオツガワはアイスコーヒーをストローでくるくるかき混ぜるばかりで飲む気配がない。カラカラと氷のぶつかる音がする。
「気持ちはいつ返してもらうの?」
「全部終わって、シャワーを浴びて、ひと眠りして起きると係員がやってきて気持ちを返してくれる」
目覚めると白い天井が見える。
天井自体が光っているのか照明は見当たらない。
「目が覚めましたか?」と言う声に「はい」と答えると、係員が部屋に入ってくる。
ベッドに仰向けで寝たままの自分に向かって「両手をまっすぐ伸ばしてください」と言いながら、先に見た箱より少し大きめの箱を伸ばした両手に被せた。
「で、気持ちが返ってくるわけだ」
「そう」
クヌギハラは頷く。
「気持ちが返ってきた時ってどんな感じ?」
「目が覚めた感じ」
「ふうん」
オオツガワのアイスコーヒーの氷はほとんど溶けてしまった。クルクルストローを回すがほとんど音はしなかった。
「別になんて事ないよ。気持ちを預けたあと作業の説明もしてくれるし、うまくできないと手伝ってくれる。なんてことないよ」
クヌギハラは溶けたアイスとメロンソーダを混ぜた。
「うーん」
「優良遺伝子を持つ者の義務だから。でもそれをすれば、今後、死ぬまでの生活がきちんと保障されるんだ」
「おまえはもう条件クリアしたの?」
オオツガワが訊ねる。
「うん。3回済ませた」
「そっか」
そこで初めてオオツガワがアイスコーヒーを口にした。
「美味しい?」
怪訝そうな顔でクヌギハラが訊く。
「オレ、薄めが好きだから」
オオツガワが答える。
「子作りねぇ…どうも気が乗らないんだよなぁ」
オオツガワが言う。
「だから、気持ちを預けるんだよ」
クヌギハラはそう言うと、不透明になったメロンクリームソーダを一気に吸い込んだ。

