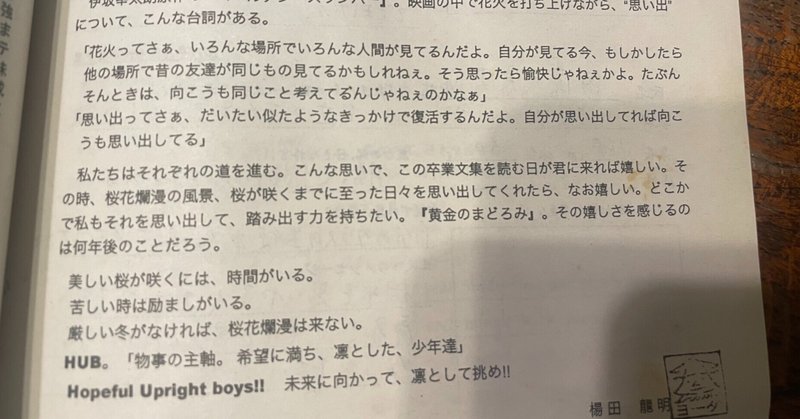
知的障害者のきょうだい⑦-ひとつかみの砂金-
なぜ学ぶのだろうか。
この問いにあなたは何と答えるだろうか。人工知能の登場で学びのあり方が変容し、様々な議論がある。太宰治は『正義と微笑』の中で次のように教師に語らせている。昭和初期の文章だ。
「覚えるということが大事なのではなく、大事なのは、カルチベートされるということなんだ。カルチュアというのは、公式や単語をたくさん暗記してゐる事だけでなくて、心を広く持つということなんだ…<中略>学問なんて、覚えると同時に忘れてしまっていいものなんだ。けれども、全部忘れてしまっても、その勉強の訓練の底に一つかみの砂金が残ってゐるものだ」
暗記や知識を否定するわけではない。それ以上に学問の作業が人間をカルチベートするものである、すなわち人間それ自体を広く深く練磨してくれるものであることを、太宰治は述べている。全部忘れてしまっても、その勉強の訓練の底に残ってゐる【一つかみの砂金】──あなたは何だと考えるだろうか。
授業から15年の月日が経ち、31歳となった卒業生にnoteを読んで感想をお願いした。ありがたいことにいろんな卒業生から返信が届いた。心苦しいが、紙面の都合で全てを紹介できない。本当に申し訳ない。抜粋して紹介したい。
これは一言でいうと「差別」だと思います。
LINEで楊田先生のnoteの情報が友人から流れてきまして、1~6章まで一気に読ませてもらいました。このnoteを見て、先生が積極的に活動されていることを知り、数多くの教え子の一人として嬉しかったです。
https://note.com/tatsuaki_yoda/n/na79019dad8c5
実はこの授業を受けていたことを、このnoteを読むまで忘れていました。そういえば・・・という感じで徐々に記憶が蘇ってきた感じです、
この授業を受けた当時は「なんか面倒くさい授業やなぁ・・・なんでこんな意味わからんことせなあかんねん。」という気持ちでした。反抗期です。すみません。
私も31歳となり、幸いにも2人の子供にも恵まれた今、このnoteを読み、思ったことをつらつらと記します。
現在医療職に就いている私は、健常者と障害者の方で分け隔てなく治療にあたります。これは自信を持って言えることです。しかし公共交通機関で知的障害者が乗車している車両に乗り合わせたらどうするでしょうか。私一人だけなら特に気にしませんが、子供を連れているときはその車両に乗り続けるでしょうか。正直自信を持って乗り続けるとは言い切れません。もしも急に暴れ出したりして、子供が怪我したらどうしようと考えてしまうからです。知的障害者が必ずしも暴れるわけではないですが、病院内でそういう方を見ていることもあり、万が一を考えてしまいます。これは一言でいうと「差別」だと思います。
仕事では障害者に対し、健常者と同じ説明をせずに言い方を変えたりなど「区別」はしています。これは大人への対応と子供への対応とも同じです。つまり私は知的障害者に対し、仕事としては「差別」なく接することができますが、プライベートでは「差別」してしまうのです。 身近な人、親族、兄弟、子供に知的障害者がいないと、プライベートで差別なく接することは、難しいのかもしれません。そういった意味で、○○先生は「知的障害者について分かって欲しいと思っていないし、分かるとも思わない」と言われたのではないかと思いました。
15年以上前のことなので詳細には覚えていることは少ないのですが、楊田先生の授業は「熱」と「笑い」がこもっており、とても楽しく授業を受けていた記憶があります。私は大学生時代に塾講師としてアルバイトをしており、そこで授業をすることの難しさを身に沁みて感じ、改めて先生の授業の凄みを感じました。
Zくん

Zくんのように「noteを読むまでこの授業の記憶が自分の中からすっぽり抜け落ちていた」といった感想は、多くの卒業生が述べていた。6年間教えた中でも、抜群の社会科センスを見せ続けた社会活動家・篠田ミルくんから、次のような寄稿をもらった。
沈黙は忘却とやっぱり隣り合わせであるようだ
なにも言うことができない。言葉が見つからない。
このnoteを読んだときに僕が思い起こしたのはこの感覚だ。
社会運動に関わったり、微力ながら社会で起きていることについて考え発信するように心がけてきたつもりだった。相模原障害者施設殺傷事件が2016年に起きたときには、事件の凄惨さ、そのような事件を引き起こしてしまったこの社会のありように深く動揺し、憤った。
それでも、自分が高校生のときに受けたはずの授業の記録にあらためて目を通したときに、まず僕は言葉に詰まった。読みながら徐々に思い起こされた感情や、大人になって色々勉強したいまになって感じたことや考えたことはたくさんある。でもうまく言葉にすることができない。
なによりも僕が衝撃を受けたのは、noteを読むまでこの授業の記憶が自分の中からすっぽり抜け落ちていたことだった。
当時、自分が授業の感想にどのようなことを書いたかは全く思い出せない。でも、この言い淀む感覚、感じたことや思考の流れを言語化したくとも、自らがよって立っていたものがグラつき崩れ落ち、流れていく思考が言葉になる前に戸惑い消えてしまう感覚を薄暗い講堂で感じたことだけはよく覚えている。
「知的障害者」というステレオタイプや表象でしか認識していなかった対象が、実体を持った近くの誰かの経験として目の前に現れたとき、自らのそれまでの認識や思考がいかに浅薄で表面的だったかということを突きつけられ、高校生だった僕は沈黙した。
そして大人になったいま、この授業と再会して僕は再び沈黙した。それは自分にとって衝撃だったはずのことが月日とともに押し流され、すっぽりと自分の中から消失していたからだ。それは自分がどれだけ社会的であることを意識していても、社会に5%もいる人々のことを無意識的に頭の片隅に追いやって過ごしてきたことの裏返しであることをたしかに突きつけられたからだ。
もちろん沈黙は、衝撃的なリアリティを前にしたときの、極めて理性的な反応であるとも思う。自らが前提としていた認識の薄っぺらさや頼りなさが顕になったときに、戸惑い言葉を発することができないのは当然だ。沈黙はその後の発話や行動を用意するためのクッションでもあるはずなのだ。
でも、それと同時に沈黙は忘却とやっぱり隣り合わせであるようだ。少なくとも僕にとってはそうだった。高校生である僕は授業に衝撃を受け、深く戸惑い考え込み黙りこんだ。そしてそのままその思考は頭の片隅に追いやられてしまっていた。
楊田先生の授業はかなり熱心に受けていたほうだと思うし、自分のその後の進路にとっても少なからぬ影響があったと思う。それにもかかわらず、この授業のことが記憶の中から抜け落ちていたことは自分にとっては衝撃的だった。
沈黙をまた忘却に繋げてしまわないためにどうするべきなのかぐるぐる考えている。 篠田ミルくん
知的障害の妹を持つ○○先生の境遇を思い出すことはありませんでした。
「楊田先生との関わりは、自分にとってターニングポイントだった」とまで語ってくれたYくんも次のように綴っている。
同級生が、「兄バカ」の作文を書いたことを覚えています。同じ学校の生徒なのだから、皆似たような境遇だろうとの漠然とした認識を持っていたのですが、自分が想像すらしていなかった事情がある同級生がいたことに驚いた記憶です。それぞれの人に他人が知らない事情がある、というのは当たり前のことですが、高校生の自分はようやくそのことに気付いたのでした。
対話集会の当日、突然「では、○○先生お願いします」と紹介された○○先生が登壇された時は、何が起きたのかもよくわからず、「どうして、○○先生が呼ばれたのか?」との疑問でいっぱいでした。○○先生が話し始めてから徐々に状況が飲み込め、想像すらしていなかった状況に驚いたことを覚えています。
しかしながら、集会前の授業・集会当日において、当時の自分がどう考えていたのか、詳細はあまり思い出せないというのが正直なところです。
○○先生とも卒業後にお会いする機会があり、また、食事もさせていただいたこともありましたが、思い出していたのは、少人数クラスでの和気藹々とした授業(この授業のおかげで、苦手意識のあった当該科目が好きになりました)、質問に行けばいつでも答えてくれ(先生が他のクラスから出てくるのを待ち構えて、歩きながらでも質問していたことを覚えています)、時には一緒に考えてくれたことなどであり、対話集会の際に話をされていた境遇を思い出すことはありませんでした。 Yくん

「リフレクションは新たな学びを見つけ出す」
卒業生の振り返りを読むなかで、2010年に読売教育賞実践報告の執筆に取り組んだ自分自身のモヤモヤを思い出した。知的障害者のきょうだいの気持ちに迫り何かを掴んだように感じても言語化できなかった。言葉が見つからなかった。それを突き詰めたい。私自身の葛藤や狙いを言葉にしたいと思い、第59回読売教育賞実践報告の執筆に取り組んだ。教師自身のリフレクション学習と言えるだろう。
ジョン・デューイは「経験がその後の経験にどのように影響を及ぼすか」が重要であり、そのためにはまず「自分の現在の経験から、自分が経験しているときの経験のなかにある自分のためになるすべてを獲得すること」として現在の経験から十分な意味を引き出すことの必要性を指摘している。
このデューイの指摘を、次の2人の卒業生のリフレクションが深めてくれた。
「弁護士とは人間の業の肯定である」
当時、「作文は出せばいい」「授業は座っていたらいい」程度にしか考えていなかったことを思い出し、恥ずかしい気持ちになりました。その程度の姿勢だった私にも、中高6年間で一番印象に残っている授業です。
現在は田舎で弁護士をしています。知的な面で制約を抱えながら生活している人に関わる機会が多いです。(知的障害をお持ちの方に限らず、認知症をお持ちの高齢者の方もおられます)。私はご本人について資料に書いてあることしかわからないため、きょうだい等のご本人と密な関係を築いている人に協力をお願いし、「ご本人が好み、望む生活」は何か、それを実現するにはどうしたらいいか考え、少しでも実現できるようにしています。
弁護士業の一環としてご本人・ごきょうだいに関わっている中で、ふと「高校の時にこんな授業を受けたな」と思い出し、当時、真剣に考え、取り組んでいたら、より良い弁護士になっていただろうなと反省しました。
「弁護士とは人間の業の肯定である」と考え、悩みながら仕事をしています。
Xくん
大学時代の家庭教師で出会ったK くんのこと
早速ですが本題に入ります。note を拝読させていただき、当時の記憶を思い返しました。規定のカリキュラムではなく答えがないセンシティブな話題に関して、先生と生徒が共に真剣に考えた時間は僕にとって貴重な財産になっています。今はSNS に “答えらしき言動” をいくらでも拾える時代で知識を持っていることに意味がなくなっていると思います。そんな中、楊田先生の授業での原体験、自発的に内側から出てくる人間的な感情や意見などの価値がとても大事で、「障害者」という切り口でそのような濃密な時間を過ごせたことに感謝しています。
私の周りには障害者は居ませんが、障害者に対して家庭教師をしていたことがあります。僕1人で初めて障害者と対峙した経験で、教えていた当初も楊田先生の授業が思い出されていました(そして当時抱いていた思いも)。そこで少しでも私の体験を共有できることがあるのであればと思い、自分のためにもこの依頼をお受けすることにしました。稚拙な文章で恐縮ですがお付き合い下さい。
この記事を読んだ際に真っ先に思い浮かんだのが、大学時代の家庭教師で出会ったK くんのことだ。たまたた知り合い経由で家庭教師を頼まれ、引き受けることにした。当時、Kくんは障害者として診断されているわけでは無かった。しかし教えていると気づく違和感。何か「普通」とは違うのだ。例えば5分前に伝えたことを覚えていない、私が喋っていても違う方向を向いて考え事をし始める(明らかに集中力が無い)、何度注意しても同じような間違いを続ける、すぐに寝てしまうなど。そこでまずはこの事実を親御さんに伝えることにした。すると「そんなことはないと思う」と強い口調で言われその事実を触れて欲しくないという雰囲気さえも感じたためそれ以上踏み込めなかった。
僕は考えた。このまま何も無かったかのように教え続けることがK くんにとって良いことなのかすごく悩んだが、自分できることをしようと決めた。ネットや関連書籍を読むと、そのような人は何かに突出していることや分野がある可能性が高いということを知り、これは伝える必要があると感じて慎重にかつ丁寧に親御さん何度も機会を作り伝えた。
そうするとある日「(少し間が空いた後に恐る恐る)うすうす親としても障害である可能性は感じている。でもこの子には必ずどこかで才能があると楽観的に捉えられており、家族以外の人がそこまで真剣に考え伝えてくれたことは嬉しい。ありがとう。」と言われた。その時のニコッとされた笑顔が印象的であった。その後の指導内容はK くんの意向を考慮しつつ余裕のあるカリキュラムを組むようになり、授業中にゆっくりと話を聞き何度でも丁寧に説明をするなど工夫をした。心なしかK くんの笑顔を見ることも増えていった。本人にとっても良い方向に進んだんだと思う。
この出来事から障害者を持つ親がそれを認めることの難しさ、他人に言うことのハードルの高さを感じた。また世の中には「障害者に理解を」「少しの思いやりを持つことで〇〇」などのキャッチフレーズが多いが、まずは家族の中でそれを認めることの難しさ(家族以外の人に伝える難しさも)もひしひしと感じた出来事であった。僕は家庭教師といえどあくまでも他人。そんな僕に「障害」という言葉を使い赤裸々に語ってくれたことは驚いた。それと同時に自分が障害者の親だったらどう感じるだろう、どのような行動を取るだろうと自分ごととして捉えて考えるようになった。
この出来事を振り返るとまさに楊田先生の授業での思いが蘇りました。当時は授業を受ければ受けるほど障害者に関することを口に出すことが難しく話題に挙げることがタブーのような雰囲気があると気づきました。そして話題提供したり身近に障害者を抱えている人とのコミュニケーションをすること自体が憚られた記憶があります。
K くんの件では親としては触れて欲しくない気持ちもありつつ真剣に我が子のことを考えてくれる “同士” も求めていました。また積極的に外部に発言することでネガティブに働くこともあり、なかなか共有されず親だけの問題として内に閉じこもりやすいと聞きました。さらに “障害者だから” 何か特別なことを求めているわけではなく、周りの人に当たり前に話ができて共有できるそんな環境の優しさが一番重要であると気づきました。
授業を受けた当時は話題を出すこと自体に少しばかり違和感を覚えており私と障害者の間にギャップがあると勝手に感じていました。しかし時間が経ち自分なりの経験をしていく過程の中で、徐々に心理的な距離が縮まってきています。授業での体験が原点となり自らの経験によって考え方が醸成されていく過程を進んでいます。今後も多様な考え方に触れていく中で、当時の授業内容は「障害者」という話題に対して終わりなく考えていくきっかけになっていると思います。
ついつい長々と書いてしまいました。
中高ではいろいろな出来事や思い出がありましたが、このように共有できることは嬉しく思います。そのような原体験ができたことに感謝です。当時の記憶と経験を行き来する中で上手く表現できているか不安ですが、少しでもお役に立てれば幸いです。最後になりましたが、このような機会を提供いただきありがとうございました。他の方の振り返りもお待ちしています! Wくん
「一つかみの砂金」
ジョン・デューイの「1オンスの経験は1トンの理論にまさる」(『民主主義と教育』)との言葉を改めて思い出した。
冒頭に投げかけた「1つかみの砂金」とは何か。──勉強の訓練を自分に課し、やり遂げていったところに身に付く克己心や、人への思いやりといった人間の輝きこそ、砂金の輝きに他ならないのではないだろうか。
ご意見・ご感想があれば、是非form回答で聞かせてください。よろしくお願いします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
