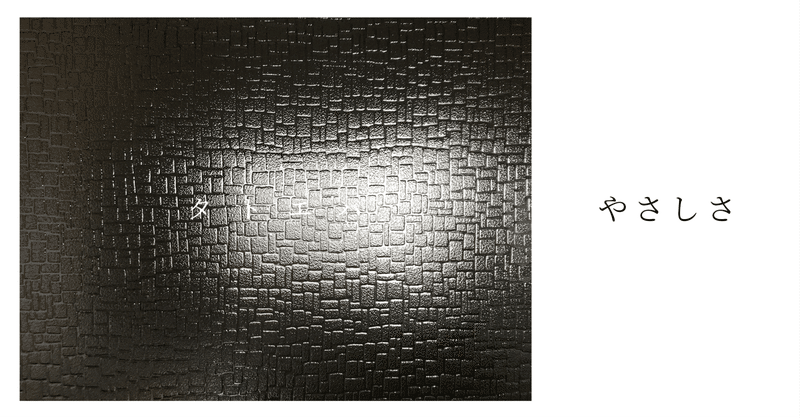
タトエバ6 やさしさ -ALSだった母と暮らして-
やさしさ 23年3月1日
21年の正月。母は落ちていた。ソファに収まっているばかりの自分に弱っていた。家事ができなくなり、正月のテレビ番組を眺めていることしかできず、傍から見て心が凹んでいるのが痛いように分かった。大袈裟に言えば、改めて希望が見当たらなくなっていたんじゃないか。だから話した。母と話す、その後続いていく包み隠さない言葉のやり取りがそこからはじまったと思う。内に内にどんどん小さくなっていくようないまを受け止めたうえで、そして、そこから外へひっくり返すような、心の選択を促すような話をしたはずだ。
明くる日、母はすぐ担当のケースワーカーへ電話をした。
週に1回のデイサービス利用が始まった。手探りで行こうと始めたものはすぐに週3日の利用に広がり、それはいまでも続いている。あづまの郷というデイサービスで出会ったスタッフの人たち。病気になってどんどんと手放すばかりになっていた母が、彼らに囲まれて、新しい関係を築いていく居場所を手に入れることになった。病気によってやってきた場所に、自分らしさをまた繰り広げられる可能性が表れてくれた。体が不自由になっていく、介助されることが大きくなっていく中で、それでも、母の考え方、姿勢、生きられてきた経験が言葉になって、若いスタッフの人たち、その多くはお母さんで子供を育てる真っ最中の彼女らに、求められそれに応えるようなやり取りが生まれていたということを、母がデイサービスから持ち帰ってくるたくさんの物語りに映し出すことができた。
いまはもうほとんど声を出して話すことはできない。おフロに入るのだって2~3人がかりで、誤嚥リスクを下げるために用意してくれるごはんをほんの少ししか食べなくなった。横になっていることが増えたけれど、それでもデイに通い続けている。繋がりがあるからだ。家族の中ではない外にできあがったそれを簡単に手放してはいけないという気持ちが母を支えている。放したくないという気持ちだと思う。見守られる母だけど、きっと彼女も見守っている。デイの人たちを見守り続けたいという思いがなくせない。
母はきっと、ぼくたち家族のためにもデイに通い続けてくれているのだ。
母はきちんとしている。背筋を伸ばして立ち、その視界で相手に向き合う。自分に対し他人に対しごまかすことがないきびしさをもっている人だ。ただそれは、彼女の優しさに繋がっていると思うようになった。だめな相手にそれではだめだという。だめな相手がだめなままで変わらなくてもそれを言い続ける。相手を評してきびしい言葉を投げかけながら、それでも相手をけっして遠ざけることがない。母にだめだしをされるような人ほど、母に近寄り離れていくことがない。母はみずからが寄り添っていくことはないが、そばにいるものを遠ざけることはない。むしろ、そばにいるというだけで相手のために自分が何をできるか考え行動にしようとする。
ぼくの場合、ひとを評して、その持っている世界を評して、それが碌でもないと思うと、簡単に手放してあきらめてしまう。反対に母は、きびしさとやさしさが相対しながら、でもくっついて同居しているように映る。そのために表れてくるのがやさしさなんだと気づいて、自分がもっていないものを考えるようになった。
ぼくが、母のために暮らしながら、病気を抱える母に対してやさしさとは真逆のひどい気持ちを自分に湧き上がらせたり、一緒に介護する父の出鱈目さやいい加減さを一々取り出して、彼に幻滅して見下げてしまうことで、家族というものを自らで壊してしまうような振る舞いをしていると、「やさしさ」という言葉、その意味が、いまこそ目の前に立ちはだかってくるように思えるのだ。
母は父をやさしいと言う。そして、母は父だめなところを指摘し続ける。それはどこまでも変わることがない。とにかく諦めないひとだ。だめなところが多い父だがたしかにやさしいひとだとは思う。足らないものを足らないままに、そのまま引き受けとめることがやさしさというものだろうか。不条理や不合理、不器用、不適当。ぼくらは不足していることが当然で、不足していないことなどあり得ない。だからこそ、足らないことを誤魔化さないで、切り捨てないで、引き受けることが僕たちにできる確かなことだと気づく。自分という不確かな存在を捉え、定かではない相手という存在を自らのことのように思うことができるときに、やさしさは表れてくるのかもしれない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
