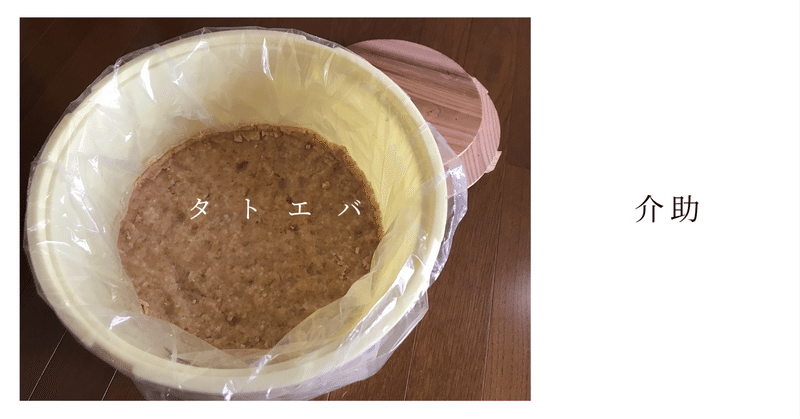
タトエバ5 介助 -ALSだった母と暮らして-
介助 23年 2月 1日
よおく見る。観察し、情報を掴まえようとしている。そして、人の動かない体を動かすために、触れ、返ってくる力を量り、体を抱えるその手応えから、情報を得ようとしている。言葉がはたらく範囲が狭まったときに、補間する媒体と手段の役割が大きくなってくる。非言語のコミュニケーションがクローズアップされ、その範疇が広がっていく。コミュニケーションという目的に対して、手段が制限されるときに、「見る」や「触る」の解像度がこれまで以上に高まっていく。「見る」は「観察する」ようになり、「触る」は「触れる」という意味に変わっていく。ひとつひとつが拡張されることがを求められている。これまで通りに見て、これまで通りに触るのでは全然に足らないという事実が、変化を促して行く。
よおく見る。という語感が当てはまる。「手の倫理」で述べられていた「触覚とは内部的にはいこむものである」という引用は実感になる。感覚を区別するのではなく、規定するのでもない。内部を目にするように見て、内部を探るように触れる。母の中に起きていることを掴まえようという目的に対して、表面に留まるのではなく内部には入り込むようようにしてはたらこうとする感覚が生まれてくると気づく。
20年12月に父母と3人で岳温泉に行っている。母の移動はそのときもう車いすだったけれど、ぼくの目の前に座ってひとりで御膳に向き合っていた。隣の父に振り向いて若々しく笑っていた。自らでごはんを食べることができていた。大好きなビールのグラスが目の前にあって、中身はもうだいぶなくなっていた。病気は確かにあって、それは着実に進んでいたけれど、写真を見るとその影はまだ写り込んでない。もちろん、いまも母は笑ってくれる。母らしい気持ちのいい笑い方をときどきしてくれる。でも、その間には失くなってしまったものがある。変化には順序があって、それはゆっくりとひとつひとつ手に入れていくものなのだけれど、毎日を生活し重ねるように続けていくことに、分かりやすい測点が打たれていくのではないといまだから分かる。
もう1度くらい、3人で温泉に行きたい。
「手の倫理」 伊藤亜紗
「ふれる」「ふれさせる」の間にはたらくのは信頼。人との接触は自分の外側にある不確実な何かを自分に取り込むことで、それを受け入れるための覚悟が必要になる。自分だけではどうにもできないものを受け入れよう、受け入れてしまおう、という心の動きがある。覚悟は、自分の内だけで済む安全を手放し、何がやってくるか分からないリスクを抱えさせるけれど、その反対に、自分が自分を超えて拡張していける、広がりを手に入れることにはたらいてくれるものだ。人と人との接触のコミュニケーションは、信頼の上にお互いに手に入れる、新しい世界への飛躍の手段になる。
信頼による拡張と対比して、安心ばかりに囚われ、不確実性を自分から遠ざけるようにすれば、可能性が生まれてくることはない。不確実性がなくなることはなく、完全な安心なんてことも有り得ない。そもそも、安心だと定義し設定するは自分自身の認識で、それこそ不確実性が溢れているのに、その根源には気づくことがない。安心という不確かで一義的なものの見方に、自分が、社会が埋め尽くされ、そして簡単に可能性を手放していくようなぼくたちのいまの姿があるから余計に、信頼という相手に委ねる姿勢にこそ、リスクを受け止めそれを上回る可能性が開かれてくるという捉え方の大切さに気づくことができる。
触覚という、距離ゼロどころか距離マイナスに入り込むことができる特性によって、関係性は、距離を置くことができずにその輪郭を曖昧にしてしまう。ぼくたちという輪郭はさわりふれることで途端に不確かさを増してしまう。しかし、それは可能性を開くということの裏返し。ぼくたちの存在は、自分たちが思っているほどに確実ではなく、定まった形があるのではないのかもしれない。触覚が、自分と相手という捉え方を超えて、認識を再構築させるような新たなコミュニケーションを作り出すかもしれない。
母の動かない体を扱おうとするとき、相手というものを丸ごと引き受けることと、自分というものが防ぎようもなくさらけ出されていることに気づく。立ち上がっているのは倫理だということが分かる。決して道徳で済むことなんかではない。
(23年2月11日書)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
