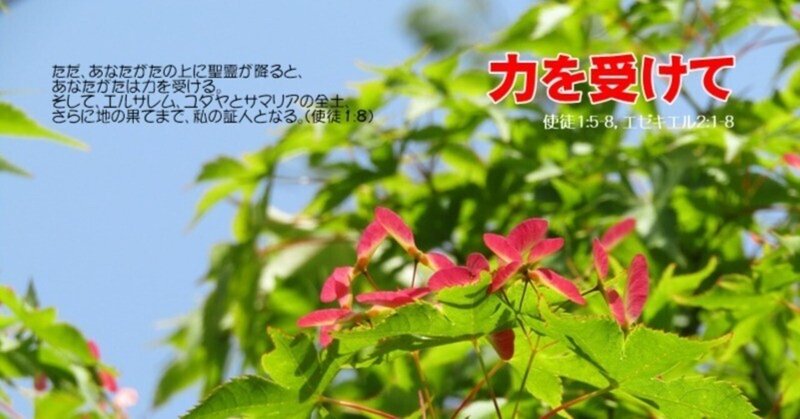
力を受けて (使徒1:5-8, エゼキエル2:1-8)
◆ペンテコステ?
教会の暦では、「ペンテコステ」礼拝となります。「ペンテコステ」とは何だ? 実は、キリスト教の三大祝祭の一つなのです。訝しく思われても仕方がないような、知名度です。「クリスマス」は早くから日本でもおなじみになりました。大正期でしょうか、激しいブームすらあったのだとか。もちろん、宗教的な意味合いではなかったのでしょうが、良かれ悪しかれ「クリスマス」は知られるようになりました。近年、「イースター」も商業路線に乗りましたし、映画などで一部の人にはかねてから知られていました。
しかし、ペンテコステの映画など、誰も知らないでしょうし、商売の材料にもなりません。それどころか、キリスト教会の中でも、あまりインパクトがない日ではないでしょうか。クリスマスは派手に宣伝もしますし、イースターも、信仰の中心という意味でも、また世間に対するアピールとしても、重要視されて然るべきです。が、ペンテコステはわざわざ宣伝もしませんし、教会内でも「祝会」のようなものは、まず催されません。
「ペンテコステ」とは、聖霊が降った日です。あるいは、教会が始まった日、とする見方もありますが、やはり昔ながらの「聖霊降臨」という出来事が、その本質を最もよく伝えるものだと言えるでしょう。
イエスの十字架と復活は、四福音書すべてが描いています。クリスマスの物語は福音書二つが扱いますが、手紙の中にも、イエスの受肉の考え方は浸透していると考えられます。しかし、ペンテコステの出来事は、使徒言行録にあるだけで、ほかは漠然とした書き方しかされていません。
つまりは、ルカと称される一人の筆者のみが、この問題について描いている、と言ってよいかと思います。言ってみれば、聖書の中でもごくマイナーな、不思議な出来事であるわけです。但し、ヨハネ伝20章には、聖霊を受けるという場面が少し描かれていると見られています。
19:その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちは、ユダヤ人を恐れて、自分たちのいる家の戸にはみな鍵をかけていた。そこへ、イエスが来て真ん中に立ち、「あなたがたに平和があるように」と言われた。
20:そう言って、手と脇腹とをお見せになった。弟子たちは、主を見て喜んだ。
21:イエスは重ねて言われた。「あなたがたに平和があるように。父が私をお遣わしになったように、私もあなたがたを遣わす。」
22:そう言ってから、彼らに息を吹きかけて言われた。「聖霊を受けなさい。
23:誰の罪でも、あなたがたが赦せば、その罪は赦される。誰の罪でも、あなたがたが赦さなければ、赦されないまま残る。」
ヨハネ伝の筆者が、ルカ伝を知っていたかどうか、は定かではありません。もし知らなかったとすれば、教会の中に一般的に、「聖霊を受ける」ということに意味があるのだ、と確かに考えられていたのではないか、と推測されます。
「聖霊」は、聖書の中では「聖い・霊」と2語で表されます。1語で「霊」というときもあります。創世記でも、「初めに神は天と地を創造された。地は混沌として、闇が深淵の面にあり、神の霊が水の面を動いていた」(1:1-2)というように、神の霊が最初からあったとされています。
言葉というものは扱いが難しいものです。「霊」と日本語で訳されたとき、人々は何を感じるでしょうか。幽霊や霊現象かもしれません。心霊現象、と呼ぶこともあります。
◆霊現象ってあるの?
少しばかり、また回り道を致します。お許しください。私の身近なところでの話を、幾つかお話しします。
どこまで本当か、知りません。私も幼かったので、どこまで正しく覚えているか、分かりません。親戚に不幸が続いたので、誰か霊能者みたいな人に伺いを立てたのだそうです。すると、故郷の島を探してみよ、と言われたのだとか。先祖の墓が荒れているから、それを直せ、と。そんなもの、聞いたことがない。しかしもしやと訪ねてみると、果たして山の中に、それを見つけました。恐れを覚え、祀ったということでした。その後、不幸事は特に起こりませんでした。
田舎も田舎、そこにいた祖父の近くに、友人とでもいうのか、ある男性がいて、祖父はずいぶん頼りにしていたようです。この人も、何か強い力をもっている、というようなことを聞いたことがあります。これは全くの思い違いかもしれませんけれど。
親戚に、ずいぶんと高齢の女性がいました。離れたところに住んでおり、また本当に超高齢であったので、会いに来るというわけにはゆきませんでしたが、幼い私が可愛かったのか、手紙をくれていました。いくつのときだったか、私が物心ついたころ、新約聖書を送ってきました。同時に、何か神秘的な本もありました。今でいう、スピリチュアルな世界の本でした。私は聖書などには縁の無い環境にいましたが、挿絵のついたその聖書を開くと、不思議なことがいろいろ書いてあることが分かりました。
その頃、子ども向けの雑誌にも、さかんに「こわい話」が載っていました。UFOや心霊現象などは、子どもたちの関心の的でした。こっくりさんもありました。尤も、こっくりさんはずいぶん以前から知られていたそうですから、時代特有というわけではありませんでしたが、ネッシーや雪男など、神秘的な話題は、子どもたちを誘うのに格好の材料だったのだと思います。ツチノコなんていうのもありましたね。
特に心霊写真は、怖かった。本当に、写真の中に、人の顔のようなものが見えるし、どう見ても腕か多いとか、滝の中に浮いた人物が写っているとか、背筋が震えるようなものがありました。めいっぱい怖がりだった私は、そういうのを見ると夜眠れなくなるような気がしました。が、もちろんちゃんと寝ていました。
土曜日など、午後からでも、歩いていけるところに山がありました。小学生の時分でも、歩いてかなり高いところにまで登れます。その山の麓には、古墳群がありました。昔からたくさんあったようで、原形を残したようなものもありました。ある円墳は、直径は10メートルもなかったかと思いますが、石室の入口が開いていました。怖がりの私が覗いてみると、白い目のように見える光ったものがあり、震えました。早速そのことを、学級新聞で発表したのですが、誰もバカにする人はいませんでした。
他愛もないことです。そんな時代がありました。
◆偽物と精神病
昔のことですが、霊能者が、まことしやかにテレビ番組でも紹介され、センセーショナルに宣伝されていたことがあり、世の中は「まさか」とは思いながらも、半信半疑くらいではなかっただろうかと思います。
霊能力者がテレビで、何かを見事に言い当てる様子も放送されていました。それを見ると、母は呟いていたものです。「霊能力があるのなら、未解決事件の犯人を見つけてやればいいのに。」
オウム真理教でも、幸福の科学でも、一種の霊能力をウリにしていました。並の人間には見えないものが見え、聞こえない声が聞こえるのだそうです。そして、どこかからお告げがあったともたらすというのは、少なからぬ宗教に現れる逸話ですが、特にそれが超能力的に操るようなものである場合は、確かにその能力を、犯人が捕まらない事件のために使ってくれたら、世の中はずいぶんと変わるのではないかと思われます。
そうした特殊な能力を用いて事件を捜査と解決へと導くことを「サイキック捜査」と呼ぶことがあるそうです。外国にはそういうのがある、という話も聞かれますが、多くの噂は、例のスピリチュアルな世界の話題であるような気もします。
それはそれとして、自分には超能力がある、ということを、金集めや、自己顕示欲を満たすために用いている例が、世の中にはたくさんあるように見えてなりません。相当なペテン師ですが、そうしたものに引き寄せられる人が、いくらかでもいるというのは、怖いことかもしれません。そこまでいかなくても、独裁者や社会の多数派に靡いていくという点では、私たちの誰もが、またこの国や社会のどれもが、危険水域の中にいることには違いない、とは思うのですが。
そんなに欲まみれの目的からではない場合もありました。日本には昔から、「狐憑き」という呼び方で、霊が取り憑いたという話が無数にありました。一種の精神的な病気ではないか、とも見られていますが、こればかりは科学がそのすべてを掴んでいる、とは言えない状態であるようです。それでも、中井久夫先生のように、故郷にあった霊的なものにまつわる現象を丁寧に拾い上げた心理学者もいます。それをもちろん先生は心理学として活かそうとしたわけですが、確かにある意味で、真面目に取り上げて考察するだけの価値はあろうかというふうにも思えます。
面白いことに、イエスの場合、こうした現象がちゃんと記録されているのであって、大抵は「悪霊」という呼び方で対処されています。精神的な病気でも、その原因が分からず、治療法がないとき、昔の人は、悪霊だの鬼だのといったもののせいにすることがよくありました。そして、加持祈祷を繰り返すしかない、というのは、平安時代を描いたテレビドラマでも、よく描かれています。
そん非科学的な、と言うべきではありません。ほんの百年前、五十年前でも、い判明している病気の幾つかは、殆どそれらと同じように見られていたのです。また、いまなお原因や治療法が分かっていない病気も沢山あります。しかしその患者に対して何らかの対処をしなければならない、という現場でやっていることは、ある意味で、悪霊に対して昔の人が行ってきたような構図に近いのかもしれません。
これは余談ですが、カトリックを舞台に展開したあの映画「エクソシスト」というものは、本当にはどの程度に、まだあったのでしょうか。あるいは、いまも、あるのでしょうか。
◆聖書の霊的体験
聖書の話題が出たところで、ここで聖書に立ち帰り、聖書の中で、たとえばどのようなこうした霊現象に触れられていたか、思いつくままに眺めてみようと思います。
憑依とでも言うのか、顕著な例として、イスラエルの初代王であるサウルの件が、まず思い出されます。複数回ありますが、ここではサムエル記上10章から紹介します。
9:サウルがサムエルと別れて帰途に着いたとき、神はサウルの心を別人のようにされた。こうしてこれらのしるしはすべてその日に起こった。
10:彼らがギブアにやって来ると、預言者の一団に出会った。すると神の霊が彼に激しく降り、サウルは彼らのただ中で預言者のようになった。
11:以前からサウルを知っていた者は皆、彼が預言者たちと一緒になって預言しているのを見て、言い合った。「キシュの息子は一体どうしたのだ。サウルもこの預言者たちの仲間なのか。」
12:そこにいた一人が答えた。「この人たちの父は誰なのか。」こうして、「サウルもこの預言者たちの仲間なのか」はことわざになった。
サウルは、音楽を奏でるダビデにいきなり槍を投げるなど、不可解な行動もありました。そもそもこのダビデが琴を弾いていたというのも、精神的な不安定なサウルの心を鎮めるためではないか、とも考えられます。偏見を加える意図がないことをお断りしておきますが、サウルには何らかの精神疾患があった、という理解もよくなされています。しかし、そうあっさりと決めつけてよいかどうか、それもまた問題です。
イエスにもまた、「悪霊を追い出す」などの表現で、人々の精神的な問題を解決してゆくことが非常に多くありました。病気のメカニズムがよく分からないとき、それを霊のせいにして説明する、というのは、周囲の者の安心のために必要な知恵であったかもしれません。それにしても、イエスはやはり解決し、癒やしを与えていったのです。
預言者たちの言葉の中にも、精神的な問題を見出すことは可能です。有名なのは、エゼキエルについて、ヤスパースをはじめとして、精神疾患がある、と見られていることです。
また、ダニエル書には、登場人物の中に、錯乱した人間の姿が明らかにされていますが、ダニエルの見た幻にしても、かなり異様な世界が記されています。幻想的なものが必ずしも病的であるのではないはずですから、どこか霊的な現象として構えて見つめることがあってもよいのではないか、と思うのです。
◆風と教会
使徒言行録の初めの第1章で、イエスが召天する場面があります。
6:さて、使徒たちは集まっていたとき、「主よ、イスラエルのために国を建て直してくださるのは、この時ですか」と尋ねた。
7:イエスは言われた。「父がご自分の権威をもってお定めになった時や時期は、あなたがたの知るところではない。
8:ただ、あなたがたの上に聖霊が降ると、あなたがたは力を受ける。そして、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで、私の証人となる。」
9:こう話し終わると、イエスは彼らが見ている前で天に上げられ、雲に覆われて見えなくなった。
聖霊が降ることの約束を告げ、イエスはこの地上から姿を隠しました。聖霊を受けると、あなたがたは力を受ける。この約束は、私たちの許へも届けられているはずです。しかし、「聖霊が降る」というのは、どういうことでしょうか。それにより私たちは「力を受ける」というのですが、どのようにでしょうか。実感が、得られるのでしょうか。
使徒言行録で、実際に聖霊が降った場面が、このペンテコステ礼拝ではよく開かれます。それでよいと思うのですが、今回は敢えてそれを外しました。その場面でない場所から、その出来事を見つめてみよう、と考えたのです。ただ、何らかの形で使徒言行録の2章は、ぜひお読みください。そこには、聖霊が降った現象の描写と、それを目撃した一般人のために、ペトロが立ち上がって説明の演説をするという様子が記されています。
このペトロの説明は、いかにもできすぎです。ペトロとてもそのとき、初めて聖霊を受けたのです。霊的な体験をしたその場面で、この霊現象の意味はこれこれである、と堂々と演説するのは、出来事としては、私たちには速やかには受け容れがたいものがあります。
1:五旬祭の日が来て、皆が同じ場所に集まっていると、
2:突然、激しい風が吹いて来るような音が天から起こり、彼らが座っていた家中に響いた。
これは、その使徒言行録2章の始まりです。ここに、「激しい風が吹いて来るような音」があったと書かれています。これはただの比喩として読むにはもったいない部分です。というのは、「風」と「霊」とは、深い関わりがあるからです。ユダヤ文化では、同じ一つの語が、「風」と「霊」とを表すことができるようになっています。あるいはまた「息」とも訳す場合があります。それは文脈によるのであり、聖書では各部分で、それぞれ訳し分けられています。しかし中にはその訳が相応しいのかどうか、考慮の余地がある場面もあります。
もちろん、この音のぬしは風でよいのですが、このとき霊が降った、というのは、その風のイメージに重なるものとして受け止めたいところです
いきものがかりの「風が吹いている」は、2012年ロンドンオリンピックのNHK放送のテーマソングに用いられました。制作段階では、「時代」という題でも考えられていたそうです。歌い出しが「時代はいま変わって行く」というように、新しい時代を希望する歌となっているためです。
「新しい風が吹く」、こうした言い回しを、私たちは使うことがあります。「風穴を開ける」という表現もあります。同じメンバーで旧態依然として活動している組織に、新しいものが入ってきて、淀んでいた空気が一変し、新たに生き返るような様を伝えます。
新しい教会に加わったとき、そのように言われたことがあります。せっかく皆さんが保ってきた中に、飛び込んできてしまって……というような気持ちがどこかにある私に向けて、新しい風が必要なのよ、と言われたわけです。いまのままでいい、これまでやってきたのだから、そんなのんびりしたムードに、新しい風を入れる。そのために、若い人の存在は必要ですし、外からの人材も貢献します。それらを排除しているようだと、もはや新陳代謝がなく、死を迎えるだけの組織となってしまうでしょう。
しかし、表向きはにこにこと「新しい風」を歓迎するような顔をしておきながら、本音では風を通してほしくないと思っているところも、あるかもしれません。本音は、いままでと同じように変わりなく、安定した一定の権威の下で、同じようにしていたいわけです。
だから、そんなときには、聖書の言葉が新しい風となるでしょう。「あなたがたの上に聖霊が降ると、あなたがたは力を受ける」のです。
◆エゼキエルの体験
先ほど、エゼキエルの体験の様子は、精神的に何かを抱えた人間の考えを示しているかもしれない、という点に触れました。幻想的な風景には、少しばかりついていけない側面があるのは事実です。しかし、そうした幻でなくても、エゼキエル書には「霊」に関して、少し考えさせる箇所があります。ふだん見落としがちだと思うので、今日はそこに光を当てて味わうことにしました。
それは、エゼキエルが初めて預言書の使命を受けたときのことです。イスラエルの民が、神に逆らっている。そこへ言って神の言葉を語れ、と命じました。エゼキエル書の2章の最初のところだけを、いま改めて取り上げます。
1:主は私に言われた。「人の子よ、自分の足で立ちなさい。私はあなたに語ろう。」
2:主が語られたとき、霊が私の中に入り、私を自分の足で立たせた。私は、語りかける者に耳を傾けた。
何かお気づきになった方もいるでしょう。私も、長年なんとなしに読み飛ばしていたのですが、先日ここを開いて祈りのひとときを過ごしていたとき、フッと気づかされたのです。主は私に命じました。「自分の足で立ちなさい」と言ったのですね。そして主が語ったら、「霊が私の中に入り、私を自分の足で立たせた」というのです。確かに「自分の足で」とは書いてあります。けれども、その主語は「霊」であり、「霊が私を立たせた」となっています。非常に不自然なことではありませんか。「自分の足で」立つように命じられた私ですが、実は「霊が立たせた」と言っているのですから。
「聖霊」とは神のひとつの姿です。いろいろややこしい議論が関わる可能性がありますが、いまはさしあたり、霊の姿をとった神、という程度で流しておきます。その霊を受けた、というのが、このペンテコステの出来事でした。私は、このエゼキエル書の不自然な書き方が、「聖霊を受ける」ということと、つながって見えてきたのです。
倒れたとき、立ち上がれないとき、たとえ神に、自分の足で立て、などと言われても、私は立てるはずがありません。そうですよね。でも、私が自分で立ち上がるのではなく、聖霊が私を立たせる、というのであれば、ありがたく感じます。聖霊が私に注がれたからこそ、それでこそ初めて、私は立ち上がることができるはずなのです。
エゼキエル書で、このようにして霊によって立ち上がることができた預言者は、そこから遣わされて行きます。もう細かく見ていく暇はありませんが、神に逆らったイスラエルの民のところに、派遣されるのです。神に逆らう反逆の家というのは、「神を知らない」という説明が付せられてはいません。神を知っているのに、反逆するのです。イスラエルの文化の中にありますから、神を知っている、と自分では考えています。自分では、たぶん神に従っているのだ、と思い込んでいるのです。それでも、実は反逆していることになるのだ、と神が実態を暴いているわけです。
エゼキエルは、主の言葉をそこに運ぶことになります。でも、エゼキエルは、人々から排除されることでしょう。思い込みから自分が正しいとして集まった者たち、権力をもった組織に対して、預言者が独り立ち向かっても、相手にされないのです。しかし神は、そこで語れ、とエゼキエルに迫ります。神の言葉を語れ、と命じます。それは、霊により立ち上がらされたからこそ可能になる出来事です。
これが、力を受けるということなのでしょう。聖霊を受けた者は、力を受けます。そうして、キリストの証人になります。キリストは生きている、救い主である、と叫ぶようになります。主が生きていること、この主こそが主人であり、人間はその僕なのだ、ということを宣言します。その伝える先は、いつしか自分が主人となっている組織や権力です。神を脇役に追いやっている者たちです。神をいつしか道具にしてしまっている者たちです。
こうした勇気の必要なことを、あなたもすることができます。あなたには聖霊が注がれているからです。あなたは神の言葉が語られる説教を心の奥底にまで聞き入れて、力を得るでしょう。するとあなたは生かされます。生き生きとされたあなたは、勇気が与えられ、ただ神の僕として、神の言葉を告げることが、できるようになります。
霊があなたに注がれたからです。霊は、息でもあります。神の息が、あなたの中に入るからです。あなたに、命が注がれたからなのです。
◆聖霊はまた来る
ペンテコステの出来事は、二千年前に起こった歴史の一コマに過ぎないのではありません。これからも起こります。いまここでも、起こり得ることです。それを信じることが、またひとつの大きな強い信仰ということです。
どうして信じることができるのでしょう。それは、イエスが予告したからです。イエスの予告が、かつて文書に記録されただけで終わりなのではなく、いまもこの聖書の中から、ここに響いてきています。それが聞こえますか。私は非力ではありますが、私を通して、聖書の中から語りかける神の声が響くように、と願っています。私には何の才覚もありませんが、私という存在を共鳴板のようにして、神の言葉が響いてくる、そういう道具でありたい、と祈っています。
いま、私たちは祈ります。イエスに祈ります。祈りの中で、イエスが現れます。神の国を建て直してくださるのは、この時ですか。神に問い、祈ります。いやいや、イエスは否みます。それはおまえの知るところではないのだよ。それよりも、こんなことがあるのだよ。聖霊が降るよ。おまえは力を受けるよ。そうして、イエス・キリストの証人となるのだよ。おまえのいるその場所でもできるよ。外へ出て行ってもできるよ。いやいや、遙か遠くに出て行って伝えることもできるだろうよ。
この後、イエスは召天します。天に、姿を消します。一旦、その姿が見えなくなります。私たちに聖霊という形で力を与えた事件の後、イエスの姿は、また見えなくなります。祈りの中で、確かにイエスを見ます。そのイエスが、ふとまた見えなくなることがあるかもしれません。たとえそうなっても、それでも、私たちの心は熱くなります。魂が熱くなります。それは、確かに聖霊がいまの時代も、ここにでも、来てくださった、という証拠です。あなたが自分の力では立ち上がれなくても、立ち上がる奇蹟が、起きようとしています。聖霊が、それをしてくださるのです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
