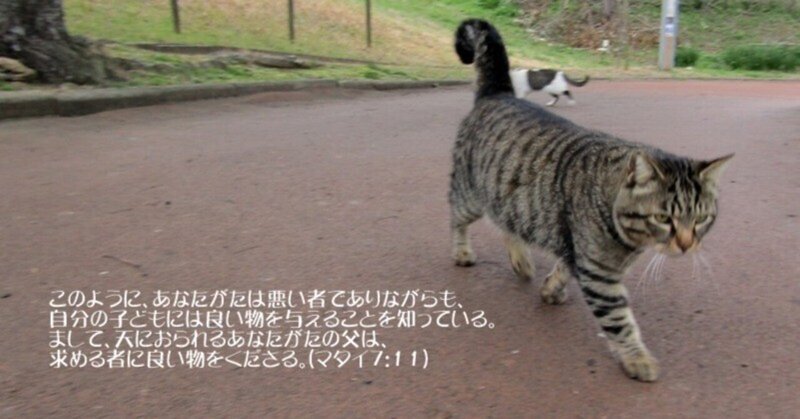
餅踏み
福岡には「餅踏み」という行事がある。1歳の誕生祝いのときに、赤ちゃんに餅を踏ませるのだ。地方によっては、餅を背負わせるというところもあるらしい。初めて誕生日を迎えるということは、古には当たり前のことと見なされることはなかったであろう。その間に命を落とすということが、しばしばあったからこそ、無事に一年間を生きたということをお祝いしよう、ということなのではないかと推測する。
餅は時に「一升」の米を使うという。もちろん「一生」と掛けているのである。九州では、子に草鞋を履かせ、餅を踏ませる。大地を踏みしめて歩むという願いをこめてのことである。
こうした習慣は、神事に基づく場合もあるようだが、さしあたり餅踏みそのものには宗教色はない。神社に赴くこともないし、祝詞を上げることもない。ただ、その子の周りにいくつかの物品を並べておいて、真っ先にどれに向かい、何を手に取るかによって、将来を占うというイベントが直後に待っている。
私は、やかんを取ったらしい。いったい、何を意味するのか分からないが、いまなおコーヒーを毎日飲んでいる。
今は、物品でなく、様々なジャンルを書いたカードが置かれることが多い。そもそもこの餅や草鞋も、業者がセットにして販売しているわけで、カードがそこに同梱されているわけである。何事も、至れり尽くせりの商売サービスである。
当然、ここに目をつけたのが、餅の業者。正月の餅も、昔ほどには食べられていないし、他の時期には餅の需要は限られている。和菓子としての餅は用途があるが、いわゆる「餅」として捌けるには限りがある。そこへ、1歳のお誕生となると、少子化とはいえ、年中いつでも需要があることになり、宣伝如何によっては、地域で確実に売れるものと思われる。そしてどうせなら、美味しい餅がいい。専門業者の技術で、餅の質がよい、となると、大きな餅を分けて食べることにも、幸福感が伴うことだろう。
こういう小さな子どもの笑顔は、親の笑顔がつくる時間空間によって育まれたものであろう。ストレスからしかめっ面ばかりであるとか、子どもに辛くあたるとかいうような環境で育てられていたら、笑顔を覚えることが難しいかもしれない。
子どもの虐待が報道される。比較的近いところの道の脇にも、その事件現場があって、通る度に胸が痛む。もちろん今どきの親がみな、あのようなことをしているわけではない。だが、子育てが苦しいという悩みを抱えている親、とくに母親が苦境に立たされている場合は、水面下に多々あると見たほうがよいのではないか。
大家族で誰かが面倒をみる、子育てを分担する時間がある、そういう時代とは異なる環境がある。親しい友人や近所の人が助けてくれる、という機会があれば助かるであろうが、ひとを頼るということのしにくい雰囲気もあるのだろう。誰かが意図的に追い詰めているわけではないのに、追い詰められ感覚が襲ってくるのかもしれない。
行政が悪い、と言うのは簡単だが、保健所や福祉業務を、事件の度に非難するのも、なんだか不条理であるような気がしてならない。
子どもは笑顔がいい。成長すると、無理に笑顔を演じることもあるから注意が必要だが、幼い子の笑顔は、大人たちをも幸せにしてくれる。政治を担う方々にも、いっそう尽力して戴きたいが、市民の誰もが、それに関与しているという自覚をしていきたい。電車の中で泣く子に対する「睨み」ひとつが、親を追い詰め、子どもの命を蝕んでゆく、ということについては、市民一人ひとりが、責を負っているというように考えたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
