
絶望の裁判所
上の画像は瀬木比呂志氏による『絶望の裁判所』の帯文である。「この門をくぐるものは一切の希望を捨てよ」。この門とはすなわち地獄への入口のことで、ダンテ『神曲』地獄篇に登場する名句だ。裁判所とは地獄なのか・・・。
日本の裁判所がどのような構造的な問題を抱えているか、これから筆者が愛読する瀬木比呂志氏の動画ナビゲーションに沿って考察しながら、同時に何故トンデモ判決が多発するのかを考えてゆきたい。
先に私の結論を申し上げておく。瀬木氏は裁判所の建前/内実の二重構造を指摘しているが、私は更にその奥に他国の関与が介在する3重構造だと見ている。伊藤詩織氏の一連の訴訟案件には裁判所の「組織的」な関与があったか、または少なくとも「忖度」が存在したはずだ。そしてそれは司法の独立性という問題を超えて「主権侵害」の疑いが濃厚な事案だ。
瀬木比呂志氏の略歴
瀬木氏は、東京大学法学部を卒業されたあと、1979年に修習を終了し東京地裁に判事補として就任。その後 アメリカ留学を経て 最高裁判所事務総局民事局局付(トップエリート)、 最高裁判所調査官などを歴任。裁判所という閉鎖的な環境により深刻な鬱に悩まされて2012年に裁判官を依願退官、明大法科大学院専任教授となる。2015年、著書『ニッポンの裁判』により城山三郎賞を受賞した。その他、著書多数。
告発の内容
瀬木氏のFCCJでの会見は自著『絶望の裁判所』上梓(2014年)直後のものだ。会見では著書『絶望の裁判所』から主要な部分を抜き出して紹介している。筆者は動画から更に要点を以下にピックアップした。
<前編>
<ポイントのピックアップ>
14:25~ 最高裁長官、事務総長、そしてその意を受けた事務総局は裁判官の人事を一手に握ることにより、容易に裁判官の支配・統制を行うことが可能になっています。こうした人事について怖ろしいのは、裁判所当局による報復が何を根拠として行われるか、いつ行われるかも分からないということです。そのため裁判官たちはともかく最高裁や事務総局の気に入らない判決を書かないようにという事から、ヒラメのようにそちらの方向ばかりを伺いながら裁判をするようになり、結論の適正さ、当事者の権利は二の次になりがちです。
22:08~ また、このような事態を生む裁判官の精神構造の病理については、P174~P192で詳しく触れています。
*この部分は筆者が手元の著書より引用で補完する。要するにサイコパスということらしい。
(2)エゴイズム、自己中心性、他者の不在、共感と想像力の欠如
裁判官の、むき出しの、無邪気ともいえるほどのエゴイズム、天動説的な自己中心性には、本当に驚かされることが多かった。他者の存在というものが、全くみえていないのである。
自分だけがかわいく、自分にはいいことがあって当然、そして、いいことが自分を差し置いてほかの人にあることは許せない、というタイプが非常に多い。(P176より)
25:55~ その(息苦しさの)原因の1つはおそらく社会の二重構造、二重規範にあるのではないかと思います。つまり法などの明確な規範の内側に、それぞれの部分社会特有の見えない規範があるのです。人々はどちらかといえばその見えない規範に縛られています。日本の裁判官の社会はインビジブル(不可視の)ルールが極めて強固であり、またそれに触れた場合の制裁が極めて過酷な社会なのです。
27:30~ 日本国憲法76条には、すべて裁判官はその良心に従い、独立してその職権を行い、この憲法および法律にのみ拘束されると記載されています。しかし日本の裁判官の実態はすべて裁判官は最高裁と事務総局に従属してその職権を行い、もっぱら組織の掟とガイドラインによって拘束されるといったものになっています。憲法の先の条文は日本国憲法ほかの数多くの輝かしい条文同様、愚弄され踏みにじられているといえます。
28:50~ 日本の裁判官制度が根本的に改革されなければ、日本の裁判はほんとうの意味において良くはならないでしょう。また、現在の裁判所はもはや自浄能力を欠いており、法曹一元制度による根本的な改革が必要かと考えます。
29:50~ まとめの言葉として以下のように述べておきたいと思います。本書は司法という狭い世界ではなく日本社会全体を批判する書物です。バブル経済崩壊以降の日本社会の行き詰まりには私がこの書物で分析したような問題に起因する部分が大きいのではないでしょうか。日本の裁判官組織は→(後編に続く)
<後編>
<ポイントのピックアップ>
0:00~ (前編からの続き)エリートの非常に閉ざされた官僚集団であるために、そのような問題が集約、凝縮されて表れていると考えます。その意味で本書で私が提起した問題には、かなり大きな普遍性があるのではないかと考えています。
7:25~ 日本の裁判システムはある意味で非常に効率的であり機能的です。ただ、Due Processの考え方、法の支配の考え方が浸透しているかといえば、そうではないということです。
18:40~ 田中幸太朗長官が砂川事件に関する情報をアメリカ大使・公使にリークしていた事件を思い出しますと、たしかに日本の司法は裏側ではかなり不透明なことをしている場合があり得る、そのことはこの私の書物の中でも述べているところです。
*砂川事件は非常に重要なリマークであり、後述するので覚えておいて頂きたい。
21:05~ 一般的に裁判官の能力は、だんだん低くなりつつあるとはいえ、これまではかなり高かったのですが、ドイツのような根本的な改革は全く行われず、そのために戦前の禍根を引き継いでいると思います。
23:32~ 裁判官の能力について一言補っておきます。たしかに日本の裁判官の能力は過去においてはかなり高かったといえるのですが、私がこの本に書いているとおり、2000年代以降、裁判所の機構の問題、また裁判官たちの個人的な事情からその能力はかなり落ちてきており、これは日本の司法の大きな問題です。なぜなら日本の司法は、裁判官の能力が高いことを前提にし、彼らに非常に大きな権限を与えているからです。
28:59~ 一つ補っておきます。これは日本の社会全般について皆さんも感じておられることではないかと思いますが、一種の形式主義というものがあり、裁判所もまたこの形式主義に捕らわれている部分があります。つまり表に出る部分は綺麗に取り繕うのですが、裏側では非常に不透明であるという、こういうダブルスタンダード(二重性)の問題が日本社会の大きな問題であり、司法においてそれは非常に顕著に顕れています。
34:04~ 一般的に言えば日本ではまだ弁護士も少ない、裁判官も少ないということは言えるであろうと思います。しかし一方、ここ10年ほど裁判所に提起される全訴訟事件以外の事件も含めた全事件は非常に減っています。私が言っているのは執行事件、破産事件等を含むということです。一方、訴訟事件だけについても、ここ3年減少しており増えてはいません。このあたりには現在の司法に対する人々の失望が感じられます。
私が言えることはやはり日本の司法全体をリフォームする必要がある。そうしなければ本当に提起されるべき訴訟も人々は起こさない、なぜなら人々は司法については良くは知らないが、そこでは自分の思いがなかなか理解してもらえないとは思っているからです。そのような人々の気持ちをまずは変えること、それから司法全体を改善し、弁護士が増えるのであれば裁判官も増やすことが必要だと思います。
*質問のパートでは、軍属の問題だけは良い質問だが、構造的な問題を指摘している話者に対して、徴用工や小沢一郎など個別の事件について問うしか能のない無能な記者たち。
司法制度改革が意味するもの
瀬木氏は司法全体のリフォームの必要性を力説していた。それでは1999年に日本でスタートした「司法制度改革」は、そのような要望に応えるものだったのだろうか。
2008年に出版の『司法の崩壊』は河井克行氏の著書である。河井氏といえば法務副大臣を経験し、また米副大統領時代のバイデンとの間で拗れた日米関係修復のために渡米して駆けずり回って修復のお膳立てをした立役者である(この件については山口敬之著『暗闘』に詳しい)。後に刑事被告となることなどこの時の河井氏は想像だにしていなかったに違いない。
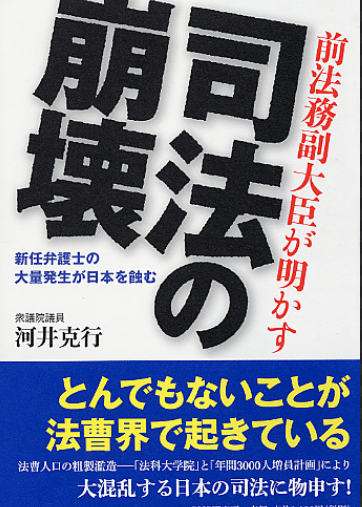
本書では、ロースクールを真似たはいいが利権化するのみで機能しない法科大学院のことや、弁護士の大量増員が日本社会を混乱に陥れ、日本が訴訟地獄と化すことが既に2008年時点で予言されていた。弁護士が余ればとうぜん食えない弁護士が大量発生する。するとどうなるか。積極的にニーズを作り出すことに走り、離婚しなくて済むケースを離婚訴訟まで持って行ったり、あるいは恫喝訴訟をそそのかす悪徳弁護士も出現するだろう。トラブルが増えれば増えるほど弁護士の懐は潤う。
司法制度改革の中には、裁判員制度のように(不十分ではあっても)一歩前進といえる改革も含まれていた。ただし裁判員制度新設の裏側には刑事裁判官の権力強化が伏在していたし、改革が眼目として掲げた「国民にとって身近な司法」とは即ち、アメリカ並みの訴訟社会の到来を意味する。「法的需要の拡大」とは、これまで皆が丁寧に話し合い、問題解決を図ろうとしていた過程をすっとばして、「裁判沙汰」に持ってゆくことであり、議論も交渉もどちらの技術も持たないバカが「訴えてやる!」と息巻くことである。
ではなぜ、法曹界はこのような日本の風土に合わない、むしろ改悪といえるようなリフォームをすすめたのか。長年の謎は関岡英之著『拒否できない日本』を読むことで完全にクリアになる。クリアになったはいいが代わりにゾッとする。
年次改革要望書について
2004年出版の『拒否できない日本』には、おそろしい事が書いてある。
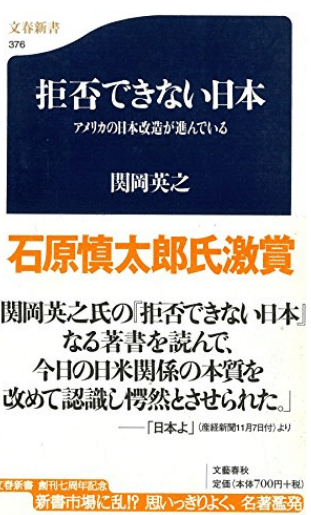
なんと「司法制度改革」はアメリカが定期的に日本に突きつけてくる「年次改革要望書」に盛り込まれていたというのだ!年次改革要望書は1993年の宮沢-クリントン会談が嚆矢で翌年の1994年に第1回要望書が提出されて以来、「年次」の名のとおり毎年、次々と新たな要望がアメリカから出されている。形式的には相互に要望を交換するという建前になっているが、実態はGHQの命令そのものである。
過去に米国側からの要望が施策として実現した例としては、建築基準法の改正や法科大学院の設置、著作権の保護期間の延長や著作権の強化、裁判員制度をはじめとする司法制度改革、独占禁止法の強化と運用の厳密化、労働者派遣法改正(労働者派遣事業の規制緩和)、郵政民営化等がある。
関岡氏によればアメリカの究極の目的は司法制度をアメリカ流に統一し、日本の司法をアメリカ流に改良すること(日本は英米法ではなく大陸法なのでそもそもコンセプトが違うので無理な注文だが)で、さもなくば国際社会で締め出されるように事を運ぶこと。それに伴い日本の司法市場に参入することだという。更にはアメリカがそうであるように「行政権力」よりも「司法権力」が優位に立つよう日本社会を改良すること。司法を通じて更に日本をコントロールしようというわけだ。司法が乗っ取られた時点ですでに主権国家としては終わっているのだが。
(データは'97年のものと古いが)日本の弁護士の人口は約1.6万人、翻ってアメリカでは約90.7万人と総人口比においてもアメリカは比べものにならないほど多い。規格統一という地ならしをした上でアメリカの余剰弁護士に日本マーケットが開放されれば、彼らは大喜びだ。やがて日本でも契約も裁判は英語で行われ、NYの州法が適用されるディストピアが訪れるのかもしれない。鈴木仁志著『司法占領』というSF小説には、アメリカのローファームに支配された日本のビジネス社会の近未来像が描かれているらしい。
「年次改革要望書」が届くと、そこに項目ごとに綿密に記載された改善要求(という名の命令)は各担当省庁に振り分けられ、官僚たちは目的の達成のために一斉に知恵を絞るという。
思い出してみよう。日本の首都上空の制空権はアメリカが持っているのだ。羽田に着陸するのになぜ大きく千葉上空を回り込まねばならないのか。それは日本の国土であっても日本が立ち入れない空域があるからだ。もちろん皇居の上空も例外ではない。
まとめ
日本の司法制度が戦前の悪癖を踏襲しているとしても、99年からの「司法制度改革」は日本のリーガル市場を当て込むアメリカの野望が介在したものであり、日本人にとって効果的に機能するとは到底言い難いしろものだ。2021年現在、事態は関岡氏が2004年に、河井氏が2008年に予測したとおり、良くない方向に進んでいる。
自浄能力を欠いた古くからの日本の官僚組織の体質に、「改革要望」の形をとった圧力が上乗せされ、裁判官個人の属人的能力の低下と相俟ってトンデモ判決が多発する目下の状況が現出しているものと見られる。個別の裁判に見る堕落ぶりは、裁判所を含めた日本の司法全体の腐敗の一片に違いなく、問題の根幹には「統治と支配」の問題が伏在している。「統治と支配」とは日本政府のことではなく、敗戦後の占領統治以来続いており80年代には日米構造協議として、90年代からは「年次改革要望書」として顕現する付加・加速された内政干渉を示す。
昭和32年の砂川事件とは、在日米軍基地に立ち入った日本人7名が、日米安保条約に基く行政協定(現在の地位協定)違反で起訴された事件。その後、裁判は在日米軍の存在そのものが日本国憲法違反かどうか問うものとなった。東京地裁は昭和34年、違憲判決(つまり立ち入った7名は無罪)を出したが、最終的に瀬木氏が言及した最高裁(田中耕太郎長官)は、「日米安保のように高度な政治性をもつ条約については、一見してきわめて明白に違憲無効と認められない限り、その内容について違憲かどうかの法的判断を下すことはできない(統治行為論)」という奇妙キテレツな理屈をひり出して原判決を破棄し地裁に差し戻した。後にこの判決はジョン・B・ハワード国務長官特別補佐官による指南があったことが判明している。
話を戻すと、構造的な問題を抱えた裁判所では将来を嘱望されるエリートほどその輝かしいキャリアとは裏腹に国民の権利を守らない保身の判決を出しがちということになる。悪徳弁護士が増える一方で、判事の属人的な資質はといえば落ちる一方、あとは日本のリーガル市場がハゲタカの餌食になるのを待つばかりか。
今の日本は伝統的な対米従属の延長戦と半島からのイヤガラセと大陸からのシャープパワー攻撃が加わり、挟撃される日本がとれる戦略は限られる複雑で困難な状況だ。
法曹界は西の方向を向いている。それはほぼ間違いない。では裁判所にとって伊藤詩織案件とは何なのか。裁判官にとっては、単にアメリカ発祥の#MeTooムーブメントの脅威みならず、刑法改正の動きだけにも留まらず、背後にアメリカが見え隠れする危険物扱いだったのだろう。直截的な介入がなかったとしても上司または ”宗主国” への「忖度」は確実に存在する。地裁の鈴木昭洋裁判長はバカではない。しかし伊藤山口裁判の一審判決文はバカにしか書けないシロモノだった。鈴木裁判長しかり、イラスト+RT裁判の小田正二裁判長しかり、どちらも実質的な審理を放棄しておざなりの判決に逃げたのは、タッチしたくない危険物扱いだったからであり、ヘタに判断すると出世にかかわると判断したのだと推測される。だが、その度に当事者の誠心誠意の陳情は一顧だにされず、当事者国民の権利は踏みにじられ、ないがしろにされる。
日本の法文化には、瀬木氏が指摘するような前近代的で非合理な面もあるのだろうが、一方で日本文化の中には共生や協調といった、これからの世界にとって不可欠な叡智を先取りしている面もある。白黒つけずに曖昧にしておく慣習も、混沌として白黒つけ難い事象が多発する現代にあっては悪習とは言い切れない。そのような状況にあって、我々一般国民には何ができるのか。
まずはメディアを鵜呑みにせず、情実に流されずに、トンデモ判決をトンデモと認識する所からではないだろうか。司法は元来、法律家のためにあるのではなく我々庶民を、国民を、守る為にあるものだ。また、司法は一国の文化を凝縮した形で体現するものでもある。この原点を忘れずに一人でも多くの人がメディアに惑わされず、「法」と「ファクト」を重視する正しいリーガルマインドを養うことが庶民にできる司法を含む文化防衛の第一歩なのではないだろうか。
