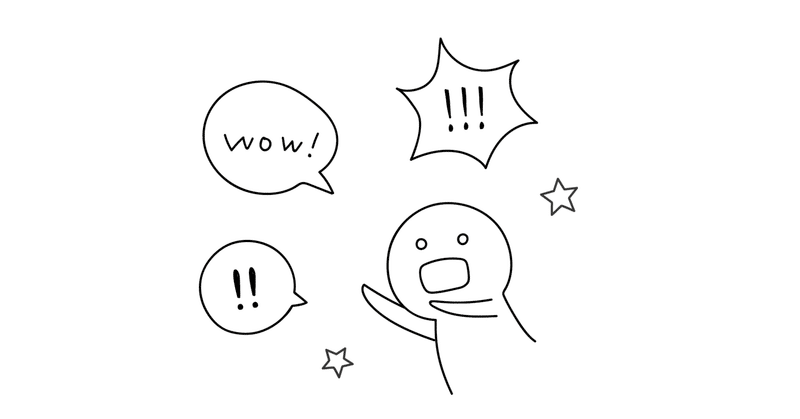
やらなければならないことが多いときの大学1年生の対処方法
背景
前回のnote「大学生は、ヒマじゃなくなったのか?」で、「高校生から大学生になって、やらなければならないことをする時間は減少」と書いた。大学の授業は毎日1限から5限まであるわけでなく、自ら選択した時間以外は自由に使えるはずである。しかし、5月になると1年生から「やらなければならないことがいっぱいでどうしたらいいかわからない」と少々パニックになった相談を受けることが多い。
私は、そんな時、「テトリス」をイメージする。高校から大学になって、自分が自由に使える時間が増えた=テトリスの幅が広がった。やらなければならないことは減ったが、やりたいこと、やった方がいいこと、たぶんやったほうがいいことが増えた。=多様な形の落下物が増えた。でも、まだ落下物を回転させたり、いい場所に落とすことができない。だから、課題が上に重なって苦しくなっているんだろうと。
最初にやること
自分の場合、まずは一通り話を聞くことにしている。つい口を挟みたくなるしょーもない言い訳があっても黙って聞く。この作業が大切で、相づちか、多少納得しなくてもそうだよねと共感するフリをしている。そうしないとこちらの話を聞いてもらえないからである。喩えるならば、コップに水を入れる前に、十分吐き出してもらわないと水が入らないのと同じである。
見える化
次に、じゃあ書き出してみようかと言って整理させてみる。基本的には相手に書き出してもらうが、無理そうならこちらで書くこともある。できればボードに書いて、共有する形だと加筆したり整理しやすい。整理ができた時点で、かなり落ち着いてくることがわかる。
何からやるか(優先順位の付け方)
これは色んな対処方法がある。
1 嫌なことからやる
嫌なことを先にやって終われば、後はスムーズにできるというものである。たしかにそうだが、これは難しい。上級者向けである。(だから紹介しない)
2 期限が近いものを確認して、重要度が高いものからやる。プランA。
重要度で考えるが、期限もみる、まあ、王道、基本だろう。基本を伝えるのは大事だが、悩む学生には伝わらないことがある。期限はわかっても重要度の違いが判らない、どうしたらいいのかとパニックが続いているケースである。そんな時には、プランBを伝えてみる。
3 早く終わるものからやる、プランB。
やらなければならないことの種類の多さが焦りの原因になっている時、早く終わるものからやるのが有効である。状況把握ができていない、または思考停止状態の時である。学生と話すと、30分以内に終わるものが多い、ものによっては5分で終わるものも混ざっているので、これらを先に片付けると、状況把握がしやすい。例えば、やらなければならないことが10個あっても、2時間で5個に減らせられれば有効である。数が減るだけでも安心するが、多少の自信にもなって、残りがあとあれとこれかと把握できるとかなり安心できる。
4 2番目に嫌なものからやる、プランC。
1番やりたくないことがある時、2番目にやりたくないことのハードルが下がることがある。たとえば、試験前にめったにやらない部屋の掃除に夢中になるのと同じである。心理学でありそうだが、経験上、これを活かすケースが時々ある。特に、誰かと交渉するものが1番やりたくないことになっていることが多い。先にやった方がいいのだが。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
