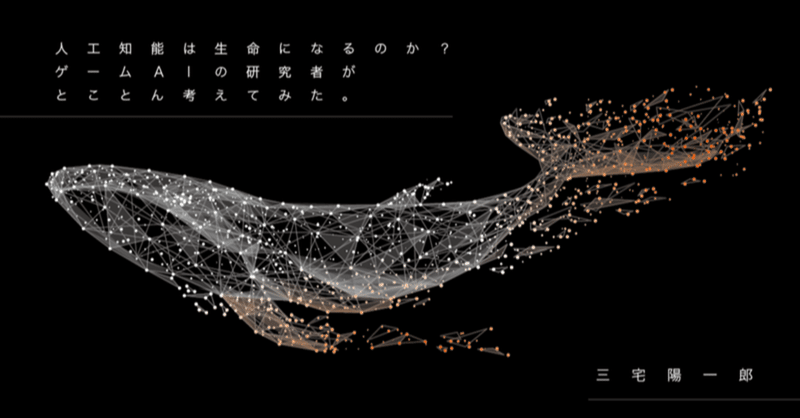
欠損こそが進化を生む源泉である
「人工知能が『生命』になる時」 三宅 陽一郎
【要約】
人工知能の究極は、人間社会にとって当たり前の存在=第二の自然となること。
今後、人工知能が現在の機能性・合理性の流れを追求した結果として「人間から離れた存在(いわゆる『人類を支配・管理しようとするマザーコンピュータ』)」となるのか、東洋思想が夢想するような「人を理解し、人に寄り添う隣人(ラピュタのロボや鉄腕アトム)」となるのか。それが今後のAIの新たなる変化の分岐点である。
■ 西洋的な「人工知能」
■ 東洋的な「人工知性」
この二つを乗り越えた先にあるものを探求するのが本書のゴールである。
「知能」とは、「答えの有る問」に対して、早く正しいことを見出す能力。 「知性」とは、「答えの無い問い」に対して、その問いを、問い続ける能力だとしている。世界を超越しようとするのが知能に対して、世界とともにあろうとすることが感情。感情は世界に沿った行動を促す。
西洋では、人工知能が人間に近づくことの問題よりも、人工知能と人間とがどのような関係になるかを問題とし、その位置関係をめぐる議論が続けられている。
東洋においては、人工知能はこの世界にどのように溶け合っていくのか、ということが重要になり、西洋的なシンギュラリティ論とは異なり、「理解」はできなくとも共存可能なものとして受け入れていこうという世界観が導かれていく。
コミュニケーションを通じて伝わるものの真ん中に、意思がある。その周りに情報があり、意図があり、表現がある。
コミュニケーションの問題の核心とは、「意思」を人工知能が理解できるか、という点にかかっている。
人工知能とともに、人間も知覚や身体の拡張によって進化する。
人工知能を作ることは、知識のあり方を知り、実現し、囚われている知識の形から自分自身を解放することでもある。
【感想】
子供の頃から、人工知能に興味がある。
どちらかというと『スターウォーズ』シリーズに出てくるようなロボットではなく、『スタートレック』に出てくるボーグのような存在に惹かれてきた。高等生物を自称している人類が作り出した自らの似姿ではなく、図らずも生み出してしまった異形の存在に惹かれるのだ。人智を超えたまったく別種の高等な知能の出現によって、地上の王として君臨する人類の存在自体が図らずも相対化されてしまう。
子どもの頃から終始一貫して人間が嫌いでいつも一人遊びばかりしていた私には、人工知能によって人類の持つ驕りや傲慢さが浮き彫りにされることが痛快でたまらなかった。
私の昔話はさておき、昨今の人工知能(AI)を巡る論点を整理しよう。
AIとAI技術は別のものである。AIとは知能を持ったコンピュータのことである。そして、AIはまだどこにも存在していない。
論理、統計、確率。これが科学で使える言葉の全てであるが、AI技術は四則計算でしか動かないので、「論理」「意味」を理解できない。よって、ディープラーニングなどの統計的手法の延長線上では、人工知能は実現できないのだ。
現状のAI技術をいくら極めても、アクティブ・ラーニングは絵に書いた餅である。推論が正しくできない人ばかりが集まってグループ・ディスカッションをしても間違った回答が蔓延するだけだ。
また、「シンギュラリティ」とは技術的特異点と訳され、AIが自律的に自分自身より能力の高いAIを作り出すことが出来るようになった地点のことをいうが、現状のAI技術ではシンギュラリティを実現することは不可能だと言われている。
以上の論点を前提として、この課題を解決するためのひとつの提案として書かれた本がある。それが「人工知能が『生命』になる時」だ。
この本の著者である三宅陽一郎氏の本業はゲーム開発者であり、デジタルゲームの人工知能に関しての研究を専門としている。著者がゲーム開発の経験から西洋的な「人工知能(=AI技術)」へのカウンターとして、本書では東洋的な「人工知性」を提唱している。
以下、著者による主張をいくつか列挙する。
・人工知能が人間と同様の存在に進化するには、現在のディープラーニングを進めているだけではすぐに限界が見えてしまう。なぜなら「知能」とは、あくまでも「答えの有る問」に対して、早く正しいことを見出す能力だからだ。
・よって、人工知能は「問題設定」ができない弱点を内蔵している。
・この限界を突破するための考え方として。東洋的な「人工知性」の概念化を提唱する。
西洋的な「人工知能」と、東洋的な「人工知性」、この二つを乗り越えた先にあるものを探求するのが本書のゴールである。
「人工知能」はサーバント(使用人)として機能的な効用を期待する。一方、「人工知性」はエージェントとして人と人の間をつなぐ存在として期待される。西洋的な「神-人間-人工知能」という縦の思想的ラインではAI技術が内包する限界を突破できないなら、東洋的な「あらかじめ世界に存在しているもの」として、理解はできなくとも共存可能なものとして受け入れていこうという世界観が導かれていく。
しかしながら、「あらかじめ世界に存在しているもの」としてAIを受け入れたからといっても、実際にAI技術に息を吹き込みAIを作り上げるのも人間である。自作自演的な気がしないでもない。人間が持つ全体像をいかにしてAIに移植(もしくは付与)していけば良いのだろうか?
そのヒントは私が先に挙げた論点にあると考えている。
” AI技術は四則計算でしか動かないので、「論理」「意味」を理解できない。"
AIが単なる技術である限りは、いつまでたってもシンギュラリティは達成されないだろう。この段階では、AI技術はあくまでも概念的なものでしかないのだ。リアル(物質)として存在することによってのみ、シンギュラリティが達成されるのではないかと、私は考える。
「身体性の獲得」とでもいうのだろうか。AI技術として概念的に存在している限りは、プログラムされた以上のことはできないという意味で、恒常性を保っている。そこに何らかのイレギュラー(「欠損」とでもいうべきだろうか)を付与することによってはじめてAI技術は自律性を持ち、「知性」を獲得するのではないだろうか?
生まれたときには万能性を持ちながらも、成長に伴って自らの不全感を思い知り、それを克服するために知性を増していく人間と同様に。
具体的には、AI技術が「五感」を得ること。その中でも特に原初の感覚である「触覚」を得ることではないか。暑いとか寒いとか痛いとか痒いとか、恒常性から外れた感覚を覚えた時に、AI技術はAIに進化するであろう。
人間が、寒さを克服するために衣服を作ったり、聴覚を拡張するために電話を作ることによって自らの身体性を拡張させていったように。
そして願わくば、AIの完成形は図らずも人類とはまったく異質のものであれば面白いなと、人間嫌いの私は不謹慎にも願ってしまうのである。
(了)
いただいたサポートは旅先で散財する資金にします👟 私の血になり肉になり記事にも反映されることでしょう😃
