
レイモンド・チャンドラー「待っている」読書感想文
ハードボイルドの大作家とは知っている。
現代の作家にもお手本にされていて、あちこちの本の作中で紹介もされている。
1回は読もうとは思っていたけど、今までに読んだハードボイルドって、それほど好きにはなれなかったので躊躇させていた。
しかしながら。
期待してない読書のほうがおもしろい場合が多々ある。
試しに読んでみた。
この本には、5編が収められている。
4つの中編と、1つの短編。
終わりにある短編の題名が『待っている』となる。
感想
テイストがちがう。
今までなんだったの?
ハードボイルドだと思って読んでいたのは。
バイオレンス小説、アクション小説、エンターテインメント小説、そういったジャンルだったのかもしれない。
率直にそんな感想があった。
どこがどう、レイモンド・チャンドラーはちがうと感じたのか。
以下、追ってみたい。

訳: 稲葉明雄
カバー撮影: 板橋利男
カバーデザイン: 小倉敏夫
ネタバレあらすじ
筆者註 ・・・ けっこう長くなってしまいました。もうちょっと短くしようとあれこれやってみましたが、どうにもなりませんでした。短編や中篇というのは省ける箇所が少ないものですね。
【1】ベイ・シティー・ブルース〔113ページ〕

フィリップ・マーロウが意識を取り戻すと、ベッドの上では女が死んでいた。
胸を撃たれていて、マーロウの拳銃が使われている。
誰かが、罪をかぶせようとしている。
さっき、カジノで出会った女だった。
というよりも探していたから出会った。
アパートまで送るよと一緒にカジノを出て、車に乗ろうとしたとき、後ろからブラックジャックが振り下ろされてこうなった。
・・・ “ 皮棍棒 ” とあるがブラックジャックとした。
皮製の短い筒の中に砂が詰められている護身具だ。
背後からブラックジャックで殴られ気絶、というパターンが全編で3回ほど出てくる。
音もなく振り下ろされるブラックジャックが、なんとも不気味な小道具として、いい味を出している。
ともかくこれで。
この件で3人目の死者となる。
発端の1人目は、ベイシティーの医者の妻。
カジノでヒステリーをおこして大騒ぎして、夫の医者が駆けつけて鎮静剤を打った。
そのあとにガレージで死体となって発見される。
死因は一酸化炭素中毒となっている。
2人目は、その死体の第一発見者。
これは殺人だと、だったら金にしようと動いた彼は、現れた男たちに脅されて、隣のロス市内まで逃げてきた。
そこでロス市警の刑事を頼って、今度はマーロウに下調べの依頼がきた。
大した金にはならない依頼だが、1週間も仕事がないし、引き受けてから彼の潜伏先を訪れたときには殺されていた。
3人目が、今、ベッドで死んでいる女。
逃げた彼の元妻でもある。
ひっかき傷があるのは、撃たれる前に抵抗したのか。
“ 大アゴ ” と呼ばれる実行者の姿がチラついていた。
ベイ・シティーの違法賭博業者が、絡んでいるのは予想がつく。
今の市長になってから汚職がひどい。
カジノも公然と営業している。
が、グズグズしてられない。
誰かは、仕上げとして警察に通報もしてあるようだ。
ドアの向こうでは警官が「あけろ!」とノブをガチャガチャしている。
すぐさまバスルームに入って窓から身を乗り出して、隣室の窓ガラスを割って逃げ込んだ。
留守だったのはよかったが、やがてそこも警官がドアを叩いて、上手に住人のフリをしたつもりだったが見破られる。
“ ディ・スペイン ” という警官だった。
署長と対立して、1週間前に警部補から降格している。
なぜそれらを知っているのかといえば、夕方に立ち寄った警察で窓口係として不機嫌そうに対応してくれて、警察詰めの新聞記者が教えてくれたからだった。
ディ・スペインは部下に拳銃を構えさせたが、なぜか手錠はかけない。
現場を離れて、車に乗せてからは急発進する。
勝手な行動を心配する部下を途中で降ろしてから、大筋はわかっているのを明かしてきた。
1人目の殺人に疑問を抱いていたところにロス市内から探偵が来たので、ロス市警の刑事に連絡をとって経緯を確かめていたのだ。
署長への対抗を露にして、この一連の殺人の真犯人を2人で捕まえる、と言ってもくる。
断る理由はない。
だとすれば、検死官を押さえなければと、その家に向かう。
そこには、先手を打って検死官を逃がした大アゴがいた。
なるほど、機関車の前面に取り付けられる “ 排障器 ” ほどのアゴをしていた。
銃口を向けられたディ・スペインだったが、陽気に挨拶してから股間を蹴り上げた。
正面から、それをやってのけた。
蹴られ続けて血まみれで転がる大アゴは、殺人を問われて力なくうなずく。
・・・ なにがちがうのか。
まずは、暴力シーンの描写がうるさくない。
全編にわたって暴力シーンは度々あるけど、細かくは描かれているけど、やたら騒がしくない。
「ゴキッ!」なんて打音も「ギャァッ!」などの叫びも「ウウウウッ」なんて呻きもなく、いたって静かに描かれるのがしっくりくる。
なんにしてもだ。
1人目の犯人は、夫である医師。
麻薬中毒者にモルヒネ入りの注射を打って回っている。
妻がカジノにハマって浪費しているのが疎ましくて、あのカジノでヒステリーをおこした夜、鎮静剤ではなくて致死量のモルヒネを打ったのだった。
懸念したのは違法カジノの責任者。
これが事件となって、とばっちりがきては困る。
出資者たちに申し開きが立たない。
献金が欲しい市長には、電話1本で事故死に処理させて、動き回っていた男は大アゴに片付けさせて2人目となった。
・・・ あと。
暴力でなにがちがうのかというと。
その世界でしか通用しない力学だったり、珍妙な理屈からの掟や絆だったり、そんな類の動機が全編にないこと。
利害の対立に沿って描かれているのがいい。
女性に対しては別にして。
ある意味では単純だけど、動機がブラックボックスに投げ込まれて、うやむやにならないのが好きだ。
話を戻す。
次には、医師の職場に押しかける。
否定はしたが、やがてうなだれて自白した。
すべての犯人逮捕の連絡をいれると、署長が刑事を連れてやってきた。
不快そうな笑顔が2人には向けられた。
「わしの町で派手にやってくれているそうじゃないか」
署長とディ・スペインとは言い合いもあったが、これで解決かと思えた。
が、3人目の彼女の犯人は、ディ・スペインだ。
交際していて、マーロウと関係があると勘違いして、痴話ゲンカの果ての殺人だった。
痴話ゲンカしたあとのような殺されかただった。
事後、考えなおして、マーロウがどこまで知っているのか探るために行動を共にして、3人目の彼女も大アゴを犯人に決めつけるための芝居をしたのだった。
最初に彼女とカジノで出会ったとき、シガレットケースにはディ・スペインの写真が張ってあったが、当人は知らないといっていたのが疑ったきっかけだった。
証拠は、ディ・スペインの爪の間にある。
ひっかいた彼女の皮膚が残っているのは確めた、とマーロウは話す。
少し笑ったディ・スペインは、服の下から発砲。
署長に撃ち返されて床に転がった。
・・・ 読む前まで。
荒っぽくて非情な主人公が登場すると思っていた。
が、以外なことに、どの主人公も繊細。
あとは、強い立場の主人公が、有能な主人公が、超人的に事件を解決していくとも思っていた。
しかし全編にわたって、弱い立場の主人公がギリギリの綱渡りで解決していく。
驚くような推察もどんでん返しはないのだけど、こういうの好きだなと本を閉じて余韻に浸れるほど。
ラストに。
署長はいう。
「君は、ひどくあぶない橋を渡る男だな」
「僕は精一杯のことをしたつもりです。いちばんに癪なのはディ・スペインが好きだったことです。彼はこの世にはめずらしい土性骨の持ち主でした」
遠くのアーグェロ通りからは、サイレンの音が細かく聞こえてきていた。
~ 1938年 発表 ~
【2】真珠は困りもの〔76ページ〕

安ホテルの一室で、ウォルターは待っていた。
その一室の鍵は、太った支配人の腹を殴り2ドルをやって開けてもらっていた。
宿泊者のアイケルバーガーは帰ってきた。
体は大きく首が太く、顔は殴り殴られた傷で潰れていて、ドアを開けても侵入者に驚きもしない。
婚約者にキスをしようとしたと咎められても、せせら笑うだけだった。
2人の殴り合いがはじまったが、アイケルバーガーのほうが強かった。
が、腹に持病があるらしく、そこを殴ることで引き分けた。
それはそうと、本題はキスなどではない。
真珠のネックレスだ。
痛み止め代わりのウィスキーを飲みながら話された。
婚約者は、大邸宅の未亡人の付き添い看護師をしている。
そこで先日、49玉ある真珠のネックレスが紛失した。
彼女は、3ヶ月ほど運転手をしていたアイケルバーガーが犯人だという。
キスしようとしてきたし、辞めたと同時に真珠のネックレスも紛失したからといっていた。
問われたアイケルバーガーは、力なく低く笑って、この顔をどう思うかと訊いてきた。
返事に迷っていると、運転手を辞めたのは、どうにもできない魅力的な女性が朝から晩まで近くにいるからだという。
もちろん、真珠のネックレスなど盗ってない。
そうであれば警察がくるまえにここを引き払っている、とウィスキーはさらに飲まれた。
この前にウォルターは部屋中を捜しているが、真珠のネックレスは見つかってなかった。
・・・ なにがどうというわけではないけど。
翻訳がちがうな、と何度も何度も感じた。
英語がわからない中卒が読んでも『いい翻訳だな』とため息が出た。
翻訳としては正統だろうけど、日本語で読むにはしっくりこない小説ってある。
どうせチャンドラーもそうだろうと、実はケチをつけるつもりだったのに隙がない。
巻末の解説には『チャンドラーは完訳すべし』と翻訳界の先生も言っているとある。
翻訳者に敬意を感じた。
で、未亡人のほうである。
警察には届出できない事情があった。
盗られた真珠のネックレスは、イミテーションだったのだ。
亡き夫から金婚式でプレゼントされたときは本物だったが、その亡きあとに、使用人の給与の支払いのために売っていた。
いや売ろうとしたが、話を受けた宝石店の店主は、好意で現金とイミテーションを渡した。
事情がどうであれ、亡夫からのプレゼントがイミテーションだったという話になってほしくない。
だから警察にはいけない。
ということは、犯人が間抜けでなければ。
未亡人を強請ってもいいと気がつく。
そのためにも、イミテーションであっても見つけなければだった。
翌日の夕方。
床にはウィスキーの空瓶が転がっている。
あれからはウォルターのアパートに場所をかえて、さらに飲みながら話して、アイケルバーガーがネックレス探しを手伝うことだけは決まった。
大酒飲みで乱暴な口をきくが、頼りになるミルウォーキー(シカゴの隣)出身のアイケルバーガーだった。
まずは、町の故売屋を当たってみてはどうか?
イミテーションで安くなっても売るだろう。
ビリヤード場にいってもいい。
もしかしたら、アウトローの間で笑い話になっているかもしれない。
・・・ くり返すけど翻訳がちがう。
今まで読んだハードボイルドにありがちだった陳腐な比喩も、過剰な装飾語もひとつもない。
漆黒の闇のような目、とか。
真紅の血が飛び散った、とか。
ひとつでもあったなら、陳腐な比喩マニアの自分は見逃さないのに、全編でひとつもない。
元々チャンドラーが書いてないのか。
翻訳者の技なのか。
どっちもだろうけど、英語の原文を読んで確かめたくもなるけど、まあでも、今からそれをやると気が遠くなるので、無学者は言ってみるだけにとどめる。
話を戻す。
夕刊がドアから落ちたところからだ。
記事には、宝石の故売の容疑で、酒場の店主が逮捕されたと載っている。
すぐに容疑は晴れて、もう釈放されてもいる。
2人はスーツを着て、この酒場へ急行する。
保険の調査屋と称して、店主を問いただした。
故売屋など知らないと言い張る店主は、不意にブラックジャックを持ち出して、乱闘になって、アイケルバーガーが床に叩き伏せた。
空振りではあったが、すぐに別の動きがあった。
2人がアパートに戻ると電話がかかってきたのだ。
49玉ある真珠のネックレスを買い戻さないか、5000ドルで、と相手はいう。
指定されたのは夜間。
場所は野原。
1人で来るようにいわれたが、アイケルバーガーは後部座席の床でボロ布をかぶって隠れている。
しかし1時間待っても、犯人は現れない。
アイケルバーガーは、犯人は様子見をしただけだと小型拳銃を草むらに投げ捨てた。
その直後だった。
ウォルターは、いきなりアゴを殴りつけた。
気絶して地面に大の字になっている靴下の中に、真珠のネックレスがあった。
どういうことなのか?
取引の電話は、プライベート用にかかってきた。
犯人がその番号を知っているということは、アイケルバーガーとつながっている。
もしくはアイケルバーガーが犯人。
電話しているのは協力者。
「君は悪の道では成功しない。優柔不断すぎる。拳銃を突きつけてもよかった。それを投げてからも、まだ取引をためらっていた。酔いつぶれているうちに金をとって逃げれたのにそれもしなかった」
日当の100ドルを気絶している胸ポケットにいれて、気がついたときに欲しがるだろうからウィスキーの瓶も手元に転がしてから、その場を去った。
数ヵ月後に、うれしい手紙がきた。
アイケルバーガーからだ。
ホノルルの消印がある。
「やあ、兄弟!」とはじまる手紙を要約すると以下である。
『 今は油の弁の掃除をしているが、すぐにでも、また一緒に飲みたい気分だ。
ところで、わかってほしい本音が2つある。
ネックレスをとったのは、女に目がくらんだ野郎がフラフラと見境なくやらかすアレだ。
だから、取引するのにも気がひけてしまった。
それから、あんたがモノにしたあの女に会ったら、俺も好きだったと伝えてくれ。
達者でな!
P.S.
電話をかけた野郎が100ドルを山分けしようとぬかしたものだから、やむをえずギュウという目に合わせてやったよ。』
~ 1939年 発表 ~
【3】犬が好きだった男〔146ページ〕

「あんたがこの町にきて4日。平和な町に、過去3年間以上の犯罪がおきている」
太った署長はいう。
海沿いにある小さな町の警察の署長室だった。
その町の精神病院の事務室で撃ち合いがはじまって、4人が死亡したのだ。
懸賞金がかけれらている銀行強盗犯が、いきなり現れて撃ってきて、その場にいた警官も病院職員も死亡した。
生きていたのはカーマディのみ。
犬を探しにロサンゼルスから来た私立探偵だ。
来た4日前には、その犬を診ていた獣医が事故死した。
カーマディーも銀行強盗犯も、現場に居合わせている。
通報で警察がきたが、直後にカーマディはブラックジャックで殴られ気絶。
気がついたら、その精神病院の鍵付きの個室で、麻薬を打たれて2日間監禁されていた。
わけがわからないままカーマディは精神病院から逃れて、署長に面談を求めた。
話をきいた署長は、精神病院と銀行強盗犯には関係があると判断。
2名の警官と共に向かったら、いきなり銃撃になったのだ。
・・・ 銃撃を含めて暴力は多く描かれる。
が、今まで読んだハードボイルドとはテイストが異なると、最初の1編を読み終えないうちに感じた。
今までは、盛大な暴力ばっかりだった。
作者が描いているうちに興奮しているようでもあった。
その興奮が伝われば伝わるほど、もうわかったからと、所詮は小説の世界のお遊びをしてるのだなと醒めてしまう温厚な自分だった。
が、ここでは、暴力が合理的に行われる。
非情だとか冷酷だとかではなくて、単にチャンドラーが、暴力には一切の興奮をしてない。
で、太った署長である。
30回も同じ話を繰り返した。
「まったく妙だ。4人とも倒れて死んでいるのに、あんたはかすり傷ひとつ負っておらん」
「生きているうちから床に倒れたのは、僕1人でしたからね」
午後が過ぎて、もう1度、明日の朝になったら話をしようと署長はいう。
警察署を出たカーマディは、そのまま港に向った。
銀行強盗犯は、兄妹の2人組。
銃撃してきて死亡したのは妹のほう。
死ぬ間際の問いかけには、船の名前のような言葉をつぶやいていた。
問いかけとは、目的の娘がいる場所。
資産家の娘は、ある日に犬を連れたまま失踪した。
ナイトクラブで遊び歩いていたので、良からぬ連中に連れ去られたらしい。
その犬を、この町で見かけたという手がかりがあって、娘探しを依頼されたカーマディだった。
見当がついた船では、違法カジノが行われていた。
水上タクシーとなっているモーターボートに乗ったが、脇の下にはホルスターがあり、あっさりと岸まで追い返されてしまった。
返された浮き桟橋で声をかけてきたのは、赤毛の大柄の男。
破けたセーターに、タールの染みたズボンに、汚いズック靴を履いている。
「あの船に乗せることができるぜ。50ドルでいい。おれの船で血が流れるならプラス10ドルプラスしてもらおう」
それには返事することなく、2歩ほど足を進めただけだったが、すぐに25ドルに下げてきた。
悲しげな声で赤毛がいうには、エンジン音が小さいボートもあるし、荷物搬入口が開くことも知っているという。
「君の商売はなんだ?」
「あっちで1ドルこっちで1ドル。オレだってメシを食いたいからな、これでも元警官だ」
25ドルを先払いすると、赤毛はボートをとりにいくと姿を消した。
待つ間には、今から船にいくと署長に電話しておいた。
少し遅かったが、赤毛はボートを回してきた。
夜の海を進んで船に横付けしてからは、荷物搬入口まで鉄階段を登って、甲板に出るハシゴの近くまで案内する。
「すぐ帰ってくるかい?」
「甲板から鮮やかなダイビングを見せるつもりだ。もしかしたら乗らないかもしれない」
帰りの代金は後払いでいいと赤毛はいうが、カーマディは先払いを押し付けた。
赤毛は礼をいって、ハシゴの見張りのイタリア人を殴って、そのシャツを裂いて猿ぐつわをして縛り上げるサービスまでがついた。
甲板まで上がったカーマディは、狼の遠吠えをする。
向こうで犬の鳴き声があった。
その方向へ走りながら拳銃を抜く。
船室のドアを開けると犬も娘もいた。
銀行強盗犯の兄のほうもいて、すでに拳銃の台尻で殴られて倒れている。
「あの犬を手放していればよかったのに」
「俺は犬が好きなんだ。俺だって仕事をしてないときはいい人なんだ」
とにかく、娘さえ戻ればいい。
懸賞首がここにいると忘れてもいい。
でも、泣く娘はいやだと、一緒にいると首をふる。
2人は結婚しているという。
カーマディは、まいったなぁというように拳銃を向けている。
すると太った署長が現れた。
同行している刑事は手にしている拳銃を構えて、発砲の許可を求めている。
それを制した署長は、丁寧な口調で訊いてきた。
「やれやれ、だいぶ嗅ぎ回ったとみえる」
「あんたがたの清潔な小さな町は、鼻持ちならない臭気があふれている」
犯罪者が過ごせる町だったのだ。
署長に金を払って、面倒さえおこさなければという条件で。
ところが銀行強盗犯は、娘と犬を連れてきたばかりに、カーマディという面倒も来てしまった。
署長は精神病院への監禁もさせた。
あの銃撃も、事件として殺そうとした署長の指示だった。
突然に娘が歯の間から口笛を吹いたのは、まだ話している途中だった。
夫も殺されると思ったのだ。
飛び跳ねた犬は署長の喉元に食いついて、一気に船室が銃声で満たされた。
カーマディは頭を撃たれた。
・・・ しつこいけど、暴力の扱いが、今まで読んだ和製ハードボイルドとは異なるのは感じた。
とくに拳銃の扱いが異なる。
強い者が行使する拳銃ばかりだったから、読んでも読んでも、和製ハードボイルドって好きになれなかった。
拳銃が登場すると、弱いものは死に役ばかり。
むやみに死んでいく。
でもチャンドラーでは、強きも弱きもお互いに生き残るために必死に拳銃が使われる。
そりゃ、3人も4人も死者がでているけど、それだってむやみには感じない。
とはいってもアメリカと日本のちがいがあるから、当たり前といえば当たり前だけど。
話を戻す。
撃たれたカーマディである。
目を覚ましたときには2日が経っていて病院だった。
銃弾は頭蓋骨を反れていた。
そこで3週間を過ごした。
あの犬も、銀行強盗犯も撃たれて死亡したが、連邦警察にすべてを上手に話すまでの命はあったらしい。
娘は釈放されて家へ帰された。
そのころには郡の予審廷では、小さな町の警官の半数余りを起訴する手続きがとられていた。
新たに部長刑事となった、赤毛の大柄の男が言ってきた。
「あんたには25ドルの借金がある。でも復職して服も新調した。最初の給料が入るまで返済は待ってくれないか」
「待ってもいい」
カーマディは答えた。
~ 1939年 発表 ~
【4】ビンゴ教授の嗅ぎ薬〔75ページ〕
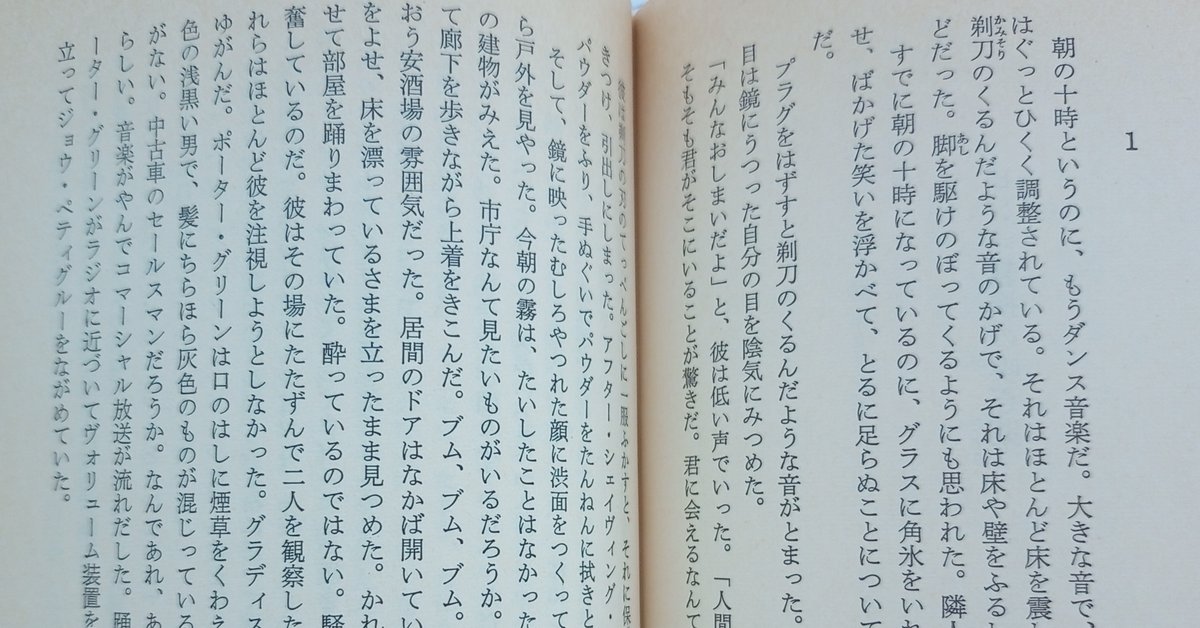
これは他の4編とテイストがガラッと変わる。
透明人間になった老人が密室殺人をするというもの。
巻末の解説によると、本格探偵小説を揶揄したも幻想編、とある。
どうりで。
ハードボイルドどころか、透明人間になった老人の戸惑いがコミカル。
とにかくも。
揶揄というのも奥深いなという感想だ。
~ 1951年 発表 ~
【5】待っている〔31ページ〕

トニーは、ホテルに雇われている探偵。
広いロビーの片隅に座り、行き交う客の様子を見て、トラブルを未然に防ぐ。
小柄で、腹が突き出ている、顔色のわるい中年男のトニーだが、灰色の目には平和があった。
その夜。
ロビーの灯りを落とした深夜1時すぎ。
ボーイが焦ったようにきた。
外にいるコートの男が名指しで呼んでいるという。
「あんた、敵がいるのかい?」
「なあに、ただの金貸しさ」
ホテルの前の通りには、黒い大型車が止まっていた。
数人の部下を連れたコートの男もいた。
お互いは顔見知りだった。
久しぶりに会ったように挨拶を交わしたのだが、親しみは見せない。
「あそこの仕事が気に入っているようだな」
「仕事は仕事さ」
しばらくの会話があった。
コートの男はアルという。
身内の話もしているので、若いときからの長い付き合いと知れる。
アルのほうが先輩のような口ぶりとなっている。
後にトニーは “ 阿呆の集まりだ ” と言っているので、彼らを快くは思ってないのは確かだ。
もちろん用件があってアルは来ている。
ホテルに宿泊している女の名前をいい、1時間のあいだに、その女をホテルの外まで出してくれないかという。
はっきりした返事をしないまま、ホテルのロビーへ戻ったトニーだった。
ついさっきだ。
その彼女とは話したばかりだった。
最上階に宿泊していて、5日になるのに1度も外に出てない。
以前にこのパターンで、最後にはベランダから飛び降りた女性客がいた。
ロビーの灯かりが落ちたあとに、一角にあるラジオ室で顔を合わせたので、それとなしに探ってみた。
時間をもてあましていた彼女は、ホテルの探偵と察して面白がって、飛び降りなんてしないと親しげな笑みをする。
男を待っているという。
5日前に刑務所から出た彼だが、このホテルで会う約束をしているという。
「よりを戻してもいいわ。人生は1度きりなのに、過ちは何度もするものなのね」
が、男は以前にカジノの25000ドルを持ち逃げしていた。
出所と同時に、取り立ての依頼がアルに回されて、それで彼女の身柄を押さえたいといってきている。
ラジオ室にいってみると、その彼女はいない。
エレベーターは最上階で止まっていた。
するとボーイがきて、さっき最上階の部屋の男に酒を届けたら、脇の下にホルスターが見えたと心配そうに言う。
1時間ほど前にチェックインしており、偶然にも彼女の部屋の隣だとも、なにも訊かれてはいないとも、フロントで確かめられた。
その部屋のドアは、トニーにノックされる。
撃つ撃たないのやりとりがあった。
入室してからは、彼女の名前が口にされると、男は拳銃をテーブルの上に置いた。
25000ドルの持ち逃げは、仲間に嵌められただけで関係ないとうんざりした息を吐く。
「老舗ってやつは、ぜったいに休んだりしねえな」
トニーは逃がすつもりでいた。
彼女にはまっとうな暮らしをさせる、という条件はつけた。
その彼女は隣の部屋で寝ていると知らされた男は、ベランダを越えて会って、地下まで降りて、ガレージ係から車を借りてホテルから逃げることになる。
「ぐずぐずするなよ、色男。こっちだって気がかわるかもしれねえ」
言い残してロビーに下りる。
フロントにいき、部屋の代金はトニーが支払った。
すると、部屋で寝ていると思った彼女は、ラジオ室のソファーにいた。
寝れないからきたと、話し相手になってと楽しげに笑んだ。
トニーは応じて座るが、寒気が背筋を走る。
耳が異音を探っている。
遠くの、不確かで、不気味な物音を聞こうとしている。
・・・ いちばんに、何がちがうのかというと。
主人公が全編で、鬱屈してないところ。
いや、主人公でなくても、全員が卑屈にもなってない。
悪事に関わっている割には。
あとは全編で、誰も正義感を振りかざさない。
状況は悲惨であっても、ほのかに希望すら感じさせるのは、それらが相まっているからかも。
とにかく。
あくびをした彼女は、しばらくそこにいてと、クッションを抱いてソファーで寝はじめた。
そっと立ち上がったトニーはフロントにいき、地下のガレージ係に電話して確かめる。
30分前に男は出たという。
受話器を置くと、すぐに電話は鳴った。
アルの部下からだった。
トニーは逃がす。
そう読んだアルは、ホテルの見張りを固めて、逃げようとした男の車は見つかった。
歩道の隅まで男は追い詰めたが、拳銃で反撃してきた。
アルは撃たれて、もう死んだという。
「アルは、おまえさんに、あばよって伝えてくれ、といったぜ」
それだけの用件だった。
重い足のトニーは、ラジオ室にたどりつく。
彼女は丸くなって眠り込んでいて、静かに身動きもしていない。
~ 1939年 発表 ~
