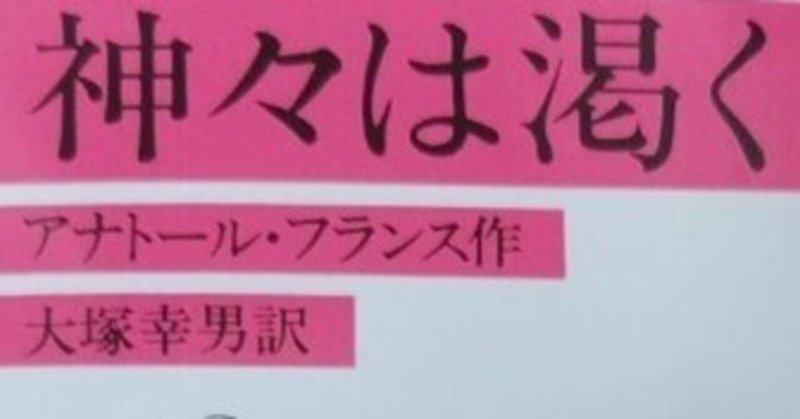
『神々は渇く』(アナトール・フランス著 大塚幸男訳)
<<感想>>
読書会主宰者から紹介をいただいた。
フランス革命を人々の視点から書かれた歴史的小説である。
ロベスピエールの恐怖政治の末期。フランス国民の多くが「革命に疲れてきた」タイミングで、依然ロベスピエールを信奉し、革命のためには手段を選ばない恐怖政治を支持する若い画家(エヴァリスト・ガムラン)を取り巻く人々の愛の物語である。当時の社会環境・生活・雰囲気や副次的な登場人物の様子が手に取るようにわかる名著であると思う。
そもそも彼の不幸は推薦を受け、革命裁判所の判事になったことにある。当時のフランスは反革命的な言動をすれば即訴えられ、革命裁判にかけられる。そしてその多くはギロチン送りとなる。
当時はもはや「人の命より革命」だったのだろう。特に革命支持者は完全にマヒしていたようだ。著書の記載にもあるように、裁判所では傍聴席から死刑を求める声があったり、判事自身も私怨や感覚で即死刑判決をくだしていた。
純真な若者であったエヴァリストも判事となってからは、いつの間にか人が変わってしまったようだ。妹の愛人だけではなく、妻となったエロディの昔の愛人と思わせる人物(本当はまったく関係なかった)を嫉妬から平気にギロチン処刑にした。
妹の愛人を救ってほしいとの母の言葉にも耳を貸さないエヴァリスト。
その時に母の口からでた「人でなし」という言葉。
人の命を軽く扱っていた当時のフランス社会の風潮をあらわすキーワードだったのかもしれない。
当たり前のことだが、一般の人々は穏やかな社会を望んでいたはずである。それを、恐怖政治を支持・推進する一部の「人でなし」が「自由・平等・友愛」という理念の実現を遠ざけてしまったというわけか。
しかし、実は革命指導者・推進者も病んでいた。エヴァリスト自身も悪夢にうなされたり、疲労困憊となる。それは著書に登場したロベスピエールのやつれた表情(描写)にもうかがえた。
結果的にエヴァリストは、多くの犠牲者の血に染まった自分自身の厭わしさに耐えられなくなり、妻のエロディに別れを告げることになる。
やはり彼も悩んでいた。
彼は本当は「ひとでなし」ではなかったのかもしれない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
