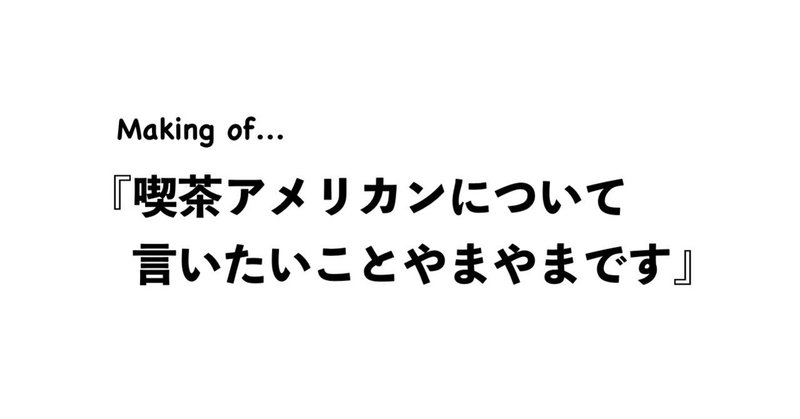
【第2回】アウトライナーに向いた人
前回の記事はこちら▼
「アウトライナーに向いた人」とはどんな人か
やままさんはアウトライナーに向いた人だという感覚がありました。もっというと、アウトライナーを必要としている人だという感覚がありました。やままさんとは数回しか会ったことがなかったのですが、その数回の会話の結果として勝手にそう思っていました。もちろんこれは私がアウトライナーフリークだからという面が大きいのですが、とにかくそう思っていました。
アウトライナーは「2,000字ならなんとか書けるけれど20,000字は書けない」という人を助けてくれるツールだと私は思っています。書こうとしている、書きつつある全体をイメージし、流れと前後の依存関係をコントロールしながら書き続けることを、アウトライナーは(そしてその使いこなし技術としてのアウトライン・プロセッシングは)助けてくれます。
「アウトライナーに向いた人」とはどんな人か。ひと言でいうと、それは「アウトライン通りに書けない人」です。そう言うと、ほとんどの人は怪訝な顔をします。アウトライナーとは「アウトラインにもとづいて文章を書く(あるいは情報を整理する)ためのもの」だと思われているからです。
でも「アウトラインにもとづいて文章を書くことができる人」なら、最初からアウトライナーなど必要としないはずです。それは「何をどう書くべきか最初からわかっている」ということだからです。
ブログ程度の短い文章(1,500〜2,000字程度)なら、勢いのままに書くこともできるかもしれません。でも、一定以上の長い文章になるとそうはいきません。
20,000字の文章は2,000字の文章を10回書けばできそうな気がします。でもそんなに簡単な話ではないことは、やってみればすぐわかります。20,000字がひとつの有機的な全体となった文章は、2,000字の文章を10個集めてもできないのです。
まず、文字量が増えるほど、書いたことの相互依存関係は複雑になります。同じ話の説明が前半と後半で異なったり、前提となる話が後に出てきたりすることは避けなければならない。伏線は回収されなければならない。回収されないのであれば、それは意図的でなければならない(特に文学作品などで例外はあり得ますが、一般論として)。
文章が長くなるほど、その調整の難しさは増していきます。だから「構成」を意識する必要が出てきます。これが「アウトライン」です。
矛盾や不自然なところがないように、あらかじめ構成と流れをアウトラインの形で決めておけば、後はアウトラインに合わせて書いていけばいい。「構成案」とか「目次案」とか「プロット」とか呼ばれるものは、アウトラインの一種です。
一方で、多くの人にとっての「自分の文章」は、気ままに書かないと出てこないという面があります。プロでもない書き手に「自分の文章」なるものが存在するのかという問題はありますが、ここでは「自分自身で書いたものが自分自身のものと感じられる」というくらいのふわっとした意味に取っておいてください。
(ちなみに気ままでなくても「自分の文章」が書ける人を「プロの書き手」というのだと個人的には思っています)
とにかく、多くの人は構成にこだわると気ままに書けなくなります。すると何が起こるかというと、文章の勢い、エネルギーみたいなものが失われてしまうのです。そして結果的に「自分の文章(と感じられる文章)」が書けなくなる。
特に文章の勢いに乗せて書きたいことを自分の中から引き出していくタイプ、投射したエネルギーに言葉を乗せていくタイプの書き手にとって、その影響は大きいものです。私自身がまさにそういうタイプなのですが、やままさんもおそらくそうなのだろうという印象を持っていました。
その感覚は、こんなツイートに現れています。
ああーっ!「構成」と「気ままに書く」の間をうまく行き来できない!どうしてこんなに行儀よくなってしまうんだッッ!あああーーーーーーーー!!!つまらん!!!
— やままあき◆Kindle本『妖怪べきねば』発売開始! (@yamama48) April 14, 2019
わかりすぎるくらい、わかる。
どうしてこんなに行儀よくなるんだ
アウトラインに合わせて書こうとすると「行儀よく」枠にはまった文章になってしまう。自分の文章が書けなくなってしまう。
なぜそうなるのか。アウトラインというのは文章にはめた枠だからです。枠にはまるように書こうとしているのだから、行儀よくなるのも当然のことなのです。
アウトラインの枠は文章の勢いを殺してしまう。でも、プロでもない書き手が勢いだけで数万字以上の長文を書ききることは簡単ではありません。ではどうすればいいのか。その矛盾を解決してくれるのがアウトライナーです。
アウトライナーの機能をうまく使うと、「アウトライン」のもつ意味が劇的に変わります。書かれた文章に合わせてアウトラインをアップデートし続けることが可能になるからです。つまり自由に(勢いにまかせて)書くことと、アウトラインをコントロールすることを両立できるようになるのです(このあたりのアウトライナーの機能とその意義については、アウトライン・プロセッシングミニ入門という記事にまとめてあります)。
実はやままさんは、電子書籍『凡人の星になる』の執筆にアウトライナーを使おうとしたらしいのです。
最初はDynalistでアウトラインを作り、そこに内容を入れていく書き方をしようとした。でもそれだと「行儀よく」なってしまって面白くない。そこでブログの文章のような勢いを取り戻すために、非公開のブログを作ってそこに原稿を書きためていったというのです。
非公開のブログを作ってブログ記事の感覚で書いていくというのは、(特にブログを書き慣れている人の)執筆の初期段階には非常に良い方法だと思います。
しかし、それによって自分らしい文章を取り戻すことには成功したけれど、今度は(やはりというべきか)本としてまとめる段階でまとまらず、大変な苦労をしたということでした(倉下忠憲さんのポッドキャスト「うちあわせCast」第4回「やままさんと『凡人の星』について」で詳しく語られています)。
この話を聞いて、やままさんがアウトライナーに向いた人だという思いを新たにしたわけです。やままさんがアウトライナーをうまく使えなかった原因は、アウトライナーを「アウトラインを作るため」に使おうとしたことだと考えられます。つまり、アウトライナー以前の紙のアウトラインと同じ使い方を(無意識に)しているのです。
(つづく)
次回の記事はこちら▼
最終的にできあがった本はこちら▼
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
