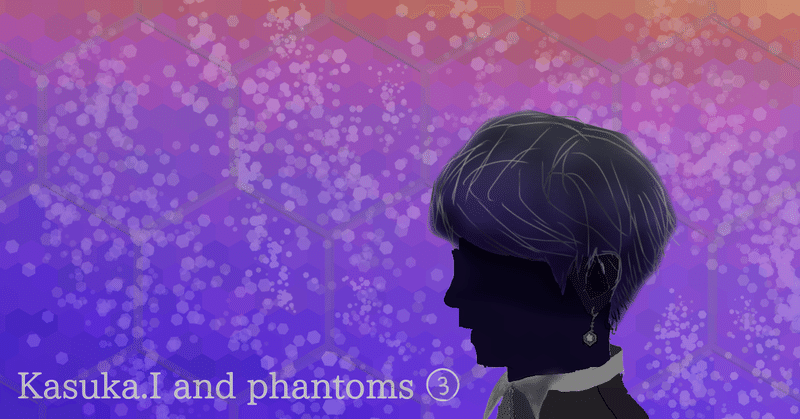
暗渠の「ガラッパさん」(連作小説:微と怪異③)
N市にある自宅から自動二輪を飛ばして20分。ロードサイドに並ぶ大型チェーン店は、いかにも地方都市といった様相だ。
その一角、サイフォンで淹れたコーヒーを売りにしている喫茶店チェーンの駐輪場に、井城微はバイクを止めた。
腕時計を見ると午後2時50分、店内はコーヒー片手に談笑する年配の客が数組いた。
待ち合わせ時間の10分前ではあったが、待ち合わせの相手は既に窓際の席に座っているのが、店の外からでも見て取れた。
「お待たせしちゃってたみたいで。怪異研究家の井城といいます」
一つ目小僧のイラストが描かれた手作りの名刺を渡すと、待ち合わせ相手の女性は丸縁眼鏡をずり上げてじっと見た。
「かわいいお名刺ですね。あ、わたしは平と申します。隣のK町で小学校の教員をやっています」
「先生をされてるんですか。小学校は怪談に事欠きませんから、いいですね。でもK町にお住まいなら、ここは少し遠くありませんでした?」
「ええまあ。でも校区内だと、うっかり知り合いに会ったりしますから、休日は車でよくこのあたりに出かけるんですよ」
お冷を運んで来た店員は、微を物珍しげにちらりと見た。普段よりは少し大人しめな、濃紺の髪にシルバー系のアクセサリーをつけているが、それでも目立ってしまっているのだろうか。
「それで、僕の同人誌――この前出した『地方都市の怪異譚』をお読みになって情報提供というのは......確かその中の「用水路の怪異」に関してですよね」
微の趣味というかライフワークは、各地に伝わる怪異の伝承や怪談、都市伝説を集めることだ。
蒐集した怪異譚を同人誌にまとめてマニア向けの即売会で売ったり、時折知り合いの民俗学者と連名で雑誌に論文を寄稿したりしている。
彼女が出した本や論文を読んで、メールで感想や似たような体験談を送ってくる人が時折いて、平もその1人だ。もっとも、いたずらでネットで拾ってきた嘘の体験談が送られてくることもあるが。
平はこくりと頷いた。微は鞄から取り出したB6の小さな冊子を開いた。
川以外で水にまつわる怪異といえば、住宅地などでも見かける、用水路に関するものがある。『昔用水路で溺れた子供の霊が出る』というシンプルな怪談もあれば、『用水路の蓋がガタガタ動いて中から不気味な声がする』(N県Y市)といった、『特に名前はついていない気味の悪い現象』まで様々だ。
京都の堀に河童が出たという話もそうだが、都市においても水にまつわる怪異はよく目撃される。現代においても周りを田んぼに囲まれた住宅地は夜に歩くと薄暗く、怪異譚が生まれてもおかしくない。都市が排除しきれない闇が生んだ不可解な現象に名前をつける。そうした営みが妖怪譚を生んだのかもしれない。
「私が子供の頃体験した話なんですが、親や周りの大人に話しても『見間違いだ』『嘘つくんじゃない』って言われるばかりで。それ以来、話しても信じてくれないだろうって、あまり他人に話してこなかったんですが」
平はお冷を一口、ごくりと飲んだ。長い黒髪に縁取られた顔には、一筋の汗が伝っていた。店の冷房は、寒いくらいに効いているというのに。
「それに今は、教員としての立場もありますし......そんな中でこの本を読んで、似たような話があるんだって思って......」
「是非、聞かせてください」
微は、彼女の遠慮がちな声を遮るようにそう言った。中指にはめた銀の指輪が、お冷のグラスに反射してキラキラ輝いていた。
「類例はたくさんあるに限りますし、直接経験されたお話を伺えるのが、一番信頼性がありますから」
それに、個人的にとても興味があります。そう言う微の瞳もまた、きらきらと輝いていた。
微の様子に、平はくすりと笑い、肩の力を抜く。
二人の前に運ばれてきたアイスコーヒーを一口飲むと、彼女は口を開いた。
☆ ☆ ☆
「どこからお話すればいいのか......わたしの実家は、K町の隣にあるF町の郊外にあります。元々田んぼがあったところに新しく住宅やスーパーができた、いわゆる新興住宅地ですね。他にも集合住宅なんかがあったので、通っていた小学校は児童数が多かった記憶があります」
「今から約15年前、わたしが小学校中学年のとき、その家から学校に通う通学路の脇に用水路があったんですが――」
「用水路、というとドブ川みたいなものですか?」
「ええ。かなり深いもので、半分くらいはコンクリートで地下に埋められてたんですが、道の脇に露出してる部分もあって」
「なるほど、用水路というか暗渠というか、という感じですね」
「道路に露出している部分は、安全のためコンクリートの蓋が被せられたり、柵が周りに取り付けられてたりしました」
「というと、そこに転落する人がいたと……」
「昔は結構あったみたいですね。わたしの親なんかは浅いところに落ちて泥だらけになったって話してましたが、水量が多いところに落ちて流されてしまった子供もいたみたいで......」
「......なるほど。続けてください」
「ええと、でその用水路から、変な声が聞こえるって噂を、同じ通学団の低学年の子がしていたんですよ。しかも唸り声とかじゃなくて、名前を呼んでるみたいだって」
先ほどまで店内で談笑していたお客はいつの間にかいなくなっていた。カフェの店内には、ピアノ協奏曲が控えめな音量で流れている。
「名前を?」
「ええ。例えばたけしという名前の子が、用水路のそばを自転車で通ったら『たけちゃん』と呼ばれた、という話とか」
「……普段呼ばれている呼び名で呼ばれた、ということですか」
「はい。唸り声とかなら聞き間違いかもしれないですけど、名前を呼ばれるのは少し気味が悪いですよね」
「そういう話に尾ひれがついて、『名前を呼ばれたら用水路に引きずりこまれる』みたいな噂が、主に低学年の子の間で広まって。学校の行き帰りで用水路の近くを通る時は、皆怯えながら走り抜けてました」
微はふうん、と呟くと顎に手を当てた。
「それだけならよかったんですが、わたしたちの通学団が通っていた道は、用水路と交差している場所があって、どうしてもそこを横切らないといけなくて――」
「もちろん、蓋も柵もあるんですけど、低学年の子でそこを通りたくないって泣く子も出始めて」
「それは大変だったんじゃないですか? 集団登校って、みんな一緒に行かないとダメですよね」
「ええ。うちの学校は連帯責任というか、そのあたりがすごく厳しかったので、上の学年の私たちが怒られました」
「だから私たちはある時、用水路から聞こえる声に『名前』をつけようって考えたんです。かわいらしい名前がついてしまえば、怖くなくなるんじゃないかって」
「名前を。それはどなたが言い出したんですか?」
微はアイスティーを飲む手を止め、平に尋ねた。
不思議な現象に名前をつける――それは妖怪そのものの成立に関わるものだ。
例えば水辺で見つかった不可解な水死体。原因不明のままであったそれに「河童の仕業だ」と名前がつき、それを人々が信じることで、「妖怪」が生まれる。
しかしその名前が恐ろしげなものでなく、ポップで、親しみやすいものならどうなるだろう?
「言い出しっぺが誰かまでは覚えてませんが、わたしと同じ中学年の誰かだった気がします。あの声は、『ガラッパさん』って名前だと教えてあげよう、って」
「……その名前ひょっとして」
微は脇に置いていた、黒いレザーの鞄に手を伸ばす。
「『がらっぱくん』からとりました?『川太郎と水の王国』に出てくる、いつもドブに落っこちてばかりのドジな河童の...…」
微は、鞄からポップな河童のようなキャラクターが描かれた、やや色褪せたポーチを取り出した。平は目を丸くした。
「ご存じなんですか? 随分昔の、子ども向けのアニメなのに」
「妖怪が出てくるアニメですから当然ですよ。がらっぱくんが人間をおどかそうとしてドブに落っこちて、水面から『助けて〜』って声が聞こえておしまい、というコメディタッチの話が結構ありましたね」
微のポーチのイラストにも、ドブから顔をだす河童のコミカルな姿があった。主人公ではなかったが、妙に人気があったキャラクターだった。
「え、ええ...…だから用水路から聞こえる謎の声も、暗渠に住んでるガラッパさんの仕業だよ、という風に教えたら、怖くなくなるかなと」
「そうしたら、次第に泣くほど怖がってしまう子はいなくなりました。うちの通学団だけだったと思いますが、用水路を横切るときは、『ガラッパさん、通りますよ』って言って、通るようになったり」
平は空になったグラスの氷をカラン、と鳴らした。
「名前をつけた効果はあった、ということですね」
「ええ。でも――あんな名前、付けなければよかったかもしれません」
平の暗い声に、微は顔を上げた。丸眼鏡の奥の瞳は暗く沈んでいて、顔も、最初に挨拶を交わした時と比べても、ひどく強張っていた。
氷がまた少し溶けて、カランとひとりでに音を立てる。窓際の西日が差し込む席のはずなのに、妙に寒い。微は店員を呼び、ホットの紅茶を注文した。
しばらくして運ばれてきたガラスのポットから温かい紅茶をカップに注ぐと、平の前に差し出した。
紅茶を一口飲んだ平は、少し息を吐いた。じんわり、身体の中にあった固く冷たい部分が解けていく感触。
微は、低くそれでいて柔らかな声色で語りかけた。
「平さん。何があったのか、話していただけますか」
☆ ☆ ☆
「……ガラッパさん、という名前をつけてからしばらくして、夏休みに入りました。夏休みになれば、集団で登下校することももちろんありません」
「ただ、うちの地区には市営プールも学童も図書館もなくて。そうなると学校がある地区まで行くしかなかったんです。だからいつも登下校に使っている道も、子供たちがたくさん行き交っていました」
「わたしも、友達と学校のプールに行ったり、図書館に行ったりするときは、そこをよく通っていました。例の用水路を横切るときは、なんとなく『ガラッパさん』に挨拶をしていました」
平は少し冷めてしまった紅茶に、ポットから温かい紅茶を継ぎ足した。
「いつもは昼過ぎには家に帰っていたんですが、帰りが夕方になってしまった時は、少し薄暗いのでやだなあと思いながらその道を通っていたんです」
「すると何か変だなというか……水たまりにはまってしまったわけでもないのに、靴やワンピースが濡れてたり。横を歩いていた子がふらついて用水路の柵に突っ込みそうになったりしてたんです」
「『ガラッパさん』を信じてたわけではないんですけど、そんなことが続いたんで、なんとなく暗い時間は歩かないようにしていました」
「けれどある日――夏休みももうすぐ終わりなのに、調べ学習が終わっていない友達に付き合って図書館に閉館ギリギリまでいたことがあったんです」
すっかり日が暮れた後のその道は静かで、虫の鳴き声ばかりが響いていたという。
「友人は自転車を押しながら私の前を歩いていて、先に用水路と交差しているところを渡っていきました。その後わたしも渡ろうとしたら、前から低学年らしき男の子が歩いてきたんです」
「低学年らしき、というのは……?」
「その子は、下校の時やプールに行く道で何度かすれ違ってて。一言二言交わしたことはあったんですが名前とか学年、クラスまでは知らなくて。少し遠いところに集合住宅があって、そこは子供が多かったんで、そこの子だろうなと」
「それで、その子も用水路の上を渡るのかな、と思っていたら、急にその手前で立ち止まったんです」
「気にせず横を通ったら、なにかブツブツ言っていて。不思議に思いながらその子の脇を通り過ぎた直後、ドボン、という音がして、振り返るとその男の子はいなくなっていたんです」
そこまで一息で言うと、平は冷めてしまった紅茶のカップから手を離した。
「用水路に落ちたんだ、わたしはそう思いました。慌てて前を歩いている友達に知らせて、通りがかった大人に助けを求めました。大人はすぐに消防団に知らせてくれて――でも、その男の子は、どこを探しても、見つからなかったんです」
「見つから……なかった……?」
「用水路の中を探しても――こういう言い方をするのは憚られますが、下流で川と合流するところまで遡っても、その男の子はどこにもいなかったんです」
「それどころか、その近辺で行方不明になった男の子自体、探してもいなかったんです」
「……平さんが見た男の子自体が、身元不明、ってことだったんですか」
「ええ。だから警察や消防団の人、親や教師にまで、『本当にそんな子供はいたのか』『見間違いじゃないのか』って、問い詰められました。一緒にいた友人も『そんな子いたなんて気付かなかった』と言い出す始末で」
平が視線を落とした先、冷めた紅茶にはうっすらと脂が浮かんでいた。
スプーンでかき混ぜると、脂の浮いた水面はぐにゃりと歪み、底にとごった茶葉の破片が浮かんでは沈んだ。
「……見間違いなんかじゃない、とは思いながらも、周りにそうやって言われるとわからなくなっていました。そんなことがあって、夏休み明けはしばらく、学校を休みがちにもなっていました」
「そんな時、ふと、その男の子がブツブツ呟いていた言葉を、思い出したんです」
ガラッパさん、ガラッパさん。僕の名前はガラッパさん。暗渠のガラッパさん。
しんと静まり返った店内。窓の外から差し込んだ、半分ほど沈んだ太陽のオレンジ色の光が、二人の座るテーブルだけを照らしていた。
「あの男の子は、一体誰だったんでしょうか。わたしたちが勝手に名を付けた声の主は一体――何だったんでしょうか」
ーー
薄暗い暗渠を通り抜けたら、花畑の中に立つ煉瓦づくりの建物に出る、という謎の夢を見たことがあります。一体何なんだ。(とらつぐみ・鵺)
