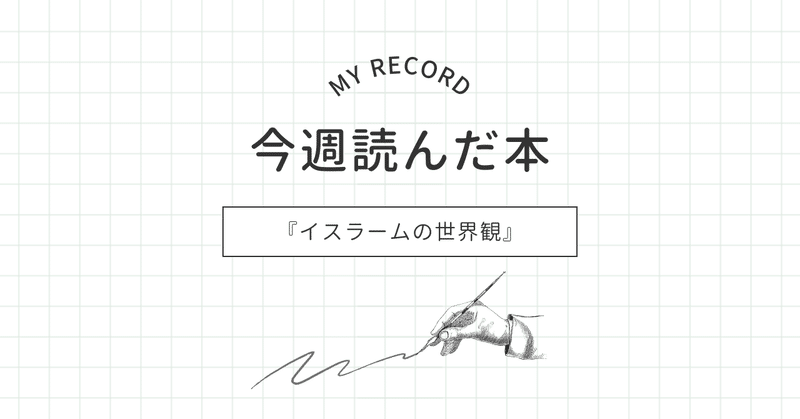
変わらない場所から動きの世界へ
書架から片倉もとこさんの『イスラームの世界観 〜「移動文化」を考える〜』を取り出した。長年のフィールドワークで得られた知見をもとに書かれた比較文化論エッセイで、イスラームで重んじられる「うごき」が主題になっている。
日本では当たり前のように「相変わらず元気です」や「おかげさまで変わりありません」と挨拶する。「変わらないこと」をよしとしている。これに対してイスラームでは、同じところに居続けると退行すると考えるそうだ。この本を読んではじめて知った。
"ひとつの拠点にじっとしていることに重要性をおかない。点と点のあいだを結ぶ線上のうごき自体にも、重要性をおくのである。人間活動の軌跡としての「点」と「線」は、いずれも同様に大切なもの、等価であるものとして考えられる。そこでは一カ所に「おちつく」ことがけっして目的にはならない。”(p.7−8)
この数行に動揺した。私たちは今いる場所と目的地のことばかり考えて、そこに到着するまでの道程を、「ただの移動」と考えていないか。それを時間という数字で表すだけで、移動そのものを軽んじていないか。
何時に出て、何時に到着する。無味乾燥な数字だ。同じことが、人生においてもいえるのではないだろうか。生まれた点と、亡くなる点。その間の線を、私たちはじゅうぶんに味わっているだろうか。
うごくことを念頭に置いた契約書と、動かないことを念頭に置いたそれでは、様式がだいぶ違うという例も面白く、旅する学者、真珠を取る砂漠の遊牧民、旅人保護の精神、カナダの墓地など興味深い話が並び、その一節ずつを味わって読んだ。
オスマン帝国の非ムスリムに対する保護・宗教自治制度ミッレトから考える、作者がいうところの「区別的共生」や「まあい共生」については、最近ぼつぼつと考えていたことを代弁してくれるような章だった。
すっかり心酔して検索したところ、著者は2013年に他界されていた。残念に思いながらエピローグまで進むと、
”このごろの日本では「さようなら」のかわりに、「頑張ってください」という言葉が、よくつかわれます。(中略)いわれた通りに、ますます一生懸命に頑張った結果、はやばやと逝ってしまった人もいるようです。
頑張らないで、「元気であちらにでかけたいな」とわたしは考えています。あの世でもフィールドワークをしてみたいのです。報告書は、筆でゆっくり書いてもいいし、この世にいる人に「あんがい、いいところよ。そっちでぐずぐずしていないで、早くこっちへ来ない?」と便りをおくってみるのもいいかしら、と思っています。”(p236−237)
まるでお便りを受け取ったように感じてドキッとした。
はじめまして。片倉さん。あなたの本を読みました。私の中には漂泊への憧れが、まるでそうしなさいと何かに突き動かされるように、強くあるのです。そちらはいいところですか。そこまでの道のりを楽しみながら、どこかでお目にかかれることを信じて旅していきますね。
目的や合理性からときはなたれ、変わっていくことを恐れず、頑張らないで生きていく。今の自分は、だいぶそんな感じ。
4年前に病を得て、融通の効かない体になってしまった。もともと境界線上をふらふらするのを愉快に思っていたけれど、いよいよ社会からこぼれ落ちた。おぼつかない日々を恨んだ瞬間もあったのに、こうなってしまって感じる自由もある。
何も持たず、流れに逆らわない自分は、あの頃よりゆたかな気もする。お金はないけれど。
化学物質過敏症への理解・協力の輪を広げるための活動は、みなさまのあたたかいサポートで続けられます。いただいたサポートは、化学物質過敏症の記事を増やすためのリサーチ等に充てさせていただきます。
