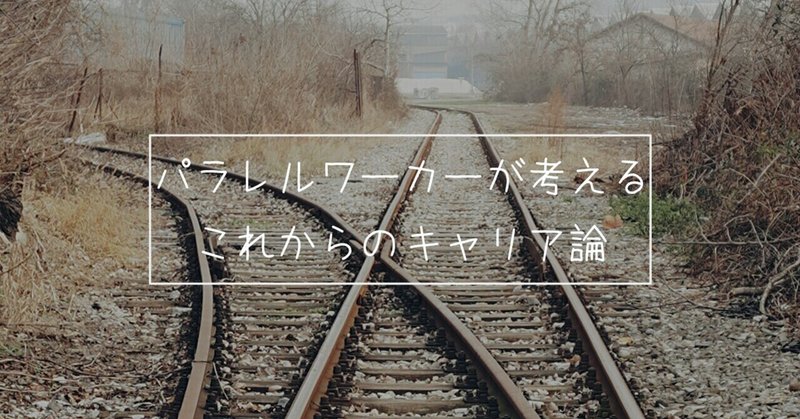
パラレルワーカーが考えるこれからのキャリア論
誰しも「何者かになりたい」という承認欲求や自己実現欲求は多かれ少なかれ抱くものだと思います。日本的な終身雇用・年功賃金制度が求心力を失い、人材の流動化がすすむなか、「何者でもない“私”」が「何者か」になるためのキャリア論を考えてみました。
自己紹介
そもそも「お前は何者だ」との指摘が飛んできそうなので、私のこれまでのキャリアをお話しいたします。
年齢不詳とよく言われますが、93年生まれの28歳です。プライベートでは、24歳で結婚し26歳で長女を授かり、現在は一児の父として奮闘しています。
私は法政大学社会学部を卒業していますが、大学は奨学金とアルバイトで学費を賄う自力進学でした。今も奨学金の返済を行っています。
大学卒業後は新卒で鉄鋼系商社の営業職としてキャリアをスタートしました。鉄鋼業界はとてもレガシーな業界で、平日夜は「飲み会」でお得意様を接待し、休日になればゴルフでお得意様を接待。日本的な営業スタイルが色濃く残る業界でした。
一方で、若手の私でも退職する頃には月間取扱高が10億円程度と、非常に大きな仕事をさせてもらえる業界でもありました。国内需要が年々減少していく業界ではありましたが、「信頼資本」と「データドリブン」を掛け合わせて毎年担当先出荷量を増やしており、やりがいのある仕事でした。
そんな商社時代から私はパラレルキャリアを進むことを選択していました。
入社から1年後、学生時代に興した「武蔵てらこや」という小学生の居場所づくりを行う団体の法人化に動きます。活動主体は大学生ですが、それをバックアップするために地域の大人がコミットする団体です。社団法人格を取得した後に、役員を拝命し大学生の指導と活動補佐を行なっています。
同時期に盟友と、中学・高校の「探究学習」や「キャリア教育」を支援する任意団体を設立しました。主に高校から依頼を受け、授業設計から実施まで代行する活動を行なっています。こちらも、2020年に社団法人格を取得し理事に就任しました。
ここまでで3つのキャリアを歩むことになりました。
そして、転機となったのは2019年の暮れ。「新規事業を立ち上げるから企画職として力を貸してくれないか」とお誘いを受けます。武蔵てらこやでの活動を見てくれていた、ある経営者からのお誘いでした。レガシーな企業から一転して草創期の事業に携わることになりました。
そこが私の職能であるマーケティングに出会うきっかけでした。「企画職としてマーケティングをやってほしい」転職して初めて仰せつかったミッションです。曖昧模糊な指令だなと思いつつ、事業のプランニングという点では2つの団体を興してきた経験がありましたが、運営という点においては明るくないため、必死に学習しました。SNSでアンテナを張り最先端の情報を集めながら、書籍によるマーケ知識の習得を行いました。集客はウェブがメインになったため「ウェブ解析士」という資格も取得し、転職から半年で売上規模を3倍に、売り場を4倍に拡大することに貢献してきました。
そんな折、前職の関係筋から「うちでもマーケティングを手伝ってくれないか」というお誘いを受けました。
ここから4つ目のキャリアが生まれます。個人事業主としてマーケ相談とウェブコンサルを行う事業を開きました。個人事業主として事業を始めてから半年でクライアント企業は2社となり、収入はサラリーマンとしての収入の3分の2程度まで拡大しました。
自己紹介が長くなりましたが、私は現在、1)サラリーマンとしての企画職、2)個人事業主としてのマーケ支援、3)小学生向け団体の役員、4)中高向け授業支援団体の理事 という4つのキャリアを歩んでいます。
これまでのキャリア観とこれからのキャリア観
これまでは、一つの会社に骨身を埋め、粉骨砕身の精神で企業に貢献していく終身雇用が前提のキャリア観が当たり前でした。
転職するにも年齢制限が暗黙のうちに障壁となり、キャリア転換も難しい世の中でした。
しかし、昨今は人材の流動化が進み、終身雇用制度は過去の遺物となりつつあります。裏を返せば、いざというときに「企業は社員を守らない」可能性が以前に比べて高くなっているということです。
株式会社刀のCEO、森岡毅氏は著書『苦しかった時の話をしようか』でこう説きます。
会社と結婚するな、職能と結婚せよ −会社に依存するのではなく、自分自身のスキル(職能)に依存するキャリアの作り方を、君には強く勧めたい。文字通り就“職”活動であって、就“社”活動ではない。個人にとって、会社は職能を身につけるための手段だ。
どれだけ会社と結婚したくても、私たちのアジェンダとは無関係に企業活動は行われるので永遠の片思いで終わってしまう。と言うのです。まさに、その通りだと思います。一流企業に就職することでキャリアに花を添えることはできるでしょうが、そこで飼い慣らされるだけで終わる可能性も考えなければなりません。
昨今は45歳定年が提唱され、今後議論が活発化することになると思います。既に、一部の大企業では一定年齢を超えると個人事業主としての業務委託契約に切り替わるという話も聞いています。
45歳と言えば、私で言えば子供が大学受験を控える頃となります。そんなタイミングで、なんの職能も身に付けず、若さという武器もない状態で職を失い、猛者が犇めく転職市場に投げ出されることに恐怖を感じます。
ですから、自身の強みを見つけ、“職能”という武器に育て上げそれに磨きをかけておかなければならないのです。
そのためには、一つの企業で身につけられるスキルには上限があります。システム化された企業の中では、個人差はあるものの天井が決まってきます。
そこで、私がお勧めしたいのがキャリアの複線化、複々線化です。その中でもオーナーシップを持てるキャリア=自分の事業を持つことを強くお勧めします。
会社から別れを告げられても、自身の事業があれば当面食い凌ぐことができます。言い方を換えると「自分でコントロールできる範囲を持っておく」ということです。
サラリーマンと事業主
では、サラリーマンとしてのキャリアと事業主としてのキャリアをどう棲み分けるのか。と言う私なりの考えをお伝えします。
サラリーマンキャリアとはrice work(食い扶持の確保)だと考えています。その一方で、事業主としてのキャリアはlife work(自己実現への挑戦)になるのではないでしょうか。
サラリーマンキャリアでは、社会人としての経験を体系的に身につけることができる他、「会社」と言う看板を背負うことで得られる「信頼」を基に人脈を広げることができます。自社内での人間関係だけでなく、仕入れ先、取引先、制作会社など様々な企業と関係性を持つことができます。それらの体験を消費するだけでなく、会社から借りた「信頼」を自分の「資本」へと昇華していくことができれば、life workを始める基礎を作ることができます。また、個人事業では扱えないスケールの案件を動かすことでしか得られない経験を積むことができ、チームでの活動があるのであればマネジメントを学ぶこともできるでしょう。自身がメンバー(マネジメントされる側)であっても、真似をしたい人や逆に反面教師にしたい人を見つけることができます。
言ってしまえば、サラリーマンキャリアとは自身の事業の修行・実践練習をお給料をもらいながらできるのです。どんな業務からでも学べることがあると言う姿勢を持つことがサラリーマンキャリアでは重要です。そうすることで、自身の事業をグロースさせることができるのではと考えています。
一方で、個人事業では「会社」と言う看板がなくなるので「信頼」が何にも変え難い「資本」になります。信頼資本の少ないスタート時はサラリーマンで扱っていたような大きな案件の獲得は難しいでしょう。しかし、小さなことをコツコツと積み上げることで見えてくる視点もありますし、業務委託と言う外野だから見える景色もあります。そうして得た知見をサラリーマンキャリアへ逆輸入することで、サラリーマンとしてのキャリアもグロースさせることができます。
サラリーマンキャリアと事業主としてのキャリアは切り離して考えるべきではないと思います。私は、それらは相互に作用しあうものと考え、どうしたらシナジーが生まれるかと問いながら活動しています。
何者かになるには
かく言う私も、大それた人間ではありません。インフルエンサーにはなれないし、抱え切れないほどの仕事や高単価の仕事の依頼があるわけでもありません。しかし、ありがたいことに「あなただからお願いしたい」「あなたと仕事がしたい」と言ってくれる人が何人もいます。私は何者でもないけれど、私に仕事を依頼したい、私と協働したいと言ってくれる人からすれば、唯一無二の存在になれているのではないでしょうか。
それは、先ほどから申し上げている「信頼資本」を大事にしてきた結果だと思っています。では、信頼資本はどのように築き上げれば良いのでしょうか。
端的に言えば、「相手の期待に応える」ことでしょう。
例えば、私がマーケティングを始めるきっかけとなった転職の誘いの時、「企画職として新規事業を手伝ってほしい」と声をかけられました。この時、私は<新規事業を組み立てること>を期待されていました。そして、入社後に「マーケティングをして欲しい」と指令を受けています。この時は<マーケティングで集客を行い、販売実績を作ること>を期待されていました。
私はこれに全力で応えました。新規事業を行うためのプランニングからマーケティングのフレームワークまでを勉強し、競合をベンチマークしながら集客方法を確立していきます。結果は自己紹介でも述べた通り、売上規模と売り場を数倍に拡大しました。
こうして得られた「信頼資本」は「役職」と言う目に見えるものに形を変えて私のキャリアを底上げしてくれました。
また、その過程で取引をさせていただいた制作会社や広告代理店とのやりとりも真摯に行ない、相手の期待に応え続けたことで、個人事業主の仕事も依頼できるまで関係性を築くことができました。今では「あなたの仕事なら協力します」と言っていただけるまで「信頼資本」は大きく積み上がりました。
参考までに、この制作会社が私に期待していたのは<社内調整>(=見積もり金額を大幅に下げずに決裁をとることや、納期調整などのディレクション)でした。制作会社も発注側の自社も損を被らないように調整を行うことで最初の「信頼資本」を築き上げました。
私は「何者かになる」ための方法としてここまで記しましたが、もっと綺麗に言語化しているのが井上大輔氏の『マーケターのように生きろ』です。
井上氏はマーケティングの4STEPを抑えることで「求められる人」になれると言います。「求められる人になる」と言うのは私が申し上げている「何者かになる」と同義語だと思っています。
キャリアの終着点
複線化したキャリアの終着点がどこへ行き着くのかはわかりません。私も4つのキャリアを同時に歩んでいますが、どこかで全ての路線が交わる時が来るかもしれませんし、並走したまま走り抜けるのかもしれません。
変化の激しい時代にあって、路線が一本しか走っていないと大きな外的要因で脱線した時に、立ち止まることしかできません。しかし、複線化していれば“振替輸送”が可能になります。複線として敷設していたつもりが、新幹線に化けることも可能性としてはあり得ます。
どう転ぶか分からない時代だからこそ、選択肢や可能性を少しでも多く握っておくことが必要なのだと思います。ただ、バラバラに選択肢を握るのではなく、相乗効果を狙っていくことで、それぞれの選択肢が可能性を拡げてくれることでしょう。
「何者でもない“私”」ですが、複数のキャリアを抱えることで少しずつ「何者か」になりかけていると信じています。
終わりに
ここまで申し上げたのは、「何者かになる」ための手法の話です。ですから、別の手法があって然るべきです。唯一の手法だとは思わないでください。一つの企業に貢献し続け、叩き上げで 社長まで上り詰める人もいます。或いは、キャリアは一本だけど転職を繰り返すことで知名度をあげる人や、独立して名声をあげる人もいるでしょう。
私のような小心者が極力リスクを取らずに「何者かになる」ための方法論の一つとしてご笑納いただければ幸いです。
また、井上大輔氏は令和の時代を「ホールネスの時代」だと指摘します。
ホールネス:社会が個人を成り立たせ、個人が社会を成り立たせる=自分だけができるやり方で、世界の欠けたピースを埋める
ですから、これまでのキャリア論のように終身雇用を前提とした、画一化されたキャリア観ではなく、その人にしか体現できないキャリア観を育てる時代になるのでしょう。それが私の場合は「キャリアの複々線化」であっただけで、皆さんにそれが適しているとは限りません。
自分でキャリア観を醸成しなければならない時代とは、なんて酷な時代なのでしょう。しかしながら、自分でキャリアを切り開く=「自分らしく」生きていくチャンスだとも捉えられます。
私自身ももっとキャリアについて考えていきます。そして、キャリア教育に携わりながら、若い世代にも考えるきっかけを作っていきたいと思います。
駄文にお付き合いいただきありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
