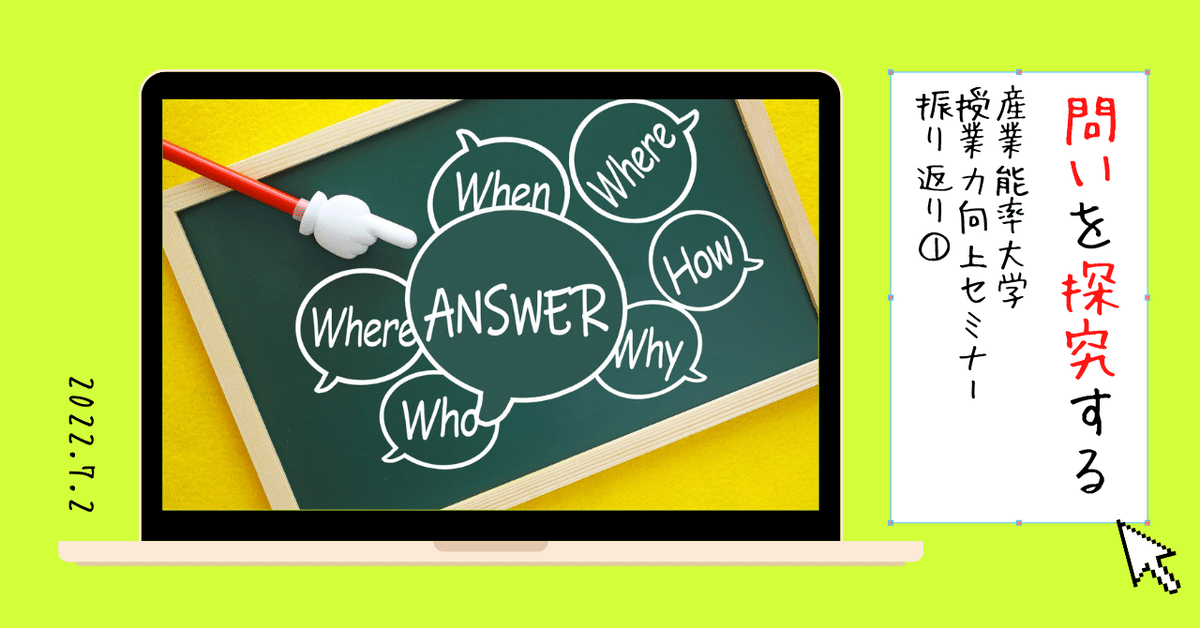
[note29]問いについて考えた1日PART①(産業能率大学授業力向上セミナー)
産業能率大学が主催する授業力向上セミナーに参加しました。
今回は「深まる・広がる・ワクワクする‘’問い‘’の作り方を学ぶ」と題したプログラムに参加しました。率直に参加して良かったなというのが感想です。「問い」については関心があり、色々な本を読みましたが、まだまだ自分の中に落とし込めていません。今回のセミナーも内容が濃く、自分の中で消化するためには少し時間がかかりそうですが、記憶が鮮明なうちにいくつかまとめておきたいと思います。
人はもともと問いをもって生きている
頭はモヤモヤ、心はワクワク
問いとは何か・問いの作り方、問いが生まれる場の在り方など色々な学びのあった1日でしたが、印象に残ったことが上の言葉です。
「問い作り」という言葉があり、そこに興味を持って自分なりに学んでいますが、そもそも人は日常的に問う存在であること。「問い」を投げかける立場は、それを掘り起こすことが求められるのかも知れない。そして、問いは人をモヤモヤさせるけれど、それがイライラや単なる消化不良ではなく、ワクワクにつながるならば、大きな意味が出てくる(と解釈しました)。
自分を知らないと自分ごとにはならない!
もう1つ、セミナーのワークで自己理解を深めるパートがありました。勤務校で行っている中学生対象のゼミの大きなテーマが「社会問題を自分ごととして考える」ということです。以前、他のセミナーで「社会問題を本当に自分事として捉えきることは可能なのか?」という問題提起があり、それが自分の中の「問い」として残っていました。確かに色々な社会問題があるけれど、本当に自分ごととして考えることはできるのか、当事者でなければ入り込めない絶対的な領域があるのではないか、自分ごととして捉えたと認識することは危険な場合もあるのではないか…。
こうした自分の中の問いに対して、まずは自己理解が問いにつながるという指摘は腑に落ちるものでした。正直、様々な問題を当事者でない立場で理解することには限界があると思っています。しかし、当事者になれなくとも、それに近い位置に自分を置くことで物事を思考することはできるのではないか。そのためにも、何よりも自分を理解することから始める必要がありそうです。
問いをどう考えるか?
ここが自分にとっても最大の関心事なわけですが、当日のスライドや自分の授業を振り返りながら、もう少し整理してまとめたいと思います。
相互研究の重要性
今回のセミナーではレクチャー部分も非常に濃密で学ぶことが多い内容でした。それと同時に5人程のグループ内で、個々に「問い」を意識した授業案を考え、15分ずつ検討し合うというセッションの充実感が強かったです。
15分間は「語り切る+聞き切る」ことに集中できる贅沢な時間です。自分が属したグループは地歴公民、保健体育、数学、国語の先生方で構成されていて、授業案も多彩でした。やはり、授業について教師同士が学び合うことが不可欠であることを実感します。その時に重要なことが「場」の在り方です
★安心できる場所であることが問いを生み出す条件★
研究授業などはどうしても構えることが多くなりがちです。勤務校でも授業見学を行う機会がありますが、それをじっくりフィードバックしたり、意見交換をする機会を作るのは難しいのが現状です。しかし、何を言っても否定されない安心感のある場で授業について考え、話し合う時間は極めて重要であると考えます。そして、それは普段の自分の居場所で作っていくべき時間なのだと思います。
今回のセミナーを運営して下さった3名の講師の方々、同じ時間を共有した全国の先生方、多くの学びをありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
