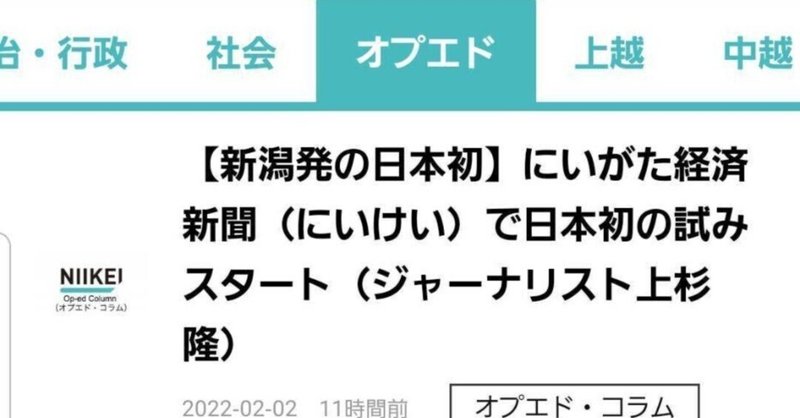
【新潟発の日本初】にいがた経済新聞(にいけい)で日本初の試みスタート
東京一極集中が叫ばれて久しい。様々な施策が講じられているものの、結局、ヒトも、富も、情報も東京に集まってしまっている。
コロナ時代において、「ニューノーマル」やら「リモート国家」やら喧しい。巷に期待の言葉は溢れているが、結局、地方の時代にはなっていないのではないか。
50代の筆者は、地方への人口移動は、社会に多様性をもたらし、効率的な都市の出現と富の再分配が達成されると教わってきた。学校でも、メディアでもそう教わったのだ。
しかし、現実はどうだろうか。細胞生物学におけるニューロンではないが、生命体も都市構造もつまるところ、一極に偏るのがむしろ自然であり、効率的だと判断しているのではないだろうか。
すると、新潟もこのまま静かに退潮していくのだろうか?
一方で、歴史的なイノベーションや先駆的な文明開化が、必ずしも中央から発生するとは限らない。むしろ、パイロット自治体の言葉が象徴するように、地方がきっかけとなることも少なくない。
保守王国・新潟の地で、日本初の試みが始まった。新興メディアの新潟経済新聞社、そう、この『にいけい』(通称)がその舞台である。
この2月から『にいけい』が導入したオプエドは、世界標準のメディアシステムで、日本初の採用となる。1970年代、かつて筆者の所属した『ニューヨーク・タイムズ』が世界に先駆けて導入した制度だといわれている。
Op-ed (opposite the editorial page / opposite editorial、オプエド)とは、新聞の記事のうち、当該紙の編集委員会の支配下にない外部の人物が、ある新聞記事に対して同じ新聞内で意見や見解(反論や異論)を述べる欄のことである。通常、社説の反対側に設けられることからこの名がついた。社説が主に社内の編集委員によって執筆され、署名がされないのに対し、op-edは社外(時に社内も)の人物が署名付きで執筆するという点が異なる(拙著『ジャーナリズム崩壊』(幻冬舎)より)。
とはいえ、100年以上の歴史のある日本の新聞社が、過去に一紙も採用できなかったという現実がその困難を物語っている。前途は容易いものではない。フェアなディベートに慣れておらず、情報リテラシーの高くない日本人にはそもそもオプエド自体が向かないかもしれない。
しかし、時代は変わった。アンフェアなシステムは社会を停滞させるばかりで、メリットがないと多くの日本人が気づき始めている。その未踏の領域にチャレンジするのが『にいけい』だ。その心意気やよしとしようではないか。
新潟経済新聞社はウェブ上の新聞『にいけい』を発刊しているローカルメディアである。創刊5年。地元新潟に特化した情報を仔細に報じ続け、域内情報や訃報などまでも、県内の話題を丁寧に拾っている。小さいながらも、多くの読者を獲得しはじめているのはそうした理由からだろう。
驚くべきことに、その小さなメディア『にいけい』は、最大県紙である『新潟日報』の倍近いアクセスを稼いでいるという(2021年度実績9000万ページビュー/Google調べ)。
とはいえ、とてもではないが、1877年創刊の売上150億円超の地方紙の巨人「新潟日報」に、記者数人の『にいけい』が太刀打ちできるわけがない。大きさや分量では勝ち目はないが、質であるならば勝負になるかもしれない。日本で初めての「オプエド・コラム」を成功させれば、ジャーナリズム自体が変わるきっかけになるかもしれない。
新潟のメディアを変えはじめている『にいけい』が、果たして、次は日本を変えようとしているのだろうか?ジャーナリズム活動23年目の筆者が、いまもっとも注目しているメディアとその試みは、新潟で始まったばかりである。
※筆者追記
Op-ed(オプエド)では、同じ新聞に異なった記事が掲載されることで、同じ社の記者同士が激しく論争することもあり、結果として言論の活性化に繋がっているとされ、また、それによって多様性と少数意見を保つというジャーナリズム本来の役割をも果たせるとされている。 報道機関が自らの記事を絶対視することを防ぐとともに、読者もまた絶対的に正しい意見など存在しないことを知ることで、「リテラシー(情報を読み解く力)」を高める効果があるとされてい[1]、「バイライン(署名)」「ソース(情報源)」「クレジット(引用・参照元)」「コレクション(訂正欄)」と共に世界のジャーナリズムで一般的かつ重要な機能とみなされている(筆者インタビューから/Wikipedia)。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
