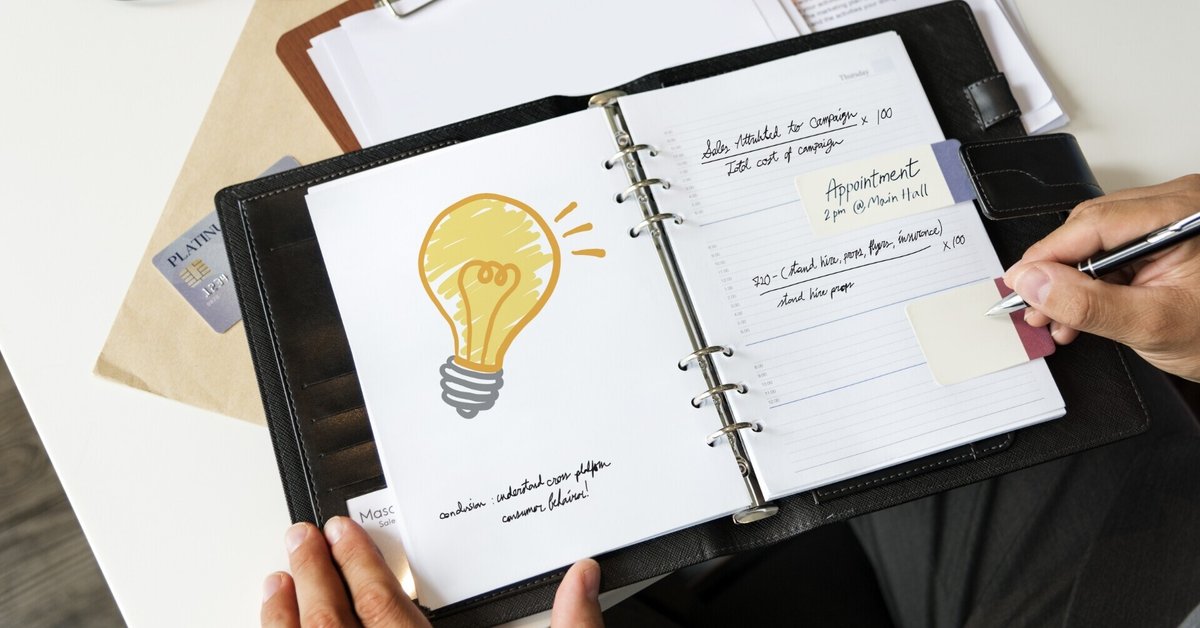
当事者の視点で日常を捉えよ!:『現象学的社会学』(アルフレッド・シュッツ著)を読んで。
日常の社会学とでも呼べるような、日常生活における社会学に多大な影響を与え、現象学のフッサールの思想を引き継いだ人物が、本書の著者であるアルフレッド・シュッツです。
昨秋にフッサールを立教の有志で読んだときに、本書を読んでおくべきだったと後悔しました。というのも、本のタイトル通り、現象学を基にして社会学を論じているため、抽象的なフッサール現象学を具体的にイメージしやすいのです。フッサールの副読本としてぜひ手元におきたい一冊です。
シュッツは、大学を卒業した後、昼間は銀行員として働き、夜間にはフッサールの現象学とウェーバーの理解社会学を研究し続けるという学問と実践とを両立した異色のキャリアを歩んでいます。その中で、機能主義的な認識論に基づくタルコット・パーソンズの社会学に対して、解釈主義的な認識論に基づく社会学を打ち立てた主要な一人として後世に名を残しています。(この辺りの話は坂下先生の書籍を扱った際に述べました)
シュッツは、私と同じ空間にいて相対している他者(「汝」とシュッツは呼びます)と私との関係について長く論じています。私は、私の現在の思考や行為についてリアルタイムで把握することができず、将来時点から振り返らなければわからないと捉えます。それに対して、汝の思考と行為についてはリアルタイムで把握することが可能だと捉え、私[汝]は汝[私]について自分自身よりも知っているのです。
では、どのようにして他者の行為を社会学者は論じることが可能なのでしょうか。
シュッツは、社会学者が科学的概念によって二次的に再構成する以前の、行為者が常識的概念によって一次的に経験している社会を、行為者自身の視点から記述するべきだ、としています。つまり、第三者の視点から客観的に捉えるのではなく、当事者の視点から主観的に捉えよ、ということです。
フッサールが生活世界において「いまーここ」を捉えようとしたものを、シュッツは日常生活世界として受け継ぎました。それを、行為者が一次的に構成する経験そのものを当事者目線で描き出そうというアプローチとしてシュッツは論じてみせた、と言えそうです。
おまけ
この手の社会学の書籍を読む際には、私は以下の本を辞書がわりに活用しています。この記事を書く際にもお世話になったのでご紹介までです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
