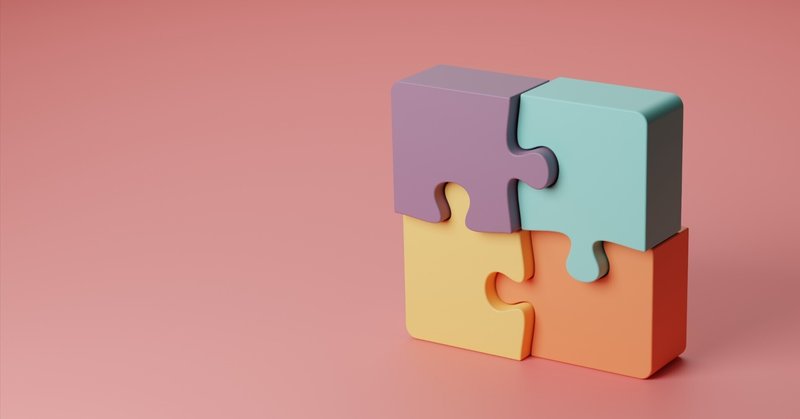
【徹底解説】キャリア・アダプタビリティ尺度(2)関心・統制・好奇心・自信:Savickas & Porfeli(2012)
キャリア・アダプタビリティは、関心(concern)、統制(control)、好奇心(curiosity)、自信(confidence)の4つの下位尺度から構成されます。これは、初期の論文の頃から一貫してサビカス先生が提示していたものであり、結論を先取りすれば、本論文で開発された尺度でも4つの下位尺度で構成されると検証されています。調査や分析に移る前の4つの点に関する解説がたった二段落でありながらコッテリとした解説なので、今回はその内容をまとめてみます。
Savickas, M. L., & Porfeli, E. J. (2012). Career Adapt-Abilities Scale- Construction, reliability, and measurement equivalence across 13 countries. Journal of vocational behavior, 80(3), 661-673.
4つの下位尺度
こってり解説に行く前に、4つの下位次元についてざっと見ます。既に知っているよ!という方はこの節は飛ばして次節へどうぞ。まず、サビカス先生の他の論文では以下のような表にまとめて説明してくれています。

英語はめんどいです、、、という方向けには、私が過去の勉強会でざっと訳したものがあるので以下をご参考までにご笑覧ください。

キャリア・アダプタビリティは特性的?状態的?
ここまでの基本的な内容を踏まえて、こってり解説に移ります。まず、キャリア・アダプタビリティという概念はtrait like(特性的)なのかstate like(状態的)なのかという点について、本論文では以下のように書かれています。
We presume that resources reflect adaptability, which is therefore a composite of more durable psychological and more labile psychosocial aspects.
(ざっくり和訳)
私たちは、資源とはより不変的な心理的側面とより可変的な心理社会的側面の複合体である(キャリア・)アダプタビリティを反映していると推定しています。
不変的な心理的側面という点では特性的と言え、他方で可変的な心理社会的側面という点からは状態的と言え、両者から構成されている概念であると著者たちが述べていることからすると両方である、ということのようです。すっきりしないとも言えますが、どちらの観点も含まれると言及されていることはありがたいです。
というのも、特性と比べると可変的でありながらも反応や成果変数と比較すると不変的であることがわかるからです。したがって、キャリア・アダプタビリティとの影響関係を検討する概念の位置付けをよく考慮した上で研究をデザインすれば良い、ということになるのではないでしょうか。
キャリア・アダプタビリティの作用と成果
こうして4つの下位尺度から構成されるキャリア・アダプタビリティはどのような影響を与えるものなのでしょうか。
The four adapt-ability syndromes, for short the 4Cs, support self-regulation strategies.
(ざっくり和訳)
4つの適応能力症候群、略して4C、は自己調整戦略を支援する。
まず作用する対象としては自己調整戦略であると本論文ではしています。キャリアにおける課題や移行における課題に対して自身で調整しながら対処していくというプロセスを想定していると考えられます。
Increasing a client's career adaptability resources or career adapt-abilities is a central goal in career education and counseling.
(ざっくり和訳)
クライエントのキャリア・アダプタビリティ資源やキャリア・アダプタビリティを高めることは、キャリア教育やカウンセリングにおける中心的な目標である。
状態的でありながら特性的でもあるという特徴を持つキャリア・アダプタビリティを高めることによって、自己調整戦略をクライエントが遂行できるようにすることが、カウンセラーの目標となるようです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
